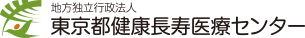研究者総覧
菊地 和則 (キクチ カズノリ)
|  | ||
Last Updated :2025/04/04
研究活動情報
論文
- Kazunori Kikuchi; Tatsuya Ooguchi; Tomoko Ikeuchi; Shuichi AwataPsychogeriatrics 25 3 2025年03月
- Kazunori Kikuchi; Tomoko Ikeuchi; Shuichi AwataGeriatrics & gerontology international 24 5 499 - 501 2024年05月 [査読有り]
- Kazunori Kikuchi; Tomoko Ikeuchi; Shuichi AwataGeriatrics & gerontology international 23 11 890 - 891 2023年11月 [査読有り]
- 意思決定支援会議と専門職後見人-社会福祉士調査からみえてきたことー菊地和則実践 成年後見 107 58 - 65 2023年10月 [招待有り]
- 認知症サポート医が困難事例対応において期待される役割井藤佳恵; 津田修治; 山下真理; 菊地和則; 畠山啓; 扇澤史子; 古田光; 粟田主一日本老年医学会雑誌 60 3 251 - 260 2023年07月 [査読有り]
- Kazunori Kikuchi; Tatsuya Ooguchi; Tomoko Ikeuchi; Shuichi AwataGeriatrics & Gerontology International 23 5 362 - 365 2023年04月 [査読有り]
- Kazunori Kikuchi; Tatsuya Ooguchi; Tomoko Ikeuchi; Kae Ito; Shuichi AwataGeriatrics & gerontology international 22 8 684 - 686 2022年07月 [査読有り]
- 菊地 和則; 大口 達也; 池内 朋子; 粟田 主一老年精神医学雑誌 32 4 469 - 479 (株)ワールドプランニング 2021年04月 [査読有り]
- Ayako Edahiro; Fumiko Miyamae; Tsutomu Taga; Mika Sugiyama; Kazunori Kikuchi; Tsuyoshi Okamura; Shuichi AwataGeriatrics & Gerontology International 20 11 1050 - 1055 2020年09月 [査読有り]
- 介護保険データを用いた若年性認知症有病者数の推計における「みなし第2号被保険者」の影響菊地 和則; 中西 亜紀; 小長谷 陽子; 多賀 努; 枝広 あや子; 杉山 美香; 岡村 毅; 宮前 史子; 山村 正子; 粟田 主一日本老年医学会雑誌 57 Suppl. 112 - 112 (一社)日本老年医学会 2020年07月
- 若年性認知症の診断後支援に関する現状とその課題 若年性認知症の有病率及び生活実態に関する調査から多賀 努; 枝広 あや子; 杉山 美香; 宮前 史子; 山村 正子; 菊地 和則; 粟田 主一日本認知症ケア学会誌 19 1 227 - 227 (一社)日本認知症ケア学会 2020年04月
- Kazunori Kikuchi; Mutsuo Ijuin; Shuichi Awata; Takao SuzukiGeriatrics & gerontology international 19 9 902 - 906 2019年09月 [査読有り]
- 多賀 努; 枝広 あや子; 杉山 美香; 岡村 毅; 宮前 史子; 山村 正子; 菊地 和則; 粟田 主一老年精神医学雑誌 30 増刊II 187 - 187 (株)ワールドプランニング 2019年06月
- 枝広 あや子; 杉山 美香; 多賀 努; 山村 正子; 宮前 史子; 岡村 毅; 菊地 和則; 粟田 主一老年精神医学雑誌 30 増刊II 202 - 202 (株)ワールドプランニング 2019年06月
- 菊地 和則; 中西 亜紀; 小長谷 陽子; 多賀 努; 枝広 あや子; 杉山 美香; 岡村 毅; 宮前 史子; 山村 正子; 粟田 主一老年精神医学雑誌 30 増刊II 224 - 224 (株)ワールドプランニング 2019年06月
- Hajime Iwasa; Yukie Masui; Hiroki Inagaki; Yuko Yoshida; Hiroyuki Shimada; Rika Otsuka; Kazunori Kikuchi; Kumiko Nonaka; Hiroto Yoshida; Hideyo Yoshida; Takao SuzukiAging clinical and experimental research 30 4 383 - 393 2018年04月
- 菊地 和則; 伊集院 睦雄; 粟田 主一; 鈴木 隆雄日本老年医学会雑誌 53 4 363 - 373 (一社)日本老年医学会 2016年10月 [査読有り]
- Iwasa H; Masui Y; Inagaki H; Yoshida Y; Shimada H; Otsuka R; Kikuchi K; Nonaka K; Yoshida H; Yoshida H; Suzuki TGerontology & geriatric medicine 1 2333721415609490 2015年01月 [査読有り]
- 大塚 理加; 菊地 和則; 野中 久美子; 新開 省二; 三浦 久幸老年社会科学 35 4 447 - 453 日本老年社会科学会 2014年01月
- 大塚 理加; 野中 久美子; 菊地 和則; 大島 浩子; 三浦 久幸老年社会科学 34 3 403 - 411 日本老年社会科学会 2012年10月
- 大塚 理加; 菊地 和則; 野中 久美子; 高橋 龍太郎社会福祉学 51 4 104 - 115 一般社団法人 日本社会福祉学会 2011年 [査読有り]
- 野中 久美子; 大塚 理加; 菊地 和則社会福祉学 50 3 54 - 65 一般社団法人 日本社会福祉学会 2009年 [査読有り]
MISC
- 若年性認知症の診断後支援のあり方に関する検討 東京都若年性認知症の有病率及び生活実態に関する調査の経過報告多賀 努; 枝広 あや子; 杉山 美香; 岡村 毅; 宮前 史子; 山村 正子; 菊地 和則; 粟田 主一 老年精神医学雑誌 30 (増刊II) 187 -187 2019年06月
- 認知症疾患医療センターにおける若年性認知症の年間鑑別診断数と発生率の検討枝広 あや子; 杉山 美香; 多賀 努; 山村 正子; 宮前 史子; 岡村 毅; 菊地 和則; 粟田 主一 老年精神医学雑誌 30 (増刊II) 202 -202 2019年06月
- 介護保険第2号被保険者データを用いた若年性認知症の状態像に関する研究菊地 和則; 中西 亜紀; 小長谷 陽子; 多賀 努; 枝広 あや子; 杉山 美香; 岡村 毅; 宮前 史子; 山村 正子; 粟田 主一 老年精神医学雑誌 30 (増刊II) 224 -224 2019年06月
- 岩佐 一; 吉田 祐子; 稲垣 宏樹; 増井 幸恵; 島田 裕之; 菊地 和則; 大塚 理加; 野中 久美子; 吉田 裕人; 鈴木 隆雄 厚生の指標 65 (15) 1 -7 2018年12月
- 認知症の徘徊、現状と課題 認知症の徘徊による行方不明の実態 全国調査からわかったこと菊地 和則; 伊集院 睦雄; 粟田 主一; 鈴木 隆雄 日本老年医学会雑誌 54 (Suppl.) 99 -99 2017年05月
- 都市部在宅療養高齢者の主観的健康感の関連要因の検討 主に日常活動との関連について増井 幸恵; 菊地 和則; 河合 恒; 伊東 美緒; 大渕 修一 老年社会科学 38 (2) 269 -269 2016年06月
- 都市部在宅療養高齢者の生活実態大渕 修一; 河合 恒; 菊地 和則; 増井 幸恵; 伊東 美緒 日本老年医学会雑誌 53 (Suppl.) 136 -136 2016年05月
- 在宅療養者の在宅生活と連携、地域コミュニティとの関連 居宅介護支援事業所調査より三澤 仁平; 菊地 和則; 大塚 理加 日本公衆衛生学会総会抄録集 73回 463 -463 2014年10月
- 増井 幸恵; 岩佐 一; 稲垣 宏樹; 吉田 祐子; 吉田 英世; 菊地 和則; 吉田 裕人; 野中 久美子; 島田 裕之; 大塚 理加; 鈴木 隆雄 老年社会科学 36 (2) 235 -235 2014年06月
- 菊地 和則; 三澤 仁平; 大塚 理加; 三浦 久幸 Geriatric Medicine 52 (2) 137 -140 2014年02月
- 三澤 仁平; 菊地 和則; 大塚 理加 Geriatric Medicine 52 (2) 141 -145 2014年02月
- 災害後の状況における在宅医療を利用する高齢者の在宅生活を継続する要因の検討大塚 理加; 菊地 和則; 三澤 仁平 日本公衆衛生学会総会抄録集 72回 440 -440 2013年10月
- 東日本大震災後の自治体における在宅医療整備の実態と今後の展望三澤 仁平; 菊地 和則; 大塚 理加 日本公衆衛生学会総会抄録集 72回 541 -541 2013年10月
- 稲垣 宏樹; 増井 幸恵; 吉田 祐子; 岩佐 一; 吉田 英世; 菊地 和則; 吉田 裕人; 野中 久美子; 島田 裕之; 大塚 理加; 鈴木 隆雄 老年社会科学 35 (2) 180 -180 2013年06月
- 増井 幸恵; 稲垣 宏樹; 吉田 祐子; 岩佐 一; 吉田 英世; 菊地 和則; 吉田 裕人; 野中 久美子; 島田 裕之; 大塚 理加; 鈴木 隆雄 老年社会科学 35 (2) 179 -179 2013年06月
- 大渕 修一; 菊地 和則; 伊東 美緒; 増井 幸恵; 小島 基永; 大塚 理加; 高橋 龍太郎 老年社会科学 34 (2) 205 -205 2012年06月
- 伊東 美緒; 大渕 修一; 菊地 和則; 増井 幸恵; 小島 基永; 大塚 理加; 高橋 龍太郎 老年社会科学 34 (2) 206 -206 2012年06月
- 稲垣 宏樹; 増井 幸恵; 吉田 祐子; 岩佐 一; 大塚 理加; 吉田 英世; 菊地 和則; 吉田 裕人; 野中 久美子; 島田 裕之; 鈴木 隆雄 老年社会科学 34 (2) 246 -246 2012年06月
- 吉田 祐子; 増井 幸恵; 稲垣 宏樹; 岩佐 一; 大塚 理加; 吉田 英世; 菊地 和則; 吉田 裕人; 野中 久美子; 島田 裕之; 鈴木 隆雄 老年社会科学 34 (2) 247 -247 2012年06月
共同研究・競争的資金等の研究課題
- 日本学術振興会:科学研究費助成事業研究期間 : 2022年04月 -2025年03月代表者 : 井藤 佳恵; 菊地 和則; 扇澤 史子; 古田 光; 山下 真里; 枝広 あや子初年度は、困難事例への対応において、地域の認知症支援システムに関わる専門職が、認知症サポート医に期待する役割を明らかにすることを目的とした研究をおこなった。日本語論文として発表し、日本老年医学雑誌に受理された(2023年4月現在印刷中) 方法:対象は、2021年4月から2022年3月の期間に東京都健康長寿医療センター認知症支援推進センターおよび認知症疾患医療センターが主催した、地域の認知症支援システムに関わる専門職を対象とした研修の受講者1173人である。郵送による自記式アンケート調査を実施し、調査項目には、基本属性、困難事例対応の際の相談・連携先、相談・連携先に期待する役割と相談・連携内容、困難事象の経験を含めた。 結果: 578人から有効票を回収し、有効回収率は49.3%であった。認知症サポート医は、かかりつけ医、地域包括支援センター職員、行政機関職員から、認知症の診断と困難事例対応の全般的助言を期待され、かかりつけ医からはさらに抗認知症薬による薬物療法とBehavioral and Psychological Symptoms of Dementia: BPSDに対する薬物療法を期待されていた。また、認知症サポート医の困難事象経験値は認知症疾患医療センターと同等で、かかりつけ医の経験値よりも有意に高かった。一方で、認知症サポート医が相談・連携先として挙がる頻度は、認知症疾患医療センター、かかりつけ医と比較して低かった。 結論:認知症サポート医は、幅広い困難事象を抱える困難事例を扱っており、認知症の診断、薬物療法、他の専門職に対するスーパーバイズが期待されていること、一方で、相談・連携先としての優先度は低いことが明らかになった。多職種連携教育の中で認知症サポート医の役割と連携方法が周知され、彼らがもつ認知症診療のスキルが、困難事例をふくめた認知症者との共生社会の実現をめざす取り組みのなかで有効に活用されることが期待される。
- 独居認知症高齢者等の地域での暮らしを安定化・永続化するための研究厚生労働省:厚生労働科学研究費補助金(認知症政策研究事業)研究期間 : 2022年04月 -2025年03月代表者 : 粟田 主一; 岡村 毅; 津田 修治; 石山 麗子; 涌井 智子; 井藤 佳恵; 堀田 聰子; 大塚 理加; 菊地 和則; 桜井 良太; 石崎 達郎
- 日本学術振興会:科学研究費助成事業研究期間 : 2014年04月 -2018年03月代表者 : 菊地 和則; 池田 恵利子; 川端 伸子国の調査によると、2014年、15739人の高齢者が家族に虐待されたのに対して、施設職員に虐待された高齢者は300人しかいなかった。施設職員による虐待が行われた場合、市町村が対処しなければならない。我々は全市町村を対象とした郵送調査を実施した。日本には約1700の市町村があるが、3割以上の市町村はこれまでに施設職員による虐待に対処したことがない。 自治体が施設職員による虐待に対処する能力の向上に最も関連する要因は対処の経験を積むことであった。その他の要因は、市町村内の関係部署で連携すること、都道府県が実施する研修に参加すること、そしてマニュアルの準備であった。
- 日本学術振興会:科学研究費助成事業研究期間 : 2012年04月 -2014年03月代表者 : 菊地 和則; 石崎 達郎; 伊東 美緒養護者による高齢者虐待への対応においては、高齢者への医療や認知症ケアが必要とされるだけでなく、養護者への医療も必要になるなど医療機関との連携は欠かせない。しかし、医療機関の高齢者虐待対応への協力は十分とは言えない。 医療機関の虐待対応への協力を促進するため、東京都内の医療機関など関係機関を対象とした郵送調査を行った。その結果、医療機関が虐待対応に協力するためには「高齢者の医療費支払いの確保」、「養護者の脅し・暴力当があった場合の支援」、「医療同意を行う家族・親族の確保」、「区市町村判断による医療機関一時保護制度の創設」、「成年後見人の専任」などが必要とされていることが明らかとなった。
- 日本学術振興会:科学研究費助成事業研究期間 : 2009年 -2010年代表者 : 菊地 和則高齢者虐待防止法に基づき、養介護施設従事者等による高齢者虐待(以下、施設虐待)が生じた場合は市町村が事実確認調査や改善指導などを実施する。しかし、これまでの施設虐待の研究は虐待が生じた施設や虐待を行った職員に関するものが中心であり、施設虐待に対応する市町村を対象とした研究はほとんどない。本研究は、施設虐待に対応する市町村の実態と課題、市町村への支援の必要性を明らかにすることにより市町村の施設虐待への対応能力向上を図り、もって被虐待高齢者の権利擁護に資することを目的としている。上記の目的のため、平成21年12月に全市町村(特別区、政令指定都市の区を含む)1963ヶ所と都道府県を対象とした調査票を用いた郵送調査を実施した。その結果、市町村748票(有効票735票)、都道府県35票(有効票35票)の返送があった。 調査結果を分析して市町村の施設虐待への対応能力のために次の4つの提言をまとめた。 (1) 市町村および都道府県は、施設虐待に対応するための準備を可及的速やかに行うこと。 (2) 国は、虐待とはどのような行為を指すのかについての判断の指針を示すこと。 (3) 国は、未届け老人ホーム、養介護施設ではない病院・診療所、介護付き高齢者専用賃貸住宅などでの虐待に対して、市町村および都道府県が法令に基づいて対応できるように高齢者虐待防止法を改正すること。 (4) 国は、市町村と養介護施設が協力関係(市町村直営を含む)にある場合にも、適切に事実確認調査・改善指導等が実施されるような仕組みを検討すること。 そして調査結果を還元するために、提言および市町村と都道府県の調査結果を載せた報告書を作成し、国、都道府県、全市町村に送付した。
- 日本学術振興会:科学研究費助成事業研究期間 : 2007年 -2008年代表者 : 菊地 和則ケアマネジメントを行う多職種チームのチームアプローチ促進のためにはチームが「共有メンタルモデル」を獲得する必要がある。そのための手法として「チームマップ」を考案し、東京都内の3ヶ所の地域包括支援センターの協力を得て試行的研修を実施した。その結果、チームアプローチ促進のためチームマップを使用することの有用性は確認できたが、実際に使用するためには更なる改良が必要であることが示唆された。なお、「チームマップ」という用語については商標登録を行った。
- 日本学術振興会:科学研究費助成事業研究期間 : 2006年 -2008年代表者 : 大竹 登志子; 菊池 和則; 前川 佳史; 石井 賢二; 菊池 和則; 前川 佳史; 石井 腎二高齢者の排尿障害に対して,現状では泌尿器科あるいは婦人科外来で対応しているが,まだ十分とはいえない.そこで当事者本人がアクセス可能な「さわやか(排尿)相談室」を導入し,その効果をみた.成果として, 1)排尿状態の現状と本人の理解度と日常生活実態が分かりやくし,高齢者が記入しやすい冊子「さわやか日誌(排尿日誌)」と「高齢者排尿問題解決問診表(老研・大竹版)」を作成した. 2)個別の面談ケアにより,高齢者の排尿問題解決に面談ケア方法という手法が開発され,このシステムを東京都老人医療センターに導入した.
- 日本学術振興会:科学研究費助成事業研究期間 : 2006年 -2008年代表者 : 高橋 龍太郎; 杉原 陽子; 菊地 和則; 須田 木綿子; 出雲 祐二; 西村 昌記; 杉原 陽子; 菊地 和則; 須田 木綿子; 出雲 祐二; 西村 昌記要介護高齢者の在宅生活の限界点とその規定要因を明らかにすべく、東京都葛飾区および秋田県大館市の居住者を対象に、平成15年度、平成17年度に引き続き、1373組の要介護高齢者と家族主介護者の第3波追跡調査を平成19年度に行った。平成20年度はこの縦断データの解析と、研究者が直接インタビューを実施して得られた質的研究データについて分析を進め、今までに得られた結果をもとに協力者に向けたリーフレットを作成し送付した。また、第1波と第2波のデータを中心に、11章からなる研究成果の単行本の発刊を予定している。
- 日本学術振興会:科学研究費助成事業研究期間 : 2005年 -2006年代表者 : 菊地 和則平成18年4月の介護保険制度改正により、地域包括支援センターが設置された。地域包括支援センターでは保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員のチームアプローチが必要とされ、また、その業務の中には包括的・継続的ケアマネジメント支援があり、医療連携の重要性が指摘されている。 これらは全てチームアプローチがキーワードとなっているが、その重要性の指摘に比べて、実際にチームが機能するための取り組みは遅れていると言わざるを得ない。本研究は、欧米、特に米国で行われているチーム研究およびチームトレーニングに関する研究を援用し、ケアマネジメントを行う多職種チームのチームパフォーマンス向上に資する、チーム・トレーニング・プログラムを開発することを目的している。 チームトレーニングとは、チームワークに関する教育を統合的に行うために、各種ツールや教授法及び教育内容を一つにまとめたものであり、その教育内容がチームコンピテンシーである(Salas et al.2001)。チームコンピテンシーは、知識(Knowledge)、技術(Skill)そして態度(Attitude)の3次元から構成され、それぞれに複数の項目が設定されている。チームコンピテンシーについては重要な概念であるにも関わらず、我が国では一部の専門家を除いてほとんど知られていない。そのため、チームコンピテンシーについて理解を促進するためのテキストが必要とされる。平成17〜18年度の研究成果として、チームトレーニングの具体的な内容であるチームコンピテンシーを解説したテキストとなる報告書を作成した。特に、チームアプローチという現象を説明するために最も重要なコンピテンシーである「共有メンタルモデル」と、医師と他の専門職との指示関係による権威勾配の問題と関係し、多職種チームにとって中核的な課題である「意思決定」について詳細に述べた。
- 日本学術振興会:科学研究費助成事業研究期間 : 2003年 -2005年代表者 : 冷水 豊; 石川 久展; 菊地 和則研究目的1:高齢者のためのフォーマルケア(FC)の実状と問題点および今後の課題を、研究対象のC市全域レベルで明らかにする。成果:介護保険施行によってFCが大きく転換する時期にあって、C市におけるFCの新たな多くの課題とFCの対応の変化が明らかになった。また、高年住民のFCに対する将来不安や公的な在宅・施設サービスに対する利用選好がかなり高いことも明らかになった。 研究目的2:FCの推進を前提として、高齢者のための新たな住民主体のインフォーマルケア(IC)形成の可能性を、市全域およびその中の各地域レベルで明らかにする。成果:現状では、住民やボランティアによるICはまだ萌芽状態にあるが、高年住民の意識やフォーカスグループ面接調査におけるIC関係者の意向から見て、住民主体のIC形成の潜在的可能性がさまざまな面で大きいことが明らかになった。またそれらの可能性は、各地域レベルで多様に異なることも明らかになった。 研究目的3:「地域生活の質」の観点から高齢者のためのFCとICの適切な組み合わせ地域モデルを、地元のFC関係者およびIC関係者の参加を得て設計する。成果:「地域生活の質」については、先行研究が乏しい中で一定の概念整理をした上で「評価項目(C市版)」を試作してデルファイ法調査を行った結果、同市の高齢者ケアの現状と優先課題について、「地域生活の質」の観点から見た現実妥当性の高い評価が示された。FC/IC組み合わせ選好については、それが4種類のケアによって明確な差異があることが、高年住民の意識を通して明らかになった。また、デルファイ法調査結果を踏まえたフォーカスグループにおいて、優先課題ごとにFCおよびICによる対応を検討した結果、(1)主にFCで対応すべき課題、(2)主にICで対応すべき課題、(3)FCとICの双方が分担して対応すべき課題を、一定程度明らかにすることができた。
- 日本学術振興会:科学研究費助成事業研究期間 : 1997年 -1998年代表者 : 菊地 和則平成12年4月に施行される介護保険法ではケアマネジメントが居宅介護支援として制度上に位置づけられる。従って、保健・医療・福祉など分野の異なる専門職の協働・連携によるチームケアを円滑かつ効果的に行うことは重要な課題である。 しかし、多職種によるチームケアは様々な要因によって促進あるいは阻害されるため、またチームケアのアウトプットを客観的な指標で測ることが困難であったため、統計的な手法による調査は十分に行われてこなかった。そこで、探索的に多職種チームの実態とその機能に影響する要因を明らかにするため、社団法人日本社会福祉士会の協力を得て、会員に対して調査票を使用した郵送留め置き調査を行った。 多職種チームがどの程度に機能しているかにっていは自己評価法によって測っているので、一定の限界があるものと考えられるが、これまでのチーム研究で指摘されているチームの機能に関する要因が有意に影響していることが明らかになり、多職種チームにチーム理論を適用する可能性が示された。 チームに関する非常に多くの先行研究があるが、対人援助サービスを行う多職種チームについては、必ずしも十分な研究があるとは言えない。特に、実践現場で多職種チームを有効に機能させるために、介護支援専門員としての役割を期待されている社会福祉士などに、研修を通して多職種チームを機能させる手法を提供する研究が必要であることが分かった。