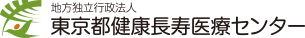研究者総覧
大澤 郁朗 (オオサワ イクロウ)
| |||
Last Updated :2025/04/05
研究者情報
学位
ホームページURL
科研費研究者番号
- 30343586
J-Global ID
研究キーワード
研究分野
- ライフサイエンス / 細胞生物学 / 細胞老化、分裂老化
- ライフサイエンス / 分子生物学
- ナノテク・材料 / 生物分子化学 / 水素分子
- ライフサイエンス / 栄養学、健康科学 / 老化、加齢科学、水素医学
- ライフサイエンス / 神経科学一般 / 神経変性疾患
経歴
- 2010年04月 - 現在 東京都健康長寿医療センター研究所生体調節機能研究研究副部長
- 2008年 :日本医科大学老人病研究所教授
- 2003年 :日本医科大学老人病研究所講師
- 2001年 :日本医科大学老人病研究所助手
- 2001年 : Researcher Associate, Institute of Gerontology, Nippon Med Sch
- 1994年 :国立精神・神経センター神経研究所代謝研究部ポスドク
- 1994年 : Researcher, National Institute of Neuroscience, NCNP,
- 1984年 :日本ゼオン株式会社研究員
- 1984年 : Researcher, Zeon Corporation
学歴
所属学協会
研究活動情報
論文
- Ruri Sugiyama; Junya Hanaguri; Harumasa Yokota; Akifumi Kushiyama; Sakura Kushiyama; Takako Kikuchi; Tsutomu Igarashi; Masumi Iketani; Ikuroh Ohsawa; Seiyo Harino; Hiroyuki Nakashizuka; Satoru Yamagami; Taiji NagaokaTranslational Vision Science & Technology 13 10 36 - 36 2024年10月
- Masumi Iketani; Mai Hatomi; Yasunori Fujita; Nobuhiro Watanabe; Masafumi Ito; Hideo Kawaguchi; Ikuroh OhsawaJournal of neurochemistry 2024年06月
- Toshiyuki Aokage; Masumi Iketani; Mizuki Seya; Ying Meng; Kohei Ageta; Hiromichi Naito; Atsunori Nakao; Ikuroh OhsawaExperimental gerontology 180 112270 - 112270 2023年09月
- Yasunori Fujita; Shoji Shinkai; Yu Taniguchi; Yuri Miura; Masashi Tanaka; Ikuroh Ohsawa; Akihiko Kitamura; Masafumi ItoThe journals of gerontology. Series A, Biological sciences and medical sciences 78 9 1701 - 1707 2023年08月
- 細胞外小胞上の前立腺特異的膜抗原(PSMA)測定系の構築と前立腺がんおよび腎がんにおける有用性の検討川上 恭司郎; 藤田 泰典; 加藤 卓; 梅澤 啓太郎; 津元 裕樹; 三浦 ゆり; 片桐 恭雄; 宮崎 龍彦; 大澤 郁朗; 水谷 晃輔; 伊藤 雅史基礎老化研究 47 2 88 - 88 日本基礎老化学会 2023年06月
- 経口水素水は2型糖尿病モデルマウスにおける網膜循環調節障害を改善させる杉山 瑠璃; 花栗 潤哉; 横田 陽匡; 櫛山 暁史; 櫛山 櫻; 菊池 貴子; 五十嵐 勉; 大澤 郁朗; 池谷 真澄; 張野 正誉; 山上 聡; 長岡 泰司日本眼科学会雑誌 127 臨増 205 - 205 (公財)日本眼科学会 2023年03月
- Masumi Iketani; Iwao Sakane; Yasunori Fujita; Masafumi Ito; Ikuroh OhsawaMedical gas research 13 3 133 - 141 2023年
- Tsutomu Igarashi; Ikuroh Ohsawa; Maika Kobayashi; Kai Miyazaki; Toru Igarashi; Shuhei Kameya; Asaka Lee Shiozawa; Yasuhiro Ikeda; Yoshitaka Miyagawa; Mashito Sakai; Takashi Okada; Iwao Sakane; Hiroshi TakahashiScientific reports 12 1 13610 - 13610 2022年08月
- Yasunori Fujita; Masumi Iketani; Masafumi Ito; Ikuroh OhsawaExperimental gerontology 165 111866 - 111866 2022年08月
- Mayu Yoneda; Jannatul Aklima; Ikuroh Ohsawa; Yoshihiro OhtaArchives of biochemistry and biophysics 720 109172 - 109172 2022年05月
- Yosuke Fukutani; Yuko Nakamura; Nonoko Muto; Shunta Miyanaga; Reina Kanemaki; Kentaro Ikegami; Keiichi Noguchi; Ikuroh Ohsawa; Hiroaki Matsunami; Masafumi YohdaInternational journal of molecular sciences 23 1 2021年12月
- Toshiyuki Aokage; Mizuki Seya; Takahiro Hirayama; Tsuyoshi Nojima; Masumi Iketani; Michiko Ishikawa; Yasuhiro Terasaki; Akihiko Taniguchi; Nobuaki Miyahara; Atsunori Nakao; Ikuroh Ohsawa; Hiromichi NaitoBMC pulmonary medicine 21 1 339 - 339 2021年10月
- Kyojiro Kawakami; Yasunori Fujita; Taku Kato; Kengo Horie; Takuya Koie; Keitaro Umezawa; Hiroki Tsumoto; Yuri Miura; Yasuo Katagiri; Tatsuhiko Miyazaki; Ikuroh Ohsawa; Kosuke Mizutani; Masafumi ItoScientific reports 11 1 15000 - 15000 2021年07月
- Taichi Fukunaga; Shuuichi Mori; Takuya Omura; Yoshihiro Noda; Yasunori Fujita; Ikuroh Ohsawa; Kazuhiro ShigemotoBiochemical and Biophysical Research Communications 540 116 - 122 2021年02月
- Ikuroh OhsawaCurrent pharmaceutical design 27 5 659 - 666 2021年
- Yasunori Fujita; Masafumi Ito; Ikuroh OhsawaArchives of biochemistry and biophysics 696 108668 - 108668 2020年12月
- Hiroko Hoshi; Fuka Monoe; Ikuroh Ohsawa; Shigeo Ohta; Takeshi MiyamotoBiochemical and biophysical research communications 527 1 270 - 275 2020年06月
- Takeshi Arima; Tsutomu Igarashi; Masaaki Uchiyama; Maika Kobayashi; Ikuroh Ohsawa; Akira Shimizu; Hiroshi TakahashiInternational journal of ophthalmology 13 8 1173 - 1179 2020年
- Tsutomu Igarashi; Ikuroh Ohsawa; Maika Kobayashi; Yusuke Umemoto; Takeshi Arima; Hisaharu Suzuki; Toru Igarashi; Toshiaki Otsuka; Hiroshi TakahashiAmerican journal of ophthalmology 207 10 - 17 2019年11月
- Yosuke Fukutani; Ryohei Tamaki; Ryosuke Inoue; Tomoyo Koshizawa; Shuto Sakashita; Kentaro Ikegami; Ikuroh Ohsawa; Hiroaki Matsunami; Masafumi YohdaThe Journal of biological chemistry 294 40 14661 - 14673 2019年10月
- Yasuhiro Terasaki; Mika Terasaki; Satoshi Kanazawa; Nariaki Kokuho; Hirokazu Urushiyama; Yusuke Kajimoto; Shinobu Kunugi; Motoyo Maruyama; Toshio Akimoto; Yoko Miura; Tsutomu Igarashi; Ikuroh Ohsawa; Akira ShimizuJournal of cellular and molecular medicine 23 10 7043 - 7053 2019年10月
- Mayu Kimura; Kanae Sasaki; Yosuke Fukutani; Hiderou Yoshida; Ikuroh Ohsawa; Masafumi Yohda; Kaori SakuraiBioorganic & medicinal chemistry letters 29 14 1732 - 1736 2019年07月
- Yasuhiro Terasaki; Tetsuya Suzuki; Kozue Tonaki; Mika Terasaki; Naomi Kuwahara; Jumi Ohsiro; Masumi Iketani; Mayumi Takahashi; Makoto Hamanoue; Yusuke Kajimoto; Seisuke Hattori; Hideo Kawaguchi; Akira Shimizu; Ikuroh OhsawaLaboratory investigation; a journal of technical methods and pathology 99 6 793 - 806 2019年06月
- Masumi Iketani; Kanako Sekimoto; Tsutomu Igarashi; Mayumi Takahashi; Masaki Komatsu; Iwao Sakane; Hiroshi Takahashi; Hideo Kawaguchi; Ritsuko Ohtani-Kaneko; Ikuroh OhsawaScientific reports 8 1 16822 - 16822 2018年11月
- Masumi Iketani; Kanako Sekimoto; tsutomu igarashi; Mayumi Takahashi; Masaki Komatsu; Iwao Sakane; Hiroshi Takahashi; Hideo Kawaguchi; Ritsuko Ohtani-Kaneko; Ikuroh OhsawaScientific Reports 8 1 16822 2018年11月 [査読有り]
- Kazuhide Takahashi; Yuri Miura; Ikuroh Ohsawa; Takuji Shirasawa; Mayumi TakahashiScientific reports 8 1 15585 - 15585 2018年10月
- Kiyomi Nishimaki; Takashi Asada; Ikuroh Ohsawa; Etsuko Nakajima; Chiaki Ikejima; Takashi Yokota; Naomi Kamimura; Shigeo OhtaCurrent Alzheimer Research 15 5 482 - 492 2018年
- Kazuhide Takahashi; Ikuroh Ohsawa; Takuji Shirasawa; Mayumi TakahashiExperimental gerontology 98 217 - 223 2017年11月
- Masumi Iketani; Jumi Ohshiro; Takuya Urushibara; Mayumi Takahashi; Tomio Arai; Hideo Kawaguchi; Ikuroh OhsawaSHOCK 48 1 85 - 93 2017年07月 [査読有り]
- Yayoi Murakami; Masafumi Ito; Ikuroh OhsawaPLOS ONE 12 5 2017年05月 [査読有り]
- Masumi Iketani; Ikuroh OhsawaCURRENT NEUROPHARMACOLOGY 15 2 324 - 331 2017年 [査読有り]
- Shingo Shimada; Kenji Wakayama; Moto Fukai; Tsuyoshi Shimamura; Takahisa Ishikawa; Daisuke Fukumori; Maki Shibata; Kenichiro Yamashita; Taichi Kimura; Satoru Todo; Ikuroh Ohsawa; Akinobu TaketomiARTIFICIAL ORGANS 40 12 1128 - 1136 2016年12月
- Tsutomu Igarashi; Ikuroh Ohsawa; Maika Kobayashi; Toru Igarashi; Hisaharu Suzuki; Masumi Iketani; Hiroshi TakahashiScientific reports 6 31190 - 31190 2016年08月
- Kazuhide Takahashi; Ikuroh Ohsawa; Takuji Shirasawa; Mayumi TakahashiEXPERIMENTAL GERONTOLOGY 81 65 - 75 2016年08月
- Masaya Ishigaki; Masumi Iketani; Maki Sugaya; Mayumi Takahashi; Masashi Tanaka; Seisuke Hattori; Ikuroh OhsawaMITOCHONDRION 28 79 - 87 2016年05月 [査読有り]
- Kumiko Nakata; Naoki Yamashita; Yoshihiro Noda; Ikuroh OhsawaMedical Gas Research 5 1 2015年01月 [査読有り]
- Nakashima Y; Ohsawa I; Nishimaki K; Kumamoto S; Maruyama I; Suzuki Y; Ohta SBMC Complement Altern Med. 14 1 - 9 2014年10月 [査読有り]
- Muto J; Lee H; Lee H; Uwaya A; Park J; Nakajima S; Nagata K; Ohno M; Ohsawa I; Mikami TScientific reports 4 4199 2014年02月 [査読有り]
- Kazuhide Takahashi; Yoshihiro Noda; Ikuroh Ohsawa; Takuji Shirasawa; Mayumi TakahashiExperimental Gerontology 58 146 - 153 2014年 [査読有り]
- Tsuyoshi Mitsuishi; Ikuroh Ohsawa; Toshihiko Kato; Nagayasu Egawa; Tohru KiyonoPLoS ONE 8 11 e79592 2013年11月 [査読有り]
- Kumpei Tanisawa; Eri Mikami; Noriyuki Fuku; Yoko Honda; Shuji Honda; Ikuro Ohsawa; Masafumi Ito; Shogo Endo; Kunio Ihara; Kinji Ohno; Yuki Kishimoto; Akihito Ishigami; Naoki Maruyama; Motoji Sawabe; Hiroyoshi Iseki; Yasushi Okazaki; Sanae Hasegawa-Ishii; Shiro Takei; Atsuyoshi Shimada; Masanori Hosokawa; Masayuki Mori; Keiichi Higuchi; Toshio Takeda; Mitsuru Higuchi; Masashi TanakaBMC genomics 14 248 - 248 2013年04月
- Akio Iio; Mikako Ito; Tomohiro Itoh; Riyako Terazawa; Yasunori Fujita; Yoshinori Nozawa; Ikuroh Ohsawa; Kinji Ohno; Masafumi ItoMedical gas research 3 1 6 - 6 2013年03月
- Ikuroh Ohsawa; Yasuhiro Terasaki; Yayoi MurakamiJOURNAL OF PHYSIOLOGICAL SCIENCES 63 S78 - S78 2013年
- Hoshi Hiroko; Hao Wu; Fujita Yoshinari; Funayama Atsushi; Miyauchi Yoshiteru; Hashimoto Kazuaki; Miyamoto Kana; Iwasaki Ryotaro; Sato Yuiko; Kobayashi Tami; Miyamoto Hiroya; Yoshida Shigeyuki; Mori Tomoaki; Kanagawa Hiroya; Katsuyama Eri; Fujie Atsuhiro; Kitagawa Kyoko; Nakayama Keiichi I; Kawamoto Toshihiro; Sano Motoaki; Fukuda Keiichi; Ohsawa Ikuroh; Ohta Shigeo; Morioka Hideo; Matsumoto Morio; Chiba Kazuhiro; Toyama Yoshiaki; Miyamoto TakeshiJournal of Bone and Mineral Research 27 9 2015 - 2023 2012年09月
- Yasuhiro Terasaki; Ikuroh Ohsawa; Mika Terasaki; Mikiko Takahashi; Shinobu Kunugi; Kang Dedong; Hirokazu Urushiyama; Shunsuke Amenomori; Mayuko Kaneko-Togashi; Naomi Kuwahara; Arimi Ishikawa; Naomi Kamimura; Shigeo Ohta; Yuh FukudaAMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-LUNG CELLULAR AND MOLECULAR PHYSIOLOGY 301 4 L415 - L426 2011年10月 [査読有り]
- Tsuyoshi Mitsuishi; Kenji Kabashima; Hideaki Tanizaki; Ikuroh Ohsawa; Fumino Oda; Yuko Yamada; Yilinuer Halifu; Seiji Kawana; Toshihiko Kato; Kazumi IidaJournal of Dermatological Science 63 3 184 - 190 2011年09月 [査読有り]
- Kamimura, N; Nishimaki, K; Ohsawa, I; Ohta, SObesity 19 7 1396 - 1403 2011年07月 [査読有り]
- Sanae Nakajima; Ikuroh Ohsawa; Shigeo Ohta; Makoto Ohno; Toshio MikamiBehavioural brain research 211 2 178 - 84 2010年08月
- Nakajima, S; Ohsawa, I; Ohta, S; Ohno, M; Mikami, TBehav Brain Res. 211 2 178 - 184 2010年08月 [査読有り]
- Alexander M Wolf; Sadamitsu Asoh; Hidenori Hiranuma; Ikuroh Ohsawa; Kumiko Iio; Akira Satou; Masaharu Ishikura; Shigeo OhtaThe Journal of nutritional biochemistry 21 5 381 - 9 2010年05月
- Tsuyoshi Mitsuishi; Yukie Iwabu; Kenzo Tokunaga; Tetsutaro Sata; Takehiko Kaneko; Kuniaki Ohara; Ikuroh Ohsawa; Fumino Oda; Yuko Yamada; Seiji Kawana; Kohji Ozaki; Mayuka Nakatake; Osamu YamadaBMC Cancer 10 2010年03月 [査読有り]
- Hideaki Oharazawa; Tsutomu Igarashi; Takashi Yokota; Hiroaki Fujii; Hisaharu Suzuki; Mitsuru Machide; Hiroshi Takahashi; Shigeo Ohta; Ikuroh OhsawaInvestigative ophthalmology & visual science 51 1 487 - 92 2010年01月
- I-Chien Wu; Ikuroh Ohsawa; Noriyuki Fuku; Masashi TanakaAnnals of the New York Academy of Sciences 1201 111 - 120 2010年 [査読有り]
- Hideaki Oharazawa; Tsutomu Igarashi; Takashi Yokota; Hiroaki Fujii; Hisaharu Suzuki; Mitsuru Machide; Hiroshi Takahashi; Shigeo Ohta; Ikuroh OhsawaInvestigative Ophthalmology and Visual Science 51 1 487 - 492 2010年01月 [査読有り]
- Endo Jin; Sano Motoaki; Katayama Takaharu; Hishiki Takako; Shinmura Ken; Morizane Shintaro; Matsuhashi Tomohiro; Katsumata Yoshinori; Zhang Yan; Ito Hideyuki; Nagahata Yoshiko; Marchitti Satori; Nishimaki Kiyomi; Wolf Alexander Martin; Nakanishi Hiroki; Hattori Fumiyuki; Vasiliou Vasilis; Adachi Takeshi; Ohsawa Ikuroh; Taguchi Ryo; Hirabayashi Yoshio; Ohta Shigeo; Suematsu Makoto; Ogawa Satoshi; Fukuda KeiichiCirculation Research 105 11 1118 - 1127 2009年11月
- Yuya Nakashima; Ikuroh Ohsawa; Fumiko Konishi; Takashi Hasegawa; Shoichiro Kumamoto; Yoshihiko Suzuki; Shigeo OhtaNeuroscience letters 464 3 193 - 8 2009年10月
- Naomi Nakashima-Kamimura; Takashi Mori; Ikuroh Ohsawa; Sadamitsu Asoh; Shigeo OhtaCancer chemotherapy and pharmacology 64 4 753 - 61 2009年09月
- Yoshihiko Suzuki; Motoaki Sano; Kentaro Hayashida; Ikuroh Ohsawa; Shigeo Ohta; Keiichi FukudaFEBS Letters 583 13 2157 - 2159 2009年07月 [査読有り]
- Sanae Nakajima; Ikuroh Ohsawa; Kazufumi Nagata; Shigeo Ohta; Makoto Ohno; Tetsuo Ijichi; Toshio MikamiBehavioural brain research 200 1 15 - 21 2009年06月
- Fu Y; Ito M; Fujita Y; Ito M; Ichihara M; Masuda A; Suzuki Y; Maesawa S; Kajita Y; Hirayama M; Ohsawa I; Ohta S; Ohno KNeuroscience letters 453 2 81 - 85 2009年04月 [査読有り]
- Yutaka Harita; Hidetake Kurihara; Hidetaka Kosako; Tohru Tezuka; Takashi Sekine; Takashi Igarashi; Ikuroh Ohsawa; Shigeo Ohta; Seisuke HattoriThe Journal of Biological Chemistry Vol.284 No.13 8951 - 8962 2009年03月 [査読有り]
- Yayoi Murakami; Ikuroh Ohsawa; Tadashi Kasahara; Shigeo OhtaNeurobiology of aging 30 2 325 - 9 2009年02月
- Kazufumi Nagata; Naomi Nakashima-Kamimura; Toshio Mikami; Ikuroh Ohsawa; Shigeo OhtaNeuropsychopharmacology : official publication of the American College of Neuropsychopharmacology 34 2 501 - 8 2009年01月
- Ikuroh Ohsawa; Kiyomi Nishimaki; Kumi Yamagata; Masahiro Ishikawa; Shigeo OhtaBiochemical and biophysical research communications 377 4 1195 - 8 2008年12月
- Minoru Kogiku; Ikuroh Ohsawa; Koushi Matsumoto; Yuichi Sugisaki; Hiroshi Takahashi; Akira Teramoto; Shigeo OhtaJournal of Clinical Neuroscience 15 11 1198 - 1203 2008年11月 [査読有り]
- Megumi Watanabe; Ken-ichiro Katsura; Ikuroh Ohsawa; Genki Mizukoshi; Kumiko Takahashi; Sadamitsu Asoh; Shigeo Ohta; Yasuo KatayamaBrain research 1238 199 - 207 2008年10月
- Kentaro Hayashida; Motoaki Sano; Ikuroh Ohsawa; Ken Shinmura; Kayoko Tamaki; Kensuke Kimura; Jin Endo; Takaharu Katayama; Akio Kawamura; Shun Kohsaka; Shinji Makino; Shigeo Ohta; Satoshi Ogawa; Keiichi FukudaBiochemical and Biophysical Research Communications 373 1 30 - 35 2008年08月 [査読有り]
- Ken-ichiro Katsura; Kumiko Takahashi; Sadamitsu Asoh; Megumi Watanabe; Makoto Sakurazawa; Ikuroh Ohsawa; Takashi Mori; Hironaka Igarashi; Seiji Ohkubo; Yasuo Katayama; Shigeo OhtaJournal of neurochemistry 106 1 258 - 70 2008年07月
- Ikuroh Ohsawa; Kiyomi Nishimaki; Yayoi Murakami; Yuko Suzuki; Masahiro Ishikawa; Shigeo OhtaThe Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience 28 24 6239 - 49 2008年06月
- Alexander M. Wolf; Sadamitsu Asoh; Ikuroh Ohsawa; Shigeo OhtaJournal of Nippon Medical School 75 2 66 - 67 2008年04月 [査読有り]
- Kei-ichi Fukuda; Sadamitsu Asoh; Masahiro Ishikawa; Yasuhiro Yamamoto; Ikuroh Ohsawa; Shigeo OhtaBiochemical and biophysical research communications 361 3 670 - 4 2007年09月
- Ikuroh Ohsawa; Masahiro Ishikawa; Kumiko Takahashi; Megumi Watanabe; Kiyomi Nishimaki; Kumi Yamagata; Ken-Ichiro Katsura; Yasuo Katayama; Sadamitsu Asoh; Shigeo OhtaNature medicine 13 6 688 - 94 2007年06月
- Shigeo Ohta; Ikuroh OhsawaJournal of Alzheimer's disease : JAD 9 2 155 - 66 2006年07月
- Suzuki Y; Ando F; Ohsawa I; Shimokata H; Ohta SJournal of human genetics 51 1 31 - 37 2006年 [査読有り]
- Ikuroh Ohsawa; Toshiyuki Aokage; Shigeo OhtaJournal of Nippon Medical School 72 3 136 2005年06月 [査読有り]
- Kentaro Sudo; Sadamitsu Asoh; Ikuroh Ohsawa; Daiya Ozaki; Kumi Yamagata; Hiromoto Ito; Shigeo OhtaBiochemical and biophysical research communications 330 3 850 - 6 2005年05月
- Masaki Uematsu; Ikuroh Ohsawa; Toshiyuki Aokage; Kiyomi Nishimaki; Kouji Matsumoto; Hiroshi Takahashi; Sadamitsu Asoh; Akira Teramoto; Shigeo OhtaJournal of Neuro-Oncology 72 3 231 - 238 2005年05月 [査読有り]
- Toshiyuki Aokage; Ikuroh Ohsawa; Shigeo OhtaJournal of Nippon Medical School 72 2 72 - 73 2005年04月 [査読有り]
- Ikuroh Ohsawa; Taiji Nishimura; Yukihiro Kondo; Go Kimura; Mitsuhiro Satoh; Ichiro Matsuzawa; Tsutomu Hamasaki; Shigeo OhtaJournal of Nippon Medical School = Nippon Ika Daigaku zasshi 71 6 379 - 83 2004年12月
- Shigeo Ohta; Ikuroh Ohsawa; Kouzin Kamino; Fujiko Ando; Hiroshi ShimokataAnnals of the New York Academy of Sciences 1011 36 - 44 2004年04月
- Toshiyuki Aokage; Ikuroh Ohsawa; Shigeo OhtaBiochemical and biophysical research communications 314 3 711 - 6 2004年02月
- Nakano K; Ohsawa I; Yamagata K; Nakayama T; Sasaki K; Tarashima M; Saito K; Osawa M; Ohta SMitochondrion 3 1 21 - 27 2003年08月 [査読有り]
- Ikuroh Ohsawa; Kiyomi Nishimaki; Chie Yasuda; Kouzin Kamino; Shigeo OhtaJournal of neurochemistry 84 5 1110 - 7 2003年03月
- Ikuroh Ohsawa; Kouzin Kamino; Keiko Nagasaka; Fujiko Ando; Naoakira Niino; Hiroshi Shimokata; Shigeo OhtaJournal of human genetics 48 8 404 - 409 2003年
- Sadamitsu Asoh; Ikuroh Ohsawa; Takashi Mori; Ken-Ichiro Katsura; Tomoharu Hiraide; Yasuo Katayama; Megumi Kimura; Daiya Ozaki; Kumi Yamagata; Shigeo OhtaProceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 99 26 17107 - 12 2002年12月 [査読有り]
- Haruhito Harada; Hisaki Nagai; Yoichi Ezura; Takashi Yokota; Ikuroh Ohsawa; Kenjiro Yamaguchi; Chiharu Ohue; Michiko Tsuneizumi; Iwao Mikami; Yoshie Terada; Aya Yabe; Mitsuru EmiGene 296 1-2 171 - 7 2002年08月
- I Ohsawa; C Takamura; S KohsakaJournal of Neurochemistry 76 5 1411 - 20 2001年03月 [査読有り]
- I Ohsawa; C Takamura; T Morimoto; M Ishiguro; S KohsakaThe European journal of neuroscience 11 6 1907 - 13 1999年06月 [査読有り]
- T Morimoto; I Ohsawa; C Takamura; M Ishiguro; Y Nakamura; S KohsakaThe Journal of Neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience 18 22 9386 - 93 1998年11月 [査読有り]
- S Koizumi; M Ishiguro; I Ohsawa; T Morimoto; C Takamura; K Inoue; S KohsakaBritish journal of pharmacology 123 8 1483 - 9 1998年04月 [査読有り]
- T Morimoto; I Ohsawa; C Takamura; M Ishiguro; S KohsakaJournal of neuroscience research 51 2 185 - 95 1998年01月 [査読有り]
- M Ishiguro; I Ohsawa; C Takamura; T Morimoto; S KohsakaBrain research. Molecular brain research 53 1-2 24 - 32 1998年01月 [査読有り]
- I Ohsawa; C Takamura; S KohsakaBiochemical and biophysical research communications 236 1 59 - 65 1997年07月 [査読有り]
- M Shinoda; K Toide; I Ohsawa; S KohsakaBiochemical and biophysical research communications 235 3 641 - 5 1997年06月
- I Ohsawa; Y Hirose; M Ishiguro; Y Imai; S Ishiura; S KohsakaBiochemical and biophysical research communications 213 1 52 - 8 1995年08月
- Fujisawa, Ayumi; Abe, Takaharu; Ohsawa, Ikuro; Kamogawa, Kouichi; Izumi, YoshikazuFEMS Microbiology Letters 110 1 1993年
- Fujisawa, Ayumi; Abe, Takaharu; Ohsawa, Ikuro; Shiozaki, Shozo; Kamogawa, Kouichi; Izumi, YoshikazuBioscience, Biotechnology and Biochemistry 57 5 1993年
- OHSAWA, I; T KISOU; K KODAMA; YONEDA, I; D SPECK; R GLOECKLER; Y LEMOINE; K KAMOGAWAJOURNAL OF FERMENTATION AND BIOENGINEERING 73 2 121 - 124 1992年 [査読有り]
- D Speck; I Ohsawa; R Gloeckler; M Zinsius; S Bernard; C Ledoux; T Kisou; K Kamogawa; Y LemoineGene 108 1 39 - 45 1991年12月 [査読有り]
- J Sabatié; D Speck; J Reymund; C Hebert; L Caussin; D Weltin; R Gloeckler; M O'Regan; S Bernard; C Ledoux; I Ohsawa; K Kamogawa; Y Lemoine; SW BrawnJournal of biotechnology 20 1 29 - 49 1991年08月 [査読有り]
- S W Brown; D Speck; J Sabatié; R Gloeckler; M O'Regan; J F Viret; Y Lemoine; I Ohsawa; T Kisou; K HayakawaJournal of chemical technology and biotechnology (Oxford, Oxfordshire : 1986) 50 1 115 - 21 1991年 [査読有り]
- R Gloeckler; I Ohsawa; D Speck; C Ledoux; S Bernard; M Zinsius; D Villeval; T Kisou; K Kamogawa; Y LemoineGene 87 1 63 - 70 1990年03月 [査読有り]
- M O'Regan; R Gloeckler; S Bernard; C Ledoux; I Ohsawa; Y LemoineNucleic acids research 17 19 8004 - 8004 1989年10月 [査読有り]
- I Ohsawa; D Speck; T Kisou; K Hayakawa; M Zinsius; R Gloeckler; Y Lemoine; K KamogawaGene 80 1 39 - 48 1989年08月 [査読有り]
MISC
- 大澤 郁朗 老年精神医学雑誌 33 (2) 175 -181 2022年02月
- 大澤 郁朗 日本病態生理学会雑誌 30 (2) 30 -30 2021年12月
- 青景 聡之; 池谷 真澄; 藤崎 宣友; 大澤 郁朗; 内藤 宏道; 中尾 篤典 日本救急医学会雑誌 32 (12) 1738 -1738 2021年11月
- 植松 賢司; 座波 清誉; 松本 浩; 野々山 恵章; 松本 直通; 齋藤 潤; 伊藤 正孝; 松本 志郎; 藤田 泰典; 大澤 郁朗 脳と発達 53 (Suppl.) S213 -S213 2021年05月
- 大澤 郁朗 ビタミン 95 (4) 251 -251 2021年04月
- 川上恭司郎; 藤田泰典; 加藤卓; 堀江憲吾; 古家琢也; 梅澤啓太郎; 津元裕樹; 三浦ゆり; 片桐恭雄; 宮崎龍彦; 大澤郁朗; 水谷晃輔; 水谷晃輔; 伊藤雅史 日本分子生物学会年会プログラム・要旨集(Web) 44th 2021年
- 横山茜; 横山茜; 小松真希; 小松真希; 池谷真澄; 藤田泰典; 川口英夫; 川口英夫; 大澤郁朗 日本分子生物学会年会プログラム・要旨集(Web) 44th 2021年
- 池谷真澄; 坂根巌; 坂根巌; 藤田泰典; 伊藤雅史; 大澤郁朗 日本分子生物学会年会プログラム・要旨集(Web) 44th 2021年
- 藤田泰典; 池谷真澄; 伊藤雅史; 大澤郁朗 日本分子生物学会年会プログラム・要旨集(Web) 44th 2021年
- 藤田泰典; 池谷真澄; 伊藤雅史; 大澤郁朗 日本ミトコンドリア学会年会要旨集 20th 2021年
- 【「ミトコンドリアダイナミクスと代謝調節」】複製老化プロセスにおけるミトコンドリアの変遷藤田 泰典; 大澤 郁朗 基礎老化研究 45 (1) 25 -30 2021年01月
- Ikuroh Ohsawa Current Pharmaceutical Design 27 (5) 759 -766 2021年
- 大村卓也; 福永大地; 森秀一; 河野真子; 野田義博; 藤田泰典; 大澤郁朗; 重本和宏 日本分子生物学会年会プログラム・要旨集(Web) 44th 2021年
- 重本和宏; 福永大地; 森秀一; 大村卓也; 野田義博; 藤田泰典; 大澤郁朗 日本生化学会大会(Web) 94th [1S05m -01] 2021年
- Yasunori Fujita; Masafumi Ito; Ikuroh Ohsawa Archives of Biochemistry and Biophysics 696 2020年12月
- 水素吸入療法は間質性肺炎遠隔期の呼吸機能を温存する ブレオマイシン処理マウスを用いた研究青景 聡之; 平山 隆浩; 池谷 真澄; 大澤 郁朗; 内藤 宏道; 中尾 篤典 日本救急医学会雑誌 31 (11) 1644 -1644 2020年11月
- ミトコンドリアのシアン耐性電子伝達の検討田中 日菜子; 志田 枝実香; 大澤 郁朗; 太田 善浩 日本生化学会大会プログラム・講演要旨集 93回 [3Z02 -268)] 2020年09月
- 急性肺傷害に対する治療開発 水素吸入療法の炎症・線維化の抑制効果 マウスを用いた検証青景 聡之; 池谷 真澄; 瀬谷 瑞樹; 平山 隆浩; 石川 倫子; 内藤 宏道; 大澤 郁朗; 中尾 篤典 日本集中治療医学会雑誌 27 (Suppl.) 476 -476 2020年09月
- 大澤 郁朗 神経治療学 37 (3) 344 -347 2020年05月
- 水素ガス 臨床における期待大澤 郁朗 臨床麻酔 44 (臨増) 251 -260 2020年03月
- 小松真希; 小松真希; 池谷真澄; 藤田泰典; 川口英夫; 大澤郁朗 日本分子生物学会年会プログラム・要旨集(Web) 43rd 2020年
- 池谷真澄; 坂根巌; 藤田泰典; 伊藤雅史; 大澤郁朗 日本分子生物学会年会プログラム・要旨集(Web) 43rd 2020年
- 大澤郁朗 神経治療学(Web) 37 (3) 2020年
- 大澤 郁朗 神経治療学 36 (6) S116 -S116 2019年10月
- 分子状水素による多様な疾患への多機能効果の分子機構 CD36を介したマクロファージの制御による分子状水素の血管老化制御池谷 真澄; 小松 真希; 藤田 泰典; 川口 英夫; 伊藤 雅史; 大澤 郁朗 日本生化学会大会プログラム・講演要旨集 92回 [3S12a -04] 2019年09月
- 分子状水素による多様な疾患への多機能効果の分子機構 分子状水素による酸化ストレス防御の分子機構大澤 郁朗 日本生化学会大会プログラム・講演要旨集 92回 [3S12a -05] 2019年09月
- 大澤 郁朗 Geriatric Medicine 57 (8) 791 -795 2019年08月
- 池谷 真澄; 関本 香奈子; 小松 真希; 高橋 眞由美; 金子 律子[大谷]; 川口 英夫; 大澤 郁朗 基礎老化研究 43 (2) 91 -91 2019年06月
- 小松 真希; 池谷 真澄; 高橋 眞由美; 羽富 舞; 川口 英夫; 大澤 郁朗 基礎老化研究 43 (2) 97 -97 2019年06月
- 大澤 郁朗 基礎老化研究 43 (2) 107 -108 2019年06月
- 安齋政幸; 安齋政幸; 野田義博; 石渡俊行; 大澤郁朗; 東里香; 山鹿優真; 山崎脩杜; 佐藤翔太; 斎藤勝彦; 尾崎美樹; 安達那央子 日本野生動物医学会大会・講演要旨集 25th 2019年
- 大澤郁朗 神経治療学(Web) 36 (6) 2019年
- 単一ミトコンドリアイメージングによるクリステ構造安定化機構の研究米田 真由; 柴田 貴弘; 大澤 郁朗; 太田 善浩 バイオイメージング 27 (2) 82 -82 2018年08月
- clk-1トランスジェニックマウスにおける筋ミトコンドリア機能低下と寿命延長高橋 真由美; 野田 義博; 大澤 郁朗; 白澤 卓二; 高橋 和秀 日本老年医学会雑誌 52 (Suppl.) 162 -162 2015年05月
- 大城樹実; 大城樹実; 鈴木徹也; 鈴木徹也; 寺崎泰弘; 渡名喜梢; 渡名喜梢; 池谷真澄; 高橋眞由美; 川口英夫; 服部成介; 大澤郁朗 基礎老化研究 39 (2) 2015年
- 高橋真由美; 野田義博; 大澤郁朗; 白澤卓二; 高橋和秀 基礎老化研究 39 (2) 60 -60 2015年
- 寺崎泰弘; 大澤郁朗; 鈴木徹也; 渡名喜梢; 漆山博和; 寺崎美佳; 功刀しのぶ; 福田悠; 清水章 日本病理学会会誌 103 (1) 2014年
- 野田義博; 中田久美子; 倉本和直; 遠藤玉夫; 山下直樹; 大澤郁朗 Journal of Mammalian Ova Research 31 (2) S82 -S82 2014年
- 鈴木徹也; 寺崎泰弘; 渡名喜梢; 大澤郁朗 基礎老化研究 37 (2) 2013年
- 寺崎泰弘; 大澤郁郎; 寺崎美佳; 高橋美紀子; 功刀しのぶ; 康徳東; 漆山博和; 雨森俊介; 富樫真由子; 福田悠 日本病理学会会誌 100 (1) 2011年
- ラット網膜虚血再灌流モデルにおける水素点眼による神経保護効果小原澤 英彰; 五十嵐 勉; 横田 隆; 藤井 博明; 鈴木 久晴; 町出 充; 高橋 浩; 太田 成男; 大澤 郁朗 日本眼科学会雑誌 114 (臨増) 312 -312 2010年03月
- 西槙貴代美; 大澤郁朗; 永田和史; 村越徳英; 太田成男 日本分子生物学会年会講演要旨集 32nd (Vol.3) 2009年
- Takaharu Katayama; Motoaki Sano; Jin Endo; Kentaro Hayashida; Tomohiro Matsuhashi; Satori Tokudome; Toshimi Kageyama; Shinsuke Yuasa; Takeshi Adachi; Makoto Suematsu; Kiyomi Nishimaki; Ikuroh Ohsawa; Shigeo Ohta; Satoshi Ogawa; Keiichi Fukuda CIRCULATION 118 (18) S320 -S320 2008年10月
- Kentaro Hayashida; Motoaki Sano; Ikuroh Ohsawa; Ken Shinmura; Kayoko Tamaki; Kensuke Kimura; Jin Endo; Shigeo Ohta; Keiichi Fukuda; Satoshi Ogawa JOURNAL OF CARDIAC FAILURE 14 (7) S168 -S168 2008年09月
- Kentaro Hayashida; Motoaki Sano; Ikuro Ohsawa; Ken Shinmura; Kayoko Tamaki; Kensuke Kimura; Jin Endo; Takaharu Katayama; Shigeo Ohta; Satoshi Ogawa; Keiichi Fukuda CIRCULATION RESEARCH 103 (5) E59 -E60 2008年08月
- Alexander M. Wolf; Sadamitsu Asoh; Ikuroh Ohsawa; Shigeo Ohta BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-BIOENERGETICS 1777 S58 -S58 2008年07月
- 永田和史; 上村尚美; 三上俊夫; 大澤郁朗; 大澤郁朗; 太田成男 生化学 2008年
- Ohta, S; Ohsawa, I J. Alzheimer’s Dis. 9 (2) 155 -166 2006年
産業財産権
- 特開2021-075507:p16INK4a及び/又はp21の発現抑制剤 2021年05月20日坂根 巌, 大澤 郁朗, 池谷 真澄 株式会社 伊藤園, 地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター 202103006031327104
- 高橋 浩, 大澤 郁朗, 五十嵐 勉 高橋 浩, 大澤 郁朗, 五十嵐 勉 202003009845277517
- 山下 直樹, 中田 久美子, 大澤 郁朗 山下 直樹, 地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター 201903003817876074
- 太田 成男, 大澤 郁朗, 室田 渉 太田 成男 201303018962206314
- 太田 成男, 大澤 郁朗, 西槙 貴代美 株式会社マイトス 201103064869121691WO2005/020681
- 特開2009-114084:水素分子を含む神経新生を促進する組成物 2009年05月28日太田 成男, 大澤 郁朗 太田 成男, 株式会社マイトス 200903055403493010
- 特開2008-292424:腫瘍の検出方法 2008年12月04日太田 成男, 大澤 郁朗 学校法人日本医科大学 200903089524577654
- WO2008-026785:水素分子を含む脂質代謝改善剤 2008年03月06日太田 成男, 室田 渉, 大澤 郁朗 太田 成男, 室田 渉 201003024937134099
- 特開2004-138522:腫瘍診断剤およびその用途 2004年05月13日太田 成男, 大澤 郁朗, 瀬川 辰也, 木下 憲明 株式会社 免疫生物研究所 200903090730230740
- 斉藤 修治, 大川 節子, 佐伯 早木子, 大澤 郁朗, 船戸 洋乃, 入谷 好一, 青山 茂美, 高橋 清人 日本ゼオン株式会社 201103001369260677
- 特開平7-099978:新規な組み換えベクター、および組み換えマイコプラズマとその製造方法 1995年04月18日大澤 郁朗, 高橋 美穂, 鴨川 幸市 日本ゼオン株式会社 200903087546520025特開平7-99978
- ビオチン合成酵素をコードする遺伝子とその利用特開昭63-44889
- ビオチン抑制解除菌選択プラスミド、それを用いたビオチン抑制解除菌選択方法特開平3-247289
- 生体内の有害なフリーラジカル除去剤特願2005-238572
共同研究・競争的資金等の研究課題
- 日本学術振興会:科学研究費助成事業 基盤研究(C)研究期間 : 2022年04月 -2025年03月代表者 : 松本 浩; 大澤 郁朗; 鈴木 郁郎
- 日本学術振興会:科学研究費助成事業 基盤研究(C)研究期間 : 2022年04月 -2025年03月代表者 : 大澤 麻登里; 松本 浩; 大澤 郁朗
- 日本学術振興会:科学研究費助成事業 基盤研究(C)研究期間 : 2022年04月 -2025年03月代表者 : 青景 聡之; 大澤 郁朗; 中尾 篤典
- 日本学術振興会:科学研究費助成事業 基盤研究(C)研究期間 : 2021年04月 -2024年03月代表者 : 河田 光弘; 大澤 郁朗急性大動脈解離発症に伴い、全身性炎症反応症候群が起こり、サイトカインストームに至り、急性肺障害・肺酸素化障害を引き起こす。分子状水素(H2)の投与では、多くの非感染性炎症においてサイトカインストームの抑制効果が報告されている。 本研究では、保存的治療が主となる急性大動脈解離Stanford B型でのH2ガス吸入療法の確立を目指す。大動脈解離の動物モデルを用いて、H2ガスの最適な投与方法、ガス濃度、投与期間を明らかにする。次に急性大動脈解離で重篤な合併症が無い患者を対象に、標準的内科治療にH2ガス吸入療法を併用することにより抗炎症作用で肺酸素化障害を軽減、予防できるか検討する。 令和3年度については、倫理委員会などの諸手続きが完了し、水素ガス吸引療法に必要な混合ガス吸入装置、水素ガス濃度計、安全装置などのセットが完了して、既に数名の急性大動脈解離Stanford B型患者について投与試験を開始し次年度も引き続き研究進行していく。
- 日本学術振興会:科学研究費助成事業 基盤研究(B)研究期間 : 2020年04月 -2023年03月代表者 : 野々山 恵章; 松本 浩; 大澤 郁朗; 大澤 麻登里; 關中 悠仁Chediak東症候群(CHS)は神経変性および免疫不全を呈する疾患である。原因遺伝子はLYSTであるが、神経変性の発症機序は不明である。本研究ではChediak東症候群(CHS)患者6症例からiPS細胞を樹立し、神経細胞に分化させた。6症例のLYST遺伝子変異は全て異なっていたが、5症例で神経症状があり1例は幼児のため神経症状は解析不能であった。
分化誘導した神経細胞で、細胞内小器官であるリソソーム、ミトコンドリア、オートファゴソームの解析を行った。その結果、蛍光顕微鏡および電子顕微鏡による解析で、リソソームでは、巨大化、PAS染色陽性物質の沈着、細胞内部のフィラメント様構造および黒色顆粒の出現などの形態異常を認めた。機能解析ではカルシウム依存性エキソサイトーシス障害を認めた。ミトコンドリアでは、電子顕微鏡の解析で、形態の不整、肥大化、内部の黒色顆粒を認めた。また核周囲への局在化、分布異常も認めた。オートファゴソームについては、DAP Green染色による蛍光顕微鏡の解析で輝度の亢進および閾値以上の細胞の割合の増加を認めた。
以上の結果から、Chediak東症候群(CHS)では細胞内小器官の異常があることを明らかにした。このことから、Chediak東症候群(CHS)の神経細胞では、リソソーム機能異常により異常な細胞内小器官および老廃物の処理ができず細胞内に蓄積し、これにより神経障害が発症することが示唆された。 - 日本学術振興会:科学研究費助成事業 基盤研究(B)研究期間 : 2020年04月 -2023年03月代表者 : 大澤 郁朗; 藤田 泰典; 池谷 真澄; 伊藤 雅史本研究はH2による健康長寿促進を目指して、三つの問いを解明するための包括的研究である。第一の研究では、培養細胞系を中心にリピドームとメタボローム解析から、神経芽細胞SH-SY5Yを水素存在下で培養すると、1時間後にはカルジオリピンなどの特定のリン脂質が上昇し、同時にエネルギー代謝経路が広く抑制されることが判明した。この変化は一過的であり、その間にグルタチオンの低下など酸化ストレスの上昇が認められた。これがミトホルミシスなどの細胞防御機構を誘導することがH2の作用機序の一つであることを示しすことができた。さらに細胞死を抑制する機序については、水素ガス吸入による幼弱マウスの麻酔ガス吸入時脳細胞死抑制効果を確認し、その脳内で細胞死シグナル変化を解析している。第二の研究については、デキストラン硫酸塩投与の大腸炎モデルマウスで、水素水を1日1回投与するだけで病態が緩和された。デキストラン硫酸塩投与は小腸パイエル板でFoxp3の発現を減少し、Il6の発現を上昇させる。水素水の飲用はこれを抑制したことから、IL-6の抑制によって制御性T細胞の恒常性が維持されたものと考えられる。H2が免疫恒常性に関与するメカニズムについてさらに解析中である。第三の研究については、倫理委員会などの諸手続きが完了し、水素ガス吸引療法に必要な混合ガス吸入装置、水素ガス濃度計、安全装置などのセットが完了して、既に数名の急性大動脈解離患者について投与試験を完了し引き続き研究進行中である。
- 日本学術振興会:科学研究費助成事業 基盤研究(C)研究期間 : 2019年04月 -2022年03月代表者 : 青景 聡之; 中尾 篤典; 大澤 郁朗; 宮原 信明; 石川 倫子実験3:間質性肺炎モデルに対する水素ガス投与21日後の呼吸生理学評価。ブレオマイシン気管内投与後、21日間3.2% 水素を投与し、線維化期の呼吸生理学評価を行った。肺胞コンプライアンス(ml/cmH2O)は、コントロール(C)群0.069 ±0.003、水素投与なし(A)群0.039±0.010、水素投与あり(H)群0.052±0.009であり、水素ガス投与により、慢性期の肺胞コンプライアンスの低下を抑制した(p=0.009)。 実験4:間質性肺炎モデルに対する水素ガス投与による肺内IL-6、IL-4、IL-13値と、M2マクロファージ数の評価。炎症性サイトカインのmRNAレベルをブレオマイシン投与7日後に評価した。IL-6、IL-4、IL-13は、H群がA群よりも有意に低かった。H群の肺胞間質に存在するM2マクロファージは、A群に比べて有意に少なかった(3.1%[95%CI:1.6%~4.5%]対1.1%[95%CI:0.3%~1.8%]、p=0.008)。 実験1-4より、水素吸入により、間質性肺炎より21日後の肺線維化抑制、肺生理機能の温存が認められ、その効果は、2型サイトカイン(IL-4、IL13)の発現抑制と、M2マクロファージの分化抑制が関与していることが示唆された。 上記の研究結果は、第48回日本救急医学会総会(2020/11/18-21)にて報告した。
- 日本学術振興会:科学研究費助成事業 基盤研究(C)研究期間 : 2017年04月 -2022年03月代表者 : 野田 義博; 大澤 郁朗本研究は、近年報告された分子状水素(H2)の医療への応用(水素分子医学)という革新的な研究の一端である。生殖医療におけるH2の応用研究は、本申請時点で申請者の研究グループ以外からの報告はまだない。このため、精子への酸化ストレス障害と、それにより引き起こされる受精能の低下をH2が改善できるか確かめる本研究の独創性は極めて高い。現在までの研究成果より、マウス精子に過酸化水素を添加することで精子の運動機能低下を誘導する酸化ストレス障害モデル精子の実験系を確立した。そして、これにより生じる精子運動機能、体外受精による受精率および胚移植による個体発生率の低下に対するH2の抑制効果を検証した。その結果、H2は酸化ストレス障害を受けたマウス精子の運動機能改善効果を呈した。さらに、精子の機能低下とミトコンドリア活性に着目し、形態学的な観察と蛍光プローブを用いたミトコンドリアの構造解析について検討した。そして、ミトコンドリアの呼吸活性についても更なる検討を進めた。本研究は臨床の観点からも極めて高い意義を持つ。不妊治療では可能な限り体外受精(IVF)が選択される。H2による精子運動性の活性化がIVFによる受精率向上につながれば、安全で効果的な新しい男性不妊治療法となりうる。また、凍結保存精子の出生率改善も期待できる。このように、本研究の遂行により、薬剤治療の困難な 「生殖医療」に安全性の高いH2を応用が、社会的問題となっている高齢出産における不妊を始めとした諸問題の解決への基盤となる知見を得ることができる。
- 日本学術振興会:科学研究費助成事業 基盤研究(C)研究期間 : 2018年04月 -2021年03月代表者 : 池谷 真澄; 大澤 郁朗水素分子(H2)は体内に取り込むと抗酸化・抗炎症作用を発揮することが知られているが、作用機序は不明な部分が多い。今回の研究で、細胞にわずか1時間H2を曝露するだけで細胞膜を構成するリン脂質が変化することが明らかになった。細胞小器官のミトコンドリアやエンドソームで機能することが知られるリン脂質の増加が見られた。それぞれ、疾患との関係が密接な細胞小器官である。ミトコンドリアが関係する代謝に変化が無いか調べた所、多くの代謝産物がH2曝露1時間で低下しており、一過的な酸化ストレスが誘導されていた。またエンドソームを調べたところエンドソーム輸送の遅滞が起こることが分かった。
- 日本学術振興会:科学研究費助成事業 基盤研究(B)研究期間 : 2016年04月 -2019年03月代表者 : 大澤 郁朗; 伊藤 雅史多様な疾患防御機能を示す水素分子の作用機序にはミトホルミシス効果による酸化ストレス障害防御システムの誘導があることを細胞実験で突き止めた。これは従来の水素分子による活性酸素種還元とは異なる。敗血症モデル動物においても水素水の飲用は予防的に働いた。さらに水素水による抗酸化、抗炎症効果により抗がん剤副作用で増悪された急性肺障害が抑制されること、高脂肪による血管老化が抑制されることを明らかにした。
- 日本学術振興会:科学研究費助成事業 挑戦的萌芽研究研究期間 : 2015年04月 -2018年03月代表者 : 大澤 郁朗; 本田 修二; 池谷 真澄ミトコンドリアは老化と寿命制御の中核的オルガネラである。各呼吸鎖複合体はクリステ膜上に存在するが、その構造は200 nmの光学限界以下である為、そのダイナミズムとミトコンドリア機能との相関は不明である。本研究では、超解像STED顕微鏡を用いて、膜電位感受性色素(TMRM)で染色したミトコンドリアの内部構造(内膜クリステ)変化を数10 nmの解像度で経時的に観察する手法を確立した。さらに各呼吸鎖複合体のサブユニットを蛍光タンパク質でラベルしてクリステ上での局在を観察したところ、複合体IとIII、IVが近接したスーパーコンプレックスの存在を示唆する画像を得ることができた。
- 日本学術振興会:科学研究費助成事業研究期間 : 2014年04月 -2017年03月代表者 : 高橋 浩; 大澤 郁郎; 五十嵐 勉; 金田 誠内眼手術と酸化ストレスの関連では、白内障超音波乳化吸引術(PEA)における角膜内皮障害の原因としてフリーラジカル特にヒドロキシラジカル(・OH)の関与が示唆されてきた。水素ガスがPEAにおける酸化ストレス障害から保護できるか検討を行った。ウサギを用い前房内でPEAを行い、水素含有眼内灌流液と通常の眼内灌流液の比較検討を行った。5時間後、角膜を摘出し、角膜浮腫、酸化ストレスマーカーのリアルタイムPCRと免疫染色を行った。角膜浮腫は有意に減少し、酸化ストレスマーカーも水素群で有意に減少した。今回の研究により、水素含有眼内灌流液はPEA由来の酸化ストレスから角膜内皮保護する結果を証明した。
- 日本学術振興会:科学研究費助成事業 基盤研究(B)研究期間 : 2013年04月 -2016年03月代表者 : 嶋村 剛; 武冨 紹信; 深井 原; 木村 太一; 西川 祐司; 大澤 郁朗ラット正常肝、脂肪肝を用いて、新規臓器保存液、新規灌流液、低温酸素化灌流、水素ガスの併用治療の有効性を確認し、Proof of Concept を得ることができた。低温酸素化灌流の課題である、灌流中の門脈抵抗上昇やグラフト膨張を抑制した画期的な方法論を確立することに成功した。しかしながら、当初の目的であった脂肪肝の修復は完全には達成できなかった。その原因として心停止肝の胆管障害が挙げられ、動脈灌流も必要と考えられた。
- 日本学術振興会:科学研究費助成事業 基盤研究(C)研究期間 : 2012年04月 -2015年03月代表者 : 大澤 郁朗疾患の新規治療法として水素分子(H2)投与の可能性が数多く示されてきた。しかし、反応性の高い活性酸素種のみを無毒化するというH2の選択的還元作用のみで多様な疾患抑制効果を説明することは困難である。本研究では、H2存在下で培養した神経芽細胞SH-SY5Yが酸化ストレスにたいして抵抗性を獲得することを明らかにした。H2がミトコンドリアを活性化すると共に軽度の酸化ストレスが細胞に負荷され、Nrf2の活性化により抗酸化酵素類の発現が増加した。このような適応応答あるいはミトホルミシス効果が,水素水などを投与した場合の多様な疾患抑制効果に結びついているものと考えられる。
- 日本学術振興会:科学研究費助成事業 基盤研究(C)研究期間 : 2010年 -2012年代表者 : 寺崎 泰弘; 大澤 郁朗; 福田 悠; 寺崎 美佳多様な呼吸器疾患の病態には酸化ストレス関与が強く示唆されているが、水素分子(H2)の抗酸化作用はハイドロキシラジカル(-OH)などの酸化力が強い活性酸素種への選択的還元性と高い生体膜通過性を特徴としている。今回-OHが主な傷害活性酸素種である放射線肺障害やイレッサ薬剤性肺障害モデルとなる培養細胞、マウスを用いたモデル実験においてH2処理はいずれも抗酸化、傷害抑制効果をもたらした。副作用の少ない独創的な抗酸化剤としてその臨床応用が期待される。
- 日本学術振興会:科学研究費助成事業 基盤研究(C)研究期間 : 2009年 -2011年代表者 : 小原澤 英彰; 大澤 郁朗ラット網膜虚血-再灌流モデルを用い、網膜虚血-再灌流時の酸化ストレス障害に対して水素分子(H_2)点眼液が網膜の神経保護効果があるかを検討した。H_2点眼液投与群と生理食塩水投与群で比較検討した。H_2点眼液投与群では、酸化ストレスマーカー陽性およびTUNEL陽性細胞が有意に減少しており、網膜神経細胞の障害を抑制することが確認された。また、グリオーシスを伴う網膜厚の菲薄化も抑制され、H2点眼液が網膜の神経保護に有効であることが確認された。
- 日本学術振興会:科学研究費助成事業 基盤研究(B)研究期間 : 2008年 -2010年代表者 : 太田 成男; 大澤 郁朗; 上村 尚美生活習慣病の原因のひとつは酸化ストレスであり、酸化ストレス軽減によって、生活習慣病の改善と予防が期待される。水素分子は、新しい概念の抗酸化物質であり、生活習慣病への予防効果が期待される。本研究では、認知症モデルマウス、動脈硬化モデルマウス、糖尿病・高脂血症モデル動物に水素分子を溶解した水を自由摂取させることにより、その改善効果と予防効果があることを明らかにした。
- 日本学術振興会:科学研究費助成事業 基盤研究(C)研究期間 : 2008年 -2010年代表者 : 大澤 郁朗; 太田 成男; 三上 俊夫本研究は、うつ病などを含む気分障害のモデルとなるストレス負荷動物に対して酸化ストレスの効果的な抑制剤である水素分子を投与することで、ストレスによって生じる酸化ストレスを抑制、海馬におけるニューロン新生の低下を回復し、海馬に依存した認知・記憶障害やうつ症状の抑制について検討するものである。主要な結果は、Neuropsycopharmacology誌で報告した。マウスに6週間、1日10時間の拘束ストレスを負荷し、水素を飽和量含有する水(水素水)を与える実験を行った。水迷路テスト、受動回避テスト、新奇物体探索テストの結果から、ストレスで生じた認知・記憶障害が水素水の投与により抑制されることが判明した。また、拘束により海馬歯状回における神経前駆細胞新生低下が認められたが、これも水素水の投与群では抑制されていた。さらに拘束ストレスによって蓄積する海馬領域の酸化ストレス(4-HNEやMDAを指標とした)は、水素水の投与により抑制されていた。一方、複数のストレスを組み合わせて与えるうつモデルでは水素水の効果を検証できなかった。しかし、このモデルでも神経前駆細胞新生低下が水素水の投与で抑制されたことから、神経細胞に対する水素の効果について分子機構を培養細胞で詳細に検討中である。
- 日本学術振興会:科学研究費助成事業 基盤研究(C)研究期間 : 2008年 -2010年代表者 : 上村 尚美; 大澤 郁朗; 太田 成男酸化ストレスは、糖尿病を誘発する原因のひとつと考えられている。一方、活性酸素種の中には、一酸化窒素のように生理作用に必要なものもある。従って、抗酸化物質を摂取する場合、有害な活性酸素種のみを除去し、生理作用に必要な活性酸素種を損なわないようにしなければならない。本研究では、糖尿病モデルマウスにおいて、水素分子を摂取することにより肝臓での酸化ストレスが軽減し高血糖や肥満の改善効果が得られることが明らかとなった。
- 日本学術振興会:科学研究費助成事業 萌芽研究研究期間 : 2007年 -2008年代表者 : 太田 成男; 大澤 郁朗組織が虚血再灌流(I/R)に曝露されると、再灌流の早期段階でROSが大規模に生成され、肝、脳、心臓および腎など様々な臓器の組織に深刻な障害を引き起こす。これまで酸化ストレスによる1/R傷害は基礎研究および臨床研究の重要な焦点とされてきた。 I/R誘発性臓器障害の考えられる基礎的な機序は、多くの因子が関与し、相互依存的であり、低酸素症、炎症反応およびフリーラジカル障害に関与している。I/R傷害の病因は未だ解明されていないが、酸素フリーラジカルが重要な役割を担っていることは明らかである。それゆえI/R傷害への臨床的対応としては、フリーラジカル・スカベンジャーが実用的であると考えられている。実際に、これまでにもnicaraven, MCL-186,MESNA,およびαトコフェロールとGdCl_3などの多くの薬剤が、I/R傷害を予防するためのスカベンジャーとして試みられてきた。 私たちは、2007年に水素分子がラットの中脳動脈閉塞モデルを用いた研究で、水素分子が治療的抗酸化活性を呈することを報告した。また、昨年は、肝臓の虚血再灌流障害が、水素ガス吸引によって軽減されること、ヘリウムでは効果がなかったことを示した。虚血再灌流障害で、最も患者が多く、適用可能性が高いのは心筋梗塞であると予測されるので、心筋の虚血再灌流障害に対する水素ガスの吸引効果をラットモデルを用いて調べた。 結果は、水素ガスを吸引させると虚血状態でも心臓内に水素が浸透しることが確認できた。また、心筋梗塞モデルラットで水素ガスを吸引させることで、梗塞層が小さくなり、心機能の低下も抑制された。分離した心臓を用いても虚血再灌流障害を水素は抑制することが明らかとなった。
- 日本学術振興会:科学研究費助成事業 特定領域研究研究期間 : 2006年 -2007年代表者 : 太田 成男; 大澤 郁朗; 上村 尚美大部分のがん細胞のミトコンドリアDNA(mtDNA)には、体細胞変異が蓄積している。発がん初期段階でmtDNAに変異が生じると変異mtDNAと正常mtDNAが混在した状態から、細胞内で変異mtDNAだけの状態に移行し、ついで変異mtDNAだけをもつ細胞のみの集団に移行する.本研究の目的は、(1)発がんにおける過程におけるmtDNA体細胞変異の蓄積の分子機構を明らかにする。(2)発がん時における変異mtDNAが原因のアポトーシス抑制機構を明らかにする。(3)ミトコンドリア機能が低下するにもかかわらず、細胞増殖が促進される機構を明らかにする。 患者のがん組織のミトコンドリアDNAの全塩基配列を決定し、がん細胞と正常細胞のミトコンドリアDNAの配列の違いを比較し、抗癌剤耐性との相関関係を調べ、正の相関関係があることを明らかにした。また、抗癌剤耐性の細胞株のミトコンドリアDNA塩基配列を決定し、そのミトコンドリアDNAを別細胞に移植し、抗癌剤耐性が消失することから抗癌剤耐性はミトコンドリアDNAに存在することを明確にした。 さらに抗癌剤耐性細胞を作り出し、その60%にはミトコンドリアDNAの変異が生じており、ミトコンドリアを移植する方法によって抗癌剤耐性が消失することから、これもミトコンドリアに抗癌剤耐性の原因があることを明確にした。 抗癌剤はアポトーシスを誘導するので、ミトコンドリアDNAの変異によってアポトーシスが阻害され、がん細胞にミトコンドリアDNAの変異が蓄積することを明確にした。さらに、ミトコンドリア機能が低下することと相関していることを明らかにした。乳酸が上昇しているので、ミトコンドリア機能を代償するために解糖系が亢進していることを明らかにした。
- 日本学術振興会:科学研究費助成事業 基盤研究(C)研究期間 : 2005年 -2007年代表者 : 大澤 郁朗; 上村 尚美; 太田 成男神経幹細胞におけるエネルギー代謝の一時的抑制が神経細胞への終末分化に必須であるとする仮説を検証することが本研究の目的である。今までに複数のヒト神経芽細胞でTCAサイクルの主要酵素であるジヒドロリポアミド・サクシニル転移酵素(DLST)に変異があり、エネルギー代謝が低下し、その低下が神経芽細胞の分化に必須であることを突き止めてきた。低下抑制は細胞死を促進する。さらに培養過程で神経細胞へと分化可能な細胞とグリア様の形態をとる細胞が混在してくる神経芽細胞SH-SY5Yについて、ミトコンドリア膜電位依存的に蛍光強度が増加するTMRMで染色し経時的に観察した。神経細胞へと分化可能な細胞はTMRMによる染色性が弱く、一方でグリア様の形態をとる細胞はTMRMの染色性が高いまま分裂を繰り返した。この結果は、グリア細胞へと分化する細胞が神経細胞へと分化する細胞に比べてエネルギー産生が高いことを示している。実際にラット胎仔脳をミトコンドリア膜電位依存的蛍光色素MitoTracker Redで染色した結果、増殖中の神経幹細胞(nestin陽性)から分化した神経細胞(TUJ1陽性)に移行する過程で、細胞の移動と共にミトコンドリア膜電位の一過的低下が認められた。これはエネルギー代謝の低下がin vivoでも起こっていることを示している。近年、ATP低下により生じるAMPで活性化されるAMPキナーゼの活性化が神経分化に必要なことが報告された。この点について解析中である。また、酸化ストレスによる神経細胞死を水素分子が抑制することも見いだした。
- 日本学術振興会:科学研究費助成事業 基盤研究(C)研究期間 : 2005年 -2007年代表者 : 麻生 定光; 大澤 郁朗; 森 隆本研究の目的は薬剤によって誘導される肝組織変性を抑制するPTD-FNKを治療に適用し、薬物やアルコールによる急性および慢性肝炎の病態、また虚血再灌流による肝傷害の病態を改善することである。 我々はアポトーシス抑制因子Bcl-x_Lの3アミノ酸をそれぞれ同種のアミノ酸に置換することで、そのアポトーシス抑制活性が著しく増強されたFNK蛋白を作製した。さらに、HIV/Tat蛋白の蛋白質導入領域(PTD)をFNKに付加することでFNK蛋白を細胞内に導入させた。腹腔内に投与されたPTD-FNKは血液脳関門を通過し、前脳虚血による海馬神経細胞の遅発性神経細胞死を抑制した(Proc.Natl.Acad.Sci.USA.2002). 本課題によって、PTD-FNKの肝臓保護効果を明らかにした。PTD-FNKを実験モデル動物に投与することで、四塩化炭素、エタノール、デキサメタゾンなどの薬物や虚血再灌流傷害による肝組織変性を軽減し、血清中のALTやASTの上昇やアポトーシスおよびネクローシスを抑制した。PTD-FNKは速やかに培養細胞HepG2に取り込まれ、ミトコンドリアの機能を維持し、四塩化炭素やTNFαに対する耐性を増強した。虚血再灌流傷害に対するPTD-FNKの軽減効果は脳や心臓でも発揮された。本課題遂行中に得られた結果や技術は他の疾患モデル動物に適用され、PTD-FNKについては血液内耳関門を通過してアミノグリコシドによる難聴を軽減すること、骨髄単核球の移植効率を上昇させること、筋萎縮性側索硬化症、LPS経口投与による急性肺傷害や抗癌剤副作用による脱毛に軽減効果を示すことを明らかにした。これらはすべて国際的な一流雑誌に論文発表することができた。また、世界的に権威ある総説誌Advanced Drug Delively ReviewsにFNKの総説を発表した。
- 日本学術振興会:科学研究費助成事業研究期間 : 2005年 -2006年代表者 : 高松 研; 浜ノ上 誠; 大澤 郁郎髄鞘形成細胞であるオリゴデンドロサイト(OLG)は様々な刺激に反応して容易にアポトーシス(細胞死)を実行し脱落しやすい細胞である。このOLGの脱落は脱髄性神経疾患の一因と考えられており、OLGのアポトーシス制御を含めたその生存機構の解明は、脱髄性神経疾患の治療及び機能再生という点で重要である。p38MAPキナーゼ(p38 MAPK)は様々な外的刺激により誘導されるセリン・スレオニンキナーゼであり、中枢神経系を始め全身の細胞に存在し、細胞増殖・分化・生存などの機能を担っていることが知られているが、成熟OLGにおける発現や機能についての詳細は不明である。 本研究課題では、1.成熟OLGにおけるp38 MAPK発現、2.p38 MAPKと成熟OLG生存活性の関連性、3.細胞膜透過性を有するHuman immunodeficiency virus (HIV)-Tatペプチドとp38 MAPKタンパク質との融合タンパク質のOLG内への導入による効果、について解析し、脱髄性疾患の予防及び治療法の開発に資することを目的とした。 1.免疫細胞化学染色、ウェスタンブロット解析により、成熟OLGはp38 MAPKを発現し、その一部は活性型となっていることを明らかとした。2.p38 MAPK特異的阻害剤を用いた細胞生存活性および細胞死活性の測定の結果、p38 MAPK阻害による成熟OLGのアポトーシス誘導と、著明な生存活性の低下を認めた。これらのことから、p38 MAPKは成熟OLGの生存維持に必須の因子であることが示唆された。3.成熟OLGの生存に深く関わるp38 MAPKを直接制御する目的で、細胞膜透過性を有するHIV-TATペプチドとp38 MAPKタンパク質の融合タンパク質を作製した。TAT-p38 dominant negative型融合タンパク質は培養OLGに取り込まれ、生存する成熟OLG細胞数の減少を引き起こした。このことから、成熟OLGの生存がTAT融合p38 MAPKタンパク質により直接制御できることを明らかにした。現在、in vitroおよびin vivoでp38 MAPKタンパク質導入によるOLG生存維持の効果について解析を続けている。
- 日本学術振興会:科学研究費助成事業 特定領域研究研究期間 : 2005年 -2005年代表者 : 太田 成男; 宮戸 靖幸; 大澤 郁朗; 上村 尚美(1)癌細胞におけるミトコンドリアDNAの体細胞変異の蓄積 多くの癌組織、癌細胞のmtDNAに体細胞変異が蓄積していることが明らかにされている。しかし、この体細胞変異の蓄積が、癌の形成過程の二次的結果として生じているのか、癌形成の原因のひとつとして、癌の促進に関与したために変異mtDNAをもつ癌細胞が多くなったのか、明らかではなかった。 (2)サイブリドを用いたmtDNAの役割の研究 細胞には核ゲノムとミトコンドリアゲノムが共存しているので、mtDNAの役割を明らかにするためには、核が共通でmtDNAだけが異なる細胞を比較しなければならない。そこで、mtDNAを消失しているHeLa細胞と脱核した細胞質を融合し、核が共通で正常mtDNAをもつ細胞と変異mtDNAをもつ細胞を作製した。この融合細胞を細胞質の融合であるのでサイブリド(cybrid)と呼ぶ。このサイブリドを用いて、mtDNAの癌の増殖速度へ対する効果とアポトーシ耐性効果、抗癌剤への耐性効果を調べた。 (3)癌の増殖に対する変異mtDNAの効果 変異mtDNAを持つサイブリド細胞と正常mtDNAもつサイブリド細胞をヌードマウスに移植すると、移植直後からの腫瘍体積の増加が正常mtDNAをもつサイブリド細胞より速く、mtDNA変異が癌増殖促進に寄与していることが示された。変異mtDNAをもつサイブリドでは、自発的におきるアポトーシス頻度が低下しており、アポトーシスの頻度の低下が見かけ上の増殖促進に寄与していることが示唆された。 (4)抗癌剤へ対する耐性獲得とmtDNA変異 mtDNA変異によってアポトーシスが抑制されたので、抗癌剤への耐性へのmtDNAの役割をサイブリドを用いて解析した。変異mtDNAをもつサイブリドは正常mtDNAをもつサイブリドよりも抗癌剤耐性であった。
- 日本学術振興会:科学研究費助成事業 基盤研究(C)研究期間 : 2002年 -2004年代表者 : 麻生 定光; 太田 成男; 桂 研一郎; 大澤 郁朗本研究課題では、細胞死抑制活性が強化されたタンパク質を生体に投与によって脳虚血による神経細胞死を抑制し、その病態を改善することを目的としている。本研究で投与しているタンパク質FNKは、抗アポトーシス抑制因子Bcl-xLの3個のアミノ酸を置換して作製されたFNKタンパク質で、カルシウムイオノホア、酸化ストレス、血清除去など種々の細胞死刺激に対してBcl-xLより強力な細胞死抑制活性を発揮する。このFNKを細胞内に取り込ませるために、HIV/Tatタンパク質の細胞膜を自由に通過することのできるタンパク質導入領域(PTD : protein transduction domain)をN末端に付加したPTD-FNKを作製した。本研究期間中に、PTD-FNKを培地に添加すると、初代培養神経細胞のグルタミン酸処理による細胞内カルシウム濃度の致死的な不可逆的上昇を抑制し、その毒性を顕著に軽減した。PTD-FNKをスナネズミ腹腔内に投与することで前脳虚血による海馬の遅発性神経細胞死を抑制することを明らかにした。さらに、ヒト脳梗塞の病態に近いラット中大脳動脈(MCA)閉塞(90分)モデルを用いて、再還流開始時の投与で、梗塞体積が対照群に比べて1/3に縮小され、24時間後では対照群はほとんど動けないのに対し、FNK投与群は自発的歩行が可能であった。PTD-FNKによって細胞死を免れた神経細胞は正常に機能していると考えられた。免疫抑制剤FK506との併用により、投与許容時間を3時間延長できた。このように、PTD-FNKが急性期の脳硬塞治療に効果を発揮することが示唆された。この他に、軟骨組織スライスにPTD-FNK処理すると軟骨細胞に取り込まれてその細胞死が抑制されること、PTD-FNK投与で四塩化炭素によるネクローシスを抑制することで肝炎の病態を軽減すること、凍結再融解による細胞死を抑制することなど、PTD-FNKの適用の有効性について多くのことが明らかになった。
- 日本学術振興会:科学研究費助成事業 基盤研究(C)研究期間 : 2002年 -2004年代表者 : 大澤 郁朗; 太田 成男; 麻生 定光中枢神経系における神経細胞の生存維持機構については、未だ解明されていない点が多い。発生過程では大量の神経細胞死が起こり、その後は成熟した神経細胞が長期生存維持される。この成熟神経細胞も、神経変性疾患や神経毒によって細胞死に至る。従って、神経細胞生存維持にはアポトーシス抑制機構を含む強力な細胞死抑制機構が存在する。そこで、本研究ではサバイビンの神経細胞生存維持における役割を初代神経細胞含む培養細胞を用いた解析と組換えマウスの育種とを中心に明らかする。サバイビンは、IAP(inhibitor of apoptosis protein)ファミリーに属するアポトーシス抑制蛋白であり、多くの腫瘍で高発現している。我々は、サバイビンが分化した神経細胞でも発現していることをマウスの初代培養神経細胞と大脳皮質組織片の免疫染色によって見いだした。神経細胞を抗サバイビン抗体で染色したところ、ほとんど全ての細胞の核でその染色が認められた。一方、神経幹細胞では、細胞質分裂時の収縮環両側でのサバイビンの蓄積が認められた。また、アストロサイトは一部が強い陽性像を示した。さらに胎生16日令の大脳皮質を抗サバイビン抗体で免疫染色した。その結果、MAP2陽性の神経細胞核がサバイビン陽性となり、サバイビンが成熟神経細胞の発達・生存維持に重要な役割を担っている可能性を強く示唆された。一方、サバイビンがアストロサイトで発現していたことから、抗サバイビン抗体でグリオーマ患者脳切片を染色したところ、その悪性度に応じて染色性が増加した。従来の病理判定では悪性度が低いと判定されたものでも、サバイビン高発現の場合は予後不良であった。抗サバイビン抗体による組織染色はグリオーマの診断に有益である。さらにサバイビンをELISAで検出するシステムを作製し、尿を検査することで膀胱癌を診断できる可能性も示した。
- 日本学術振興会:科学研究費助成事業 基盤研究(B)研究期間 : 2000年 -2002年代表者 : 太田 成男; 大澤 郁朗; 金森 崇; 麻生 定光ミトコンドリアに局在するアルデヒド脱水素酵素ALDH2は、エタノール代謝においてアセトアルデヒドから酢酸への反応を触媒する。その一塩基置換の遺伝子多型であるALDH2^*2はドミナント・ネガティブに働き、ALDH2活性を抑制する。我々は、ALDH2^*2が晩期発症型アルツハイマー病(AD)の危険因子であり、ALDH2^*2をもつ健常人集団の血清には、過酸化脂質がより多く蓄積していることを示した。過酸化脂質は、毒性の強いアルデヒド類である4-ヒドロキシ-2-ノネナール(4-HNE)に自然に変換されることから、4-HNEがALDH2の標的基質であることを想定した。 すなわち、ALDH2酵素活性が低下すると4-HNEが蓄積し、毒性を発揮すると想定した。 この想定を証明するために、マウス型ALDH2^*2遺伝子をPC12細胞に導入し、ALDH2活性をドミナント・ネガティブ低下させた。そして、ALDH2活性欠損株に酸化ストレスを与えると、4-HNEの蓄積と細胞死が促進されることを証明して、この仮説が正しいことを証明した。 すなわち、ALDH2は酸化ストレスへの防御機構として働いていることが示唆された。 次に個体レベルにおいてALDH2活性の欠失が及ぼす影響を調べるため、アクチン・プロモーター下にマウスのALDH2^*2を挿入し、トランスジェニック(Tg)マウスを作製した。3系統のTgマウスについて解析したところ、骨格筋において、過酸化脂質の分解物であるマロンジアルデヒドと4-ヒドロキシアルケナールが蓄積していた。しかも、筋繊維は生後直後正常であり、age-dependentの筋繊維の萎縮であることを見いだした。そこで、ALDH2欠損マウスでは、酸化ストレスが亢進されていることが推定された。さらに、ALDH2欠損筋繊維では、ミトコンドリア脳筋症の指標であるragged-red-fiberとミトコンドリアの凝集が認められた。 このTgマウスでは、ALDH2^*2によりALDH2活性が抑制され、酸化ストレスによって生じるアルデヒド類の解毒能が低下した結果として筋萎縮が生じたものと考えられる。ragged-red fiberが出現したことから、ミトコンドリア脳筋症のモデル動物となる可能性がある。
- 日本学術振興会:科学研究費助成事業 特定領域研究(C)研究期間 : 2001年 -2001年代表者 : 太田 成男; 大澤 郁朗; 金森 崇; 麻生 定光ミトコンドリアゲノムは核ゲノムとは空間的に独立して存在しており、その挙動は多くの疾患において重要な役割を果たしていることが明らかになりつつある。糖尿病全体の1%におよぶ患者にはmtDNAの変異が蓄積していることがすでに報告されている。しかし、この変異が糖尿病にどのように影響を及ぼすのかは不明である。糖尿病患者と健常人において、ヘテロプラズミー変異の比率の相関関係を定量的に検討し、糖尿病とmtDNAのヘテロプラズミー変異の因果関係を明らかにし、糖尿病の危険因子となりうることを証明するのが本研究の目的である。 (1)糖尿病の原因のミトコンドリアtRNAの点変異によって、アンチコドンの塩基修飾が変化して、mRNAへの親和力が低下し、蛋白合成が正常に行われなくなることを明らかにした。この結果は、わずかな量の変異mtDNAでも不完全が蛋白を合成することによって細胞に影響を及ぼす可能性を示した。 (2)mtDNAのヘテロプラズミー変異の検出法を確立した。この方法の確立によって、ヘテロプラズミー変異を定量的に検討することが可能になった。 糖尿病患者の血液細胞において、体細胞変異が健常人よりも4倍多いことを明らかにした。さらに、多変量解析により、糖尿病の羅患期間に依存してmtDNAの塩基番号3243変異が増加することを明らかにした。 ミトコンドリアtRNA遺伝子変異によって生じるミトコンドリア機能低下の分子機構は多くの研究室で研究されているが、当研究室がはじめて分子機構を明らかにした。mtDNAのヘテロプラズミー変異と糖尿病の関連については多数の報告があるが、微量なヘテロプラズミー変異の定量についての研究はなく、定量的解析は当研究がリードしている。
- 水素分子の生体における機能解析、医学への応用.加齢に伴う神経変性疾患における酸化ストレスの影響.
- Hydrogen as a therapeutic antioxidant, its molecular and cellular mechanisms