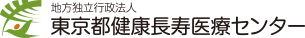研究者総覧
野藤 悠 (ノフジ ユウ)
|  | ||
Last Updated :2025/04/18
研究者情報
学位
ホームページURL
J-Global ID
研究分野
経歴
- 2019年04月 - 現在 独立行政法人東京都健康長寿医療センター社会参加と地域保健研究チーム研究員
- 2015年04月 - 2019年03月 公益社団法人地域医療振興協会ヘルスプロモーション研究センター
- 2011年10月 - 2015年03月 独立行政法人東京都健康長寿医療センター社会参加と地域保健研究チーム研究員
学歴
研究活動情報
論文
- Hiroki Mori; Satoshi Seino; Yuri Yokoyama; Mari Yamashita; Yu Nofuji; Takuya Ueda; Akihiko Kitamura; Shinji Hattori; Minoru Yamada; Katsunori Kondo; Hidenori Arai; Hayato Uchida; Erika Kobayashi; Yoshinori FujiwaraGeriatrics & gerontology international 2025年03月
- Tao Chen; Sanmei Chen; Takanori Honda; Hiro Kishimoto; Yu Nofuji; Kenji NarazakiBritish Journal of Sports Medicine bjsports - 2024 2025年01月
- Yuri Yokoyama; Yu Nofuji; Takumi Abe; Kumiko Nonaka; Yumi Ozone; Yuka Nakamura; Shiina Chiaki; Takumi Suda; Naoko Saito; Mai Takase; Hidenori Amano; Susumu Ogawa; Hiroyuki Suzuki; Hiroshi MurayamaJournal of Epidemiology 2025年
- Sanmei Chen; Tao Chen; Takanori Honda; Hiro Kishimoto; Yu Nofuji; Kenji NarazakiGeroScience 2024年12月
- Yu Nofuji; Shoji Shinkai; Yosuke Osuka; Satoshi Seino; Miki Narita; Kumiko Nonaka; Yuri Yokoyama; Shizue Hagiwara; Toshie Fujikura; Yoshinori Fujiwara; Hiroshi Murayama[Nihon koshu eisei zasshi] Japanese journal of public health 2024年11月
- Hideaki Matsuzaki; Taishi Tsuji; Tao Chen; Sanmei Chen; Yu Nofuji; Kenji Narazaki[Nihon koshu eisei zasshi] Japanese journal of public health 2024年06月
- 藤原 佳典; 清野 諭; 秦 俊貴; 野藤 悠; 横山 友里; 阿部 巧; 成田 美紀; 森 裕樹; 小林 江里香; 新開 省二老年社会科学 46 2 176 - 176 日本老年社会科学会 2024年06月
- Satoshi Seino; Takumi Abe; Yu Nofuji; Toshiki Hata; Shoji Shinkai; Akihiko Kitamura; Yoshinori FujiwaraFrontiers in Public Health 12 2024年04月
- Takumi Abe; Yoshinori Fujiwara; Akihiko Kitamura; Yu Nofuji; Yukiko Nishita; Hyuma Makizako; Seungwon Jeong; Masanori Iwasaki; Minoru Yamada; Narumi Kojima; Katsuya Iijima; Shuichi Obuchi; Ken Shinmura; Rei Otsuka; Takao SuzukiGeriatrics & gerontology international 24 4 352 - 358 2024年04月
- 大都市在住高齢者におけるCOVID-19流行下の通いの場への参加が1年後のフレイルに及ぼす影響清野 諭; 横山 友里; 森 裕樹; 植田 拓也; 山下 真里; 野藤 悠; 北村 明彦; 服部 真治; 山田 実; 近藤 克則; 荒井 秀典; 藤原 佳典Journal of Epidemiology 34 Suppl. 171 - 171 (一社)日本疫学会 2024年01月
- Tomoko Ikeuchi; Takumi Abe; Yu Taniguchi; Satoshi Seino; Yuri Yokoyama; Yu Nofuji; Hidenori Amano; Akihiko Kitamura; Shoji Shinkai; Yoshinori FujiwaraGeriatrics & Gerontology International 2023年11月
- M. Kitago; S. Seino; S. Shinkai; Y. Nofuji; Y. Yokoyama; H. Toshiki; T. Abe; Y. Taniguchi; H. Amano; H. Murayama; A. Kitamura; M. Akishita; Yoshinori FujiwaraThe Journal of nutrition, health and aging 27 11 946 - 952 2023年11月
- Yoshinori Fujiwara; Satoshi Seino; Yu Nofuji; Yuri Yokoyama; Takumi Abe; Mari Yamashita; Toshiki Hata; Koji Fujita; Hiroshi Murayama; Shoji Shinkai; Akihiko KitamuraGeriatrics & gerontology international 23 11 855 - 863 2023年11月
- 類型別にみた高齢者の居場所の特徴 居場所への期待と居場所の有無との関連山城 大地; 藤田 幸司; 相良 友哉; 森 裕樹; 植田 拓也; 倉岡 正高; 清野 諭; 野藤 悠; 山下 真里; 阿部 巧; 藤原 佳典日本公衆衛生学会総会抄録集 82回 431 - 431 日本公衆衛生学会 2023年10月
- 地域在住高齢者における新型コロナウイルス感染症流行直後の生活行動の変化と食品摂取多様性との関連成田 美紀; 大曽根 由実; 新開 省二; 阿部 巧; 横山 友里; 野藤 悠; 秦 俊貴; 北村 明彦; 藤原 佳典; 村山 洋史日本応用老年学会大会 18回 51 - 51 (一社)日本応用老年学会 2023年10月
- 地域在住高齢者における肉・卵の摂取頻度が低い要因に関する実態把握 2023年度草津町調査大曽根 由実; 野藤 悠; 横山 友里; 阿部 巧; 成田 美紀; 村山 洋史; 新開 省二日本応用老年学会大会 18回 87 - 87 (一社)日本応用老年学会 2023年10月
- COVID-19流行前後における高齢者の食生活 食品摂取多様性と関連要因の変化成田 美紀; 大曽根 由実; 新開 省二; 横山 友里; 阿部 巧; 野藤 悠; 秦 俊貴; 村山 洋史; 藤原 佳典日本公衆衛生学会総会抄録集 82回 523 - 523 日本公衆衛生学会 2023年10月
- COVID-19流行前後における高齢者の食生活 食品摂取多様性の変化をもたらす要因大曽根 由実; 成田 美紀; 新開 省二; 横山 友里; 野藤 悠; 阿部 巧; 秦 俊貴; 村山 洋史; 藤原 佳典日本公衆衛生学会総会抄録集 82回 523 - 523 日本公衆衛生学会 2023年10月
- Tao Chen; Sanmei Chen; Takanori Honda; Hiro Kishimoto; Yu Nofuji; Kenji NarazakiThe international journal of behavioral nutrition and physical activity 20 1 91 - 91 2023年07月
- Tao Chen; Sanmei Chen; Takanori Honda; Yu Nofuji; Hiro Kishimoto; Kenji NarazakiJournal of physical activity & health 20 9 1 - 8 2023年06月
- Yuri Yokoyama; Yu Nofuji; Satoshi Seino; Takumi Abe; Hiroshi Murayama; Miki Narita; Shoji Shinkai; Akihiko Kitamura; Yoshinori FujiwaraPublic health nutrition 1 - 8 2023年05月
- JST版活動能力指標との関連性における身体機能と認知機能の差異 長寿コホートの総合的研究(ILSA-J)阿部 巧; 藤原 佳典; 北村 明彦; 野藤 悠; 西田 裕紀子; 牧迫 飛雄馬; 鄭 丞媛; 大塚 礼; 鈴木 隆雄; 岩崎 正則; 山田 実; 小島 成実; 飯島 勝矢; 大渕 修一; 新村 健; 島田 裕之; 鈴木 宏幸; 吉村 典子; 渡辺 修一郎; 村木 功; 近藤 克則日本老年医学会雑誌 60 Suppl. 148 - 149 (一社)日本老年医学会 2023年05月
- JST版活動能力指標との関連性における身体機能と認知機能の差異 長寿コホートの総合的研究(ILSA-J)阿部 巧; 藤原 佳典; 北村 明彦; 野藤 悠; 西田 裕紀子; 牧迫 飛雄馬; 鄭 丞媛; 大塚 礼; 鈴木 隆雄; 岩崎 正則; 山田 実; 小島 成実; 飯島 勝矢; 大渕 修一; 新村 健; 島田 裕之; 鈴木 宏幸; 吉村 典子; 渡辺 修一郎; 村木 功; 近藤 克則日本老年医学会雑誌 60 Suppl. 148 - 149 (一社)日本老年医学会 2023年05月
- Yu Nofuji; Satoshi Seino; Takumi Abe; Yuri Yokoyama; Miki Narita; Hiroshi Murayama; Shoji Shinkai; Akihiko Kitamura; Yoshinori FujiwaraPreventive medicine 169 107449 - 107449 2023年04月
- Y Osuka; Y Okubo; Y Nofuji; K Maruo; Y Fujiwara; H Oka; S Shinkai; S R Lord; H SasaiOccupational medicine (Oxford, England) 2023年03月
- Takumi Abe; Satoshi Seino; Yu Nofuji; Yuri Yokoyama; Hidenori Amano; Mari Yamashita; Shoji Shinkai; Akihiko Kitamura; Yoshinori FujiwaraExperimental gerontology 173 112094 - 112094 2023年03月
- 基本チェックリストを用いた要介護化リスク評価尺度のカットオフ値の妥当性 9年間の前向き追跡研究松崎 英章; 辻 大士; 岸本 裕歩; 陳 涛; 陳 三妹; 野藤 悠; 楢崎 兼司健康支援 25 1 78 - 78 日本健康支援学会 2023年02月
- 地域高齢者における食品摂取の多様性がヘモグロビン値の変化に与える影響秦 俊貴; 清野 諭; 横山 友里; 阿部 巧; 野藤 悠; 成田 美紀; 谷口 優; 天野 秀紀; 西 真理子; 新開 省二; 北村 明彦; 藤原 佳典Journal of Epidemiology 33 Suppl.1 86 - 86 (一社)日本疫学会 2023年02月
- Noriko Yamanaka; Mitsuyo Itabashi; Yoshinori Fujiwara; Yu Nofuji; Takumi Abe; Akihiko Kitamura; Shoji Shinkai; Toru Takebayashi; Takashi TakeiHypertension Research 46 3 556 - 564 2022年12月
- Yosuke Osuka; Yu Nofuji; Satoshi Seino; Kazushi Maruo; Hiroyuki Oka; Shoji Shinkai; Yoshinori Fujiwara; Hiroyuki SasaiJournal of occupational health 64 1 e12374 2022年12月 [査読有り]
- Hideaki Matsuzaki; Hiro Kishimoto; Yu Nofuji; Tao Chen; Kenji NarazakiGeriatrics & Gerontology International 22 11 985 - 986 2022年10月
- Yuri Yokoyama; Takahiro Yoshizaki; Ayaka Kotemori; Yu Nofuji; Satoshi Seino; Mariko Nishi; Hidenori Amano; Miki Narita; Takumi Abe; Shoji Shinkai; Akihiko Kitamura; Yoshinori Fujiwara[Nihon koshu eisei zasshi] Japanese journal of public health 69 9 665 - 675 2022年09月
- 在宅高齢者における一緒に食べる相手の二年間の変化とフレイル発生との関連成田 美紀; 横山 友里; 阿部 巧; 清野 諭; 天野 秀紀; 野藤 悠; 山下 真里; 秦 俊貴; 北村 明彦; 新開 省二; 藤原 佳典日本公衆衛生学会総会抄録集 81回 218 - 218 日本公衆衛生学会 2022年09月
- 体操を中心とした通いの場への参加が地域在住高齢者のフレイルに及ぼす効果横山 友里; 清野 諭; 野藤 悠; 阿部 巧; 村山 洋史; 西 真理子; 天野 秀紀; 成田 美紀; 新開 省二; 北村 明彦; 藤原 佳典日本公衆衛生学会総会抄録集 81回 351 - 351 日本公衆衛生学会 2022年09月
- 「シルバー人材センターと連携した通いの場」への参加による要介護化の抑制効果野藤 悠; 清野 諭; 阿部 巧; 横山 友里; 成田 美紀; 村山 洋史; 吉田 由佳; 新開 省二; 北村 明彦; 藤原 佳典日本公衆衛生学会総会抄録集 81回 354 - 354 日本公衆衛生学会 2022年09月
- 社会活動の選択に関連する性格特性 活動種類別の検討山下 真里; 清野 諭; 野藤 悠; 阿部 巧; 菅原 康弘; 成田 美紀; 秦 俊貴; 北村 明彦; 新開 省二; 藤原 佳典日本公衆衛生学会総会抄録集 81回 373 - 373 日本公衆衛生学会 2022年09月
- 横山 友里; 吉崎 貴大; 小手森 綾香; 野藤 悠; 清野 諭; 西 真理子; 天野 秀紀; 成田 美紀; 阿部 巧; 新開 省二; 北村 明彦; 藤原 佳典日本公衆衛生雑誌 69 9 665 - 675 日本公衆衛生学会 2022年09月
- Tomoko Ikeuchi; Yu Taniguchi; Takumi Abe; Yuri Yokoyama; Satoshi Seino; Miki Narita; Mariko Nishi; Hidenori Amano; Yu Nofuji; Shoji Shinkai; Akihiko Kitamura; Yoshinori FujiwaraGeroPsych 35 4 226 - 233 2022年08月
- Hideaki Matsuzaki; Hiro Kishimoto; Yu Nofuji; Tao Chen; Kenji NarazakiGeriatrics & Gerontology International 22 9 723 - 729 2022年08月
- 野藤 悠; 清野 諭; 天野 秀紀; 横山 友里; 西 真理子; 阿部 巧; 山下 真里; 成田 美紀; 村山 洋史; 北村 明彦; 新開 省二; 藤原 佳典応用老年学 16 1 30 - 39 (一社)日本応用老年学会 2022年08月
- 野藤 悠; 清野 諭; 天野 秀紀; 横山 友里; 西 真理子; 阿部 巧; 山下 真里; 成田 美紀; 村山 洋史; 北村 明彦; 新開 省二; 藤原 佳典応用老年学 16 1 30 - 39 (一社)日本応用老年学会 2022年08月
- 植田 拓也; 倉岡 正高; 清野 諭; 小林 江里香; 服部 真治; 澤岡 詩野; 野藤 悠; 本川 佳子; 野中 久美子; 村山 洋史; 藤原 佳典日本公衆衛生雑誌 69 7 497 - 504 日本公衆衛生学会 2022年07月
- Takumi Abe; Yu Nofuji; Satoshi Seino; Toshiki Hata; Miki Narita; Yuri Yokoyama; Hidenori Amano; Akihiko Kitamura; Shoji Shinkai; Yoshinori FujiwaraArchives of Gerontology and Geriatrics 101 104708 - 104708 2022年07月
- Mari Yamashita; Takumi Abe; Satoshi Seino; Yu Nofuji; Yasuhiro Sugawara; Shoji Shinkai; Akihiko Kitamura; Yoshinori FujiwaraJournal of health psychology 13591053221105350 - 13591053221105350 2022年06月
- Satoshi Seino; Yu Nofuji; Yuri Yokoyama; Yui Tomine; Mariko Nishi; Toshiki Hata; Shoji Shinkai; Yoshinori Fujiwara; Akihiko KitamuraJournal of epidemiology 32 6 301 - 301 2022年06月
- Erika Kobayashi; Takuya Ueda; Junta Takahashi; Satoshi Seino; Yu Nofuji; Yuta Nemoto; Masataka Kuraoka; Yoshinori Fujiwara[Nihon koshu eisei zasshi] Japanese journal of public health 69 7 544 - 553 2022年05月
- 地域在住高齢者における健康な食事スコアとフレイル・サルコペニアとの横断的関連成田 美紀; 新開 省二; 横山 友里; 清野 諭; 阿部 巧; 天野 秀紀; 西 真理子; 野藤 悠; 北村 明彦; 藤原 佳典日本老年医学会雑誌 59 Suppl. 121 - 121 (一社)日本老年医学会 2022年05月
- 地域在住高齢者の骨格筋指数の加齢変化パターンとその予測要因清野 諭; 谷口 優; 成田 美紀; 阿部 巧; 野藤 悠; 横山 友里; 天野 秀紀; 新開 省二; 北村 明彦; 藤原 佳典日本老年医学会雑誌 59 Suppl. 129 - 129 (一社)日本老年医学会 2022年05月
- 高齢期の就業は介護予防・認知症予防に有効か? フレイル有無別の検討藤原 佳典; 清野 諭; 野藤 悠; 横山 友里; 阿部 巧; 山下 真里; 成田 美紀; 秦 俊貴; 新開 省二; 北村 明彦日本老年医学会雑誌 59 Suppl. 135 - 136 (一社)日本老年医学会 2022年05月
- 高齢期の就業は介護予防・認知症予防に有効か? フレイル有無別の検討藤原 佳典; 清野 諭; 野藤 悠; 横山 友里; 阿部 巧; 山下 真里; 成田 美紀; 秦 俊貴; 新開 省二; 北村 明彦日本老年医学会雑誌 59 Suppl. 158 - 159 (一社)日本老年医学会 2022年05月
- Satoshi Seino; Akihiko Kitamura; Takumi Abe; Yu Taniguchi; Hiroshi Murayama; Hidenori Amano; Mariko Nishi; Yu Nofuji; Yuri Yokoyama; Miki Narita; Shoji Shinkai; Yoshinori FujiwaraJournal of cachexia, sarcopenia and muscle 13 2 932 - 944 2022年04月
- Yosuke Osuka; Yoshiro Okubo; Yu Nofuji; Hiroyuki Sasai; Satoshi Seino; Kazushi Maruo; Yoshinori Fujiwara; Hiroyuki Oka; Shoji Shinkai; Stephen R Lord; Hunkyung KimGeriatrics & gerontology international 22 4 338 - 343 2022年04月
- Sanmei Chen; Tao Chen; Takanori Honda; Yu Nofuji; Hiro Kishimoto; Kenji NarazakiInternational journal of environmental research and public health 19 4 2022年02月
- Masanori Iwasaki; Yuki Ohara; Keiko Motokawa; Misato Hayakawa; Maki Shirobe; Ayako Edahiro; Yutaka Watanabe; Shuichi Awata; Tsuyoshi Okamura; Hiroki Inagaki; Naoko Sakuma; Shuichi Obuchi; Hisashi Kawai; Manami Ejiri; Kumiko Ito; Yoshinori Fujiwara; Akihiko Kitamura; Yu Nofuji; Takumi Abe; Katsuya Iijima; Tomoki Tanaka; Bo-Kyung Son; Shoji Shinkai; Hirohiko HiranoJournal of prosthodontic research 67 1 62 - 69 2022年01月
- 野藤 悠; 阿部 巧; 清野 諭; 横山 友里; 天野 秀紀; 村山 洋史; 吉田 由佳; 新開 省二; 藤原 佳典; 北村 明彦日本公衆衛生雑誌 69 1 26 - 36 日本公衆衛生学会 2022年01月
- Satoshi Seino; Takumi Abe; Yu Nofuji; Toshiki Hata; Shoji Shinkai; Akihiko Kitamura; Yoshinori FujiwaraJournal of Epidemiology 2022年
- 東日本大震災から8年後の被災地におけるアパシーの実態とフレイルとの関連山下 真里; 清野 諭; 野藤 悠; 菅原 康宏; 成田 美紀; 秦 俊貴; 北村 明彦; 新開 省二; 藤原 佳典Journal of Epidemiology 32 Suppl.1 130 - 130 (一社)日本疫学会 2022年01月
- Satoshi Seino; Yu Nofuji; Yuri Yokoyama; Takumi Abe; Mariko Nishi; Mari Yamashita; Miki Narita; Toshiki Hata; Shoji Shinkai; Akihiko Kitamura; Yoshinori FujiwaraJournal of epidemiology 2021年12月
- 山下 真里; 清野 諭; 野藤 悠; 菅原 康宏; 成田 美紀; 横山 友里; 西 真理子; 秦 俊貴; 北村 明彦; 新開 省二; 藤原 佳典厚生の指標 68 13 13 - 20 (一財)厚生労働統計協会 2021年11月
- 高齢者の身体活動、多様な食品摂取、社会交流の累積が介護予防に及ぼす影響清野 諭; 野藤 悠; 横山 友里; 阿部 巧; 西 真理子; 山下 真里; 成田 美紀; 秦 俊貴; 新開 省二; 北村 明彦; 藤原 佳典日本公衆衛生学会総会抄録集 80回 244 - 244 日本公衆衛生学会 2021年11月
- 運動習慣、食品摂取状況、孤立状況及びその変化と二年後のフレイル改善との関連成田 美紀; 清野 諭; 新開 省二; 阿部 巧; 横山 友里; 西 真理子; 野藤 悠; 山下 真里; 秦 俊貴; 北村 明彦; 藤原 佳典日本公衆衛生学会総会抄録集 80回 247 - 247 日本公衆衛生学会 2021年11月
- 就業は、フレイル高齢者の介護予防に有効か? 性・フレイル有無別の検討藤原 佳典; 清野 諭; 野藤 悠; 横山 友里; 阿部 巧; 西 真理子; 山下 真里; 成田 美紀; 秦 俊貴; 新開 省二; 北村 明彦日本公衆衛生学会総会抄録集 80回 403 - 403 日本公衆衛生学会 2021年11月
- 地域高齢者における食品摂取の多様性と要介護認知症発症との関連 養父コホート研究横山 友里; 野藤 悠; 清野 諭; 村山 洋史; 阿部 巧; 成田 美紀; 吉田 由佳; 新開 省二; 北村 明彦; 藤原 佳典日本公衆衛生学会総会抄録集 80回 474 - 474 日本公衆衛生学会 2021年11月
- 東日本大震災被災地における高齢住民の孤独感の実態とその関連要因山下 真里; 清野 諭; 野藤 悠; 菅原 康宏; 成田 美紀; 横山 友里; 西 真理子; 秦 俊貴; 北村 明彦; 新開 省二; 藤原 佳典厚生の指標 68 13 13 - 20 (一財)厚生労働統計協会 2021年11月
- 地域在住高齢者における早期低栄養リスクの関連要因の検討成田 美紀; 新開 省二; 横山 友里; 清野 諭; 山下 真里; 野藤 悠; 菅原 康宏; 秦 俊貴; 北村 明彦; 藤原 佳典日本応用老年学会大会 16回 36 - 36 (一社)日本応用老年学会 2021年10月
- 再考-独居は新規要介護認定のリスク要因か? 性・フレイル有無別の検討藤原 佳典; 清野 諭; 野藤 悠; 横山 友里; 阿部 巧; 西 真理子; 山下 真里; 成田 美紀; 秦 俊貴; 新開 省二; 北村 明彦日本応用老年学会大会 16回 66 - 66 (一社)日本応用老年学会 2021年10月
- Takumi Abe; Satoshi Seino; Yu Nofuji; Yui Tomine; Mariko Nishi; Toshiki Hata; Shoji Shinkai; Akihiko KitamuraPreventive medicine 153 106768 - 106768 2021年08月
- Satoshi Seino; Yu Nofuji; Yuri Yokoyama; Yui Tomine; Mariko Nishi; Toshiki Hata; Shoji Shinkai; Yoshinori Fujiwara; Akihiko KitamuraJournal of epidemiology 31 6 401 - 402 2021年06月
- 地域在住高齢者における性格特性とフレイルの関連山下 真里; 清野 諭; 野藤 悠; 菅原 康宏; 阿部 巧; 西 真理子; 秦 俊貴; 新開 省二; 藤原 佳典; 北村 明彦老年社会科学 43 2 204 - 204 日本老年社会科学会 2021年06月
- 高齢者の身体組成・身体機能と要介護・総死亡リスクとの量・反応関係清野 諭; 新開 省二; 阿部 巧; 谷口 優; 野藤 悠; 天野 秀紀; 西 真理子; 横山 友里; 成田 美紀; 北村 明彦日本老年医学会雑誌 58 Suppl. 179 - 179 (一社)日本老年医学会 2021年05月
- Mari Yamashita; Satoshi Seino; Yu Nofuji; Yasuhiro Sugawara; Yosuke Osuka; Akihiko Kitamura; Shoji ShinkaiJournal of epidemiology 2021年04月
- 成田 美紀; 北村 明彦; 谷口 優; 清野 諭; 横山 友里; 野藤 悠; 天野 秀紀; 西 真理子; 武見 ゆかり; 新開 省二日本老年医学会雑誌 58 1 81 - 90 (一社)日本老年医学会 2021年01月
- 大都市在住高齢者の要介護化リスク因子 3年間の縦断分析による検討清野 諭; 新開 省二; 遠峰 結衣; 秦 俊貴; 西 真理子; 野藤 悠; 横山 友里; 成田 美紀; 藤原 佳典; 北村 明彦Journal of Epidemiology 31 Suppl. 135 - 135 (一社)日本疫学会 2021年01月
- Miki Narita; Akihiko Kitamura; Yu Taniguchi; Satoshi Seino; Yuri Yokoyama; Yu Nofuji; Hidenori Amano; Mariko Nishi; Yukari Takemi; Shoji ShinkaiNihon Ronen Igakkai zasshi. Japanese journal of geriatrics 58 1 81 - 90 2021年
- 天野 秀紀; 北村 明彦; 西 真理子; 野藤 悠; 清野 諭; 横山 友里; 成田 美紀; 池内 朋子; 吉田 裕人; 藤原 佳典; 新開 省二老年精神医学雑誌 31 増刊II 188 - 188 (株)ワールドプランニング 2020年12月
- Akihiko Kitamura; Satoshi Seino; Takumi Abe; Yu Nofuji; Yuri Yokoyama; Hidenori Amano; Mariko Nishi; Yu Taniguchi; Miki Narita; Yoshinori Fujiwara; Shoji ShinkaiJournal of cachexia, sarcopenia and muscle 12 1 30 - 38 2020年11月
- Yu Taniguchi; Akihiko Kitamura; Takumi Abe; Gotaro Kojima; Tomohiro Shinozaki; Satoshi Seino; Yuri Yokoyama; Yu Nofuji; Tomoko Ikeuchi; Yutaka Matsuyama; Yoshinori Fujiwara; Shoji ShinkaiGeriatrics & gerontology international 20 11 1072 - 1078 2020年11月
- 孤食とフレイルまたは精神的健康との関連に社会的支援および孤立は交絡するか新開 省二; 清野 諭; 秦 俊貴; 遠峰 結衣; 西 真理子; 横山 友里; 野藤 悠; 成田 美紀; 北村 明彦日本公衆衛生学会総会抄録集 79回 251 - 251 日本公衆衛生学会 2020年10月
- 高齢者の身体活動、多様な食品摂取、社会参加が新規要介護認定に及ぼす累積的影響清野 諭; 新開 省二; 遠峰 結衣; 西 真理子; 秦 俊貴; 野藤 悠; 横山 友里; 成田 美紀; 藤原 佳典; 北村 明彦; 東京都健康長寿医療センター研究所社会参加と地域保健研究チーム日本公衆衛生学会総会抄録集 79回 253 - 253 日本公衆衛生学会 2020年10月
- 高齢者の健康支援でのICT活用可能性 利用率と利用者特性、介護予防への影響の検討遠峰 結衣; 清野 諭; 秦 俊貴; 西 真理子; 野藤 悠; 横山 友里; 成田 美紀; 新開 省二; 藤原 佳典; 北村 明彦日本公衆衛生学会総会抄録集 79回 382 - 382 日本公衆衛生学会 2020年10月
- 高齢期の社会参加が健康行動の継続に及ぼす影響 社会活動の種類に着目した縦断研究阿部 巧; 清野 諭; 遠峰 結衣; 西 真理子; 野藤 悠; 横山 友里; 山下 真里; 新開 省二; 藤原 佳典; 北村 明彦日本公衆衛生学会総会抄録集 79回 333 - 333 日本公衆衛生学会 2020年10月
- 高齢者の生活機能チェックによる要介護発生リスクの推定野藤 悠; 阿部 巧; 山下 真里; 清野 諭; 横山 友里; 成田 美紀; 村山 洋史; 吉田 由佳; 新開 省二; 北村 明彦日本公衆衛生学会総会抄録集 79回 386 - 386 日本公衆衛生学会 2020年10月
- 震災から8年後の被災地における地域在住高齢者の孤独感の関連要因山下 真里; 清野 諭; 野藤 悠; 菅原 康宏; 横山 友里; 西 真理子; 成田 美紀; 秦 俊貴; 新開 省二; 藤原 佳典; 北村 明彦; 東京都健康長寿医療センター研究所社会参加と地域保健研究チーム日本公衆衛生学会総会抄録集 79回 387 - 387 日本公衆衛生学会 2020年10月
- 孤食とフレイルまたは精神的健康との関連に社会的支援および孤立は交絡するか新開 省二; 清野 諭; 秦 俊貴; 遠峰 結衣; 西 真理子; 横山 友里; 野藤 悠; 成田 美紀; 北村 明彦日本公衆衛生学会総会抄録集 79回 251 - 251 日本公衆衛生学会 2020年10月
- 高齢者の身体活動、多様な食品摂取、社会参加が新規要介護認定に及ぼす累積的影響清野 諭; 新開 省二; 遠峰 結衣; 西 真理子; 秦 俊貴; 野藤 悠; 横山 友里; 成田 美紀; 藤原 佳典; 北村 明彦; 東京都健康長寿医療センター研究所社会参加と地域保健研究チーム日本公衆衛生学会総会抄録集 79回 253 - 253 日本公衆衛生学会 2020年10月
- 高齢期の社会参加が健康行動の継続に及ぼす影響 社会活動の種類に着目した縦断研究阿部 巧; 清野 諭; 遠峰 結衣; 西 真理子; 野藤 悠; 横山 友里; 山下 真里; 新開 省二; 藤原 佳典; 北村 明彦日本公衆衛生学会総会抄録集 79回 333 - 333 日本公衆衛生学会 2020年10月
- 高齢者の健康支援でのICT活用可能性 利用率と利用者特性、介護予防への影響の検討遠峰 結衣; 清野 諭; 秦 俊貴; 西 真理子; 野藤 悠; 横山 友里; 成田 美紀; 新開 省二; 藤原 佳典; 北村 明彦日本公衆衛生学会総会抄録集 79回 382 - 382 日本公衆衛生学会 2020年10月
- 高齢者の生活機能チェックによる要介護発生リスクの推定野藤 悠; 阿部 巧; 山下 真里; 清野 諭; 横山 友里; 成田 美紀; 村山 洋史; 吉田 由佳; 新開 省二; 北村 明彦日本公衆衛生学会総会抄録集 79回 386 - 386 日本公衆衛生学会 2020年10月
- 震災から8年後の被災地における地域在住高齢者の孤独感の関連要因山下 真里; 清野 諭; 野藤 悠; 菅原 康宏; 横山 友里; 西 真理子; 成田 美紀; 秦 俊貴; 新開 省二; 藤原 佳典; 北村 明彦; 東京都健康長寿医療センター研究所社会参加と地域保健研究チーム日本公衆衛生学会総会抄録集 79回 387 - 387 日本公衆衛生学会 2020年10月
- Takumi Abe; Akihiko Kitamura; Satoshi Seino; Yuri Yokoyama; Hidenori Amano; Yu Taniguchi; Mariko Nishi; Yu Nofuji; Tomoko Ikeuchi; Takemi Sugiyama; Shoji ShinkaiInternational journal of environmental research and public health 17 17 2020年09月
- 地域在住高齢者の身体組成指標と要介護化リスクとの量・反応関係清野 諭; 北村 明彦; 阿部 巧; 野藤 悠; 天野 秀紀; 横山 友里; 西 真理子; 成田 美紀; 谷口 優; 新開 省二日本老年医学会雑誌 57 Suppl. 83 - 83 (一社)日本老年医学会 2020年07月
- 高齢健診受診者におけるサルコペニアの有所見率と死亡・要介護リスク北村 明彦; 清野 諭; 阿部 巧; 野藤 悠; 天野 秀紀; 横山 友里; 西 真理子; 成田 美紀; 谷口 優; 新開 省二日本老年医学会雑誌 57 Suppl. 83 - 84 (一社)日本老年医学会 2020年07月
- 地域在住高齢者の血清アルブミン濃度と総死亡リスクとの量・反応関係新開 省二; 清野 諭; 阿部 巧; 野藤 悠; 天野 秀紀; 横山 友里; 西 真理子; 成田 美紀; 谷口 優; 北村 明彦日本老年医学会雑誌 57 Suppl. 94 - 94 (一社)日本老年医学会 2020年07月
- 地域在住高齢者における食品摂取多様性の加齢変化パターンとその予測要因成田 美紀; 北村 明彦; 谷口 優; 天野 秀紀; 西 真理子; 清野 諭; 横山 友里; 野藤 悠; 新開 省二日本老年医学会雑誌 57 Suppl. 96 - 96 (一社)日本老年医学会 2020年07月
- 地域在住高齢者の身体組成指標と要介護化リスクとの量・反応関係清野 諭; 北村 明彦; 阿部 巧; 野藤 悠; 天野 秀紀; 横山 友里; 西 真理子; 成田 美紀; 谷口 優; 新開 省二日本老年医学会雑誌 57 Suppl. 83 - 83 (一社)日本老年医学会 2020年07月
- 高齢健診受診者におけるサルコペニアの有所見率と死亡・要介護リスク北村 明彦; 清野 諭; 阿部 巧; 野藤 悠; 天野 秀紀; 横山 友里; 西 真理子; 成田 美紀; 谷口 優; 新開 省二日本老年医学会雑誌 57 Suppl. 83 - 84 (一社)日本老年医学会 2020年07月
- 地域在住高齢者の血清アルブミン濃度と総死亡リスクとの量・反応関係新開 省二; 清野 諭; 阿部 巧; 野藤 悠; 天野 秀紀; 横山 友里; 西 真理子; 成田 美紀; 谷口 優; 北村 明彦日本老年医学会雑誌 57 Suppl. 94 - 94 (一社)日本老年医学会 2020年07月
- 地域在住高齢者における食品摂取多様性の加齢変化パターンとその予測要因成田 美紀; 北村 明彦; 谷口 優; 天野 秀紀; 西 真理子; 清野 諭; 横山 友里; 野藤 悠; 新開 省二日本老年医学会雑誌 57 Suppl. 96 - 96 (一社)日本老年医学会 2020年07月
- 地域在住高齢者における咀嚼能力と歯数、栄養および体力指標との横断的関連小原 由紀; 白部 麻樹; 五十嵐 憲太郎; 野藤 悠; 横山 友里; 本川 佳子; 枝広 あや子; 平野 浩彦; 北村 明彦; 新開 省二日本老年医学会雑誌 57 Suppl. 132 - 132 (一社)日本老年医学会 2020年07月
- 野藤 悠; 天野 秀紀; 横山 友里; 吉田 由佳; 谷垣 知美; 清野 諭; 成田 美紀; 北村 明彦; 新開 省二老年社会科学 42 2 137 - 137 日本老年社会科学会 2020年06月
- 清野 諭; 北村 明彦; 遠峰 結衣; 西 真理子; 野藤 悠; 横山 友里; 天野 秀紀; 藤原 佳典; 新開 省二老年社会科学 42 2 139 - 139 日本老年社会科学会 2020年06月
- 野藤 悠; 天野 秀紀; 横山 友里; 吉田 由佳; 谷垣 知美; 清野 諭; 成田 美紀; 北村 明彦; 新開 省二老年社会科学 42 2 137 - 137 日本老年社会科学会 2020年06月
- Satoshi Seino; Akihiko Kitamura; Takumi Abe; Yu Taniguchi; Yuri Yokoyama; Hidenori Amano; Mariko Nishi; Yu Nofuji; Miki Narita; Tomoko Ikeuchi; Yoshinori Fujiwara; Shoji ShinkaiJournal of the American Medical Directors Association 21 6 726 - 733 2020年06月
- Takumi Abe; Yu Nofuji; Satoshi Seino; Hiroshi Murayama; Yuka Yoshida; Tomomi Tanigaki; Yuri Yokoyama; Miki Narita; Mariko Nishi; Akihiko Kitamura; Shoji ShinkaiMaturitas 136 54 - 59 2020年06月
- 横山 友里; 新開 省二; 清野 諭; 光武 誠吾; 西 真理子; 村山 洋史; 成田 美紀; 石崎 達郎; 野藤 悠; 北村 明彦日本公衆衛生雑誌 67 10 752 - 762 日本公衆衛生学会 2020年
- 清野 諭; 天野 秀紀; 藤原 佳典; 新開 省二; 北村 明彦; 遠峰 結衣; 田中 泉澄; 西 真理子; 野藤 悠; 横山 友里; 野中 久美子; 倉岡 正高日本公衆衛生雑誌 67 6 399 - 412 日本公衆衛生学会 2020年
- 北村 明彦; 阿部 巧; 藤原 佳典; 新開 省二; 清野 諭; 谷口 優; 横山 友里; 天野 秀紀; 西 真理子; 野藤 悠; 成田 美紀; 池内 朋子日本公衆衛生雑誌 67 2 134 - 145 日本公衆衛生学会 2020年
- 北村 明彦; 清野 諭; 野藤 悠; 藤原 佳典; 新開 省二地域保健 = The Japanese journal of community health care 50 6 34 - 39 東京法規出版 2019年11月
- 地域在住高齢者の主観的な「若返り」は身体的健康の予測因子となりうるか池内 朋子; 清野 諭; 谷口 優; 野藤 悠; 北村 明彦; 新開 省二日本応用老年学会大会 14回 37 - 37 (一社)日本応用老年学会 2019年10月
- 高齢住民に介護予防につながる行動変容を促す機能チェックフィードバック票の開発北村 明彦; 西 真理子; 清野 諭; 横山 友里; 野藤 悠; 谷口 優; 遠峰 結衣; 天野 秀紀; 藤原 佳典; 新開 省二日本公衆衛生学会総会抄録集 78回 233 - 233 日本公衆衛生学会 2019年10月
- 地域資源や社会参加へのニーズが乏しい高齢者の特徴 インタビュー調査の分析山下 真里; 西 真理子; 北村 明彦; 横山 友里; 清野 諭; 野藤 悠; 藤原 佳典; 新開 省二日本公衆衛生学会総会抄録集 78回 233 - 233 日本公衆衛生学会 2019年10月
- 住民主体で運営するフレイル予防教室の栄養プログラムの効果野藤 悠; 横山 友里; 成田 美紀; 清野 諭; 村山 洋史; 吉田 由佳; 谷垣 知美; 北村 明彦; 新開 省二日本公衆衛生学会総会抄録集 78回 405 - 405 日本公衆衛生学会 2019年10月
- 地域高齢者における血清総コレステロール値と総死亡リスクとの量・反応関係新開 省二; 清野 諭; 谷口 優; 横山 友里; 西 真理子; 天野 秀紀; 野藤 悠; 成田 美紀; 池内 朋子; 阿部 巧; 北村 明彦日本公衆衛生学会総会抄録集 78回 430 - 430 日本公衆衛生学会 2019年10月
- フレイル改善のための複合プログラムが要介護・死亡リスクと介護給付費に及ぼす影響横山 友里; 清野 諭; 光武 誠吾; 西 真理子; 村山 洋史; 成田 美紀; 石崎 達郎; 野藤 悠; 北村 明彦; 新開 省二日本公衆衛生学会総会抄録集 78回 413 - 413 日本公衆衛生学会 2019年10月
- Satoshi Seino; Akihiko Kitamura; Yui Tomine; Izumi Tanaka; Mariko Nishi; Kumiko Nonaka; Yu Nofuji; Miki Narita; Yu Taniguchi; Yuri Yokoyama; Hidenori Amano; Tomoko Ikeuchi; Yoshinori Fujiwara; Shoji ShinkaiJournal of epidemiology 29 2 73 - 81 2019年02月
- Yu Taniguchi; Akihiko Kitamura; Yu Nofuji; Tatsuro Ishizaki; Satoshi Seino; Yuri Yokoyama; Tomohiro Shinozaki; Hiroshi Murayama; Seigo Mitsutake; Hidenori Amano; Mariko Nishi; Yutaka Matsuyama; Yoshinori Fujiwara; Shoji ShinkaiThe journals of gerontology. Series A, Biological sciences and medical sciences 74 2 211 - 218 2019年01月
- 野藤 悠; 北村 明彦; 新開 省二; 清野 諭; 村山 洋史; 吉田 由佳; 谷垣 知美; 横山 友里; 成田 美紀; 西 真理子; 中村 正和日本公衆衛生雑誌 66 9 560 - 573 日本公衆衛生学会 2019年
- 清野 諭; 野藤 悠体力科学 68 5 327 - 335 一般社団法人日本体力医学会 2019年
- 小岩井 馨; 武見 ゆかり; 林 芙美; 緒方 裕光; 坂口 景子; 嶋田 雅子; 川畑 輝子; 野藤 悠; 中村 正和日本健康教育学会誌 27 1 13 - 28 日本健康教育学会 2019年
- 嶋田 雅子; 川畑 輝子; 野藤 悠; 中村 正和; 小岩井 馨; 坂口 景子; 林 芙美; 武見 ゆかり月刊地域医学 = Monthly community medicine 32 11 990 - 994 地域医療振興協会地域医療研究所 ; 1987- 2018年11月
- 認知機能の変化パターンと医療費及び介護費との関連 草津町研究谷口 優; 北村 明彦; 石崎 達郎; 清野 諭; 横山 友里; 藤原 佳典; 鈴木 宏幸; 光武 誠吾; 野藤 悠; 天野 秀紀; 西 真理子; 干川 なつみ; 濱口 奈緒美; 岡部 たづる; 新開 省二日本公衆衛生学会総会抄録集 77回 205 - 205 日本公衆衛生学会 2018年10月
- 地域におけるフレイル予防 兵庫県養父市の取り組み野藤 悠; 新開 省二; 吉田 由佳; 谷垣 知美; 清野 諭; 村山 洋史; 北村 明彦日本公衆衛生学会総会抄録集 77回 420 - 420 日本公衆衛生学会 2018年10月
- 地域におけるフレイル予防 埼玉県シルバー人材センターの取り組み新開 省二; 野藤 悠; 大須賀 洋祐; 清野 諭; 成田 美紀; 北村 明彦; 岡野 巧; 窪川 真治; 藤倉 とし枝日本公衆衛生学会総会抄録集 77回 420 - 420 日本公衆衛生学会 2018年10月
- 嶋田 雅子; 川畑 輝子; 野藤 悠; 中村 正和; 小岩井 馨; 林 芙美; 武見 ゆかり; 松本 彩香月刊地域医学 = Monthly community medicine 32 8 696 - 722 地域医療振興協会地域医療研究所 ; 1987- 2018年08月
- 野藤 悠; 清野 諭; 横山 友里月刊地域医学 = Monthly community medicine 32 5 406 - 414 地域医療振興協会地域医療研究所 ; 1987- 2018年05月
- 野藤 悠; 清野 諭月刊地域医学 = Monthly community medicine 32 4 312 - 320 地域医療振興協会地域医療研究所 ; 1987- 2018年04月
- 清野 諭; 西 真理子; 村山 洋史; 成田 美紀; 横山 友里; 野藤 悠; 北村 明彦若手研究者のための健康科学研究助成成果報告書 = Research-aid report 33 23 - 27 明治安田厚生事業団 2018年04月
- 清野 諭; 野藤 悠; 北村 明彦; 新開 省二介護予防・健康づくり 5 2 71 - 77 日本介護予防・健康づくり学会 ; 2018- 2018年
- Yu Taniguchi; Akihiko Kitamura; Hiroshi Murayama; Hidenori Amano; Tomohiro Shinozaki; Isao Yokota; Satoshi Seino; Yu Nofuji; Mariko Nishi; Yuri Yokoyama; Yutaka Matsuyama; Yoshinori Fujiwara; Shoji ShinkaiGeriatrics & gerontology international 17 11 1928 - 1935 2017年11月
- Satoshi Seino; Mariko Nishi; Hiroshi Murayama; Miki Narita; Yuri Yokoyama; Yu Nofuji; Yu Taniguchi; Hidenori Amano; Akihiko Kitamura; Shoji ShinkaiGeriatrics & gerontology international 17 11 2034 - 2045 2017年11月
- 高次生活機能の加齢変化パターンと医療費及び介護費との関連 草津町研究谷口 優; 北村 明彦; 野藤 悠; 石崎 達郎; 清野 諭; 横山 友里; 村山 洋史; 光武 誠吾; 天野 秀紀; 西 真理子; 干川 なつみ; 濱口 奈緒美; 岡部 たづる; 藤原 佳典; 新開 省二日本公衆衛生学会総会抄録集 76回 396 - 396 日本公衆衛生学会 2017年10月
- 辻 大士; 斎藤 民; 野藤 悠; 横山 友里; 中村 廣隆; 吉田 由佳; 岩﨑 文江; 楢﨑 兼司健康支援 = Japanese journal of health promotion 19 2 167 - 178 日本健康支援学会 2017年09月
- 脈波伝播速度の加齢変化パターンと死因別死亡に関する前向き研究谷口 優; 北村 明彦; 清野 諭; 村山 洋史; 野藤 悠; 横山 友里; 西 真理子; 天野 秀紀; 藤原 佳典; 新開 省二日本老年医学会雑誌 54 Suppl. 172 - 172 (一社)日本老年医学会 2017年05月
- 吉葉 かおり; 野藤 悠; 嶋田 雅子; 中村 正和月刊地域医学 = Monthly community medicine 31 3 206 - 210 地域医療振興協会地域医療研究所 ; 1987- 2017年03月
- Yu Taniguchi; Akihiko Kitamura; Satoshi Seino; Hiroshi Murayama; Hidenori Amano; Yu Nofuji; Mariko Nishi; Yuri Yokoyama; Tomohiro Shinozaki; Isao Yokota; Yutaka Matsuyama; Yoshinori Fujiwara; Shoji ShinkaiJournal of the American Medical Directors Association 18 2 192.e13-192.e20 2017年02月
- 野藤 悠; 吉葉 かおり; 嶋田 雅子; 中村 正和月刊地域医学 = Monthly community medicine 31 2 122 - 129 地域医療振興協会地域医療研究所 ; 1987- 2017年02月
- Yuri Yokoyama; M. Nishi; H. Murayama; H. Amano; Y. Taniguchi; Y. Nofuji; M. Narita; E. Matsuo; S. Seino; Y. Kawano; S. ShinkaiThe journal of nutrition, health & aging 21 1 11 - 16 2017年01月
- Yu Taniguchi; Yoshinori Fujiwara; Hiroshi Murayama; Isao Yokota; Eri Matsuo; Satoshi Seino; Yu Nofuji; Mariko Nishi; Yutaka Matsuyama; Shoji ShinkaiThe journals of gerontology. Series A, Biological sciences and medical sciences 71 11 1492 - 1499 2016年11月
- 高齢者健診受診者における認知機能推移パタンと要介護化・死亡リスクとの関係天野 秀紀; 西 真理子; 谷口 優; 清野 諭; 横山 友里; 北村 明彦; 藤原 佳典; 吉田 裕人; 渡辺 直紀; 李 相侖; 村山 洋史; 野藤 悠; 新開 省二日本公衆衛生学会総会抄録集 75回 494 - 494 日本公衆衛生学会 2016年10月
- 群馬県草津町における介護予防14年間の成果 要介護認定率、発生率の推移北村 明彦; 谷口 優; 横山 友里; 天野 秀紀; 清野 諭; 西 真理子; 野藤 悠; 村山 洋史; 岡部 たづる; 干川 なつみ; 藤原 佳典; 新開 省二日本公衆衛生学会総会抄録集 75回 507 - 507 日本公衆衛生学会 2016年10月
- 群馬県草津町における介護予防14年間の成果 高齢住民の機能的健康度の推移谷口 優; 北村 明彦; 横山 友里; 天野 秀紀; 清野 諭; 西 真理子; 野藤 悠; 村山 洋史; 岡部 たづる; 干川 なつみ; 藤原 佳典; 新開 省二日本公衆衛生学会総会抄録集 75回 507 - 507 日本公衆衛生学会 2016年10月
- Yuri Yokoyama; M. Nishi; H. Murayama; H. Amano; Y. Taniguchi; Y. Nofuji; M. Narita; E. Matsuo; S. Seino; Y. Kawano; S. ShinkaiThe journal of nutrition, health & aging 20 7 691 - 696 2016年07月
- 中村 正和; 嶋田 雅子; 増居 志津子; 吉葉 かおり; 野藤 悠; 阪本 康子; 保科 ゆい子地域医学 30 6 472 - 475 (公社)地域医療振興協会 2016年06月
- Sanmei Chen; Takanori Honda; Kenji Narazaki; Tao Chen; Yu Nofuji; Shuzo KumagaiGeriatrics & gerontology international 16 6 729 - 36 2016年06月
- 身体機能の加齢変化パターンと余命に関する前向き研究谷口 優; 清野 諭; 村山 洋史; 野藤 悠; 藤原 佳典; 西 真理子; 天野 秀紀; 新開 省二日本老年医学会雑誌 53 Suppl. 133 - 133 (一社)日本老年医学会 2016年05月
- 地域高齢者における食品摂取の多様性とサルコペニアとの関連成田 美紀; 横山 友里; 西 真理子; 村山 洋史; 谷口 優; 清野 諭; 天野 秀紀; 野藤 悠; 新開 省二日本老年医学会雑誌 53 Suppl. 103 - 103 (一社)日本老年医学会 2016年05月
- 吉田 由佳; 野藤 悠保健師ジャーナル 72 4 310 - 314 医学書院 2016年04月
- Shoji Shinkai; Hiroto Yoshida; Yu Taniguchi; Hiroshi Murayama; Mariko Nishi; Hidenori Amano; Yu Nofuji; Satoshi Seino; Yoshinori FujiwaraGeriatrics & gerontology international 16 Suppl 1 87 - 97 2016年03月
- 野藤 悠月刊地域医学 = Monthly community medicine 30 3 205 - 210 地域医療振興協会地域医療研究所 ; 1987- 2016年03月
- Yu Nofuji; Shoji Shinkai; Yu Taniguchi; Hidenori Amano; Mariko Nishi; Hiroshi Murayama; Yoshinori Fujiwara; Takao SuzukiJournal of the American Medical Directors Association 17 2 184.e1-7 2016年02月
- 清野 諭; 野藤 悠体力科学 65 1 33 - 33 一般社団法人日本体力医学会 2016年
- 長野 真弓; 森山 善彦; 畑山 知子; 野藤 悠; 西内 久人; 熊谷 秋三体力科学 65 3 315 - 326 一般社団法人日本体力医学会 2016年
- 行政区単位に虚弱予防教室の開設を目指して 兵庫県養父市における取組みの概要谷垣 知美; 吉田 由佳; 野藤 悠; 清野 諭; 新開 省二日本公衆衛生学会総会抄録集 74回 349 - 349 日本公衆衛生学会 2015年10月
- 行政区単位に虚弱予防教室の開設を目指して 兵庫県養父市における取組みの評価野藤 悠; 吉田 由佳; 谷垣 知美; 清野 諭; 新開 省二日本公衆衛生学会総会抄録集 74回 349 - 349 日本公衆衛生学会 2015年10月
- 行政区単位に虚弱予防教室の開設を目指して 継続化支援のポイント吉田 由佳; 谷垣 知美; 野藤 悠; 清野 諭; 新開 省二日本公衆衛生学会総会抄録集 74回 349 - 349 日本公衆衛生学会 2015年10月
- 草津町における介護予防共同研究事業からみた高齢者保健の課題新開 省二; 吉田 裕人; 藤原 佳典; 天野 秀紀; 西 真理子; 村山 洋史; 谷口 優; 野藤 悠; 清野 諭; 岡部 たづる; 干川 なつみ日本公衆衛生学会総会抄録集 74回 366 - 366 日本公衆衛生学会 2015年10月
- 地域高齢者健康モニター事業による健康認識およびソーシャルキャピタル醸成効果の検討成田 美紀; 西 真理子; 村山 洋史; 野藤 悠; 谷口 優; 天野 秀紀; 清野 諭; 横山 友里; 新開 省二日本公衆衛生学会総会抄録集 74回 371 - 371 日本公衆衛生学会 2015年10月
- 認知機能の加齢変化パターンと認知症発症に関する前向き研究谷口 優; 村山 洋史; 清野 諭; 野藤 悠; 松尾 恵理; 西 真理子; 天野 秀紀; 横山 友里; 成田 美紀; 藤原 佳典; 新開 省二日本公衆衛生学会総会抄録集 74回 372 - 372 日本公衆衛生学会 2015年10月
- 日本人高齢者向けのサルコペニア基準の提案と簡易チェックシステム作成の試み清野 諭; 新開 省二; 谷口 優; 西 真理子; 天野 秀紀; 村山 洋史; 野藤 悠; 成田 美紀; 横山 友里; 藤原 佳典; 大渕 修一; 河合 恒; 吉田 英世; 飯島 勝矢; 高橋 龍太郎日本公衆衛生学会総会抄録集 74回 373 - 373 日本公衆衛生学会 2015年10月
- 長野 真弓; 松尾 恵理; 森山 善彦; 野藤 悠; 畑山 知子; 西内 久人; 熊谷 秋三運動疫学研究: Research in Exercise Epidemiology 17 2 158 - 158 日本運動疫学会 2015年09月
- Tao Chen; Kenji Narazaki; Takanori Honda; Sanmei Chen; Yuki Haeuchi; Yu Y Nofuji; Eri Matsuo; Shuzo KumagaiJournal of sports science & medicine 14 3 507 - 14 2015年09月
- Chen Sanmei; Honda Takanori; Narazaki Kenji; Chen Tao; Nofuji Yu; Haeuchi Yuka; Kumagai ShuzoAlzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association 11 7 732 - 733 2015年07月 [査読有り]
- Hiroshi Murayama; Mariko Nishi; Yu Nofuji; Eri Matsuo; Yu Taniguchi; Hidenori Amano; Yuri Yokoyama; Yoshinori Fujiwara; Shoji ShinkaiHealth & place 34 270 - 8 2015年07月
- 地域高齢者健診受診者における認知機能低下の促進・抑制要因天野 秀紀; 西 真理子; 村山 洋史; 谷口 優; 野藤 悠; 松尾 恵理; 清野 諭; 藤原 佳典; 吉田 裕人; 新開 省二日本老年医学会雑誌 52 Suppl. 60 - 60 (一社)日本老年医学会 2015年05月
- 体力指標は高齢期の認知機能の軌跡にどう影響するか? 10年間の縦断データからの知見村山 洋史; 谷口 優; 天野 秀紀; 西 真理子; 野藤 悠; 清野 諭; 松尾 恵理; 深谷 太郎; 藤原 佳典; 新開 省二日本老年医学会雑誌 52 Suppl. 105 - 105 (一社)日本老年医学会 2015年05月
- 地域高齢者の健康余命に及ぼすメタボリック症候群の影響新開 省二; 西 真理子; 村山 洋史; 谷口 優; 天野 秀紀; 清野 諭; 野藤 悠; 成田 美紀; 松尾 恵理; 藤原 佳典日本老年医学会雑誌 52 Suppl. 84 - 84 (一社)日本老年医学会 2015年05月
- Hiroshi Murayama; Yu Nofuji; Eri Matsuo; Mariko Nishi; Yu Taniguchi; Yoshinori Fujiwara; Shoji ShinkaiSocial science & medicine (1982) 124 171 - 9 2015年01月
- Yu Taniguchi; Yoshinori Fujiwara; Yu Nofuji; Mariko Nishi; Hiroshi Murayama; Satoshi Seino; Rika Tajima; Yutaka Matsuyama; Shoji ShinkaiJournal of epidemiology 25 9 592 - 9 2015年
- 野藤 悠介護福祉・健康づくり 2 2 104 - 107 [日本介護福祉・健康づくり学会] ; 2014- 2015年
- 谷口 優; 清野 諭; 藤原 佳典; 野藤 悠; 西 真理子; 村山 洋史; 天野 秀紀; 松尾 恵理; 新開 省二日本老年医学会雑誌 52 3 269 - 77 一般社団法人 日本老年医学会 2015年
- 谷口 優; 松尾 恵理; 横山 友里; 新開 省二; 藤原 佳典; 篠崎 智大; 天野 秀紀; 西 真理子; 村山 洋史; 野藤 悠; 清野 諭; 成田 美紀日本老年医学会雑誌 52 1 86 - 93 一般社団法人 日本老年医学会 2015年
- Yu Taniguchi; Shoji Shinkai; Mariko Nishi; Hiroshi Murayama; Yu Nofuji; Hiroto Yoshida; Yoshinori FujiwaraThe journals of gerontology. Series A, Biological sciences and medical sciences 69 10 1276 - 83 2014年10月
- 地域在住高齢者における余命及び健康余命に関する前向き研究 栄養指標との関連横山 友里; 村山 洋史; 西 真理子; 天野 秀紀; 清野 諭; 野藤 悠; 谷口 優; 松尾 恵理; 成田 美紀; 藤原 佳典; 川野 因; 新開 省二日本公衆衛生学会総会抄録集 73回 441 - 441 日本公衆衛生学会 2014年10月
- 地域在住高齢者における余命及び健康余命に関する前向き研究 体力指標との関連谷口 優; 横山 友里; 村山 洋史; 西 真理子; 天野 秀紀; 清野 諭; 野藤 悠; 松尾 恵理; 成田 美紀; 藤原 佳典; 新開 省二日本公衆衛生学会総会抄録集 73回 441 - 441 日本公衆衛生学会 2014年10月
- 高齢期の虚弱化を先送りする社会システムの開発 ねらいと概要新開 省二; 野藤 悠; 松尾 恵理; 西 真理子; 村山 洋史; 谷口 優; 天野 秀紀; 清野 諭; 成田 美紀; 横山 友里; 小森 昌彦; 中西 智也; 北川 博巳日本公衆衛生学会総会抄録集 73回 451 - 451 日本公衆衛生学会 2014年10月
- 高齢期の虚弱化を先送りする社会システムの開発 虚弱の一次予防に向けた取り組み松尾 恵理; 野藤 悠; 西 真理子; 村山 洋史; 谷口 優; 天野 秀紀; 清野 諭; 成田 美紀; 横山 友里; 新開 省二; 吉田 由佳; 谷垣 知美; 齋藤 芸路日本公衆衛生学会総会抄録集 73回 452 - 452 日本公衆衛生学会 2014年10月
- 高齢期の虚弱化を先送りする社会システムの開発 虚弱の二次予防に向けた取り組み清野 諭; 野藤 悠; 松尾 恵理; 西 真理子; 村山 洋史; 谷口 優; 天野 秀紀; 成田 美紀; 横山 友里; 新開 省二日本公衆衛生学会総会抄録集 73回 452 - 452 日本公衆衛生学会 2014年10月
- 高齢期の虚弱化を先送りする社会システムの開発 虚弱の三次予防に向けた取り組み西 真理子; 清野 諭; 野藤 悠; 松尾 恵理; 村山 洋史; 天野 秀紀; 成田 美紀; 谷口 優; 横山 友里; 新開 省二; 山口 貴代美; 齋藤 芸路日本公衆衛生学会総会抄録集 73回 452 - 452 日本公衆衛生学会 2014年10月
- 高齢期の虚弱化を先送りする社会システムの開発 二地域での実装実験野藤 悠; 松尾 恵理; 西 真理子; 村山 洋史; 天野 秀紀; 清野 諭; 成田 美紀; 横山 友里; 谷口 優; 新開 省二; 吉田 由佳; 谷垣 知美; 山口 貴代美日本公衆衛生学会総会抄録集 73回 452 - 452 日本公衆衛生学会 2014年10月
- 野藤 悠; 新開 省二; 吉田 裕人厚生の指標 61 12 28 - 35 厚生労働統計協会 2014年10月
- Kenji Narazaki; Eri Matsuo; Takanori Honda; Yu Nofuji; Koji Yonemoto; Shuzo KumagaiJournal of Sports Science and Medicine 13 3 590 - 596 2014年09月
- Kenji Narazaki; Eri Matsuo; Takanori Honda; Yu Nofuji; Koji Yonemoto; Shuzo KumagaiJournal of sports science & medicine 13 3 590 - 6 2014年09月
- 地域高齢者の健康余命に関するコホート研究 歩行機能との関連谷口 優; 西 真理子; 清野 諭; 藤原 佳典; 野藤 悠; 天野 秀紀; 村山 洋史; 松尾 恵理; 横山 友里; 新開 省二日本老年医学会雑誌 51 Suppl. 54 - 55 (一社)日本老年医学会 2014年05月
- 地域高齢者の健康余命に関するコホート研究 栄養状態との関連新開 省二; 西 真理子; 谷口 優; 天野 秀紀; 村山 洋史; 野藤 悠; 成田 美紀; 松尾 恵理; 横山 友里; 藤原 佳典日本老年医学会雑誌 51 Suppl. 55 - 55 (一社)日本老年医学会 2014年05月
- 地域在住高齢者の健康指標としての筋量測定部位と補正方法に関する検討 新規要介護認定との関連分析より清野 諭; 西 真理子; 谷口 優; 天野 秀紀; 村山 洋史; 野藤 悠; 成田 美紀; 松尾 恵理; 藤原 佳典; 新開 省二日本老年医学会雑誌 51 Suppl. 79 - 79 (一社)日本老年医学会 2014年05月
- 地域在住高齢者における食品摂取の多様性と体組成との関連横山 友里; 西 真理子; 村山 洋史; 天野 秀紀; 谷口 優; 野藤 悠; 成田 美紀; 松尾 恵理; 川野 因; 新開 省二日本老年医学会雑誌 51 Suppl. 106 - 106 (一社)日本老年医学会 2014年05月
- 楢崎 兼司; 松尾 恵理; 本田 貴紀; 野藤 悠; 米本 孝二; 熊谷 秋三運動疫学研究: Research in Exercise Epidemiology 16 1 58 - 58 日本運動疫学会 2014年03月
- Hiroshi Murayama; Yu Nofuji; Eri Matsuo; Mariko Nishi; Yu Taniguchi; Yoshinori Fujiwara; Shoji ShinkaiJournal of epidemiology 24 6 519 - 25 2014年
- 本田 貴紀; 楢崎 兼司; 陳 涛; 西内 久人; 野藤 悠; 松尾 恵理; 熊谷 秋三運動疫学研究 16 1 24 - 33 日本運動疫学会 2014年
- 清野 諭; 松尾 恵理; 干川 なつみ; 土屋 由美子; 新開 省二; 谷口 優; 吉田 裕人; 藤原 佳典; 天野 秀紀; 深谷 太郎; 西 真理子; 村山 洋史; 野藤 悠日本公衆衛生雑誌 61 6 286 - 298 日本公衆衛生学会 2014年
- 本田 貴紀; 野藤 悠; 松尾 恵理; 楢崎 兼司; 陳 涛; 永吉 翔; 熊谷 秋三体力科学 63 1 77 - 77 一般社団法人日本体力医学会 2014年
- Hiroshi Murayama; Mariko Nishi; Eri Matsuo; Yu Nofuji; Yumiko Shimizu; Yu Taniguchi; Yoshinori Fujiwara; Shoji ShinkaiSocial science & medicine (1982) 98 247 - 52 2013年12月
- 地域在住自立高齢者の体力基準値作成の試み 性・年齢階級別の検討清野 諭; 吉田 裕人; 天野 秀紀; 西 真理子; 村山 洋史; 谷口 優; 野藤 悠; 内田 勇人; 熊谷 修; 渡辺 修一郎; 藤原 佳典; 新開 省二日本公衆衛生学会総会抄録集 72回 400 - 400 日本公衆衛生学会 2013年10月
- 地域在宅高齢者における食品摂取の多様性 栄養指標としての意義成田 美紀; 新開 省二; 横山 友里; 西 真理子; 村山 洋史; 清水 由美子; 天野 秀紀; 谷口 優; 野藤 悠; 松尾 恵理日本公衆衛生学会総会抄録集 72回 209 - 209 日本公衆衛生学会 2013年10月
- 地域在住高齢者における食品摂取の多様性 貧血との関連横山 友里; 西 真理子; 村山 洋史; 清水 由美子; 天野 秀紀; 谷口 優; 野藤 悠; 成田 美紀; 松尾 恵理; 川野 因; 新開 省二日本公衆衛生学会総会抄録集 72回 209 - 209 日本公衆衛生学会 2013年10月
- 新開 省二; 吉田 裕人; 藤原 佳典; 天野 秀紀; 深谷 太郎; 李 相倫; 渡辺 直紀; 渡辺 修一郎; 熊谷 修; 西 真理子; 村山 洋史; 谷口 優; 小宇 佐陽子; 大場 宏美; 清水 由美子; 野藤 悠; 岡部 たづる; 干川 なつみ; 土屋 由美子日本公衆衛生雑誌 60 9 596 - 605 日本公衆衛生学会 2013年09月
- 地域高齢者における虚弱の疫学研究 虚弱とadverse health outcomesとの関係成田 美紀; 新開 省二; 西 真理子; 野藤 悠; 谷口 優; 天野 秀紀; 村山 洋史; 松尾 恵理; 藤原 佳典; 吉田 裕人日本老年医学会雑誌 50 Suppl. 68 - 68 (一社)日本老年医学会 2013年05月
- 地域高齢者における虚弱の疫学研究 介護予防チェックリストの虚弱指標としての妥当性新開 省二; 西 真理子; 野藤 悠; 谷口 優; 天野 秀紀; 村山 洋史; 成田 美紀; 松尾 恵理; 藤原 佳典; 吉田 裕人日本老年医学会雑誌 50 Suppl. 73 - 73 (一社)日本老年医学会 2013年05月
- 地域高齢者における虚弱の疫学研究 虚弱の予測因子野藤 悠; 西 真理子; 成田 美紀; 吉田 裕人; 天野 秀紀; 村山 洋史; 谷口 優; 深谷 太郎; 藤原 佳典; 新開 省二日本老年医学会雑誌 50 Suppl. 74 - 74 (一社)日本老年医学会 2013年05月
- 地域高齢者における虚弱の疫学研究 老年症候群と虚弱との関連西 真理子; 吉田 裕人; 野藤 悠; 天野 秀紀; 谷口 優; 村山 洋史; 成田 美紀; 藤原 佳典; 深谷 太郎; 新開 省二日本老年医学会雑誌 50 Suppl. 113 - 113 (一社)日本老年医学会 2013年05月
- Kenji Narazaki; Yu Nofuji; Takanori Honda; Eri Matsuo; Koji Yonemoto; Shuzo KumagaiNeuroepidemiology 40 1 23 - 29 2012年12月
- 認知機能に及ぼす下肢運動機能強化プログラムの効果について長野 真弓; 野藤 悠; 佐藤 宏徳; 松尾 恵理; 森山 善彦; 熊谷 秋三健康支援 14 1 81 - 81 日本健康支援学会 2012年02月
- Yu Nofuji; Masataka Suwa; Haruka Sasaki; Atsushi Ichimiya; Reiko Nishichi; Shuzo KumagaiJournal of sports science & medicine 11 1 83 - 8 2012年
- 地域在住女性高齢者のBMIとうつ状態との関連性 太宰府研究西内 久人; 松尾 恵理; 野藤 悠; 森山 善彦; 佐藤 広徳; 長野 真弓; 熊谷 秋三体力科学 60 6 810 - 810 (一社)日本体力医学会 2011年12月
- 地域在住高齢者の身体活動量、体力と認知機能について 太宰府研究森山 善彦; 松尾 恵理; 野藤 悠; 長野 真弓; 熊谷 秋三体力科学 60 6 814 - 814 (一社)日本体力医学会 2011年12月
- 齊藤 貴文; 崎田 正博; 松尾 恵理; 野藤 悠; 森山 善彦; 長野 真弓; 古賀 崇正; 熊谷 秋三ヘルスプロモーション理学療法研究 1 1 21 - 28 日本ヘルスプロモーション理学療法学会 2011年
- 野藤 悠; 山下 幸子; 林 直亨; 熊谷 秋三健康科学 33 79 - 81 九州大学健康科学センター 2011年
- 地域在住高齢者における認知機能低下・うつ・閉じこもりの重複と身体活動量との関連性長野 真弓; 野藤 悠; 森山 善彦; 井出 幸二郎; 熊谷 秋三体力科学 59 6 842 - 842 (一社)日本体力医学会 2010年12月
- 野藤 悠; 松尾 恵理; 大島 秀武; 岸本 裕代; 長野 真弓; 熊谷 秋三運動疫学研究: Research in Exercise Epidemiology 12 32 - 33 日本運動疫学会 2010年03月
- 地域在住高齢者の身体活動量の実態 太宰府研究野藤 悠; 松尾 恵理; 大島 秀武; 岸本 裕代; 長野 真弓; 熊谷 秋三健康支援 12 1 81 - 81 日本健康支援学会 2010年02月
- 岸本 裕代; 大島 秀武; 野藤 悠健康科学 32 97 - 102 九州大学健康科学センター 2010年
- 野藤 悠; 諏訪 雅貴; 佐々木 悠; 熊谷 秋三健康科学 31 49 - 59 九州大学健康科学センター 2009年
- Yu Nofuji; Masataka Suwa; Yoshihiko Moriyama; Hiroshi Nakano; Atsushi Ichimiya; Reiko Nishichi; Haruka Sasaki; Zsolt Radak; Shuzo KumagaiNeuroscience letters 437 1 29 - 32 2008年05月
- 熊谷 秋三; 中野 裕史; 野藤 悠運動疫学研究 9 1 - 15 運動疫学研究会 2007年
- Masataka Suwa; Hiroyo Kishimoto; Yu Nofuji; Hiroshi Nakano; Haruka Sasaki; Zsolt Radak; Shuzo KumagaiMetabolism: clinical and experimental 55 7 852 - 7 2006年07月
MISC
- 森裕樹; 野藤悠; 清野諭; 秦俊貴; 藤原佳典 日本公衆衛生学会総会抄録集(CD-ROM) 81st 2022年
- 清野諭; 植田拓也; 森裕樹; 野藤悠; 根本裕太 PDCAサイクルに沿った介護予防の取組推進のための通いの場等の効果検証と評価の枠組み構築に関する研究 令和3年度 総括・分担研究報告書(Web) 2022年
- 嶋田 雅子; 川畑 輝子; 中村 正和; 野藤 悠 月刊地域医学 = Monthly community medicine 33 (6) 478 -483 2019年06月
- 川畑 輝子; 嶋田 雅子; 野藤 悠; 中村 正和; 牧野 伸子; 中村 好一 月刊地域医学 = Monthly community medicine 33 (3) 222 -229 2019年03月
- 大井 志依; 土屋 純子; 下谷 みさと; 黒岩 達哉; 目黒 真理; 川畑 輝子; 野藤 悠 月刊地域医学 = Monthly community medicine 32 (3) 228 -232 2018年03月
- 嶋田 雅子; 川畑 輝子; 野藤 悠; 中村 正和 月刊地域医学 = Monthly community medicine 31 (8) 640 -643 2017年08月
- 中村 正和; 嶋田 雅子; 増居 志津子; 野藤 悠; 阪本 康子; 川畑 輝子 月刊地域医学 = Monthly community medicine 31 (6) 482 -485 2017年06月
- 嶋田 雅子; 野藤 悠; 吉葉 かおり; 中村 正和; 牧野 伸子; 中村 好一 月刊地域医学 = Monthly community medicine 31 (4) 308 -313 2017年04月
- 野藤 悠; 吉葉 かおり; 嶋田 雅子; 中村 正和 月刊地域医学 = Monthly community medicine 31 (1) 46 -49 2017年01月
- 嶋田 雅子; 野藤 悠; 吉葉 かおり; 中村 正和 月刊地域医学 = Monthly community medicine 30 (11) 946 -949 2016年11月
- 柳川 洋; 吉葉 かおり; 嶋田 雅子; 野藤 悠; 阪本 康子; 保科 ゆい子; 中村 正和; 若林 チヒロ; 笹尾 久美子; 新村 洋未 月刊地域医学 = Monthly community medicine 30 (7) 578 -584 2016年07月
- 嶋田 雅子; 保科 ゆい子; 吉葉 かおり; 野藤 悠; 増居 志津子; 中村 正和 月刊地域医学 = Monthly community medicine 30 (5) 386 -389 2016年05月
- 野藤 悠; 吉葉 かおり; 阪本 康子; 嶋田 雅子; 中村 正和 月刊地域医学 = Monthly community medicine 30 (4) 290 -292 2016年04月
- 西 真理子; 吉田 裕人; 藤原 佳典; 深谷 太郎; 天野 秀紀; 熊谷 修; 渡辺 修一郎; 村山 洋史; 谷口 優; 野藤 悠; 干川 なつみ; 土屋 由美子; 新開 省二 厚生の指標 63 (2) 2 -11 2016年02月
- 嶋田 雅子; 野藤 悠; 吉葉 さおり 月刊地域医学 = Monthly community medicine 30 (2) 144 -147 2016年02月
- 嶋田 雅子; 吉葉 かおり; 野藤 悠 月刊地域医学 = Monthly community medicine 29 (12) 1002 -1004 2015年12月
- 吉葉 かおり; 野藤 悠; 嶋田 雅子 月刊地域医学 = Monthly community medicine 29 (10) 790 -792 2015年10月
- 嶋田 雅子; 吉葉 かおり; 野藤 悠 月刊地域医学 = Monthly community medicine 29 (8) 620 -623 2015年08月
- 嶋田 雅子; 吉葉 かおり; 野藤 悠 月刊地域医学 29 (7) 538 -541 2015年07月
- H. Amano; H. Yoshida; Y. Fujiwara; M. Nishi; H. Murayama; Y. Taniguchi; Y. Nofuji; S. Shinkai GERONTOLOGIST 54 81 -82 2014年11月
- 高齢者健診受診者における認知機能測定値と要介護化リスク天野 秀紀; 吉田 裕人; 西 真理子; 藤原 佳典; 谷口 優; 村山 洋史; 野藤 悠; 松尾 恵理; 新開 省二 日本老年医学会雑誌 51 (Suppl.) 52 -53 2014年05月
- Y. Taniguchi; S. Shinkai; H. Yoshida; M. Nishi; H. Murayama; Y. Nofuji; Y. Fujiwara; H. Uchida GERONTOLOGIST 53 315 -315 2013年11月
- 養父方式の介護予防の評価 地域巡回型介護予防教室の概要とプロセス評価吉田 由佳; 谷垣 知美; 野藤 悠; 松尾 恵理; 村山 洋史; 中西 智也; 小森 昌彦; 北川 博巳; 新開 省二 日本公衆衛生学会総会抄録集 72回 395 -395 2013年10月
- 養父方式の介護予防の評価 地域巡回型介護予防教室の効果野藤 悠; 新開 省二; 村山 洋史; 松尾 恵理; 吉田 由佳; 谷垣 知美; 中西 智也; 小森 昌彦; 北川 博巳 日本公衆衛生学会総会抄録集 72回 395 -395 2013年10月
- 養父方式の介護予防の評価 介護予防サポーターの育成と地域活動の広がり谷垣 知美; 吉田 由佳; 野藤 悠; 松尾 恵理; 村山 洋史; 中西 智也; 小森 昌彦; 北川 博巳; 新開 省二 日本公衆衛生学会総会抄録集 72回 395 -395 2013年10月
- 養父方式の介護予防の評価 地域活動への参加が生活機能に及ぼす影響松尾 恵理; 新開 省二; 野藤 悠; 村山 洋史; 吉田 由佳; 谷垣 知美; 中西 智也; 小森 昌彦; 北川 博巳 日本公衆衛生学会総会抄録集 72回 396 -396 2013年10月
- 養父方式の介護予防の評価 介護保険認定率への影響新開 省二; 野藤 悠; 村山 洋史; 松尾 恵理; 吉田 由佳; 谷垣 知美; 中西 智也; 小森 昌彦; 北川 博巳 日本公衆衛生学会総会抄録集 72回 396 -396 2013年10月
- 高齢者健康調査を通じた兵庫県養父市の地域交通の実態と課題の分析北川 博巳; 野藤 悠; 村山 洋史; 松尾 恵理; 小森 昌彦; 中西 智也; 吉田 由佳; 谷垣 智美; 新開 省二 日本公衆衛生学会総会抄録集 72回 396 -396 2013年10月
- 上腕-足首間脈波伝播速度と認知機能低下との関連性谷口 優; 新開 省二; 藤原 佳典; 吉田 裕人; 西 真理子; 村山 洋史; 野藤 悠; 天野 秀紀; 松尾 恵理 日本公衆衛生学会総会抄録集 72回 424 -424 2013年10月
- 高齢期認知機能低下の医学生物学的要因天野 秀紀; 吉田 裕人; 藤原 佳典; 西 真理子; 渡辺 直紀; 李 相侖; 深谷 太郎; 村山 洋史; 谷口 優; 野藤 悠; 松尾 恵理; 新開 省二; 土屋 由美子 日本公衆衛生学会総会抄録集 72回 423 -423 2013年10月
- 生活モデル型虚弱予防教室の効果検証(その1) プログラム概要および短期的評価成田 美紀; 村山 洋史; 西 真理子; 川畑 輝子; 武見 ゆかり; 野藤 悠; 松尾 恵理; 新開 省二 老年社会科学 35 (2) 183 -183 2013年06月
- 地域在宅高齢者における歩行機能と部位別筋肉量との関連谷口 優; 新開 省二; 藤原 佳典; 西 真理子; 村山 洋史; 野藤 悠; 天野 秀紀; 松尾 恵理 日本老年医学会雑誌 50 (Suppl.) 115 -115 2013年05月
- 健康寿命の延伸に向けて、介護予防10年間の歩みと今後 草津町における介護予防10年間の歩みと成果 ねらいとプロセス評価新開 省二; 吉田 裕人; 深谷 太郎; 藤原 佳典; 天野 秀紀; 西 真理子; 村山 洋史; 谷口 優; 野藤 悠; 干川 なつみ; 土屋 由美子 日本公衆衛生学会総会抄録集 71回 149 -149 2012年10月
- 健康寿命の延伸に向けて、介護予防10年間の歩みと今後 草津町における介護予防10年間の歩みと成果 高齢者健診のインパクト西 真理子; 新開 省二; 吉田 裕人; 藤原 佳典; 深谷 太郎; 天野 秀紀; 野藤 悠; 村山 洋史; 谷口 優; 干川 なつみ; 土屋 由美子 日本公衆衛生学会総会抄録集 71回 150 -150 2012年10月
- 健康寿命の延伸に向けて、介護予防10年間の歩みと今後 草津町における介護予防10年間の歩みと成果 地域全体の健康度の推移谷口 優; 新開 省二; 吉田 裕人; 深谷 太郎; 藤原 佳典; 天野 秀紀; 西 真理子; 村山 洋史; 野藤 悠; 干川 なつみ; 土屋 由美子 日本公衆衛生学会総会抄録集 71回 150 -150 2012年10月
- 健康寿命の延伸に向けて、介護予防10年間の歩みと今後 草津町における介護予防10年間の歩みと成果 要介護認定率の推移野藤 悠; 新開 省二; 吉田 裕人; 深谷 太郎; 藤原 佳典; 天野 秀紀; 西 真理子; 村山 洋史; 谷口 優; 干川 なつみ; 土屋 由美子 日本公衆衛生学会総会抄録集 71回 151 -151 2012年10月
- 高齢期の虚弱予防プログラムの評価(第4報) 自主グループ設立にむけた取り組み松尾 恵理; 西 真理子; 野藤 悠; 村山 洋史; 金 美芝; 清水 由美子; 成田 美紀; 藤原 佳典; 新開 省二 日本公衆衛生学会総会抄録集 71回 369 -369 2012年10月
- 兵庫県養父市での介護予防サポーター養成研修の成功要因と課題の分析吉田 由佳; 小森 昌彦; 村山 洋史; 野藤 悠; 新開 省二 日本公衆衛生学会総会抄録集 71回 378 -378 2012年10月
- 岸本 裕歩; 野藤 悠; 大河原 一憲 健康支援 14 (2) 15 -22 2012年09月
- Kenji Narazaki; Eri Matsuo; Takanori Honda; Yu Nofuji; Koji Yonemoto; Shuzo Kumagai MEDICINE AND SCIENCE IN SPORTS AND EXERCISE 44 923 -923 2012年05月
- 定期的な運動習慣が認知症発症に及ぼす影響 久山町研究野藤 悠; 岸本 裕歩; 小原 知之; 二宮 利治; 熊谷 秋三; 清原 裕 体力科学 60 (6) 815 -815 2011年12月
- 峰 悠子; 野藤 悠; 齋藤 誠二; 村木 里志; 熊谷 秋三 体力科學 57 (6) 870 -870 2008年12月
- 森山 善彦; 諏訪 雅貴; 野藤 悠; 村田 伸; 西地 玲子; 熊谷 秋三 体力科學 56 (6) 717 -717 2007年12月
- 野藤 悠; 諏訪 雅貴; 森山 善彦; 中野 裕史; 佐々木 悠; 熊谷 秋三 体力科學 55 (6) 589 -589 2006年12月
共同研究・競争的資金等の研究課題
- 日本学術振興会:科学研究費助成事業研究期間 : 2022年04月 -2026年03月代表者 : 清野 諭; 野藤 悠; 杉浦 裕太; 藤原 佳典
- 日本学術振興会:科学研究費助成事業研究期間 : 2024年04月 -2025年03月代表者 : 楢崎 兼司; 松崎 英章; 岸本 裕歩; 野藤 悠
- 日本学術振興会:科学研究費助成事業研究期間 : 2022年04月 -2025年03月代表者 : 阿部 巧; 野藤 悠; 久保田 晃生; 藤原 佳典; 清野 諭; 大森 宣暁
- 日本学術振興会:科学研究費助成事業研究期間 : 2020年04月 -2025年03月代表者 : 楢崎 兼司; 岸本 裕歩; 野藤 悠当該年度は,当初立案した研究計画に沿ってベースライン調査を的確に実施するための予備検証と調査準備を実施した. 予備検証に関しては,令和元年度までの科研費課題(課題番号:17K09146)により構築した「篠栗元気もん研究(第一次)」の8年間の追跡調査データセットを用いて,厚生労働省の「基本チェックリスト(KCL)」で簡易的に評価される複合的な要介護リスク状態と要介護認定との関連を調査した.その結果,KCL合計点は性,年齢,同居人の有無,教育年数,経済状況,飲酒・喫煙習慣,既往歴と独立して要介護認定と有意に関連していることが分かった.この検証結果に関しては,令和3年3月に開催された第22回日本健康支援学会年次学術大会(第8回日本介護予防・健康づくり学会大会との合同開催)にて口頭発表を行い,大会優秀賞を受賞した.また,この検証結果等に基づき,ベースライン調査における調査項目を確定した. 調査準備に関しては,新型コロナウイルス感染症による影響により当該年度予算の繰越承認を受けた上で,令和3年9月末までに篠栗町との協力のもと,対象者抽出,質問票や各種資料の作成・印刷,測定手順の構築および必要機材や備品等の整備,調査会実施体制の構築および測定標準化のための各種研修,行政区毎の調査会の日程調整および会場予約など,ベースライン調査を行なうために必要な準備を実施し,質問票を含む調査会関連書類一式を対象者に郵送する直前までの調査準備を完了した. 上記の通り,当該年度に予定していた研究内容に関しては,繰越承認時に設定した完了時期(令和3年9月末)までに概ね予定通り完了することができた.
- 日本学術振興会:科学研究費助成事業 基盤研究(B)研究期間 : 2020年04月 -2023年03月代表者 : 北村 明彦; 木山 昌彦; 野藤 悠; 山岸 良匡; 横山 友里; 谷口 優; 清野 諭; 新開 省二; 西 真理子; 村木 功フレイル発症の危険因子として、前期高齢期では、脳卒中や心疾患等の循環器疾患の発症、及び骨・関節疾患、サルコペニア、うつ等の老年症候群がフレイル発症の危険因子となり、後期高齢期では、さらに低栄養、認知機能低下、近隣・地域との交流の低下がフレイル発症に影響を及ぼすという研究仮説を検証するため、その第1ステップとして、地域に在住する高齢者を対象とし、フレイル進行の加齢変化について検討した。 草津町の高齢者健診受診者のうち、Fried et al.のphenotypeのフレイル評価を行った65歳以上計1698名(延べ6373件)を最長12年間追跡し、潜在クラスモデルによって加齢変化パターンを類型化した結果、65歳時でプレフレイルが進んでいる群(High group)が全体の6.5%、75歳頃からプレフレイルが進む群(Second group)が47.3%、85歳頃からプレフレイルが進む群(Third group)が30.3%、90歳までフレイルが進まない群(Low group)が16.0%であった。 以上のことから、健診受診者というバイアスがかかっているものの、約半数の高齢者が後期高齢期に入ってまもなくフレイルが進むことが示唆され、この時期を先送りすることが健康寿命の延伸をもたらすものと考えられた。次年度は、フレイル進行の加齢変化パターン別の死亡リスクおよび関連因子を検討し、最終年度にフレイル進行を先送りするための介入ポイントを明らかにするため、年齢層別にフレイル発症の危険因子の検討を行う。
- 日本学術振興会:科学研究費助成事業 若手研究研究期間 : 2020年04月 -2023年03月代表者 : 野藤 悠本研究の目的は、兵庫県養父市で2014年度より実施している「シルバー人材センターの会員が各行政区に仕事として出張し、フレイル予防教室の立ち上げ・運営を行う」という取り組み(養父モデル)により、研究①:教室参加者および教室実施地区の要介護認定率および介護給付費がどの程度抑制されるか、研究②:シルバー人材センターの会員が教室の運営を担うというモデルが他地域に普及するかを明らかにすることである。 2年目にあたる本年度は、研究①の分析の一部、および、研究②の分析のための普及状況及び課題に関する情報収集を行うことを計画していた。以下に実施状況の概要を示す。 研究①:2012年に実施したベースライン調査の対象者を2019年3月末まで追跡し、教室参加と要支援・要介護認定(以降、認定)発生との関連性を検討した。3350名のデータを使用しCox比例ハザード分析を行ったところ、教室参加者では非参加者に比べ認定発生ハザード比が0.45(95%信頼区間:0.34-0.59)と有意に低いことが確認された。これらの関連性は、対象者の背景要因を調整するために行った逆確率重み付け(IPTW)法および傾向スコアマッチング(PSM)法を用いた分析でも同様に認められた。原因別にみると、いずれの分析方法においても認知症およびその他を原因とする認定に対して有意なリスク低下が認められたが、循環器疾患および整形外科疾患を原因とする認定との関連性は認めらなかった。 研究②:埼玉県内のシルバー人材センター全58センターのうち、新たに2センターを対象に、事業の実施状況および実施する上での課題や工夫についてインタビュー調査を実施した。
- 日本学術振興会:科学研究費助成事業 基盤研究(B)研究期間 : 2017年04月 -2020年03月代表者 : 北村 明彦; 横山 友里; 谷口 優; 清野 諭; 新開 省二; 天野 秀紀; 野藤 悠; 西 真理子群馬県の一地域の高齢健診受診者約1,200人の平均8年(最大13年)の追跡研究により、フレイル及び他の危険因子が要介護発生、死亡のリスク上昇に及ぼす影響を検討した。フレイルは、①意図しない体重減少(半年以内に2~3kg)、②「自分が活気にあふれている」の質問に「いいえ」と回答、③外出が1日平均1回未満、④歩行速度が毎秒1m未満、⑤握力が男性26kg未満、女性18kg未満の5項目のうち、3項目以上該当をフレイル、1~2項目該当をフレイル予備群と判定した。 その結果、要介護発生のハザード比(その因子を有する群が有しない群に比べて、要介護が何倍発生しやすいかを表す指標)は、フレイル、フレイル予備群、認知機能低下、脳卒中既往が1.4~2.1倍と有意に高値を示した。一方、要介護発生の集団寄与危険度割合(その因子を取り除くことにより集団全体の要介護発生が何割減少するのかを表す指標)は、フレイル予備群が17%、フレイルが12%と最も高率であった。死亡についても同様であり、フレイル予備群が24%、フレイルが13%の寄与危険度割合を示した。すなわち、集団対策として、フレイル及びフレイル予備群に陥ることを防ぐことにより、約8年後までの要介護発生を約3割、死亡を約4割、それぞれ減らすことが可能となることが示唆された。さらに、年齢別に解析した結果からは、前期高齢期の方が後期高齢期よりも要介護発生や死亡に対するフレイルの影響度が大きいことが明らかになった。 以上の高齢者健診受診者を対象とした研究の結果より、フレイルを健診にて評価して、フレイルやフレイル予備群と判定された方に対して、フレイル状態の改善、及び要介護化の予防のための様々な働きかけを行うことは、高齢者の健康余命延伸に大いに貢献するものと考えられ、そうした取り組みは前期高齢期から開始した方がより効果的であることが示唆された。
- 日本学術振興会:科学研究費助成事業 若手研究(B)研究期間 : 2016年04月 -2019年03月代表者 : 野藤 悠; 清野 諭; 村山 洋史; 吉田 由佳; 谷垣 知美; 横山 友里; 成田 美紀; 西 真理子; 中村 正和; 北村 明彦; 新開 省二高齢化が進むわが国においてフレイルを予防することは喫緊の課題である.我々は2011年より兵庫県養父市にて住民や行政と協働してフレイル予防に取組んできた.その方策は,行政区毎にフレイル予防教室を開設し,シルバー人材センターの会員が仕事として一定期間教室を運営するというものであった.本研究では,この養父モデルともいうべき方策の有効性を評価し,他地域への応用可能性を検討した. ポピュレーションアプローチの評価枠組みであるPAIREMを用いて評価した結果,養父モデルはマンパワーやコスト面に一部課題を残すものの,効果,広がり,継続性という面で有効かつ他地域への応用可能性が高いモデルであることが示唆された.
- 日本学術振興会:科学研究費助成事業 基盤研究(C)研究期間 : 2008年 -2010年代表者 : 西地 令子; 熊谷 秋三; 鷲尾 昌一; 野藤 悠今回の研究において、睡眠障害とメタボリックシンドローム因子(MetS因子)との間に正の関連性が認められた。ベースラインでは、睡眠障害とMetS因子数とは双方において約2倍の保有リスクが観察された。さらに、2年間のフォローアップにおいて、MetS因子を2つ以上保有者は1つ以下の保有者と比較して、睡眠障害発症のリスクが約2.5倍であった。一方、睡眠障害はMetS因子の発症リスクとはならなかった。 また、血清BDNFレベルは、女性が男性よりも有意に低くかった。さらに、身体活動と血清BDNFとの関連性においても、男性においては血清BDNFレベルと身体活動との間に正の関連性が認められたが、女性においては観察されなかった。一方、女性において睡眠障害におけるPSQI得点との有意な負の相関関係が認められ、女性における睡眠障害保有者は非保有者に比較して血清BDNFが有意に低かった。しかし、男性においてはその差は認められなかった。 本研究結果において、MetSは睡眠障害のリスクとなる可能性を示した。さらに、睡眠障害とMetSの有病率には性差があることに、BDNFのメカニズムにおける役割があることも示唆された。