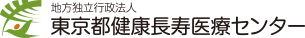研究者総覧
石崎 達郎 (イシザキ タツロウ)
| |||
Last Updated :2025/04/26
研究者情報
学位
ホームページURL
J-Global ID
研究キーワード
- 高齢者の長期ケア 慢性疾患の疫学 医療・介護の連携 在宅ケア 高齢者の医療経済学 高齢者の健康増進 加齢の疫学 社会老年学 health economics in older population Epidemiology in aging Social gerontology
研究分野
経歴
- 2011年 - 現在 東京都健康長寿医療センター研究所福祉と生活ケア研究チーム研究部長
- 2009年 - 2011年 京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻健康情報学分野准教授
- 2000年 - 2008年 京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻医療経済学分野助教授
- 1996年 - 2000年 東京都老人総合研究所疫学部門研究員
- 1992年 - 1995年 帝京大学医学部公衆衛生学講座助手
所属学協会
研究活動情報
論文
- Yukie Masui; Takeshi Nakagawa; Saori Yasumoto; Madoka Ogawa; Yoshiko Ishioka; Ayaka Kasuga; Noriko Hori; Hiroki Inagaki; Yuko Yoshida; Kae Ito; Midori Takayama; Yasumichi Arai; Kazunori Ikebe; Kei Kamide; Tatsuro Ishizaki; Yasuyuki GondoJournal of Adult Development 2024年09月 [査読有り]
- Ayako EDAHIRO; Tatsuro ISHIZAKI; Seigo MITSUTAKE; Akihiko KITAMURA; Takumi HIRATA; Atsushi SAITOArchives of Gerontology and Geriatrics Plus 2024年08月
- Tomoko Yano; Kayo Godai; Mai Kabayama; Hiroshi Akasaka; Yasushi Takeya; Koichi Yamamoto; Saori Yasumoto; Yukie Masui; Yasumichi Arai; Kazunori Ikebe; Tatsuro Ishizaki; Yasuyuki Gondo; Hiromi Rakugi; Kei KamideBMC Geriatrics 23 1 277 2023年05月 [査読有り]
- Yuri Miura; Hiroki Tsumoto; Yukie Masui; Hiroki Inagaki; Madoka Ogawa; Yuta Ideno; Kyojiro Kawakami; Keitaro Umezawa; Mai Kabayama; Yuya Akagi; Hiroshi Akasaka; Koichi Yamamoto; Hiromi Rakugi; Tatsuro Ishizaki; Yasumichi Arai; Kazunori Ikebe; Kei Kamide; Yasuyuki Gondo; Tamao EndoBiochimica et biophysica acta. General subjects 130316 - 130316 2023年01月
- Kumi Hirokawa; Ayaka Kasuga; Kiyoaki Matsumoto; Yasuko Omori; Yukie Masui; Takeshi Nakagawa; Madoka Ogawa; Yoshiko Ishioka; Hiroki Inagaki; Kazunori Ikebe; Yasumichi Arai; Tatsuro Ishizaki; Kei Kamide; Yasuyuki GondoGeriatrics & Gerontology International 22 12 1040 - 1046 2022年12月
- Kiyoaki Matsumoto; Yasuyuki Gondo; Yukie Masui; Saori Yasumoto; Yuko Yoshida; Kazunori Ikebe; Yasumichi Arai; Mai Kabayama; Kei Kamide; Hiroshi Akasaka; Tatsuro IshizakiBMC geriatrics 22 1 748 - 748 2022年09月
- Seigo Mitsutake; Tatsuro Ishizaki; Rumiko Tsuchiya-Ito; Kazuaki Uda; Hiroshige Jinnouchi; Hiroaki Ueshima; Tomoyuki Matsuda; Satoru Yoshie; Katsuya Iijima; Nanako TamiyaArchives of physical medicine and rehabilitation 103 9 1715 - 1722 2022年09月
- Tatsuro Ishizaki; Yukie Masui; Takeshi Nakagawa; Yuko Yoshida; Yoshiko L Ishioka; Noriko Hori; Hiroki Inagaki; Kae Ito; Madoka Ogawa; Mai Kabayama; Kei Kamide; Kazunori Ikebe; Yasumichi Arai; Yasuyuki GondoInternational journal of environmental research and public health 19 16 10330 - 10330 2022年08月
- Yukari Hattori; Shota Hamada; Tatsuro Ishizaki; Nobuo Sakata; Masao Iwagami; Nanako Tamiya; Masahiro Akishita; Takashi YamanakaGeriatrics & gerontology international 22 8 648 - 652 2022年08月
- Hitomi Sato; Kodai Hatta; Yuki Murotani; Toshihito Takahashi; Yasuyuki Gondo; Kei Kamide; Yukie Masui; Tatsuro Ishizaki; Mai Kabayama; Soshiro Ogata; Ken-Ichi Matsuda; Yusuke Mihara; Motoyoshi Fukutake; Hiromasa Hagino; Kotaro Higashi; Suzuna Akema; Masahiro Kitamura; Shinya Murakami; Yoshinobu Maeda; Kazunori IkebeJournal of dentistry 121 104088 - 104088 2022年06月 [査読有り]
- Yu Sun; Masao Iwagami; Nobuo Sakata; Tomoko Ito; Ryota Inokuchi; Kazuaki Uda; Shota Hamada; Miho Ishimaru; Jun Komiyama; Naoaki Kuroda; Satoru Yoshie; Tatsuro Ishizaki; Katsuya Iijima; Nanako TamiyaBMC primary care 23 1 132 - 132 2022年05月
- Kenji Toyoshima; S. Seino; Y. Tamura; J. Ishikawa; Y. Chiba; T. Ishizaki; Y. Fujiwara; S. Shinkai; A. Kitamura; A. ArakiJournal of Nutrition, Health and Aging 26 5 501 - 509 2022年05月
- Yuko Yoshida; Tatsuro Ishizaki; Yukie Masui; Yasumichi Arai; Hiroki Inagaki; Madoka Ogawa; Saori Yasumoto; Hajime Iwasa; Kei Kamide; Hiromi Rakugi; Kazunori Ikebe; Yasuyuki GondoBMC geriatrics 22 1 372 - 372 2022年04月
- Takumi Abe; Akihiko Kitamura; Mari Yamashita; Hunkyung Kim; Shuichi P Obuchi; Tatsuro Ishizaki; Yoshinori Fujiwara; Shuichi Awata; Kenji TobaGeriatrics & gerontology international 22 4 292 - 297 2022年04月
- Ayaka Kasuga; Saori Yasumoto; Takeshi Nakagawa; Yoshiko Ishioka; Akari Kikuchi; Hiroki Inagaki; Madoka Ogawa; Noriko Hori; Yukie Masui; Hwang Choe; Hiroyuki Muto; Mai Kabayama; Kayo Godai; Kazunori Ikebe; Kei Kamide; Tatsuro Ishizaki; Yasuyuki GondoGerontology and Geriatric Medicine 8 233372142211162 - 233372142211162 2022年04月
- Kae Ito; Tsuyoshi Okamura; Shuichi Awata; Yasuyuki Gondo; Yukie Masui; Hiroki Inagaki; Kei Kamide; Kazunori Ikebe; Yasumichi Arai; Tatsuro IshizakiGeriatrics & gerontology international 22 4 364 - 366 2022年04月
- Tami Sengoku; Tatsuro Ishizaki; Yoshihito Goto; Tomohide Iwao; Shosuke Ohtera; Michi Sakai; Genta Kato; Takeo Nakayama; Yoshimitsu TakahashiJournal of epidemiology and community health 76 4 391 - 397 2022年04月
- Toshiaki Sekiguchi; Mai Kabayama; Hirochika Ryuno; Kentaro Tanaka; Eri Kiyoshige; Yuya Akagi; Kayo Godai; Ken Sugimoto; Hiroshi Akasaka; Yoichi Takami; Yasushi Takeya; Koichi Yamamoto; Saori Yasumoto; Yukie Masui; Kazunori Ikebe; Yasuyuki Gondo; Yasumichi Arai; Tatsuro Ishizaki; Hiromi Rakugi; Kei KamideGeriatrics & gerontology international 22 4 286 - 291 2022年04月
- Ai Suzuki; Xueying Jin; Tomoko Ito; Satoru Yoshie; Tatsuro Ishizaki; Katsuya Iijima; Nanako TamiyaInternational journal of environmental research and public health 19 5 3065 - 3065 2022年03月
- Yuri Kiso; Yoko Matsuda; Shikine Esaka; Yuri Nakajima; Hiroto Shirahata; Yuko Fujii; Miho Matsukawa; Mototsune Kakizaki; Tatsuro Ishizaki; Tomio AraiCytopathology : official journal of the British Society for Clinical Cytology 33 2 206 - 215 2022年03月
- Yuya Akagi; Mai Kabayama; Yasuyuki Gondo; Yukie Masui; Saori Yasumoto; Nonglak Klinpudtan; Werayuth Srithumsuk; Kayo Godai; Kazunori Ikebe; Hiroshi Akasaka; Serina Yokoyama; Yoichi Nozato; Yoichi Takami; Yasushi Takeya; Koichi Yamamoto; Ken Sugimoto; Yasumichi Arai; Hiroki Inagaki; Tatsuro Ishizaki; Hiromi Rakugi; Kei KamideBMC geriatrics 22 1 158 - 158 2022年02月
- Jinmei Tuo; Kayo Godai; Mai Kabayama; Yuya Akagi; Hiroshi Akasaka; Yoichi Takami; Yasushi Takeya; Koichi Yamamoto; Ken Sugimoto; Saori Yasumoto; Yukie Masui; Yasumichi Arai; Kazunori Ikebe; Yasuyuki Gondo; Tatsuro Ishizaki; Hiromi Rakugi; Kei KamideInternational journal of hypertension 2022 5359428 - 5359428 2022年04月
- Seigo Mitsutake; Tatsuro Ishizaki; Shohei Yano; Rumiko Tsuchiya-Ito; Xueying Jin; Taeko Watanabe; Kazuaki Uda; Ian Livingstone; Nanako TamiyaGeriatrics & gerontology international 21 11 1010 - 1017 2021年11月
- 呉代 華容; 樺山 舞; 神出 計; 野上 素子; 春日 彩花; 安元 佐織; 増井 幸恵; 赤坂 憲; 池邉 一典; 石崎 達郎; 樂木 宏実; 権藤 恭之日本老年医学会雑誌 58 4 591 - 601 (一社)日本老年医学会 2021年10月
- Nonglak Klinpudtan; Richard C Allsopp; Mai Kabayama; Kayo Godai; Yasuyuki Gondo; Yukie Masui; Yuya Akagi; Werayuth Srithumsuk; Ken Sugimoto; Hiroshi Akasaka; Yoichi Takami; Yasushi Takeya; Koichi Yamamoto; Kazunori Ikebe; Saori Yasumoto; Madoka Ogawa; Tatsuro Ishizaki; Yasumichi Arai; Hiromi Rakugi; Randi Chen; Bradley J Willcox; D Craig Willcox; Kei KamideThe journals of gerontology. Series A, Biological sciences and medical sciences 2021年07月
- Motoyoshi Fukutake; Toshihito Takahashi; Yasuyuki Gondo; Kei Kamide; Yukie Masui; Ken-Ichi Matsuda; Kaori Enoki; Hajime Takeshita; Yusuke Mihara; Kodai Hatta; Hitomi Sato; Yuki Murotani; Hiromasa Hagino; Mai Kabayama; Tatsuro Ishizaki; Ken Sugimoto; Hiromi Rakugi; Yoshinobu Maeda; Paula Moynihan; Kazunori IkebeJournal of the American Geriatrics Society 69 7 1956 - 1963 2021年07月
- 崔 煌; 権藤 恭之; 増井 幸恵; 中川 威; 安元 佐織; 小野口 航; 池邉 一典; 神出 計; 樺山 舞; 石崎 達郎老年社会科学 43 1 5 - 14 日本老年社会科学会 2021年04月
- Kayo Godai; Mai Kabayama; Kei Kamide; Motoko Nogami; Ayaka Kasuga; Saori Yasumoto; Yukie Masui; Hiroshi Akasaka; Kazunori Ikebe; Tatsuro Ishizaki; Hiromi Rakugi; Yasuyuki GondoNihon Ronen Igakkai zasshi. Japanese journal of geriatrics 58 4 591 - 601 2021年10月
- Masahiro Kitamura; Kazunori Ikebe; Kei Kamide; Yasuyuki Gondo; Motozo Yamashita; Masahide Takedachi; Takenori Nozaki; Chiharu Fujihara; Satoru Yamada; Yoichiro Kashiwagi; Koji Miki; Tomoaki Iwayama; Kodai Hatta; Yusuke Mihara; Yuko Kurushima; Hajime Takeshita; Mai Kabayama; Ryousuke Oguro; Tatsuo Kawai; Hiroshi Akasaka; Yasushi Takeya; Koichi Yamamoto; Ken Sugimoto; Tatsuro Ishizaki; Yasumichi Arai; Yukie Masui; Ryutaro Takahashi; Hiromi Rakugi; Yoshinobu Maeda; Shinya MurakamiOdontology 2020年11月 [査読有り]
- Tomoko Noma; Mai Kabayama; Yasuyuki Gondo; Saori Yasumoto; Yukie Masui; Ken Sugimoto; Hiroshi Akasaka; Kayo Godai; Atsuko Higuchi; Yuya Akagi; Yoichi Takami; Yasushi Takeya; Koichi Yamamoto; Kazunori Ikebe; Yasumichi Arai; Tatsuro Ishizaki; Hiromi Rakugi; Kei KamideGeriatrics & gerontology international 20 7 720 - 726 2020年07月 [査読有り]
- Kayo Godai; Mai Kabayama; Yasuyuki Gondo; Saori Yasumoto; Toshiaki Sekiguchi; Tomoko Noma; Kentaro Tanaka; Eri Kiyoshige; Yuya Akagi; Ken Sugimoto; Hiroshi Akasaka; Yoichi Takami; Yasushi Takeya; Koichi Yamamoto; Yasumichi Arai; Yukie Masui; Tatsuro Ishizaki; Kazunori Ikebe; Michihiro Satoh; Kei Asayama; Takayoshi Ohkubo; Hiromi Rakugi; Kei KamideHypertension research : official journal of the Japanese Society of Hypertension 43 5 404 - 411 2020年05月 [査読有り]
- Seigo Mitsutake; Tatsuro Ishizaki; Rumiko Tsuchiya-Ito; Chie Teramoto; Sayuri Shimizu; Takuya Yamaoka; Akihiko Kitamura; Hideki ItoPreventive medicine reports 17 101033 - 101033 2020年03月 [査読有り]
- Srithumsuk W; Kabayama M; Gondo Y; Masui Y; Akagi Y; Klinpudtan N; Kiyoshige E; Godai K; Sugimoto K; Akasaka H; Takami Y; Takeya Y; Yamamoto K; Ikebe K; Ogawa M; Inagaki H; Ishizaki T; Arai Y; Rakugi H; Kamide KBMC Geriatrics. 20 1 24 - 24 2020年01月 [査読有り]
- Seigo Mitsutake; Tatsuro Ishizaki; Rumiko Tsuchiya-Ito; Kazuaki Uda; Chie Teramoto; Sayuri Shimizu; Hideki ItoArchives of Physical Medicine and Rehabilitation 2020年 [査読有り]
- Drug prescription patterns and factors associated with polypharmacy in over one million older adults in TokyoIshizaki T; Mitsutake S; Hamada S; Teramoto C; Shimizu S; Akishita M; Ito HGeriatrics & Gerontology International (採択) 2020年 [査読有り]
- Yusuke Mihara; Ken-Ichi Matsuda; Toshihito Takahashi; Kodai Hatta; Motoyoshi Fukutake; Hitomi Sato; Yasuyuki Gondo; Yukie Masui; Kei Kamide; Ken Sugimoto; Mai Kabayama; Tatsuro Ishizaki; Yasumichi Arai; Yoshinobu Maeda; Kazunori IkebeCommunity dentistry and oral epidemiology 2019年12月 [査読有り]
- Taniguchi Y; Kitamura A; Ishizaki T; Fujiwara Y; Shinozaki T; Seino S; Mitsutake S; Suzuki H; Yokoyama Y; Abe T; Ikeuchi T; Yokota I; Matsuyama Y; Shinkai SGeriatrics & gerontology international 19 12 1236 - 1242 2019年11月 [査読有り]
- Kodai Hatta; Yasuyuki Gondo; Kei Kamide; Yukie Masui; Hiroki Inagaki; Takeshi Nakagawa; Ken-Ichi Matsuda; Chisato Inomata; Hajime Takeshita; Yusuke Mihara; Motoyoshi Fukutake; Masahiro Kitamura; Shinya Murakami; Mai Kabayama; Tatsuro Ishizaki; Yasumichi Arai; Ken Sugimoto; Hiromi Rakugi; Yoshinobu Maeda; Kazunori IkebeJournal of prosthodontic research 2019年11月 [査読有り]
- Age is influencing on the relationship between CVD risk factors and cognitive function among in community dwelling old peoples: The SONIC study.Sawayama Y; Kabayama M; Gondo Y; Masui Y; Sugimoto K; Ikebe K; Arai Y; Ishizaki T; Rakugi H; Kamide K2019年10月
- Spatial analysis of accessibility to destinations determining mental health of Japanese older adults living in urban and rural areas.Onoguchi W; Fukukawa Y; Masui Y; Inagaki H; Yoshida Y; Ogawa M; Kabayama M; Yasumoto S; Kamide K; Arai Y; Ikebe K; Gondo T; Ishizaki T2019年10月
- Ishizaki T; Kobayashi E; Fukaya T; Takahashi Y; Shinkai S; Liang JArchives of gerontology and geriatrics 84 103904 2019年09月 [査読有り]
- Nonaka K; Fujiwara Y; Watanabe S; Ishizaki T; Iwasa H; Amano H; Yoshida Y; Kobayashi E; Sakurai R; Suzuki H; Kumagai S; Shinkai S; Suzuki TGeriatrics & gerontology international 19 7 673 - 678 2019年07月 [査読有り]
- Chie Teramoto; Tatsuro Ishizaki; Seigo Mitsutake; Haruhisa Fukuda; Takashi Naruse; Sayuri Shimizu; Hideki ItoHealth & social care in the community 27 4 899 - 906 2019年07月 [査読有り]
- Serum albumin/globulin ratio is associated with cognitive function in community-dwelling elderly people: The SONIC study.Maeda S; Takeya Y; Oguro R; Akasaka H; Ryuno H; Kabayama M; Yokoyama S; Nagasawa M; Fujimoto T; Takeda M; Takeya M; Itoh N; Takami Y; Yamamoto K; Sugimoto K; Inagaki H; Ogawa M; Nakagawa T; Yasumoto S; Masui Y; Arai Y; Ishizaki T; Ikebe K; Gondo Y; Kamide K; Rakugi HGeriatr Gerontol Int. 2019年06月 [査読有り]
- Hatta K; Ikebe K; Mihara Y; Gondo Y; Kamide K; Masui Y; Sugimoto K; Matsuda KI; Fukutake M; Kabayama M; Shintani A; Ishizaki T; Arai Y; Rakugi H; Maeda YGerodontology 36 2 156 - 162 2019年06月 [査読有り]
- Adomi M; Iwagami M; Kawahara T; Hamada S; Iijima K; Yoshie S; Ishizaki T; Tamiya NBMJ open 9 6 e028371 2019年06月 [査読有り]
- Association between recorded medical diagnoses and incidence of long-term care needs certification: a case control study using linked medical and long-term care data in two Japanese citiesIwagami, M; Taniguchi, Y; Jin, X; Adomi, M; Mori, T; Hamada, S; Shinozaki, T; Suzuki, M; Uda, K; Ueshima, H; Iijima, K; Yoshie S; Ishizaki, T; Ito, T; Tamiya, NAnnals of Clinical Epidemiology 1 2 56 - 68 2019年05月 [査読有り]
- Kiyoshige E; Kabayama M; Gondo Y; Masui Y; Ryuno H; Sawayama Y; Inoue T; Akagi Y; Sekiguchi T; Tanaka K; Nakagawa T; Yasumoto S; Ogawa M; Inagaki H; Oguro R; Sugimoto K; Akasaka H; Yamamoto K; Takeya Y; Takami Y; Itoh N; Takeda M; Nagasawa M; Yokoyama S; Maeda S; Ikebe K; Arai Y; Ishizaki T; Rakugi H; Kamide KArchives of gerontology and geriatrics 81 176 - 181 2019年03月 [査読有り]
- Mori T; Hamada S; Yoshie S; Jeon B; Jin X; Takahashi H; Iijima K; Ishizaki T; Tamiya NBMC geriatrics 19 1 69 2019年03月 [査読有り]
- Mori T; Tamiya N; Jin X; Jeon B; Yoshie S; Iijima K; Ishizaki TArchives of osteoporosis 14 1 25 2019年02月 [査読有り]
- Satomi Kobayashi; Xiaoyi Yuan; Satoshi Sasaki; Yusuke Osawa; Takumi Hirata; Yukiko Abe; Michiyo Takayama; Yasumichi Arai; Yukie Masui; Tatsuro IshizakiPublic health nutrition 22 2 212 - 222 2019年02月 [査読有り]
- Seigo Mitsutake; Tatsuro Ishizaki; Chie Teramoto; Sayuri Shimizu; Hideki ItoPreventing chronic disease 16 E11 2019年01月 [査読有り]
- A comparative analysis of treatment costs for home-based care and hospital-based care in enteral nutrition patients: a retrospective analysis of claims data.Maeda M; Fukuda H; Shimizu S; Ishizaki THealth Policy 123 4 367 - 372 2019年 [査読有り]
- The association of the measuring blood pressure at home with cognitive functioning among community-dwelling elderly.Godai K; Kabayama M; Yamamoto K; Sugimoto K; Arai Y; Ishizaki T; Ikebe K; Gondo Y; Rakugi H; Kamide K2019年01月 [査読有り]
- Fukutake M, Ikebe K, Okubo H, Matsuda KI, Enoki K, Inomata C, Takeshita H, Mihara Y, Hatta K, Gondo Y, Kamide K, Masui Y, Ishizaki T, Arai Y, Maeda Y.Fukutake M; Ikebe K; Okubo H; Matsuda KI; Enoki K; Inomata C; Takeshita H; Mihara Y; Hatta K; Gondo Y; Kamide K; Masui Y; Ishizaki T; Arai Y; Maeda Y2019年01月 [査読有り]
- Satomi Maeda; Yasushi Takeya; Ryosuke Oguro; Hiroshi Akasaka; Hirochika Ryuno; Mai Kabayama; Serina Yokoyama; Motonori Nagasawa; Taku Fujimoto; Masao Takeda; Miyuki Onishi‐Takeya; Norihisa Itoh; Yoichi Takami; Koichi Yamamoto; Ken Sugimoto; Hiroki Inagaki; Madoka Ogawa; Takeshi Nakagawa; Saori Yasumoto; Yukie Masui; Yasumichi Arai; Tatsuro Ishizaki; Kazunori Ikebe; Yasuyuki Gondo; Kei Kamide; Hiromi RakugiGeriatrics & Gerontology International 2019年 [査読有り]
- Mitsutake S; Ishizaki T; Tsuchiya-Ito R; Teramoto C; Shimizu S; Yamaoka T; Kitamura A; Hideki ItoPreventive Medicine Reports (採択) 2019年 [査読有り]
- Giovanni Sala; Daniela Jopp; Fernand Gobet; Madoka Ogawa; Yoshiko Ishioka; Yukie Masui; Hiroki Inagaki; Takeshi Nakagawa; Saori Yasumoto; Tatsuro Ishizaki; Yasumichi Arai; Kazunori Ikebe; Kei Kamide; Yasuyuki GondoPLoS ONE 14 11 e0225006 2019年 [査読有り]
- Eri Kiyoshige; Mai Kabayama; Yasuyuki Gondo; Yukie Masui; Hiroki Inagaki; Madoka Ogawa; Takeshi Nakagawa; Saori Yasumoto; Hiroshi Akasaka; Ken Sugimoto; Kazunori Ikebe; Yasumichi Arai; Tatsuro Ishizaki; Hiromi Rakugi; Kei KamideBMC Geriatrics 19 309 2019年 [査読有り]
- 地域高齢者の精神的健康の縦断変化に及ぼす老年的超越の影響の検討ー疾患罹患・死別イベントに対する緩衝効果に注目してー増井幸恵; 権藤恭之; 中川 威; 小川まどか; 石岡良子; 稲垣宏樹; 蔡 羽淳; 安元佐織; 栗延 孟; 小野口航; 髙山 緑; 新井康通; 池邉一典; 神出 計; 石崎達郎老年社会科学 41 3 247 - 258 2019年 [査読有り]
- 石崎 達郎; 光武 誠吾; 寺本 千恵; 清水 沙友里; 井藤 英喜厚生の指標 = Journal of health and welfare statistics 65 13 1 - 7 厚生労働統計協会 2018年11月
- Kuroda N; Hamada S; Sakata N; Jeon B; Iijima K; Yoshie S; Ishizaki T; Jin X; Watanabe T; Tamiya NInternational journal of geriatric psychiatry 34 3 472 - 479 2018年11月 [査読有り]
- 光武 誠吾; 石崎 達郎; 寺本 千恵; 土屋 瑠見子; 清水 沙友里; 井藤 英喜日本老年医学会雑誌 55 4 612 - 623 (一社)日本老年医学会 2018年10月
- Mihara Y; Matsuda KI; Hatta K; Gondo Y; Masui Y; Nakagawa T; Kamide K; Ishizaki T; Arai Y; Maeda Y; Ikebe KJournal of oral rehabilitation 45 10 805 - 809 2018年10月 [査読有り]
- Hatta K; Ikebe K; Gondo Y; Kamide K; Masui Y; Inagaki H; Nakagawa T; Matsuda KI; Ogawa T; Inomata C; Takeshita H; Mihara Y; Fukutake M; Kitamura M; Murakami S; Kabayama M; Ishizaki T; Arai Y; Sugimoto K; Rakugi H; Maeda YGeriatrics & gerontology international 18 10 1439 - 1446 2018年10月 [査読有り]
- Okubo H; Murakami K; Inagaki H; Gondo Y; Ikebe K; Kamide K; Masui Y; Arai Y; Ishizaki T; Sasaki S; Nakagawa T; Kabayama M; Sugimoto K; Rakugi H; Maeda Y; SONIC Study GroupJournal of oral rehabilitation 46 2 151 - 160 2018年10月 [査読有り]
- Fukutake M; Ikebe K; Okubo H; Matsuda KI; Enoki K; Inomata C; Takeshita H; Mihara Y; Hatta K; Gondo Y; Kamide K; Masui Y; Ishizaki T; Arai Y; Maeda YJournal of prosthodontic research 63 1 105 - 109 2018年10月 [査読有り]
- The Association of the blood pressure level with the cognitive decline after 3 years among community-dwelling older people:SONIC study.Kabayama M; Kamide K; Gondo Y; Yamamoto K; Sugimoto K; Masui Y; Inagaki H; Arai T; Ishizaki T; Rakugi HHypertension Beijing 2018 Final programme. 90 - 90 2018年09月 [査読有り]
- Gene polymorphisms of fraility are associated with Atherosclerosis in old Japanese:The SONIC study.Akagi Y; Kamide K; Kabayama M; Akasaka H; Sugimoto K; Yamamoto K; Gondo Y; Ikebe K; Masui Y; Ishizaki T; Arai Y; Rakugi HHypertension Beijing 2018 Final programme. 208 - 208 2018年09月 [査読有り]
- Hamada S; Takahashi H; Sakata N; Jeon B; Mori T; Iijima K; Yoshie S; Ishizaki T; Tamiya NJournal of epidemiology 2018年09月 [査読有り]
- Jeon B; Tamiya N; Yoshie S; Iijima K; Ishizaki TGeriatrics & gerontology international 18 8 1272 - 1279 2018年08月 [査読有り]
- Nagasawa M; Takami Y; Akasaka H; Kabayama M; Maeda S; Yokoyama S; Fujimoto T; Nozato Y; Imaizumi Y; Takeda M; Itoh N; Takeya Y; Yamamoto K; Sugimoto K; Nakagawa T; Masui Y; Arai Y; Ishizaki T; Ikebe K; Gondo Y; Kamide K; Rakugi HGeriatrics & gerontology international 18 6 839 - 846 2018年06月 [査読有り]
- Aida J; Ishizaki T; Arai T; Takubo K; members of the; Japan Research Society for Early Esophageal Cancer; ChromoendoscopyHuman pathology 76 156 - 166 2018年06月 [査読有り]
- Ohura T; Higashi T; Ishizaki T; Nakayama TJournal of physical therapy science 30 6 866 - 873 2018年06月 [査読有り]
- Mihara Y; Matsuda KI; Ikebe K; Hatta K; Fukutake M; Enoki K; Ogawa T; Takeshita H; Inomata C; Gondo Y; Masui Y; Kamide K; Sugimoto K; Kabayama M; Ishizaki T; Arai Y; Maeda YGerodontology 2018年05月 [査読有り]
- Fukutake M; Ogawa T; Ikebe K; Mihara Y; Inomata C; Takeshita H; Matsuda K; Hatta K; Gondo Y; Masui Y; Inagaki H; Arai Y; Kamide K; Ishizaki T; Maeda YClinical oral investigations 23 1 267 - 271 2018年04月 [査読有り]
- Antipsychotic use and related factors among people with dementia aged 75 years or older in Japan: a comprehensive population-based estimation using medical and long-term care dataKuroda, Naoaki; Hamada, Shota; Sakata, Nobuo; Jeon, Boyoung; Iijima, Katsuya; Yoshie, Satoru; Ishizaki, Tatsuro; Jin, Xueying; Watanabe, Taeko; Tamiya, NanakoInternational journal of geriatric psychiatry WILEY 2018年03月 [査読有り]
- Estimated expenditures for hip fractures using merged healthcare insurance data for individuals aged ≥ 75 years and long-term care insurance claims data in Japan.Mori, Takahiro; Tamiya, Nanako; Jin, Xueying; Jeon, Boyoung; Yoshie, Satoru; Iijima, Katsuya; Ishizaki, TatsuroArchives of Osteoporosis SPRINGER LONDON LTD 2018年03月 [査読有り]
- Taniguchi Y; Kitamura A; Nofuji Y; Ishizaki T; Seino S; Yokoyama Y; Shinozaki T; Murayama H; Mitsutake S; Amano H; Nishi M; Matsuyama Y; Fujiwara Y; Shinkai SThe journals of gerontology. Series A, Biological sciences and medical sciences 74 2 211 - 218 2018年03月 [査読有り]
- Mori T; Tamiya N; Jin X; Jeon B; Yoshie S; Iijima K; Ishizaki TArchives of osteoporosis 13 1 37 2018年03月 [査読有り]
- Ikebe K; Gondo Y; Kamide K; Masui Y; Ishizaki T; Arai Y; Inagaki H; Nakagawa T; Kabayama M; Ryuno H; Okubo H; Takeshita H; Inomata C; Kurushima Y; Maeda YPloS one 13 1 e0190741 2018年01月 [査読有り]
- Seigo Mitsutake; Tatsuro Ishizaki; Chie Teramoto; Rumiko Tsuchiya-Ito; Sayuri Shimizu; Hideki ItoNihon Ronen Igakkai zasshi. Japanese journal of geriatrics 55 4 612 - 623 2018年 [査読有り]
- Saori Fujiki; Tatsuro Ishizaki; Takeo NakayamaJOURNAL OF EVALUATION IN CLINICAL PRACTICE 23 6 1203 - 1210 2017年12月 [査読有り]
- Hitomi Okubo; Hiroki Inagaki; Yasuyuki Gondo; Kei Kamide; Kazunori Ikebe; Yukie Masui; Yasumichi Arai; Tatsuro Ishizaki; Satoshi Sasaki; Takeshi Nakagawa; Mai Kabayama; Ken Sugimoto; Hiromi Rakugi; Yoshinobu MaedaNUTRITION JOURNAL 16 1 56 2017年09月 [査読有り]
- Hirochika Ryuno; Kei Kamide; Yasuyuki Gondo; Mai Kabayama; Ryosuke Oguro; Chikako Nakama; Serina Yokoyama; Motonori Nagasawa; Satomi Maeda-Hirao; Yuki Imaizumi; Miyuki Takeya; Hiroko Yamamoto; Masao Takeda; Yoichi Takami; Norihisa Itoh; Yasushi Takeya; Koichi Yamamoto; Ken Sugimoto; Takeshi Nakagawa; Saori Yasumoto; Kazunori Ikebe; Hiroki Inagaki; Yukie Masui; Michiyo Takayama; Yasumichi Arai; Tatsuro Ishizaki; Ryutaro Takahashi; Hiromi RakugiHYPERTENSION RESEARCH 40 7 665 - 670 2017年07月 [査読有り]
- Tatsuro Ishizaki; Masaya Shimmei; Haruhisa Fukuda; Eun-Hwan Oh; Chiho Shimada; Tomoko Wakui; Hiroko Mori; Ryutaro TakahashiGERIATRICS & GERONTOLOGY INTERNATIONAL 17 5 737 - 743 2017年05月 [査読有り]
- T. Ogawa; M. Uota; K. Ikebe; Y. Arai; K. Kamide; Y. Gondo; Y. Masui; T. Ishizaki; C. Inomata; H. Takeshita; Y. Mihara; K. Hatta; Y. MaedaJOURNAL OF ORAL REHABILITATION 44 1 22 - 29 2017年01月 [査読有り]
- Uota M; Ogawa T; Ikebe K; Arai Y; Kamide K; Gondo Y; Masui Y; Ishizaki T; Inomata C; Takeshita H; Mihara Y; Maeda YJ Oral Rehabil. 43 12 943 - 952 2016年12月 [査読有り]
- Zhou H; Mori S; Ishizaki T; Takahashi A; Matsuda K; Koretsune Y; Minami S; Higashiyama M; Imai S; Yoshimori K; Doita M; Yamada A; Nagayama S; Kaneko K; Asai S; Shiono M; Kubo M; Ito HBone reports 5 168 - 172 2016年12月 [査読有り]
- Buffering Effects of Gerotranscendence on Mental Health When Experiencing Physical Function Decline.Masui Y; Gondo Y; Nakagawa T; Ishioka Y; Arai Y; Kamide K; Ikebe K; Ishizaki T2016年11月 [査読有り]
- Brian J. Morris; Randi Chen; Timothy A. Donlon; Daniel S. Evans; Gregory J. Tranah; Neeta Parimi; Georg B. Ehret; Christopher Newton-Cheh; Todd Seto; D. Craig Willcox; Kamal H. Masaki; Kei Kamide; Hirochika Ryuno; Ryosuke Oguro; Chikako Nakama; Mai Kabayama; Koichi Yamamoto; Ken Sugimoto; Kazunori Ikebe; Yukie Masui; Yasumichi Arai; Tatsuro Ishizaki; Yasuyuki Gondo; Hiromi Rakugi; Bradley J. WillcoxAMERICAN JOURNAL OF HYPERTENSION 29 11 1292 - 1300 2016年11月 [査読有り]
- Heying Zhou; Seijiro Mori; Tatsuro Ishizaki; Masashi Tanaka; Kumpei Tanisawa; Makiko Naka Mieno; Motoji Sawabe; Tomio Arai; Masaaki Muramatsu; Yoshiji Yamada; Hideki ItoJOURNAL OF BONE AND MINERAL METABOLISM 34 6 685 - 691 2016年11月 [査読有り]
- Hirochika Ryuno; Kei Kamide; Yasuyuki Gondo; Chikako Nakama; Ryosuke Oguro; Mai Kabayama; Tatsuo Kawai; Hiroshi Kusunoki; Serina Yokoyama; Yuki Imaizumi; Miyuki Takeya; Hiroko Yamamoto; Masao Takeda; Yoichi Takami; Norihisa Itoh; Koichi Yamamoto; Yasushi Takeya; Ken Sugimoto; Takeshi Nakagawa; Kazunori Ikebe; Hiroki Inagaki; Yukie Masui; Tatsuro Ishizaki; Michiyo Takayama; Yasumichi Arai; Ryutaro Takahashi; Hiromi RakugiHYPERTENSION RESEARCH 39 7 557 - 563 2016年07月 [査読有り]
- Yoshiaki Tamura; Naotaka Izumiyama-Shimomura; Yoshiyuki Kimbara; Ken-ichi Nakamura; Naoshi Ishikawa; Junko Aida; Yuko Chiba; Yoko Matsuda; Seijiro Mori; Tomio Arai; Mutsunori Fujiwara; Steven S. S. Poon; Tatsuro Ishizaki; Atsushi Araki; Kaiyo Takubo; Hideki ItoAGE 38 3 61 2016年06月 [査読有り]
- Azusa Shima; Yukako Tatsumi; Tatsuro Ishizaki; Kayo Godai; Yuichiro Kawatsu; Tomonori Okamura; Tomofumi Nishikawa; Akiko Morimoto; Ayumi Morino; Naomi MiyamatsuHypertension research : official journal of the Japanese Society of Hypertension 39 5 376 - 81 2016年05月 [査読有り]
- 島田 千穂; 石崎 達郎; 高橋 龍太郎厚生の指標 63 4 1 - 7 (一財)厚生労働統計協会 2016年04月
- Yoshimitsu Takahashi; Tatsuro Ishizaki; Takeo Nakayama; Ichiro KawachiHEALTH POLICY 120 3 334 - 341 2016年03月 [査読有り]
- Chiho Shimada; Ryo Hirayama; Tomoko Wakui; Kazuhiro Nakazato; Shuichi Obuchi; Tatsuro Ishizaki; Ryutaro TakahashiGERIATRICS & GERONTOLOGY INTERNATIONAL 16 132 - 139 2016年03月 [査読有り]
- 余暇活動と認知機能の関連-地域在住高齢者を対象として小園麻里菜; 権藤恭之; 小川まどか; 石岡良子; 増井幸恵; 中川 威; 田渕 恵; 立平起子; 池邉一典; 神出 計; 新井康通; 石崎達郎; 髙橋龍太郎老年社会科学 38 1 32 - 44 2016年 [査読有り]
- Yoshinori Fujiwara; Shoji Shinkai; Erika Kobayashi; Ushio Minami; Hiroyuki Suzuki; Hideyo Yoshida; Tatsuro Ishizaki; Shu Kumagai; Shuichiro Watanabe; Taketo Furuna; Takao SuzukiGERIATRICS & GERONTOLOGY INTERNATIONAL 16 1 126 - 134 2016年01月 [査読有り]
- Ohura T; Higashi T; Ishizaki T; Nakayama TBMC research notes 9 52 2016年01月 [査読有り]
- Ishioka Y; Gondo Y; Masui Y; Nakagawa T; Tabuchi M; Ogawa M; Kamide K; Ikebe K; Arai Y; Ishizaki T; Takahashi RShinrigaku kenkyu : The Japanese journal of psychology 86 3 219 - 229 2015年08月 [査読有り]
- Shimada C; Hirayama R; Nakazato K; Arai K; Ishizaki T; Aita K; Shimizu T; Inamatsu T; Takahashi RGeriatrics & gerontology international 15 7 927 - 928 2015年07月 [査読有り]
- Sugihara T; Ishizaki T; Hosoya T; Iga S; Yokoyama W; Hirano F; Miyasaka N; Harigai MRheumatology (Oxford, England) 54 5 798 - 807 2015年05月 [査読有り]
- Aida J; Vieth M; Shepherd NA; Ell C; May A; Neuhaus H; Ishizaki T; Nishimura M; Fujiwara M; Arai T; Takubo KThe American journal of surgical pathology 39 2 188 - 196 2015年02月 [査読有り]
- 終末期医療に関する事前の希望伝達の実態とその背景島田 千穂; 中里 和弘; 荒井 和子; 会田 薫子; 清水 哲郎; 鶴若 麻理; 石崎 達郎; 高橋 龍太郎日本老年医学会雑誌 52 1 79 - 85 (一社)日本老年医学会 2015年01月
- Ohura T; Higashi T; Ishizaki T; Nakayama TClinical Gerontologist 33 88 - 102 2015年01月 [査読有り]
- Shimada C; Nakazato K; Arai K; Aita K; Shimizu T; Tsuruwaka M; Ishizaki T; Takahashi RNihon Ronen Igakkai zasshi. Japanese journal of geriatrics 52 1 79 - 85 2015年 [査読有り]
- Fukuda H; Shimizu S; Ishizaki TPloS one 10 7 e0133694 2015年 [査読有り]
- Retinal Thickness and the Structure/Function Relationship in the Eyes of Older Adults with Glaucoma.Honjo M; Omodaka K; Ishizaki T; Ohkubo S; Araie M; Nakazawa TPloS one 10 10 e0141293 2015年 [査読有り]
- Tomoko Ohura; Takahiro Higashi; Tatsuro Ishizaki; Takeo NakayamaJOURNAL OF PHYSICAL THERAPY SCIENCE 26 12 1971 - 1974 2014年12月 [査読有り]
- S. Nakaoka; T. Ishizaki; H. Urushihara; T. Satoh; S. IkedaPLOS ONE 9 8 e99021 2014年08月 [査読有り]
- Yuka Tsujimura; Yoshimitsu Takahashi; Tatsuro Ishizaki; Akira Kuriyama; Kikuko Miyazaki; Toshihiko Satoh; Shunya Ikeda; Shinya Kimura; Takeo NakayamaDIABETES RESEARCH AND CLINICAL PRACTICE 105 2 176 - 184 2014年08月 [査読有り]
- Sachiko Nakaoka; Tatsuro Ishizaki; Hisashi Urushihara; Toshihiko Satoh; Shunya Ikeda; Mitsutoshi Yamamoto; Takeo NakayamaPLOS ONE 9 6 2014年06月 [査読有り]
- Satoshi Seino; Shoji Shinkai; Yoshinori Fujiwara; Shuichi Obuchi; Hideyo Yoshida; Hirohiko Hirano; Hun Kyung Kim; Tatsuro Ishizaki; Ryutaro TakahashiPLOS ONE 9 6 e99487 2014年06月 [査読有り]
- Kim H; Suzuki T; Saito K; Kim M; Kojima N; Ishizaki T; Yamashiro Y; Hosoi E; Yoshida HArchives of gerontology and geriatrics 57 3 352 - 359 2013年11月 [査読有り]
- Ichikawa K; Takahashi Y; Ando M; Anme T; Ishizaki T; Yamaguchi H; Nakayama TBioPsychoSocial medicine 7 1 14 2013年10月 [査読有り]
- Izeki M; Neo M; Ito H; Nagai K; Ishizaki T; Okamoto T; Fujibayashi S; Takemoto M; Yoshitomi H; Aoyama T; Matsuda SSpine 38 9 E513 - 20 2013年04月 [査読有り]
- Wada M; Nakayama T; Ishizaki T; Satoh T; Ikeda SInternational journal of general medicine 6 597 - 604 2013年 [査読有り]
- T. Yamazaki; M. Yamori; T. Ishizaki; K. Asai; K. Goto; K. Takahashi; T. Nakayama; K. BesshoInternational Journal of Oral and Maxillofacial Surgery 41 11 1397 - 1403 2012年 [査読有り]
- Takahashi Y; Ohura T; Ishizaki T; Okamoto S; Miki K; Naito M; Akamatsu R; Sugimori H; Yoshiike N; Miyaki K; Shimbo T; Nakayama TJournal of medical Internet research 13 4 e110 2011年12月 [査読有り]
- Reliability and validity tests of an evaluation tool based on the modified Barthel Index.Ohura T; Ishizaki T; Higashi T; Konishi K; Ishiguro R; Nakanishi K; Shah S; Nakayama TInternational Journal of Therapy and Rehabilitation 18 8 422 - 428 2011年08月 [査読有り]
- Masato Ota; Masashi Neo; Tomoki Aoyama; Tatsuro Ishizaki; Shunsuke Fujibayashi; Mitsuru Takemoto; Takeo Nakayama; Takashi NakamuraSPINE 36 11 E720 - E726 2011年05月 [査読有り]
- Tatsuro Ishizaki; Taketo Furuna; Yuko Yoshida; Hajime Iwasa; Hiroyuki Shimada; Hideyo Yoshida; Shu Kumagai; Takao SuzukiJOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 21 3 176 - 183 2011年05月 [査読有り]
- Takahashi, Yoshimitsu; Ohura, Tomoko; Ishizaki, Tatsuro; Okamoto, Shigeru; Miki, Kenji; Naito, Mariko; Akamatsu, Rie; Sugimori, Hiroki; Yoshiike, Nobuo; Miyaki, Koichi; Shimbo, Takuro; Nakayama, TakeoJOURNAL OF MEDICAL INTERNET RESEARCH 13 4 2011年
- Sachiko Nakaoka; Tatsuro Ishizaki; Hisashi Urushihara; Toshihiko Satoh; Shunya Ikeda; Kaoru Morikawa; Takeo NakayamaINTERNAL MEDICINE 50 7 687 - 694 2011年 [査読有り]
- Hiroyuki Shimada; Megumi Suzukawa; Tatsuro Ishizaki; Kumiko Kobayashi; Hunkyung Kim; Takao SuzukiBMC GERIATRICS 11 40 2011年 [査読有り]
- Daijun Kirigaya; Takeo Nakayama; Tatsuro Ishizaki; Shunya Ikeda; Toshihiko SatohINTERNAL MEDICINE 50 22 2793 - 2800 2011年 [査読有り]
- Harada K; Shimada H; Sawyer P; Asakawa Y; Nihei K; Kaneya S; Furuna T; Ishizaki T; Yasumura S[Nihon koshu eisei zasshi] Japanese journal of public health 57 7 526 - 537 2010年07月 [査読有り]
- Shimada H; Ishizaki T; Kato M; Morimoto A; Tamate A; Uchiyama Y; Yasumura SArchives of gerontology and geriatrics 50 2 140 - 146 2010年03月 [査読有り]
- Shimada H; Sawyer P; Harada K; Kaneya S; Nihei K; Asakawa Y; Yoshii C; Hagiwara A; Furuna T; Ishizaki TArchives of physical medicine and rehabilitation 91 2 241 - 246 2010年02月 [査読有り]
- Lee J; Imanaka Y; Sekimoto M; Ishizaki T; Hayashida K; Ikai H; Tetsuya OJournal of evaluation in clinical practice 16 1 100 - 106 2010年02月 [査読有り]
- 有村保次; 西田俊彦; 南麻弥; 横山葉子; 三品浩基; 山崎新; 石崎達郎; 川上浩司; 中山健夫; 今中雄一; 川村孝; 福原俊一医学教育 41 259 - 265 2010年 [査読有り]
- Fukuda H; Imanaka Y; Ishizaki T; Okuma K; Shirai TInternational journal for quality in health care : journal of the International Society for Quality in Health Care 21 5 372 - 378 2009年10月 [査読有り]
- Shirai T; Imanaka Y; Sekimoto M; Ishizaki T; QIP Ovarian Cancer Expert GroupThe journal of obstetrics and gynaecology research 35 5 926 - 934 2009年10月 [査読有り]
- Nojo T; Imanaka Y; Ishizaki T; Sekimoto M; Yoshino M; Kurosawa T; Takao H; Ohtomo KLung cancer (Amsterdam, Netherlands) 65 1 56 - 61 2009年07月 [査読有り]
- Ishizaki Y; Fukuoka H; Tanaka H; Ishizaki T; Fujii Y; Hattori-Uchida Y; Nakamura M; Ohkawa K; Kobayashi H; Taniuchi S; Kaneko KActa astronautica 64 9-10 864-868 2009年05月 [査読有り]
- Ishizaki T; Yoshida H; Suzuki T; Shibata HGerontology 55 3 344 - 352 2009年 [査読有り]
- Kawasaki K; Sekimoto M; Ishizaki T; Imanaka YJournal of anesthesia 23 2 235 - 241 2009年 [査読有り]
- Sekimoto M; Kakutani C; Inoue I; Ishizaki T; Hayashida K; Imanaka YHealth policy (Amsterdam, Netherlands) 88 1 100 - 109 2008年10月 [査読有り]
- Ishizaki T; Imanaka Y; Oh EH; Sekimoto M; Hayashida K; Kobuse HHealth policy (Amsterdam, Netherlands) 87 1 20 - 30 2008年07月 [査読有り]
- Ishizaki T; Imanaka Y; Sekimoto M; Fukuda H; Mihara H; Treatment of; Subarachnoid; Hemorrhage Expert GroupJournal of evaluation in clinical practice 14 3 416 - 421 2008年06月 [査読有り]
- Ishizaki TClinical calcium 18 6 795 - 801 2008年06月 [査読有り]
- Edward Evans; Yuichi Imanaka; Miho Sekimoto; Tatsuro Ishizaki; Kenshi Hayashida; Haruhisa Fukuda; Eun-Hwan OhHEALTH ECONOMICS 16 4 347 - 359 2007年04月 [査読有り]
- Masahiro Hirose; Scott E. Regenbogen; Stuart Lipsitz; Yuichi Imanaka; Tatsuro Ishizaki; Miho Sekimoto; Eun-Hwan Oh; Atul A. GawandeQUALITY & SAFETY IN HEALTH CARE 16 2 101 - 104 2007年04月 [査読有り]
- Pierre Moise; Stephane Jacobzone and the ARD-IHD Experts Group [incl. Imanaka Y; Ishizaki T; Ogawa T]OECD 2007年 [査読有り]
- Miho Sekimoto; Yuichi Imanaka; Nobuko Kitano; Tatsuro Ishizaki; Osamu TakahashiBMC HEALTH SERVICES RESEARCH 6 92 2006年07月 [査読有り]
- K Kuwabara; Y Imanaka; T IshizakiJOURNAL OF EVALUATION IN CLINICAL PRACTICE 12 2 164 - 173 2006年04月 [査読有り]
- Sekimoto M; Imanaka Y; Hirose M; Ishizaki T; Murakami G; Fukata Y; QIP Cholecystectomy Expert GroupBMC health services research 6 40 2006年03月 [査読有り]
- Ishizaki T; Kai I; Imanaka YArchives of gerontology and geriatrics 42 1 91 - 99 2006年01月 [査読有り]
- Ishizaki T; Yoshida H; Suzuki T; Watanabe S; Niino N; Ihara K; Kim H; Fujiwara Y; Shinkai S; Imanaka YArchives of gerontology and geriatrics 42 1 47 - 58 2006年01月 [査読有り]
- M Hirose; Y Imanaka; T Ishizaki; M Sekimoto; Y Harada; K Kuwabara; K Hayashida; EH Oh; E EvansWORLD JOURNAL OF SURGERY 29 4 429 - 436 2005年04月 [査読有り]
- Ishizaki Y; Ishizaki T; Ozawa K; Fukai Y; Hattori Y; Taniuchi S; Kobayashi YJournal of developmental and physical disabilities 17 2 119-132 2005年
- Y Ishizaki; H Fukuoka; T Ishizaki; H Tanaka; H IshitobiACTA ASTRONAUTICA 55 11 945 - 952 2004年12月 [査読有り]
- T Suzuki; H Kim; H Yoshida; T IshizakiJOURNAL OF BONE AND MINERAL METABOLISM 22 6 602 - 611 2004年11月 [査読有り]
- M Sekimoto; Y Imanaka; E Evans; T Ishizaki; M Hirose; K Hayashida; T FukuiINTERNATIONAL JOURNAL FOR QUALITY IN HEALTH CARE 16 5 367 - 373 2004年10月 [査読有り]
- T Ishizaki; Y Imanaka; M Hirose; K Hayashida; M Kizu; A Inoue; S SugieHEALTH POLICY 69 3 293 - 303 2004年09月 [査読有り]
- T Ishizaki; Y Imanaka; E Oh; K Kuwabara; M Hirose; K Hayashida; Y HaradaHEALTH POLICY 69 2 179 - 187 2004年08月 [査読有り]
- Kim H; Yoshida H; Hu X; Yukawa H; Shinkai S; Kumagai S; Fujiwara Y; Yoshida Y; Furuna T; Sugiura M; Ishizaki T; Suzuki T[Nihon koshu eisei zasshi] Japanese journal of public health 51 8 612 - 622 2004年08月 [査読有り]
- Y Ishizaki; H Fukuoka; T Ishizaki; M Kino; H Higashino; N Ueda; Y Fujii; Y KobayashiJOURNAL OF APPLIED PHYSIOLOGY 96 6 2179 - 2186 2004年06月 [査読有り]
- T Ishizaki; Kai, I; Y Kobayashi; Y Matsuyama; Y ImanakaAGING CLINICAL AND EXPERIMENTAL RESEARCH 16 3 233 - 239 2004年06月 [査読有り]
- Lynelle Moon; Pierre Moise; Stephane Jacobzone and the ARD-Stroke Experts Group [incl. Imanaka Y; Ishizaki T; Ogawa T]OECD 2004年 [査読有り]
- M Hirose; Y Imanaka; T Ishizaki; E EvansHEALTH POLICY 66 1 29 - 49 2003年10月 [査読有り]
- Y Fujiwara; S Shinkai; S Kumagai; H Amano; Y Yoshida; H Yoshida; H Kim; T Suzuki; T Ishizaki; H Haga; S Watanabe; H ShibataARCHIVES OF GERONTOLOGY AND GERIATRICS 36 2 141 - 153 2003年03月 [査読有り]
- T Ishizaki; Y Imanaka; M Hirose; K Kuwabara; T Ogawa; Y HaradaINTERNATIONAL JOURNAL FOR QUALITY IN HEALTH CARE 14 5 411 - 418 2002年10月 [査読有り]
- T Ishizaki; Kai, I; Y Kobayashi; Y ImanakaARCHIVES OF GERONTOLOGY AND GERIATRICS 35 2 107 - 120 2002年09月 [査読有り]
- Y Ishizaki; T Ishizaki; H Fukuoka; CS Kim; M Fujita; Y Maegawa; H Fujioka; T Katsura; Y Suzuki; A GunjiACTA ASTRONAUTICA 50 7 453 - 459 2002年04月 [査読有り]
- Comparison of the psychosocial associations of Japanese children and their parents in the US and in a rural area in Japan.Ishizaki Y; Ishizaki T; Kobayashi Y; Ozawa K; Yoshida S; Amayasu HAdvances in Psychology Research 13 151-163 2002年
- Psychosocial association of japanese mothers and their children when living temporarily abroad.Ishizaki Y; Ishizaki TSchool psychology international 22 1 29-42 2001年
- T Ishizaki; S Watanabe; T Suzuki; H Shibata; H HagaJOURNAL OF THE AMERICAN GERIATRICS SOCIETY 48 11 1424 - 1429 2000年11月 [査読有り]
- The role of geriatric intermediate care facilities in long-term care for the elderly in JapanIshizaki, T; Kobayashi, Y; Tamiya, NHealth Policy 43 2 141-151 1998年01月 [査読有り]
- 月経随伴症候群が疑われ当帰芍薬散が有効であった1例石崎優子; 葛西浩史; 大池ひとみ; 内田栄一; 降矢英成; 桂戴作; 石崎達郎漢方診療 16 1 19-21 1997年
- 母性性に関する心身医学的研究(第3報)-母性性との関わりにおける父性性,男性性のイメ-ジの検討 - Comparative images of fatherhood and manhood with motherhood in Japan -石崎優子; 桂戴作; 織田正昭; 日暮眞; 石崎達郎; 原節子心身医療 8 9 54-58 1996年
- 石崎優子; 石崎達郎; 桂戴作; 織田正昭; 日暮眞; 原節子心身医学 36 6 467-474 1996年
- 石崎優子; 石崎達郎; 桂 戴作; 織田正昭; 日暮 眞; 原 節子心身医学 36 475 - 481 1996年 [査読有り]
- 職域における動脈硬化性疾患の諸指標に関与する因子 ― 作業態様を中心にした解析 ―林剛司; 庄司幸子; 山岡和枝; 矢野栄二; 小林廉毅; 石崎達郎; 行山康; 加藤登紀子; 森正樹; 三好裕司; 村上正孝日本公衆衛生学雑誌 41 11 1050 - 1064 1994年
- Association of Trajectories of Cognitive Function with Mortality and Health Care CostsTaniguchi Y; Kitamura A; Ishizaki T; Fujiwara Y; Seino S; Mitsutake S; Suzuki H; Yokoyama Y; Abe T; Ikeuchi T; Shinkai SGeriatrics and Gerontology International (in press) [査読有り]
MISC
- 増井 幸恵; 権藤 恭之; 中川 威; 小川 まどか; 春日 彩花; 安元 佐織; 吉田 祐子; 井藤 佳恵; 神出 計; 池邉 一典; 石崎 達郎 老年社会科学 44 (2) 202 -202 2022年06月
- 地域在住高齢者における糖尿病とアテローム性動脈硬化症の関連性 SONIC研究菊池 晴奈; 呉代 華容; 樺山 舞; 赤坂 憲; 池邉 一典; 新井 康通; 石崎 達郎; 権藤 恭之; 楽木 宏実; 神出 計 日本老年医学会雑誌 59 (Suppl.) 102 -102 2022年05月
- 地域在住高齢者の高血圧、糖尿病の合併とうつ傾向の関連小林 慶吾; 呉代 華容; 樺山 舞; 赤坂 憲; 権藤 恭之; 増井 幸恵; 新井 康通; 石崎 達郎; 楽木 宏実; 神出 計 日本老年医学会雑誌 59 (Suppl.) 111 -112 2022年05月
- 地域在住高齢者における疾患への罹患と主観的健康感の関連についての検討田村 彩乃; 樺山 舞; 呉代 華容; 赤坂 憲; 権藤 恭之; 増井 幸恵; 新井 康通; 石崎 達郎; 楽木 宏実; 神出 計 日本老年医学会雑誌 59 (Suppl.) 112 -112 2022年05月
- 地域在住高齢者における睡眠薬使用・睡眠状態とフレイルの関連性は年代別で異なる SONIC研究水野 稔基; 呉代 華容; 樺山 舞; 権藤 恭之; 小川 まどか; 増井 幸恵; 新井 康通; 石崎 達郎; 楽木 宏実; 神出 計 日本老年医学会雑誌 59 (Suppl.) 125 -125 2022年05月
- 地域在住高齢者における70歳以降の就労に関連する要因についての男女別検討久保 心櫻; 呉代 華容; 樺山 舞; 赤坂 憲; 安元 佐織; 増井 幸恵; 石崎 達郎; 権藤 恭之; 楽木 宏実; 神出 計 日本老年医学会雑誌 59 (Suppl.) 136 -136 2022年05月
- 90代高齢者の心理的well-beingの関連要因 人生100年時代のwell-being井藤 佳恵; 岡村 毅; 粟田 主一; 権藤 恭之; 増井 幸恵; 稲垣 宏樹; 神出 計; 池邉 一典; 新井 康通; 石崎 達郎 日本老年医学会雑誌 59 (Suppl.) 155 -155 2022年05月
- 地域在住高齢者の動脈硬化性疾患発症における血清脂質値とその治療に関する縦断解析 SONIC研究中村 祐子; 樺山 舞; 呉代 華容; 杉本 研; 赤坂 憲; 権藤 恭之; 新井 康通; 石崎 達郎; 樂木 宏実; 神出 計 日本老年医学会雑誌 58 (4) 653 -654 2021年10月
- 骨関節疾患を有する地域在住高齢者における身体的フレイルの要因についての検討大畑 裕可; 樺山 舞; 呉代 華容; 赤坂 憲; 権藤 恭之; 増井 幸恵; 新井 康通; 石崎 達郎; 樂木 宏実; 神出 計 日本老年医学会雑誌 58 (Suppl.) 169 -169 2021年05月
- 地域在住高齢者高血圧患者における経済状況と血圧コントロールの関連野上 素子; 樺山 舞; 呉代 華容; 赤坂 憲; 権藤 恭之; 増井 幸恵; 新井 康通; 石崎 達郎; 樂木 宏実; 神出 計 日本老年医学会雑誌 58 (Suppl.) 192 -193 2021年05月
- 地域在住高齢者における疾患の種類と主観的健康感の関連の検討 SONIC研究田村 彩乃; 樺山 舞; 呉代 華容; 赤坂 憲; 権藤 恭之; 増井 幸恵; 新井 康通; 石崎 達郎; 樂木 宏実; 神出 計 日本老年医学会雑誌 58 (Suppl.) 193 -193 2021年05月
- 地域在住高齢者の高血圧とうつ傾向の関連性の検討小林 慶吾; 呉代 華容; 樺山 舞; 赤坂 憲; 権藤 恭之; 増井 幸恵; 新井 康通; 石崎 達郎; 樂木 宏実; 神出 計 日本老年医学会雑誌 58 (Suppl.) 194 -194 2021年05月
- 崔 煌; 権藤 恭之; 増井 幸恵; 中川 威; 安元 佐織; 小野口 航; 池邉 一典; 神出 計; 樺山 舞; 石崎 達郎 老年社会科学 43 (1) 5 -14 2021年04月
- Hiroyuki Muto; Yasuyuki Gondo; Ayaka Kasuga; Takeshi Nakagawa; Yoshiko Ishioka; Wataru Onoguchi; Akari Kikuchi; Hiroki Inagaki; Madoka Ogawa; Noriko Hori; Yukie Masui; Hwang Choe; Yutian Cheng; Kiyoaki Matsumoto; Saori Yasumoto; Mai Kabayama; Kayo Godai; Kazunori Ikebe; Kei Kamide; Tatsuro Ishizaki PsyArXiv 2021年03月
- 大畑裕可; 樺山舞; 呉代華容; 赤坂憲; 山本浩一; 杉本研; 池邉一典; 増井幸恵; 権藤恭之; 石崎達郎; 楽木宏実; 神出計 日本サルコペニア・フレイル学会誌 5 (Supplement) 2021年
- 三浦ゆり; 川上恭司郎; 井出野佑太; 増井幸恵; 稲垣宏樹; 津元裕樹; 梅澤啓太郎; 新井康通; 池邉一典; 石崎達郎; 神出計; 権藤恭之; 遠藤玉夫 日本プロテオーム学会大会プログラム・抄録集 2021 (CD-ROM) 2021年
- 三浦 ゆり; 川上 恭司郎; 井出野 佑太; 増井 幸恵; 稲垣 宏樹; 小野口 航; 津元 裕樹; 梅澤 啓太郎; 新井 康通; 池邉 一典; 石崎 達郎; 神出 計; 権藤 恭之; 遠藤 玉夫 電気泳動 64 (Suppl.) s16 -s16 2020年11月
- 地域在住高齢者における視覚機能と転倒の関連の検討SONIC Study70歳データを用いて堀 紀子; 増井 幸恵; 石岡 良子; 吉田 祐子; 石崎 達郎; 神出 計; 権藤 恭之 日本公衆衛生学会総会抄録集 79回 257 -257 2020年10月
- 地域在住高齢者における認知機能別に見た血糖コントロール状況に関する検討 SONIC研究井口 真由香; 樺山 舞; 権藤 恭之; 増井 幸恵; 杉本 研; 赤坂 憲; 新井 康通; 石崎 達郎; 樂木 宏実; 神出 計 日本老年医学会雑誌 57 (Suppl.) 69 -69 2020年07月
- 地域在住一般住民高齢者における血圧手帳で判断した白衣現象及び白衣高血圧の実態と関連因子の検討 SONIC研究卜 進梅; 樺山 舞; 杉本 研; 赤坂 憲; 権藤 恭之; 新井 康通; 増井 幸恵; 石崎 達郎; 樂木 宏実; 神出 計 日本老年医学会雑誌 57 (Suppl.) 103 -103 2020年07月
- 地域在住高齢者における認知機能別に見た血糖コントロール状況に関する検討 SONIC研究井口 真由香; 樺山 舞; 権藤 恭之; 増井 幸恵; 杉本 研; 赤坂 憲; 新井 康通; 石崎 達郎; 樂木 宏実; 神出 計 日本老年医学会雑誌 57 (Suppl.) 69 -69 2020年07月
- 地域在住の高齢者ならびに超高齢者の身体機能と要介護認定との関連 SONIC研究シートゥムンクウィアラユ; 樺山 舞; 呉代 華容; クリンプタンノンラツク; 杉本 研; 石崎 達郎; 権藤 恭之; 樂木 宏実; 下方 浩史; 神出 計 日本老年医学会雑誌 57 (Suppl.) 79 -79 2020年07月
- FOXO3A SNPと心血管疾患の関連性の検討クリンプタンノンラツク; 樺山 舞; 赤木 優也; シートゥムンクウィアラユ; 石崎 達郎; 権藤 恭之; 樂木 宏実; Allsopp Richard; Willcox Bradley; 神出 計 日本老年医学会雑誌 57 (Suppl.) 91 -91 2020年07月
- 地域在住一般住民高齢者における血圧手帳で判断した白衣現象及び白衣高血圧の実態と関連因子の検討 SONIC研究卜 進梅; 樺山 舞; 杉本 研; 赤坂 憲; 権藤 恭之; 新井 康通; 増井 幸恵; 石崎 達郎; 樂木 宏実; 神出 計 日本老年医学会雑誌 57 (Suppl.) 103 -103 2020年07月
- 小川 まどか; 権藤 恭之; 安元 佐織; 小野口 航; 増井 幸恵; 神出 計; 池邉 一典; 石崎 達郎 老年社会科学 42 (2) 114 -114 2020年06月
- 吉田 祐子; 増井 幸恵; 稲垣 宏樹; 小川 まどか; 松本 清明; 鈴木 隆雄; 池邉 一典; 神出 計; 新井 康通; 権藤 恭之; 石崎 達郎 老年社会科学 42 (2) 138 -138 2020年06月
- 吉田 祐子; 増井 幸恵; 稲垣 宏樹; 小川 まどか; 松本 清明; 鈴木 隆雄; 池邉 一典; 神出 計; 新井 康通; 権藤 恭之; 石崎 達郎 老年社会科学 42 (2) 138 -138 2020年06月
- 大浦智子; 鷲尾昌一; 石崎達郎; 大坪徹也; 安西将也; 甲斐一郎; 植木章三; 矢庭さゆり; 藤原佳典; 奥村二郎 日本公衆衛生雑誌 67 (7) 2020年
- 三浦ゆり; 川上恭司郎; 井出野佑太; 増井幸恵; 稲垣宏樹; 小野口航; 津元裕樹; 梅澤啓太郎; 新井康通; 池邉一典; 石崎達郎; 神出計; 権藤恭之; 遠藤玉夫 電気泳動(Web) 64 (Suppl) 2020年
- 仙石多美; 中山健夫; 石崎達郎; 加藤源太; 大寺祥佑; 岩尾友秀; 酒井未知; 後藤禎人; 高橋由光 日本疫学会学術総会講演集(Web) 30th 2020年
- 地域在住高齢者における貧血と主観的健康感の関連性 SONIC研究野間 智子; 樺山 舞; 樋口 温子; 杉本 研; 権藤 恭之; 新井 康通; 石崎 達郎; 池邉 一典; 樂木 宏実; 神出 計 日本老年医学会雑誌 56 (4) 560 -560 2019年10月
- 地域在住高齢者における貧血と主観的健康感の関連性 SONIC研究野間 智子; 樺山 舞; 樋口 温子; 杉本 研; 権藤 恭之; 新井 康通; 石崎 達郎; 池邉 一典; 樂木 宏実; 神出 計 日本老年医学会雑誌 56 (4) 560 -560 2019年10月
- 吉田 祐子; 増井 幸恵; 稲垣 宏樹; 小川 まどか; 小野口 航; 樺山 舞; 神出 計; 池邉 一典; 新井 康通; 権藤 恭之; 石崎 達郎 老年社会科学 41 (2) 220 -220 2019年06月
- 地域在住高齢者におけるAPOE遺伝子型と認知機能に関する検討綱井 仁美; 赤木 優也; 樺山 舞; 杉本 研; 増井 幸恵; 新井 康通; 権藤 恭之; 石崎 達郎; 樂木 宏実; 神出 計 日本老年医学会雑誌 56 (Suppl.) 94 -94 2019年05月
- 地域在住高齢者におけるIADL経時変化の類型化とその特徴(SONIC研究)清重 映里; 樺山 舞; 増井 幸恵; 権藤 恭之; 杉本 研; 池邉 一典; 新井 康通; 石崎 達郎; 樂木 宏実; 神出 計 日本老年医学会雑誌 56 (Suppl.) 106 -106 2019年05月
- 地域在住高齢者における心疾患と身体的フレイルの関連性の検討 SONIC研究ノンラック・クリンプタン; 樺山 舞; 赤木 優也; 和田 直子; 清重 映里; 杉本 研; 石崎 達郎; 権藤 恭之; 樂木 宏実; 神出 計 日本老年医学会雑誌 56 (Suppl.) 121 -121 2019年05月
- 地域在住高齢者における飲酒と認知機能の関連 SONIC研究赤木 優也; 樺山 舞; 赤坂 憲; 山本 浩一; 杉本 研; 池邉 一典; 権藤 恭之; 石崎 達郎; 樂木 宏実; 神出 計 日本老年医学会雑誌 56 (Suppl.) 122 -123 2019年05月
- 地域在住高齢者における脳卒中既往と認知機能低下の関連の関連性 SONIC研究シートゥムンク・ウィアラユ; 樺山 舞; 赤木 優也; 樋口 温子; 清重 映里; 杉本 研; 石崎 達郎; 権藤 恭之; 樂木 宏実; 神出 計 日本老年医学会雑誌 56 (Suppl.) 123 -123 2019年05月
- 地域在住高齢者における薬剤処方パターンの分析 SONIC研究石崎 達郎; 吉田 祐子; 小野口 航; 増井 幸恵; 樺山 舞; 神出 計; 新井 康通; 池邊 一典; 権藤 恭之; 樂木 宏美 日本老年医学会雑誌 56 (Suppl.) 150 -150 2019年05月
- 井出野佑太; 井出野佑太; 増井幸恵; 稲垣宏樹; 津元裕樹; 梅澤啓太郎; 川上恭司郎; 新井康通; 池邉一典; 石崎達郎; 神出計; 権藤恭之; 遠藤玉夫; 三浦ゆり 日本薬学会関東支部大会講演要旨集 63rd 2019年
- 要介護高齢者のリハビリテーションにおける環境の位置づけと現状の課題土屋瑠見子; 光武誠吾; 石崎達郎 老年医学 1 19 -23 2019年01月
- 神出 計; 樺山 舞; 杉本 研; 赤坂 憲; 池邉 一典; 新井 康通; 増井 幸恵; 石崎 達郎; 権藤 恭之; 樂木 宏実 日本内分泌学会雑誌 94 (4) 1561 -1561 2018年12月
- 嗜好品の継続摂取が高齢者の心身の機能に与える影響に関する縦断的検討松本 清明; 権藤 恭之; 神出 計; 池邉 一典; 増井 幸恵; 石崎 達郎 日本応用老年学会大会 13回 34 -34 2018年10月
- 喫煙と糖尿病が地域在住男性高齢者の握力に及ぼす影響について SONIC研究澤山 泰佳; 樺山 舞; 権藤 恭之; 増井 幸恵; 杉本 研; 池邉 一典; 新井 康通; 石崎 達郎; 樂木 宏実; 神出 計 日本老年医学会雑誌 55 (4) 729 -729 2018年10月
- 高齢者の信頼感と社会参加および精神的健康の関連についての縦断的検討小野口 航; 福川 康之; 樺山 舞; 増井 幸恵; 稲垣 宏樹; 小川 まどか; 神出 計; 石崎 達郎 日本公衆衛生学会総会抄録集 77回 236 -236 2018年10月
- JST版活動能力指標と心身の健康指標との関連吉田 祐子; 増井 幸恵; 稲垣 宏樹; 岩佐 一; 小川 まどか; 小野口 航; 樺山 舞; 神出 計; 石崎 達郎 日本公衆衛生学会総会抄録集 77回 431 -431 2018年10月
- 光武 誠吾; 石崎 達郎; 寺本 千恵; 土屋 瑠見子 日本公衆衛生学会総会抄録集 77回 234 -234 2018年10月
- Interpersonal exchanges and Leisure activities are associated with Hypertension and Diabetes in community-dwelling old Japanese: the SONIC study.Wada N; Kabayama M; Gondo Y; Masui Y; Yasumoto S; Sugimoto K; Arai Y; Ishizaki T; Rakugi H; Kamide K Hypertension Beijing 2018 Final programme. 2018年09月 [査読有り]
- 小川まどか; 田坂英理子; 権藤恭之; 増井幸恵; 石崎達郎; 池邉一典; 神出計 老年社会科学 40 (2 (Web)) 252 (WEB ONLY) -252 2018年06月
- 増井幸恵; 権藤恭之; 石崎達郎; 小野口航; 小川まどか; 稲垣宏樹; 石岡良子; 安元佐織; 池邉一典; 神出計; 新井康通 老年社会科学 40 (2 (Web)) 215 (WEB ONLY) -215 2018年06月
- 老年社会科学研究のための研究倫理権藤恭之; 須田木綿子; 松岡千代; 石崎達郎 2018年06月 [招待有り]
- 高齢者の孤食の地域特徴と精神的健康および社会的活動度との関連木村 友美; 権藤 恭之; 池邉 一典; 神出 計; 石崎 達郎; 増井 幸恵 日本老年医学会雑誌 55 (Suppl.) 102 -102 2018年05月
- 樺山 舞; 神出 計; 権藤 恭之; 山本 浩一; 杉本 研; 赤坂 憲; 増井 幸恵; 新井 康通; 石崎 達郎; 樂木 宏実 日本循環器病予防学会誌 53 (2) 179 -179 2018年05月
- 和田 直子; 樺山 舞; 権藤 恭之; 増井 幸恵; 安元 佐織; 杉本 研; 新井 康通; 石崎 達郎; 樂木 宏実; 神出 計 日本循環器病予防学会誌 53 (2) 184 -184 2018年05月
- 地域在住高齢者における血清脂質プロファイルと認知機能との関連性 SONIC研究樋口 温子; 樺山 舞; 山本 浩一; 杉本 研; 新井 康通; 石崎 達郎; 池邉 一典; 権藤 恭之; 樂木 宏実; 神出 計 日本老年医学会雑誌 55 (Suppl.) 96 -96 2018年05月
- 70歳前後の地域在住高齢者における認知機能の経時変化(SONIC研究)清重 映里; 神出 計; 樺山 舞; 増井 幸恵; 稲垣 宏樹; 池邉 一典; 新井 康通; 石崎 達郎; 樂木 宏実; 権藤 恭之 日本老年医学会雑誌 55 (Suppl.) 97 -98 2018年05月
- 高齢者における血圧値と3年後認知機能低下の年代別関連性の検討(SONIC研究)樺山 舞; 神出 計; 権藤 恭之; 山本 浩一; 杉本 研; 増井 幸恵; 稲垣 宏樹; 新井 康通; 石崎 達郎; 樂木 宏実 日本老年医学会雑誌 55 (Suppl.) 111 -111 2018年05月
- 地域在住高齢者における糖尿病管理と社会的要因との関連和田 直子; 樺山 舞; 権藤 恭之; 増井 幸恵; 安元 沙織; 杉本 研; 新井 康通; 石崎 達郎; 樂木 宏実; 神出 計 日本老年医学会雑誌 55 (Suppl.) 130 -131 2018年05月
- 地域一般住民高齢者を対象にした血清尿酸と頸動脈アテローム性動脈硬化症との関連について SONIC研究田中 健太郎; 樺山 舞; 杉本 研; 赤坂 憲; 池邉 一典; 新井 康通; 石崎 達郎; 権藤 恭之; 樂木 宏実; 神出 計 日本老年医学会雑誌 55 (Suppl.) 135 -135 2018年05月
- 光武誠吾; 石崎達郎; 藤本修平; 清水沙友里; 井藤英喜 総合リハビリテーション 46 (9) 867 -873 2018年 [査読有り]
- 三浦 ゆり; 岩本 真知子; 稲垣 宏樹; 増井 幸恵; 石岡 良子; 津元 裕樹; 樺山 舞; 杉本 研; 阿部 由紀子; 新井 康通; 神出 計; 池邉 一典; 石崎 達郎; 権藤 恭之; 高橋 龍太郎; 遠藤 玉夫 電気泳動 61 (Suppl.) s24 -s24 2017年11月
- 高島平Study 大都市部在住高齢者における口腔への関心に関連する因子の検討本橋 佳子; 渡邊 裕; 本川 佳子; 枝広 あや子; 白部 麻樹; 三上 友里江; 大須賀 洋祐; 平野 浩彦; 金 憲経; 北村 明彦; 藤原 佳典; 大渕 修一; 石崎 達郎; 新開 省二; 粟田 主一 日本公衆衛生学会総会抄録集 76回 399 -399 2017年10月
- 高島平Study 都市部在住高齢者の外出頻度の減少と口腔機能低下との関連三上 友里江; 渡邊 裕; 本川 佳子; 枝広 あや子; 白部 麻樹; 本橋 佳子; 大須賀 洋祐; 平野 浩彦; 金 憲経; 北村 明彦; 藤原 佳典; 大渕 修一; 石崎 達郎; 新開 省二; 粟田 主一 日本公衆衛生学会総会抄録集 76回 399 -399 2017年10月
- 高次生活機能の加齢変化パターンと医療費及び介護費との関連 草津町研究谷口 優; 北村 明彦; 野藤 悠; 石崎 達郎; 清野 諭; 横山 友里; 村山 洋史; 光武 誠吾; 天野 秀紀; 西 真理子; 干川 なつみ; 濱口 奈緒美; 岡部 たづる; 藤原 佳典; 新開 省二 日本公衆衛生学会総会抄録集 76回 396 -396 2017年10月
- 地域在住高齢者における長寿関連遺伝子SIRT1、FOXO3A遺伝子多型と動脈硬化の関連性の検討 SONIC研究赤木 優也; 神出 計; 樺山 舞; 龍野 洋慶; 赤坂 憲; 山本 浩一; 杉本 研; 池邉 一典; 増井 幸恵; 石崎 達郎; 新井 康通; 権藤 恭之; 楽木 宏実 日本高血圧学会総会プログラム・抄録集 40回 406 -406 2017年10月
- 高齢者における血圧値と認知機能の関連性(SONIC研究) 年代およびフレイル別検討樺山 舞; 神出 計; 龍野 洋慶; 権藤 恭之; 赤坂 憲; 山本 浩一; 杉本 研; 池邉 一典; 稲垣 宏樹; 増井 幸恵; 新井 康通; 石崎 達郎; 楽木 宏実 日本高血圧学会総会プログラム・抄録集 40回 412 -412 2017年10月
- 石崎 達郎; 光武 誠吾; 寺本 千恵 日本公衆衛生学会総会抄録集 76回 312 -312 2017年10月
- 光武 誠吾; 寺本 千恵; 石崎 達郎 日本公衆衛生学会総会抄録集 76回 521 -521 2017年10月
- 高齢者におけるソーシャルキャピタルの地域差と年代差―SONIC研究の横断的データから―小野口航; 福川康之; 樺山舞; 権藤恭之; 増井幸恵; 石崎達郎; 安元佐織; 松本清明 2017年09月
- 太田 美緒; 甲斐 一郎; 石崎 達郎 厚生の指標 = Journal of health and welfare statistics 64 (8) 20 -27 2017年08月
- Investigation about Associated Illness with Disability in Community-Dwelling Older Population.Kiyoshige E; Kabayama M; Sugimoto K; Arai Y; Ishizaki T; Gondo Y; Rakugi H; Kamide K The 21ST IAGG World Congress of Gerontology & Geriatrics Program Book. 80 -80 2017年07月 [査読有り]
- Urinary Albumin-to-Creatinine Ratio and Carotid Atherosclerosis in the Very Old.Arai Y; Hirata T; Takayama M; Abe Y; Ishizaki T; Masui Y; Kamide K; Gondo Y The 21ST IAGG World Congress of Gerontology & Geriatrics Program Book. 188 -188 2017年07月 [査読有り]
- Association between Protein Intake and Change in Renal Function Among Japanese General Old Subjects.Sekiguchi T; Kamide K; Ikebe K; Kabayama M; Arai Y; Ishizaki T; Gondo Y; Rakugi H The 21ST IAGG World Congress of Gerontology & Geriatrics Program Book. 148 -148 2017年07月 [査読有り]
- Premorbid Personality and the Occurrences of the Risk of MCI after 3 Years in Japanese Elderly.Masui Y; Inagaki H; Gondo Y; Kurinobu T; Ikebe K; Kamide K; Arai Y; Ishizaki T The 21ST IAGG World Congress of Gerontology & Geriatrics Program Book. 109 -109 2017年07月 [査読有り]
- Association of Genetic Variation of TOMM40 with Cognitive Decline in Older Adults: The SONIC Study.Ryuno H; Kamide K; Kabayama M; Sugimoto K; Ishizaki T; Arai Y; Gondo Y; Rakugi H The 21ST IAGG World Congress of Gerontology & Geriatrics Program Book. 193 -193 2017年07月 [査読有り]
- 健康長寿の延伸には何がどの程度重要となるのか池邉一典; 権藤恭之; 神出 計; 増井幸恵; 石崎達郎; 新井康通; 村上伸也; 前田芳信 歯界展望 130 (1) 28 -31 2017年07月 [査読有り]
- Association between Individual Chronic Diseases and Polypharmacy among Elderly Patients in Japan.Tatsuro Ishizaki; Seigo Mitsutake; Chie Teramoto; Takuya Yamaoka; Sayuri Shimizu; Hideki Ito The 21st IAGG World Congress of Gerontology and Geriatrics, San Francisco, the United States of America, July 23-27, 2017. 2017年07月
- 増井幸恵; 池邉一典; 権藤恭之; 神出計; 新井康通; 栗延孟; 小川まどか; 稲垣宏樹; 石崎達郎; 前田芳信 老年社会科学 39 (2 (CD-ROM)) 182 -182 2017年06月
- 高齢者の主観的幸福感に影響を与える要因に関する研究ー感謝感情に注目してー蔡羽淳; 権藤恭之; 中川威; 増井幸恵; 安元佐織; 神出計; 池邉一典; 石崎達郎; 高橋龍太郎; 新井康通 2017年06月
- 生活習慣病を有する地域一般住民高齢者における喫煙が認知機能に与える影響について SONIC研究澤山 泰佳; 樺山 舞; 龍野 洋慶; 杉本 研; 権藤 恭之; 増井 幸恵; 新井 康通; 石崎 達郎; 樂木 宏実; 神出 計 日本老年医学会雑誌 54 (Suppl.) 143 -143 2017年05月
- 地域一般高齢者における腎機能保持とたんぱく質摂取量との関連について SONIC studyを用いた縦断研究関口 敏彰; 神出 計; 池邉 一典; 龍野 洋慶; 樺山 舞; 杉本 研; 新井 康通; 石崎 達郎; 権藤 恭之; 樂木 宏実 日本老年医学会雑誌 54 (Suppl.) 170 -170 2017年05月
- 高齢者における血圧値と認知機能の年代別関連性の検討 SONIC研究樺山 舞; 神出 計; 龍野 洋慶; 権藤 恭之; 山本 浩一; 杉本 研; 増井 幸恵; 新井 康通; 石崎 達郎; 樂木 宏実 日本老年医学会雑誌 54 (Suppl.) 171 -172 2017年05月
- 地域一般住民高齢者を対象にした尿酸と心血管病との関連について SONIC研究田中 健太郎; 樺山 舞; 龍野 洋慶; 杉本 研; 池邉 一典; 新井 康通; 石崎 達郎; 権藤 恭之; 樂木 宏実; 神出 計 日本老年医学会雑誌 54 (Suppl.) 172 -172 2017年05月
- 地域在住高齢者における要介護認定と生活習慣病・慢性疾患の関連性の検討 SONIC研究清重 映里; 樺山 舞; 龍野 洋慶; 杉本 研; 池邉 一典; 新井 康通; 石崎 達郎; 権藤 恭之; 樂木 宏実; 神出 計 日本老年医学会雑誌 54 (Suppl.) 174 -175 2017年05月
- 澤山 泰佳; 樺山 舞; 権藤 恭之; 龍野 洋慶; 関口 敏彰; 清重 映里; 赤木 優也; 山本 浩一; 杉本 研; 池邉 一典; 新井 康通; 増井 幸恵; 石崎 達郎; 楽木 宏実; 神出 計 日本循環器病予防学会誌 52 (2) 209 -209 2017年05月
- 石崎 達郎; 光武 誠吾; 寺本 千恵; 山岡 巧弥; 清水 沙友里; 井藤 英喜 日本老年医学会雑誌 54 (Suppl.) 186 -186 2017年05月
- 表在性Barrett癌の組織学的な予後因子 多施設共同研究(Histopathologic features for prognostication of superficial Barrett's carcinoma: a multicenter study)相田 順子; 石崎 達郎; 田久保 海誉; 新井 冨生; 石渡 俊行 日本病理学会会誌 106 (1) 279 -279 2017年03月
- Hirochika Ryuno; Kei Kamide; Yasuyuki Gondo; Mai Kabayama; Ken Sugimoto; Kazunori Ikebe; Tatsuro Ishizaki; Yasumichi Arai; Hiromi Rakugi HYPERTENSION RESEARCH 40 (3) 302 -303 2017年03月 [査読有り]
- 石崎 達郎 日本老年医学会雑誌 = Japanese journal of geriatrics 54 (1) 18 -21 2017年01月
- 三浦ゆり; 岩本真知子; 稲垣宏樹; 増井幸恵; 石岡良子; 津元裕樹; 樺山舞; 杉本研; 阿部由紀子; 新井康通; 神出計; 池邉一典; 石崎達郎; 権藤恭之; 高橋龍太郎; 遠藤玉夫 電気泳動(Web) 61 (Suppl) 2017年
- 要介護高齢者の移行期ケアプログラムの現状について光武誠吾; 石崎達郎 日本老年医学会雑誌 54 41 -49 2017年
- Gondo, Y; Masui, Y; Kamide, K; Ikebe, K; Arai, Y; Ishizaki, T Encyolopedia of Geropsychology 2017年01月 [招待有り]
- 大都市圏における在宅医療の実態把握と提供体制の評価に関する研究.石崎達郎; 田宮菜奈子; 福田治久; 光武誠吾; 寺本千恵 平成28年度総括研究報告書,2017. 2017年
- Home Medical Care in Japan in Long Term Care SettingsTatsuro Ishizaki; Seigo; Chie Teramoto GERONTOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA ANNUAL SCIENTIFIC MEETING 2016年11月
- 光武 誠吾; 石崎 達郎; 寺本 千恵 日本公衆衛生学会総会抄録集 75回 521 -521 2016年10月
- 相田 順子; 石崎 達郎; 石渡 俊行; 田久保 海誉; 新井 冨生 胃と腸 51 (10) 1269 -1282 2016年09月
- The Association of The Blood Pressure with Frailty Indications among Community-Dwelling Older Man with or Without Antihypertensive Treatment.Kabayama M; Kamide K; Gondo Y; Masui Y; Ryuno H; Nakaga T; Yamamoto K; Sugimoto K; Ikebe K; Arai Y; Ishizaki T; Rakuki H The 26th Scientific Meeting of the International Society of Hypertention 2016年09月 [査読有り]
- Ryuno H; Kamide K; Gondo Y; Kabayama M; Sugimoto K; Nakagawa T; Ikebe K; Inagaki H; Masui Y; Arai Y; Ishizaki T; Rakugi H; Suppl; ISH; Abstract Book 34 Suppl 1 - ISH 2016 Abstract Book e396 2016年09月 [査読有り]
- Nakagawa Takeshi; Gondo Yasuyuki; Masui Yukie; Ishioka Yoshiko; Ogawa Madoka; Inagaki Hiroki; Tabuchi Megumi; Kozono Marina; Yasumoto Saori; Numata Keitaro; Kurinobu Takeshi; Tsai Ujyun; Goto Fumika; Takayama Midori; Ikebe Kazunori; Kamide Kei; Arai Yasumichi; Ishizaki Tatsuro; Takahashi Ryutaro INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOLOGY 51 32 2016年07月 [査読有り]
- Masui Yukie; Gondo Yasuyuki; Nakagagawa Takeshi; Ishioka Yoshiko; Ogawa Madoka; Kozono Marina; Inagaki Hiroki; Takayama Midori; Katagiri Keiko; Yasumoto Saori; Megumi Tabuchi; Kurinobu Takeshi; Arai Yasumichi; Ikebe Kazunori; Kamide Kei; Takahashi Ryutaro; Ishizaki Tatsuro INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOLOGY 51 47 2016年07月 [査読有り]
- Kozono Marina; Gondo Yasuyuki; Ogawa Madoka; Ishioka Yoshiko; Nakagawa Takeshi; Masui Yukie; Inagaki Hiroki; Tabuchi Megumi; Ikebe Kazunori; Kamide Kei; Arai Yasumichi; Ishizaki Tatsuro; Takahashi Ryutaro INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOLOGY 51 46 2016年07月 [査読有り]
- Ishioka Yoshiko; Gondo Yasuyuki; Masui Yukie; Nakagawa Takeshi; Ogawa Madoka; Inagaki Hiroki; Tabuchi Megumi; Kozono Marina; Yasumoto Saori; Kurinobu Takeshi; Takayama Midori; Katagiri Keiko; Arai Yasumichi; Kamide Kei; Ikebe Kazunori; Ishizaki Tatsuro; Takahashi Ryutaro INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOLOGY 51 45 2016年07月 [査読有り]
- Goto Fumika; Gondo Yasuyuki; Nakagawa Takeshi; Yasumoto Saori; Masui Yukie; Ogawa Madoka; Takahashi Ryutaro; Ishizaki Tatsuro INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOLOGY 51 51 -52 2016年07月 [査読有り]
- こころのフレイルを超えて:高齢期の老年的超越の発達権藤恭之; 増井幸恵; 石崎達郎; 神出計; 池邉一典; 新井康通 2016年06月 [招待有り]
- B. J. Morris; R. Chen; T. A. Donlon; D. S. Evans; G. J. Tranah; N. Parimi; G. B. Ehret; C. Newton-Cheh; T. Seto; D. C. Willcox; K. Masaki; K. Kamide; H. Ryuno; R. Oguro; C. Nakama; M. Kabayama; K. Yamamoto; K. Sugimoto; K. Ikebe; Y. Masui; Y. Arai; T. Ishizaki; Y. Gondo; H. Rakugi; B. J. Willcox HYPERTENSION 67 (5) E13 -E13 2016年05月
- 地域一般高齢者における腎機能とたんぱく質摂取量との関連について SONIC studyを用いた横断研究関口 敏彰; 神出 計; 池邉 一典; 龍野 洋慶; 樺山 舞; 杉本 研; 新井 康通; 石崎 達郎; 権藤 恭之; 樂木 宏実 日本老年医学会雑誌 53 (Suppl.) 134 -134 2016年05月 [査読有り]
- 高齢期におけるTOMM40遺伝子の認知機能低下への関与(SONIC研究3年間の追跡による知見)龍野 洋慶; 神出 計; 樺山 舞; 杉本 研; 稲垣 宏樹; 石崎 達郎; 新井 康通; 池邉 一典; 権藤 恭之; 樂木 宏実 日本老年医学会雑誌 53 (Suppl.) 138 -138 2016年05月 [査読有り]
- 石崎 達郎; 寺本 千恵; 光武 誠吾; 清水 沙友里; 井藤 英喜 日本老年医学会雑誌 53 (Suppl.) 135 -136 2016年05月
- Junko Aida; Tatsuro Ishizaki; Tomio Arai; Kaiyo Takubo LABORATORY INVESTIGATION 96 160A -160A 2016年02月
- Junko Aida; Tatsuro Ishizaki; Tomio Arai; Kaiyo Takubo MODERN PATHOLOGY 29 160A -160A 2016年02月
- 石崎 達郎 日本老年医学会雑誌 = Japanese journal of geriatrics 53 (1) 4 -9 2016年01月
- 三浦ゆり; 岩本真知子; 稲垣宏樹; 増井幸恵; 石岡良子; 津元裕樹; 龍野洋慶; 杉本研; 阿部由紀子; 新井康通; 神出計; 池邉一典; 石崎達郎; 権藤恭之; 高橋龍太郎; 広瀬信義; 遠藤玉夫 基礎老化研究 40 (Supplement) 2016年
- 石崎 達郎; 寺本 千恵; 光武 誠吾 日本公衆衛生学会総会抄録集 74回 400 -400 2015年10月
- 小池高史; 小池高史; 西真理子; 深谷太郎; 小林江里香; 鈴木宏幸; 野中久美子; 斉藤雅茂; 長谷部雅美; 村山陽; 石崎達郎; 藤原佳典 老年社会科学 37 (2) 166 2015年06月
- 龍野 洋慶; 神出 計; 権藤 恭之; 小黒 亮輔; 中間 千香子; 横山 世理奈; 中川 威; 樺山 舞; 杉本 研; 池邉 一典; 新井 康通; 増井 幸恵; 石崎 達郎; 樂木 宏実 日本循環器病予防学会誌 50 (2) 147 -147 2015年06月 [査読有り]
- 職域高血圧者における降圧剤処方間隔と3年後の血圧コントロールの関連志摩 梓; 辰巳 友佳子; 呉代 華容; 森本 明子; 河津 雄一郎; 石崎 達郎; 岡村 智教; 宮松 直美 日本循環器病予防学会誌 50 (2) 133 -133 2015年06月
- 藤原佳典; 小池高史; 西真理子; 深谷太郎; 小林江里香; 鈴木宏幸; 野中久美子; 斉藤雅茂; 新開省二; 石崎達郎 日本老年医学会雑誌 52 66 2015年05月
- 高齢者における高血圧と認知機能との関連性 服薬アドヒアランスの影響 SONIC研究龍野 洋慶; 神出 計; 権藤 恭之; 小黒 亮輔; 中間 千香子; 樺山 舞; 池邉 一典; 新井 康通; 石崎 達郎; 樂木 宏実 日本老年医学会雑誌 52 (Suppl.) 61 -61 2015年05月 [査読有り]
- Association between Hypertension and Cognitive Function in Age 70 and 80 Years from Japanese SONIC StudyHirochika Ryuno; Kei Kamide; Yasuyuki Gondo; Ryosuke Oguro; Chikako Nakama; Mai Kabayama; Kazunori Ikebe; Yukie Masui; Tatsuro Ishizaki; Yasumichi Arai; Hiromi Rakugi IAGG-ER 8th Congress Abstracts 1 208 -209 2015年04月 [査読有り]
- Effects of Anti-hypertensive Medication on Cognitive Function in Older Subjects: The SONIC StudyHirochika Ryuno; Kei Kamide; Yasuyuki Gondo; Chikako Nakama; Ryosuke Oguro; Mai Kabayama; Kazunori Ikebe; Yukie Masui; Hiroki Inagaki; Tatsuro Ishizaki; Yasumichi Arai; Hiromi Rakugi IAGG-ER 8th Congress Abstracts 1 216 -216 2015年04月 [査読有り]
- 池邉一典; 岡田匡史; 猪俣千里; 武下肇; 三原佑介; 魚田真弘; 松田謙一; 榎木香織; 多田紗弥夏; 前田芳信; 村上伸也; 北村正博; 権藤恭之; 神出計; 樂木宏実; 増井幸恵; 石崎達郎; 新井康通; 大久保公美; 佐々木敏; 新谷歩 日本歯科医学会誌 34 107 2015年03月
- 石崎 達郎 老年社会科学 37 (3) 347 -352 2015年
- 河合 恒; 清野 諭; 西 真理子; 谷口 優; 大渕 修一; 新開 省二; 吉田 英世; 藤原 佳典; 平野 浩彦; 金 憲経; 石崎 達郎; 高橋 龍太郎; 鈴木 隆雄; 古名 丈人; 岩佐 一; 熊谷 修; 渡辺 修一郎; 西澤 哲; 吉田 裕人; 湯川 晴美; 藤田 幸司; 内藤 隆弘; 井原 一茂; 端詰 勝敬; 小島 基永; 福 典之; 新名 正弥; 吉田 祐子; 天野 秀紀; 深谷 太郎; 村山 洋史; 成田 美紀; 小川 貴志子; 大場 宏美; 小宇佐 陽子; 清水 由美子; 野藤 悠; 松尾 恵理; 小原 由紀; 増井 幸恵; 宇良 千秋; 三木 明子; 石神 明人; 小島 成実; TMIG-LISA研究グループ 体力科学 64 (2) 261 -271 2015年
- M. Ogawa; Y. Gondo; Y. Masui; K. Ikebe; K. Kamide; T. Ishizaki; Y. Arai; R. Takahashi GERONTOLOGIST 54 190 -190 2014年11月
- H. Inagaki; Y. Gondo; Y. Ishioka; K. Kamide; K. Ikebe; Y. Arai; T. Ishizaki; R. Takahashi GERONTOLOGIST 54 186 -186 2014年11月
- Y. Gondo; Y. Masui; T. Nakagawa; Y. Arai; K. Ikebe; K. Kamide; T. Ishizaki; R. Takahashi GERONTOLOGIST 54 104 -104 2014年11月
- C. Nakama; K. Kamide; Y. Arai; T. Ishizaki; Y. Masui; K. Ikebe; Y. Gondo; H. Rakugi GERONTOLOGIST 54 80 -80 2014年11月
- 深谷太郎; 小林江里香; 石崎達郎; 新開省二 日本公衆衛生学会総会抄録集 73rd 592 2014年10月
- 喫煙の有無による、循環器リスク因子集積がその後9年間の外来医療費に及ぼす影響志摩 梓; 呉代 華容; 森本 明子; 辰巳 友佳子; 河津 雄一郎; 石崎 達郎; 岡村 智教; 宮松 直美 日本循環器病予防学会誌 49 (2) 163 -163 2014年07月
- 田渕恵; 権藤恭之; 中川威; 増井幸恵; 小川まどか; 石岡良子; 神出計; 池邉一典; 新井康通; 石崎達郎; 高橋龍太郎 老年社会科学 36 (2) 230 -230 2014年06月
- 中川威; 権藤恭之; 増井幸恵; 石岡良子; 小川まどか; 立平起子; 神出計; 池邉一典; 新井康通; 石崎達郎; 高橋龍太郎 老年社会科学 36 (2) 254 -254 2014年06月
- 石岡良子; 権藤恭之; 増井幸恵; 中川威; 小川まどか; 立平起子; 神出計; 池邉一典; 新井康通; 石崎達郎; 高橋龍太郎 老年社会科学 36 (2) 229 -229 2014年06月
- 高齢者における唾液分泌と栄養摂取との関連 SONIC STUDYより三原 佑介; 池邉 一典; 松田 謙一; 香川 良介; 岡田 匡史; 猪俣 千里; 武下 肇; 魚田 真弘; 権藤 恭之; 神出 計; 石崎 達郎; 増井 幸恵; 新井 康通; 前田 芳信 日本老年歯科医学会総会・学術大会プログラム・抄録集 25回 97 -97 2014年06月
- 大渕 修一; 藤原 佳典; 河合 恒; 吉田 英世; 小島 基永; 平野 浩彦; 石崎 達郎; 荒木 厚; 小山 照幸; 杉江 正光; 田中 雅嗣 理学療法学 41 (大会特別号2) 1455 -1455 2014年05月
- 咬合力と歩行の速さとの関連 タンパク質摂取の媒介の検証 SONIC studyより岡田 匡史; 池邉 一典; 香川 良介; 武下 肇; 猪俣 千里; 多田 紗弥夏; 魚田 真弘; 三原 佑介; 前田 芳信; 権藤 恭之; 神出 計; 佐々木 敏; 大久保 公美; 石崎 達郎; 増井 幸恵; 新井 康通 日本補綴歯科学会誌 6 (特別号) 110 -110 2014年05月
- Eichner B1-B2群の義歯使用の有無と栄養摂取との関係 SONIC研究より猪俣 千里; 池邉 一典; 香川 良介; 岡田 匡史; 武下 肇; 多田 紗弥夏; 魚田 真弘; 三原 佑介; 吉備 政仁; 前田 芳信; 権藤 恭之; 神出 計; 佐々木 敏; 大久保 公美; 石崎 達郎; 増井 幸恵; 新井 康通 日本補綴歯科学会誌 6 (特別号) 277 -277 2014年05月
- 辻村友香; 高橋由光; 石崎達郎; 栗山明; 宮崎貴久子; 佐藤敏彦; 池田俊也; 木村真也; 中山健夫 産業衛生学雑誌 56 (1) 43 -43 2014年01月
- 市川佳世子; 高橋由光; 安梅勅江; 安藤昌彦; 石崎達郎; 中山健夫 日本行動医学会学術総会プログラム・抄録集 20th 2014年
- 石崎 達郎 老年社会科学 36 (1) 28 -33 2014年
- 「レセプトデータを活用した療養場所移行とサービス利用の追跡調査に基づく 効果的な地域連携体制の明確化」.永田智子; 辻哲夫; 飯島勝矢; 吉江悟; 山本則子; 五十嵐歩; 石崎達郎; 村山洋史; 成瀬昂; 岩本康志; 両角良子; 湯田道生; 阪井万裕; 松本博成; 寺本千恵; 櫻井美里; 伊藤翠; 錦織梨紗; 山本なつ紀 平成25年平成25年度厚生労働省労働科学研究費補助金 健康安全・危機管理対策総合研究事業.度厚生労働省労働科学研究費補助金 健康安全・危機管理対策総合研究事業.平成25年度総合研究報告書,2014. 2014年
- 市川佳世子; 佐竹順子; 岩田和彦; 金澤忠博; 安梅勅江; 安藤昌彦; 高橋由光; 石崎達郎; 中山健夫 明治安田こころの健康財団研究助成論文集 (47) 1 -10 2012年10月
- 太田 雅人; 根尾 昌志; 青山 朋樹; 石崎 達郎; 藤林 俊介; 竹本 充; 中山 健夫; 中村 孝志 Journal of Spine Research 3 (3) 451 -451 2012年03月
- 徳本史郎; 高橋由光; 石崎達郎; 宮木幸一; 中山健夫 J Epidemiol 22 (Supplement 1) 96 2012年01月
- 市川佳世子; 高橋由光; 石崎達郎; 中山健夫 J Epidemiol 22 (Supplement 1) 101 2012年01月
- 高橋由光; 石崎達郎; 中西さやか; 関根章博; 水澤精穂; 小杉眞司; 松田文彦; 中山健夫 Journal of Epidemiology 22 (Supplement 1) 109 2012年01月
- Ishizaki T [Nihon koshu eisei zasshi] Japanese journal of public health 59 (1) 50 -51 2012年01月 [査読有り]
- S. Tokumoto; Y. Takahashi; T. Ishizaki; K. Miyaki; T. Nakayama JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY AND COMMUNITY HEALTH 65 A394 -A394 2011年08月
- Y. Tsujimura; T. Nakayama; T. Ishizaki; Y. Takahashi; K. Miyazaki; T. Satoh; S. Ikeda; S. Kimura JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY AND COMMUNITY HEALTH 65 A307 -A307 2011年08月
- 石崎 達郎 日本公衆衛生雑誌 58 (7) 560 -563 2011年07月
- Ishizaki T [Nihon koshu eisei zasshi] Japanese journal of public health 58 (7) 560 -563 2011年07月 [査読有り]
- OC2アライメントが口咽頭気道径に及ぼす影響 健常被検者における分析太田 雅人; 根尾 昌志; 青山 朋樹; 石崎 達郎; 藤林 俊介; 竹本 充; 中山 健夫; 中村 孝志 日本整形外科学会雑誌 85 (3) S328 -S328 2011年03月
- 太田 雅人; 根尾 昌志; 青山 朋樹; 石崎 達郎; 藤林 俊介; 竹本 充; 中山 健夫; 中村 孝志 Journal of Spine Research 2 (3) 532 -532 2011年03月
- 小沼梨沙; 木村真也; 辻村友香; 大浦智子; 仙石多美; 宮崎貴久子; 高橋由光; 石崎達郎; 中山健夫 J Epidemiol 21 (1 Supplement) 289 2011年01月
- 白井 貴子; 今中 雄一; 関本 美穂; 石崎 達郎 日本産科婦人科學會雜誌 61 (12) 2153 -2153 2009年12月
- 地域高齢者の外出行動に着目した介護予防に対する指導者の意識変化 無作為化比較試験原田 和宏; 萩原 章由; 島田 裕之; 古名 丈人; 浅川 康吉; 二瓶 健司; 加藤 めぐ美; 金谷 さとみ; 石崎 達郎; 安村 誠司 日本公衆衛生学会総会抄録集 68回 218 -218 2009年10月
- 村上玄樹; 今中雄一; 林田賢史; 石崎達郎 日本公衆衛生学会総会抄録集 67th 371 2008年10月
- H. Fukuda; Y. Imanaka; T. Ishizaki VALUE IN HEALTH 11 (3) A83 -A83 2008年05月
- 勅使河原弘美; 氏縄優子; 清水厚子; 石崎達郎; 林田賢史; 今中雄一 日本公衆衛生学会総会抄録集 66th 262 -263 2007年10月
- 氏縄優子; 勅使河原弘美; 清水厚子; 石崎達郎; 林田賢史; 今中雄一 日本公衆衛生学会総会抄録集 66th 263 2007年10月
- Usefulness of inferior vena cava diameter in subjects with orthostatic intorelamce induced by 10 day bed rest experiment.Yuko Ishizaki; Hideoki Fukuoka; Tatsuro Ishizaki; Yuri Fujii; Minoru Kino; Hirohiko Higashino; Nobuo Ueda; Yohnosuke Kobayashi; Shoichiro Taniuchi; Kazunari Kaneko Autonomic Neuroscience: Basic & Clinical 6 103 2007年
- 今中雄一; 林田賢史; 福田治久; 関本美穂; 村上玄樹; 大坪徹也; 深田雄志; 廣瀬昌博; 石崎達郎 診断群分類を活用した医療サービスのコスト推計に関する研究報告 平成18年度 研究報告書 総括報告書 41 -67 2007年
- 今中雄一; 林田賢史; 福田治久; 関本美穂; 村上玄樹; 大坪徹也; 深田雄志; 廣瀬昌博; 石崎達郎 診断群分類を活用した医療サービスのコスト推計に関する研究報告 平成16-18年度 総括報告書 101 -197 2007年
- 石崎達郎; 林田賢史; 今中雄一 日本公衆衛生学会総会抄録集 65th 729 2006年10月
- 中山 健夫; 福原 俊一; 今中 雄一; 白川 太郎; 小杉 眞司; 川村 孝; 石崎 達郎; 森田 智視; 東 尚弘; 安藤 昌彦 医学教育 36 (Suppl.) 62 -62 2005年07月
- 石崎 達郎; 今中 雄一 月刊保険診療 59 (11) 97 -101 2004年11月
- ISHIZAKI Tatsuro Geriatrics & gerontology international 4 S132 -S134 2004年09月
- E Oh; Y Imanaka; T Ishizaki VALUE IN HEALTH 6 (3) 209 -210 2003年05月
- T Ishizaki; Y Imanaka; E Oh GERONTOLOGIST 42 10 -10 2002年10月
- 鈴木 隆雄; 吉田 英世; 金 憲経; 湯川 晴美; 渡辺 修一郎; 熊谷 修; 吉田 祐子; 天野 秀紀; 藤原 佳典; 新開 省二; 石崎 達郎; 柴田 博 Journal of epidemiology 12 (1) 55 -55 2002年01月
- 石崎 達郎; 今中 雄一 治療 83 (10) 2826 -2830 2001年10月
- 新開 省二; 渡辺 修一郎; 熊谷 修; 吉田 祐子; 藤原 佳典; 吉田 英世; 石崎 達郎; 湯川 晴美; 金 慶経; 鈴木 隆雄; 天野 秀紀; 柴田 博 日本公衆衛生雑誌 48 (9) 741 -752 2001年09月
- 石崎 達郎; 渡辺 修一郎; 鈴木 隆雄; 吉田 英世; 柴田 博; 安村 誠司; 新野 直明 日本老年医学会雑誌 37 (7) 548 -553 2000年07月
- 鈴木 隆雄; 湯川 晴美; 吉田 英世; 石崎 達郎; 金 憲経; 渡辺 修一郎; 熊谷 修; 新開 省二; 天野 秀紀; 柴田 博 日本老年医学会雑誌 37 (1) 41 -48 2000年01月
- SHINKAI Shoji; WATANABE sHUICHIRO; KUMAGAI Shu; ISHIZAKI Tatsuro; SUZUKI Takao Journal of physiological anthropology and applied human science 19 (5) 239 -239 2000年
- Evaluation of psychological effects due to bed rest.Yuko Ishizaki Y; Hideoki Fukuoka; Tatsuro Ishizaki; Taisaki Katsura; Chang-Sun Kim; Yuko Maekawa; Masayo Fujita Journal of Gravitational Physiology 7 P183 -P184 2000年
- Tatsuro Ishizaki; Yasuki Kobayashi; Ichiro Kai Journal of Epidemiology 10 (4) 249 -254 2000年
- 石崎 達郎; 甲斐 一郎; 小林 廉毅 厚生の指標 46 (4) 23 -27 1999年04月
- 石崎 達郎; 今中 雄一; 岡本 章寛; 奥山 尚; 釜野 安昭; 木内 貴弘; 後藤 敏; 谷川 武; 中山 健夫; 本荘 哲; 水嶋 春朔; 村上 典子 イガク キョウイク 29 (6) 399 -406 1998年
- 石崎 達郎; 矢野 栄二 産業衛生学雑誌 = Journal of occupational health 37 S517 1995年03月
- Tatsuro Ishizaki; Ichiro Kai; Mitsuru Hisata; Yasuki Kobayashi; Ken‐ichi Wakatsuki; Gen Ohi Journal of the American Geriatrics Society 43 (6) 623 -626 1995年
- 石崎 達郎 日本公衆衛生雑誌 39 (2) p65 -74 1992年02月
- 石崎達郎 医学のあゆみ 162 (2) 167 -168 1992年
- I. Kai; G. Ohi; Y. Kobayashi; T. Ishizaki; M. Hisata; M. Kiuchi Asia-Pacific journal of public health / Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health 5 221 -227 1991年01月
共同研究・競争的資金等の研究課題
- 加齢に対する信念の構造と加齢プロセスに与える影響の検証日本学術振興会:科学研究費助成事業 基盤研究(A)研究期間 : 2022年04月 -2027年03月代表者 : 権藤 恭之; 石崎 達郎; 石松 一真; 石岡 良子; 西田 裕紀子; 神出 計; 片桐 恵子
- 生活困窮者の健康・自立支援のためのビッグデータ基盤整備:健康格差是正をめざして日本学術振興会:科学研究費助成事業 基盤研究(B)研究期間 : 2020年04月 -2024年03月代表者 : 高橋 由光; 光武 誠吾; 石崎 達郎; 後藤 禎人; 加藤 源太; 中山 健夫
- 高齢者における多剤処方の健康影響評価と服薬指導プログラムの研究開発日本学術振興会:科学研究費助成事業 基盤研究(B)研究期間 : 2020年04月 -2024年03月代表者 : 石崎 達郎; 増井 幸恵; 高橋 由光; 浜田 将太【研究1】地域在住高齢者における多剤処方の健康影響の評価: ①レセプトデータの分析~北海道後期高齢者医療広域連合のレセプトデータから75歳以上の補保険者を対象に、外来医療において処方された薬剤種類数を把握し、処方薬剤数とその後の健康アウトカム(新規の要介護認定、死亡)との関連を分析した。その結果、薬剤数が多いと要介護認定や死亡の発生リスクが高くなっていることが明らかとなった。 ②コホート研究データを用いた分析~当研究所が大阪大学らと共同で2010年から実施している長期縦断研究「SONIC研究」のデータを使用して、服用中の薬剤種類数と3年後の歩行速度や握力の変化との関連を分析した。調査参加者のうち70歳群と80歳群(合計1544人、70歳群が全体の47.5%)を分析対象者とした。薬剤種類数は内服薬に限定し調査対象者が持参したお薬手帳や薬剤情報提供書から情報を収集した。その結果、薬剤種類数は3年後の握力低下や歩行速度低下と有意に関連しており、カットオフ値は5種類以上と計算されたが予測能は低かった(ROC曲線下面積は0.55前後)。 【研究2】自治体が実施する服薬指導プログラムの実態把握: 国民健康保険や後期高齢者医療制度の保健事業として服薬指導を実施した区市町村の担当者を対象にヒアリング調査を計画したが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、調査は実施できなかった。服薬指導事業の内容を検討しており、事業の計画準備、服薬指導対象者の選定と呼びかけ方法、参加者数、服薬指導の手続・内容・評価方法、投入した人的資源・費用等)である。
- 医療・介護ビッグデータを用いた再入院発生予測モデルの開発と再入院予防策への提案日本学術振興会:科学研究費助成事業 基盤研究(B)研究期間 : 2020年04月 -2024年03月代表者 : 光武 誠吾; 土屋 瑠見子; 石崎 達郎
- ケアのサイエンスを実現する介護とテクノロジー融合が福祉のトラストに与える影響日本学術振興会:科学研究費助成事業 基盤研究(B)研究期間 : 2019年07月 -2022年03月代表者 : 涌井 智子; 渡辺 健太郎; 池内 朋子; 三輪 洋靖; 伊藤 沙紀子; 木下 衆; 甲斐 一郎; 石崎 達郎本研究が対象とする課題は、情報社会における介護現場にテクノロジーをいかに導入するか、およびテクノロジーの導入により介護がいかに変わるかを明らかにし、技術や介護情報、テクノロジーを導入することによって福祉そのものに対する人々の信頼をいかに維持・醸成するか?という問いである。 本年度は、地域在住の中高年(40~89歳まで)約4700名を対象に、介護におけるテクノロジー導入に対する意識調査を実施した。この調査データの解析により、現在の中高年が高齢期に希望する介護におけるテクノロジー導入状況が明らかになったとともに、介護におけるテクノロジー導入希望に対する関連要因には性差があることや、学歴などが関連することが明らかとなっている。一方、高齢者の身体・認知機能によって、テクノロジー導入に対する認識がいかに変わるを明らかにした解析からは、身体・認知機能の依存度が高くなるほど、テクノロジー導入を受容する一方で、家族の介護経験者の方が、テクノロジー導入に対する受容度が高いことが明らかになった。 わが国の介護を支えるシステムは、経済的・資源的に極めて緊迫な課題を抱えており、介護とテクノロジー融合が介護システムの持続性に必然とされている。介護施設における導入だけでなく、地域在住の一人暮らし等高齢者におけるテクノロジー導入の可能性について、今後の調査・解析によって検討をしていく予定である。
- 学際的アプローチによるポリファーマシー発生機序の探求日本学術振興会:科学研究費助成事業 挑戦的研究(萌芽)研究期間 : 2019年06月 -2022年03月代表者 : 石崎 達郎; 吉田 祐子高齢者の多くは複数の慢性疾患を抱え、ポリファーマシーとなりやすく、ポリファーマシーは高齢社会における健康政策上の重要課題である。ポリファーマシー発生には医学的要因のみならず、心理・行動科学的要因、医療制度的要因等々、多くの要因が寄与していると考えられる。本研究は、①ポリファーマシーの危険因子に関するシステマティックレビュー、②地域在住高齢者を対象とする学際的研究データを用いたポリファーマシー危険因子の分析を実施することで、ポリファーマシーの発生機序を学際的アプローチによって探求することを目的とする。 【研究1】ポリファーマシー危険因子に関するシステマティックレビューの実施 患者側の医学的要因(疾患、要介護状態の有無等)、患者・家族の心理学・行動科学的要因、居住地域における医療資源等の環境要因、処方医師の要因、調剤薬局・薬剤師の要因、医療経済学・医療制度・公衆衛生行政の要因、チーム医療・多職種連携の要因など学際的観点からPubMedを使って文献を検索し、システマティックレビューの対象論文をスクリーニングした。 【研究2】学際的高齢者長期縦断研究データを用いたポリファーマシー危険因子の分析 2010年から取り組んでいる地域在住高齢者を対象とする長期縦断研究「SONIC研究」で得られたデータを使って、ポリファーマシー状態にある者を把握し、その危険因子として性格特性に注目し、男女別に分析した。ポリファーマシーであった者は男性24%、女性27%で、多剤処方に関連していた性格特性は、男性は神経症傾向が高いこと、女性では外向性が低いことであった。
- 年齢と余命に関連する2つの過程が高齢者の幸福感に与える影響の長期縦断的検証日本学術振興会:科学研究費助成事業 基盤研究(B)研究期間 : 2017年04月 -2022年03月代表者 : 権藤 恭之; 石崎 達郎本研究の目的は、SONIC研究参加者に対して追跡調査を行い、感情の経時的変化に関する縦断的検討を行うことである。SONIC研究ではNarrow range age design に準拠した年齢幅が3歳の3年齢群(70歳、80歳、90歳)を関東・関西の都市部と田園地域において悉皆で対象者を抽出し参加を呼びかけ、公民館等を利用した招待型調査を実施してきた。 本年度は、70歳群の第4波調査を行うとともに、調査が早期に終了したため、データ整理をすすめた。また、これまで把握することができなかった、縦断調査からドロップアウトした参加者に関する情報を再収集した。これらのデータを整備すると共に、引き続き、国際共同研究を推進するためのデータセットの英語化を進めた。研究成果としてはIADLが抑うつ傾向に与える影響が年齢によって異なることを確認した。また、慢性疾患が認知機能に与える影響も同様に年齢によって異なることを確認した。この現象は異なる年齢群では生のプロセスと死のプロセスの比重が異なることによって生じると推察できる。したがった、両プロセスのバランスで高齢期のポジティブ感情およびネガティブ感情が決定するという本研究の中核的仮説を部分的に支持するものだといえた。また、活動の指標である余暇活動が認知機能と運動機能に対して影響することと、また認知機能と運動機能の間には両方に影響を与えあうことが明らかになった。また、精神的健康は両者の関係から独立していることが示された。この結果は70歳高齢者での結果なので、80歳、90歳においてこれらの関係がどのように変化するかを検討することで、生のプロセスが低下し、死のプロセスが上昇した時の影響を検証するための基礎的にモデルができた。
- 職域レセプト分析:受診行動による生活習慣病の早期発見および重症化予防への効果日本学術振興会:科学研究費助成事業 基盤研究(C)研究期間 : 2016年04月 -2022年03月代表者 : 志摩 梓; 辰巳 友佳子; 石崎 達郎; 呉代 華容; 宮松 直美本申請課題は、職域コホートの健診データとレセプトデータを継続的に突合し、①循環器疾患のリスク因子と受療状況、疾病コントロール等の関連、②がん検診および精検受診率とがん発症との関連等を検討すること、を目的としている。 2020年度は、循環器疾患については、1) 2017年健診時にII度以上の高血圧者273人を対象として実施した、医療機関への紹介状を発行する保健介入の追跡検討を行った。その結果、紹介状発行により外来受診開始が増加するだけでなく、1年後のIII度高血圧者が従来の約半数となることを公表した(OR: 0.42、95%CI: 0.19-0.90)。2) 家庭血圧測定状況の検討を進め、降圧薬服用者に限った分析において、家庭血圧測定習慣がある者は約25%であること、男女ともに他の生活習慣病治療があることが、女性では血圧管理不良と、不健康な生活習慣であることが、測定習慣なしと関連することを公表した。3) 糖尿病コントロールについて、9年間の78536件(14556人)の健診データから、101件(61人)の血糖パニック値(HbA1c: 11.0%以上、または随時血糖: 400mg/dL以上、または空腹時血糖: 300mg/dL以上)を抽出・分析し、健診直後における個別の受診勧奨により一旦は全員が医療機関を受診するものの、翌年健診時に治療継続が確認できた者は約8割で、治療継続者でも約6割でHbA1cが8%以上であることを公表した。 がん検診については、大腸がん検診(便潜血反応検査)の受診、精密検査受療状況等のデータ整理を進めたが、大腸がん罹患との関連等の検討は、後述のとおり2021年度に行うことにした。
- 日本学術振興会:科学研究費助成事業 挑戦的萌芽研究研究期間 : 2016年04月 -2020年03月代表者 : 高橋 由光; 中山 健夫; 石崎 達郎; 後藤 禎人生活習慣病3疾患(糖尿病、高血圧症、脂質異常症)を中心に、多疾患の有病割合の実態把握を行うことを目的とした。自記式調査として、国民生活基礎調査を用いて、レセプトデータとして、公的医療保険加入者についてはレセプト情報・特定健診等情報(National Database:NDB)を、生活保護受給者については医療扶助実態調査を用いて分析を行った。併存疾患として、高血圧症・脂質異常症が最も多く(5%)、高血圧症・眼の病気(4%)、高血圧症・糖尿病(4%)であった。公的医療保険加入者に比べ、生活保護受給者の3疾患の有病割合は高かった。低い社会経済状況や慢性疾患の罹患ががん検診の受診とも関連していた。
- 日本学術振興会:科学研究費助成事業 基盤研究(B)研究期間 : 2015年07月 -2018年03月代表者 : 新井 康通; 石崎 達郎; 権藤 恭之; 神出 計; 湯浅 慎介; 中岡 博史; 池邉 一典; 井ノ上 逸郎本研究は、超百寿者由来のiPS細胞を血管内皮細胞に分化させ、酸化ストレスや低酸素ストレス耐性の分子機構を解明し、得られた分子生化学的、遺伝学的成果を、多年代高齢者コホートを用いて疫学的検証を行うことを目的とした異分野連携プロジェクトである。症例数の不足のため、iPS細胞実験から、ターゲット分子を同定するには至らなかったため、心血管防御因子であるExtracellular superoxide dismutase を目的変数としたQTL解析を行い、候補遺伝子(rs1799895)を同定した。その結果をSONIC研究対象者1890名で解析し、頸動脈硬化などの老化形質を関連することを見出した。
- 日本学術振興会:科学研究費助成事業 基盤研究(C)研究期間 : 2015年04月 -2018年03月代表者 : 増井 幸恵; 権藤 恭之; 石崎 達郎; 新井 康通; 池邉 一典; 稲垣 宏樹; 神出 計; 中川 威本研究の目的は、高齢期のネガティブライフイベント経験時の老年的超越の役割について検討することであった。70歳代、80歳代の高齢者を対象に6年間で3回の追跡調査を行った。その結果、①「配偶者との死別」や「介護経験」の経験により老年的超越の発達が促進されること、②「家族の大きな病気」の経験時に生じる精神的健康の低下に対して経験以前の老年的超越は防御効果があること、が示された。しかし、老年的超越を向上させるイベントは限られており、老年的超越の防御的効果が確認されたイベントも限られていた。今後は、老年的超越が効果を示すネガティブライフベントについて焦点をあて、さらに詳細に調べていく必要がある。
- 日本学術振興会:科学研究費助成事業 基盤研究(C)研究期間 : 2015年04月 -2018年03月代表者 : 神出 計; 樂木 宏実; 権藤 恭之; 池邉 一典; 石崎 達郎; 新井 康通; 増井 幸恵; 樺山 舞; 杉本 研; 山本 浩一; 小黒 亮輔高齢者長期縦断疫学(SONIC)研究における、70,80,90歳の対象者における認知機能障害やフレイルなど老年症候群をアウトカムにすることで健康寿命延伸のための各年代の高血圧治療管理基準を明らかにすることを目的とした。解析の結果、70歳ではSBPが高いほどに、90歳ではSBPが低いほどに認知機能が低下していた。SBPが低い程認知機能が高くなる傾向は、降圧薬服用をしていない非フレイル群のみにしか認められず、降圧薬を服用しているフレイル群においてはDBPが低い程に有意に認知機能が低くなる傾向が認められた。超高齢者およびフレイル者での過降圧は認知機能の低下をもたらす可能性が示唆された。
- 日本学術振興会:科学研究費助成事業 基盤研究(C)研究期間 : 2015年04月 -2018年03月代表者 : 石崎 達郎; 高橋 由光高齢患者は複数の慢性疾患(多病)を抱える者が多く、本研究では東京都の75歳以上の高齢者を対象に、3疾患の併存頻度を同定した。国内外において、各種疾患の診療ガイドラインが作成されているが、そのほとんどは対象疾患に関する診療が中心であり、併存疾患を考慮した診療ガイドラインは少なかった。多剤処方・薬剤有害事象の発生、断片化した非効率な診療等を防ぐためにも、併存疾患を考慮する診療ガイドラインが必要である。多病を抱える高齢患者の疾病管理として、身体機能、認知機能、社会的側面を評価する総合的高齢者評価の実施と、患者の意向を重視する患者中心医療が必要である。
- 日本学術振興会:科学研究費助成事業 基盤研究(C)研究期間 : 2014年04月 -2018年03月代表者 : 杉原 毅彦; 南木 敏宏; 針谷 正祥; 石崎 達郎; 石神 昭人; 田中 雅嗣寛解あるいは低疾患活動性を目標に治療強化を行うことが関節リウマチ(RA)の関節破壊進行を抑制し身体機能と予後を改善させる。今回の研究で、高齢者においても低疾患活動性を目標とした治療で疾患活動性は制御され身体機能が改善することが示された。また、関節破壊進行を進行しやすい高齢RAの臨床像か明らかとなり、治療中に発現する合併症が長期的な身体機能に影響することが示された。治療選択の指標となることが期待された末梢血のPAD4の有用性は確認できなかった。RA発症に関連する新規疾患感受性遺伝子を同定したが、治療選択の指標としては有用でなかった。今後、治療と関連するゲノム情報を指標とした治療戦略を確立したい。
- 日本学術振興会:科学研究費助成事業 基盤研究(B)研究期間 : 2014年07月 -2017年03月代表者 : 権藤 恭之; 新井 康通; 石崎 達郎; 池邉 一典; 神出 計; 片桐 恵子; 増井 幸恵; 中川 威; 稲垣 宏樹; 上田 博司本研究は、高齢者を対象とした長期縦断研究のデータに基づいて、超高齢社会に相応しいサクセスフルエイジングモデルを構築する事であった。SONIC長期縦断調査のデータを対象にいくつかのサクセスフルエイジングモデルを検証した。その結果、機能レベルからサクセスフルエイジング達成者を分類すると、達成率は70歳、80歳、90歳でそれぞれ17%、4%、0%となった。一方、幸福感を見ると高い年齢群の方が高くなっていた。3年間の縦断データの分析においても、何れの年齢群も機能レベルは低下するにも関わらず、幸福感の上昇が観察され、機能レベルと心理レベルのサクセスフルエイジグがかい離することが確認された。
- 日本学術振興会:科学研究費助成事業 基盤研究(C)研究期間 : 2013年04月 -2017年03月代表者 : 志摩 梓; 岡村 智教; 石崎 達郎; 宮松 直美; 呉代 華容職域コホートにおいて、①循環器疾患リスク因子とその後の医療費の関連、②外来受診状況と循環器疾患リスク因子改善の関連を検討した。 本対象集団では、血圧水準が高いほどその後の外来医療費が高額であった。しかしながら、stage2高血圧者の外来医療費増加分も年間数万円に留まり、降圧治療は不十分である可能性が示唆された。そこで、高血圧者における外来受診頻度と9年後の目標血圧未達成の関連を検討したところ、月1回程度外来受診群に比べ、殆ど外来を受診しない群ではコントロール不良者が約3倍であることが示された。糖尿病についても、外来受診と1年後健診で評価したHbA1c低下者割合に正の関連が示された。
- 日本学術振興会:科学研究費助成事業 基盤研究(A)研究期間 : 2012年04月 -2015年03月代表者 : 田宮 菜奈子; 野口 晴子; 松井 邦彦; 宮石 智; 山崎 健太郎; 山本 秀樹; 斉藤 環; 阿部 智一; 武田 文; 高橋 秀人; 柏木 聖代; 泉田 信行; 松本 吉央; 柴山 大賀; 山海 知子; 阿部 吉樹; 麻生 英樹; 菊池 潤; 森山 葉子; 山岡 祐衣; 伊藤 智子; 小林 洋子; 佐藤 幹也; 石崎 達郎; 涌井 智子; 陳 礼美; 門間 貴史; 杉山 雄大本研究は、医療・介護・福祉に関わる現場と大学を両輪としたPDCAサイクルを実現することを目的として、医療福祉現場と協同でつくば市医療福祉事例検討会を進行し、問題点の集約分析や、つくば市ニーズ調査の分析を市にフィードバックすることで、現場との協同を図ってきた。また、これからのミクロレベルで成果の一般化展開も含めて、全国介護給付費データや国民生活基礎調査のビッグデータを含む種々のデータ分析により学術的研究を行い、医療と介護の連携はどうしたら進むのか、要介護者・障害児者およびその介護者にどのような支援が必要か、介護保険サービス利用の実態等を明らかにすることで、地域包括ケア推進方策を検討した。
- 日本学術振興会:科学研究費助成事業 基盤研究(B)研究期間 : 2012年04月 -2015年03月代表者 : 高橋 龍太郎; 会田 薫子; 鶴若 麻理; 島田 千穂; 石崎 達郎; 清水 哲郎高齢者の希望を医療選択に生かす取り組みが注目されている。本研究の調査で、終末期医療の希望について家族や友人との会話がある人は4割、記録がある人は1割であり、両方ない人は半数であった。そこで、研究者らは、終末期の生活について考え、事前の選択を書き残すツール「ライフデザインノート」を用いた実践的介入研究を実施した。地域診療所通院患者114名にノートを配布したが、終末期医療の希望記述者は半数程度であった。記述に伴う心理社会的要因を、インタビュー調査によって分析したところ、家族への配慮が特徴的であった。事前の希望を明示することは困難であり、記述には家族との関係性のあり方が反映される可能性が考えられた。
- 日本学術振興会:科学研究費助成事業 基盤研究(C)研究期間 : 2012年04月 -2015年03月代表者 : 石崎 達郎; 高橋 龍太郎共同研究を行っている自治体から介護保険・医療保険レセプトデータの提供を受け、データベースを構築し、要介護サービスを利用している高齢者を対象に、ひと月ごとの療養場所(自宅、病院、施設)とその移動、1年間における要介護度別入院回数を把握した。療養場所の移動前後の時期におけるケアの質の維持・向上への対応について、国内外の取り組みについて情報を収集した。これら研究成果を活用し、在宅医療と入院医療をつなぐための電子カルテフォーマットを作成し試用した。
- 日本学術振興会:科学研究費助成事業 基盤研究(A)研究期間 : 2011年04月 -2015年03月代表者 : 秋山 弘子; 小林 江里香; 直井 道子; 杉原 陽子; 杉澤 秀博; 菅原 育子; 木村 好美; 山田 篤裕; 深谷 太郎; 新開 省二; 石崎 達郎; 村山 洋史; リヤン ジャーシー1987~2012年に実施された全国高齢者の追跡調査(計8回)と、戦後生まれを含む新しい高齢者パネルの初回調査データの縦断的分析や複数時点の横断的分析を行った。 家族以外のネットワーク、喫煙本数、BMI、運動習慣、移動能力は、加齢に伴い、必ずしも直線的ではないが減少しており、一部の平均値や変化量には出生コホートによる差がみられた。コホートや調査年による差は男女で異なり、男性のみで社会的孤立化が進んでいた。また、女性では、子どもとの同居が生活満足度(LS)を高める効果が弱くなる一方、友人との接触とLSとの正の関連は強くなるなど、主観的幸福感の関連要因にもコホートや調査年による差異が示された。
- 日本学術振興会:科学研究費助成事業 挑戦的萌芽研究研究期間 : 2012年04月 -2014年03月代表者 : 菊地 和則; 石崎 達郎; 伊東 美緒養護者による高齢者虐待への対応においては、高齢者への医療や認知症ケアが必要とされるだけでなく、養護者への医療も必要になるなど医療機関との連携は欠かせない。しかし、医療機関の高齢者虐待対応への協力は十分とは言えない。 医療機関の虐待対応への協力を促進するため、東京都内の医療機関など関係機関を対象とした郵送調査を行った。その結果、医療機関が虐待対応に協力するためには「高齢者の医療費支払いの確保」、「養護者の脅し・暴力当があった場合の支援」、「医療同意を行う家族・親族の確保」、「区市町村判断による医療機関一時保護制度の創設」、「成年後見人の専任」などが必要とされていることが明らかとなった。
- 日本学術振興会:科学研究費助成事業 挑戦的萌芽研究研究期間 : 2011年 -2013年代表者 : 宮崎 貴久子; 中山 健夫; 石崎 達夫; 仙石 多美; 上田 佳代; 太田 はるか; ネフ 由紀子; 日向 美羽日本人死亡原因の約三分の一ががんによる。がん緩和ケア研究推進を目指し、必要とされる緩和ケア研究の現状と課題を検討した。1)わが国の緩和ケア研究の現状を把握するために、日本から海外に向けて発表された英文論文の記述内容分析を実施した。エビデンスレベルが高い研究の少なさが示唆された。2)大規模レセプトデータから、医療用麻薬の使用状況と、エビデンスと臨床のギャップを検討した。3)これらの調査結果をもとに、緩和ケア臨床の医師たちが、どのような研究(エビデンス)を必要としているのか、インタビュー調査を実施した。内容分析から7カテゴリーが抽出された。臨床家たちへの研究実施に向けた支援の必要性が示唆された。
- 日本学術振興会:科学研究費助成事業 基盤研究(B)研究期間 : 2009年 -2012年代表者 : 権藤 恭之; 高橋 龍太郎; 増井 幸恵; 石崎 達郎; 呉田 陽一; 高山 緑本研究は、高齢期におけるサクセスフルエイジングを達成するためのモデルが加齢に伴って、機能維持方略から論理的心理的適応方略、そして非論理的超越方略へと移行するという仮説に基づき実証研究を行ったものである。70 歳、80 歳、90 歳の地域在住の高齢者 2245 名を対象に会場招待調査を実施しそれぞれ関連する指標を収集した。その結果、高い年齢群ほど身体機能、認知機能の低下が顕著である一方で、非論理的適応方略の指標である老年的超越の得点は上昇しており、高い年齢になるほどサクセスフルエイジング達成のために非論理的適応方略が有効であることが示唆された。
- 日本学術振興会:科学研究費助成事業 挑戦的萌芽研究研究期間 : 2010年 -2011年代表者 : 中山 健夫; 石崎 達郎; 東 尚久; 野田 光彦; 宮崎 貴久子; 佐藤 敏彦; 池田 俊也; 鈴木 博道近年、各領域で診療ガイドラインが整備されつつあるが、その推奨は臨床の場で必ずしも実施されていない。また添付文書に記載された安全性情報の遵守程度も明らかではない。これらは「エビデンス・診療ギャップ」として医療の質を考える際の大きな課題となっている。本課題はレセプト・データベースを用いて、ステロイド性骨粗鬆症ガイドラインの推奨実施状況と、心弁膜症リスクが指摘され添付文書が改訂された麦角系ドパミンアゴニスト使用者での心エコー実施割合を明らかにし、レセプト・データベースの有用性を証明した。
- Health care needs and resource use among older individuals under the public long-term care insurance system研究期間 : 2009年 -2011年
- 日本学術振興会:科学研究費助成事業 基盤研究(C)研究期間 : 2009年 -2011年代表者 : 石崎 達郎; 高橋 龍太郎本研究は、介護保険施設サービス利用者として老人保健施設の入所者を取り上げ、入所中に提供された医療サービスの内容・種類、薬剤費用を把握することで、介護保険サービス利用者における医療サービスニーズを把握することを目的とする。調査の結果、最も施行されていた血液検査は栄養評価のための血清アルブミン値測定であった。画像診断は、胸部単純X線撮影が最も多く、胸部・腹部CT撮影も施行されていた。一人一日あたりの薬剤費は、10円未満から4000円弱まで、大きくばらついていた。介護保険制度は、入所中に発生した重篤な急性疾患の管理に対する介護報酬を設定しているが、慢性疾患管理としての投薬、検査、処置等は償還されない。医療ニーズの高い要介護高齢者であっても、介護保険施設を利用しやすいような介護報酬体制の設計が望まれる。
- 日本学術振興会:科学研究費助成事業 基盤研究(C)研究期間 : 2008年 -2010年代表者 : 関本 美穂; 今中 雄一; 石崎 達郎; 林田 賢史本研究は、以下の3つのトピックスにおいて、診療体制(人員配置やマンパワー)や診療マネジメントシステム)が、診療プロセスや患者アウトカムに与える影響を検討した。1)脳梗塞の急性期診療、2)集中治療室(ICU)の診療体制、3)輸血管理。これらの研究の結果から、臨床的な因子以外に、診療体制や診療マネジメントシステムが、診療プロセスがや患者アウトカムと関連することが確認された。
- 日本学術振興会:科学研究費助成事業 基盤研究(A)研究期間 : 2007年 -2009年代表者 : 今中 雄一; 関本 美穂; 林田 賢史; 猪飼 宏; 石崎 達郎; 徳永 淳也; 徳永 淳也全国から多施設病院より協力を得、診療領域毎・施設毎に診療パフォーマンスとコストを可視化し、影響要因を明らかにし、医療の向上に役立つ礎を築いた。 地域レベルで健康・要介護状態と医療・介護の資源の分布、アクセス、推移、および医療・ケアへの需要と供給のギャップや機能分担の可視化と時間縦断的・横断的な分析を進めた。これらにより医療保健介護の地域システムの体系的な評価方法を進展させた。
- 日本学術振興会:科学研究費助成事業 基盤研究(C)研究期間 : 2006年 -2008年代表者 : 石崎 達郎; 今中 雄一; 関本 美穂本研究は、高齢者の医療・介護資源の消費状況を検討することを目的とする。某県の医療費と介護費の内訳を市町村別に比較した結果、入院医療費が低額の自治体では施設介護費が高額である傾向が認められた。次に、某市の5年間の介護給付費を分析した結果、サービス利用状況は極めて不均等であることが明らかとなった。最後に、某医療機関で入院医療を受けた患者の最終退院から1年前までの累積入院医療費を分析したところ、生存退院患者よりも死亡退院患者は累積医療費が高額で、死亡退院患者では高齢になるほど医療費が低額であることが明らかとなった。
- レセプトデータを活用した薬剤処方クオリティ・インディケータ開発と診療改善への応用日本学術振興会:科学研究費助成事業 基盤研究(C)研究期間 : 2006年 -2007年代表者 : 関本 美穂; 今中 雄一; 石崎 達郎; 林田 賢史本研究はDPCデータやレセプトデータを活用して薬剤使用の適切性を評価しようとする比較的新しい試みである。研究のトピックスとして、脳梗塞急性期の薬物療法と血液製剤を選んだ。 脳梗塞急性期の薬物療法に関する研究では、DPCデータから患者毎の薬剤の使用量・使用日数の情報を抽出し、各薬剤の使用状況を病院間で比較した。病院を入院直後3日間の医療費の分布により3群(高額・中間・低額群)に分類し、3群間で薬剤の使用状況を比較した。脳梗塞急性期診療における高額医療は主に集中治療の利用によるものであり、薬物使用とは関連が見られなかった。また薬物使用は、患者アウトカムとも関連がなかった。 また血液製剤では、DPCデータを基にして血液製剤が使用された症例を同定するとともに、研究協力病院にて血液製剤の使用状況の調査と使用適切性の評価を実施した。DPCデータを利用して、血液製剤が投与された症例(赤血球製剤573例・濃厚血小板167例・新鮮凍結血漿121例・アルブミン製剤244例)を同定した。これらの症例の診療録をレビューし、われわれが開発したアルゴリズムを基にして、血液製剤の使用適切性を評価した。調査の結果、明らかな使用の適応があった症例の割合は赤血球製剤で70%、新鮮凍結血漿で15%、濃厚血小板で56%、アルブミン製剤で30%であった。血液製剤が使用される主な臨床状況は、赤血球製剤が急性出血・慢性貧血・周術期の輸血、新鮮凍結血漿が出血症状・心臓手術・出血に対する予防的投与、濃厚血小板が心臓手術・血液疾患・重症患者、アルブミン製剤が出血性ショック・心臓手術・肝硬変などであった。 またDPCデータを利用して、診断群分類を利用して血液製剤使用量の実測値と予測値の比(O/E値)を病院毎・診療科毎に計算した。診断群分類で調整した血液製剤の使用量には病院間で大きなバラツキが観察されたが、O/E値と不適切使用の頻度は必ずしも合致しなかった。
- アクシデントによって発生する損失医療費およびエラー指標算出の試みに関する研究日本学術振興会:科学研究費助成事業 萌芽研究研究期間 : 2005年 -2006年代表者 : 竹村 匡正; 吉原 博幸; 今中 雄一; 石崎 達郎本研究では、医療の質を定量的に測定するという観点から、インシデント・アクシデントレポートの情報及び医事情報を用いて新しいエラー指標の算出を行った。具体的には、医療事故に起因する診療行為の自動抽出を目的とし、それらの診療行為点数をエラー指標とした。本指標は、事故が経済的にどのような影響を与えているのかを示すと同時に、病院経営的には病院の抱えるリスクを示す指標となりうるものである。自動抽出の方法論としては、1.導入が進みつつあるDPC(Diagnostic Procedure Combination)の情報を利用して、標準化された同一疾患の患者情報を用いた。具体的には、患者の診療行為とは、(同一疾患に基づく診療行為)+(その患者特有の診療行為)+(医療事故に基づく診療行為)と捉え、診療プロセスに基づいて特に事故後に特異に発生した診療行為を事故に起因する診療行為候補として抽出することとした。次に、2.インシデント・アクシデントレポートの自動分析を行い、事故に起因する診療行為候補を自動的に検証することとした。具体的には、機械学習の方法を用いて、インシデントレポートの記述を、「患者プロフィール」、「事故発生・発見プロセス」、「事故対応」、「潜在理由」、に分類して、実際のインシデントレポートの各「文」が、どの項目を記述しているのかというタグを人の手で付与し、機械学習させた。結果、京都大学医学部附属病院で収集されたインシデント・アクシデントレポートに基づく医事情報も含めた患者情報について、本方法論を適応した結果、「転倒・転落」に分類された事例に対して、リスクマネージャが判断する事故に基づく診療行為を高い精度で抽出することが出来た。しかし、レポートの記述が標準化されていないことが人手でも事故の状況を把握できないことが逆に判明し、本方法論はレポート記述の自動評価の可能性があることが示唆された。
- 医療のコスト・パフォーマンスの実測・多施設比較と要因分析・改善策日本学術振興会:科学研究費助成事業 基盤研究(A)研究期間 : 2004年 -2006年代表者 : 今中 雄一; 石崎 達郎; 関本 美穂; 林田 賢史; 徳永 淳也; 廣瀬 昌博多施設データベースの構築を進めながら医療の質・効率性の改善の資する科学的評価手法の研究開発を以下のごとく行った。 【医療のコスト分析】多施設の悉皆的な症例からなるデータベースに基づき、医療費・医療資源関連指標を算出し、その関連要因を分析し、医療費増のリスクの調整方法を開発した。診療パターンの向上に活用するべく、より妥当な施設間比較を行い、ばらつきの要因を分析した。さらに、国内外の過去の研究においても明らかにされてこなかった安全管理および感染制御のための組織維持のコストは、国際的にも定量的に把握されておらず、人、もの、機器・設備のコスト、その他様々な経費を把握するための系統的なフレームワークを研究開発し構築し、コストを計測して関連要因を分析した。 【医療の質・パフォーマンス分析】多施設データに基づき、多領域の疾患において、で、リスク調整のモデル化を進展させながら、良好アウトカム率や死亡率、在院日数、術前・術後在院日数などについて施設間差異とその要因の分析を行った。経年的データを用い、特定の疾患による死亡率、特定の診療フェーズにおける抗生剤の使用、診療領域ごとの輸血・血液製剤の使用などの適正化のプロセスを示すことができた。 【医療のコスト・パフォーマンスと経営組織体の評価】診療行為のコストとパフォーマンスを統合的に評価し、経営戦略の理論的枠組みをふまえ各種の量的・質的なデータ・情報を収集・整理・分析し、医療の経営・運営システムの改善と持続に資する体系の構築を進めた。その中で、組織運営上重要な組織文化の構造や提供者側からの評価の構造を体系化して実測し要因分析と構造分析を行った。
- 高齢患者における医療資源の消費に関する研究日本学術振興会:科学研究費助成事業 基盤研究(C)研究期間 : 2003年 -2005年代表者 : 石崎 達郎; 今中 雄一医療費の増加要因には人口の高齢化や医療技術の高度化などの他、長期入院や薬剤・検査の過剰使用も増加要因として指摘されている。本研究は、1)厚生労働省「社会医療診療行為別調査」を用い、年齢階級に診療行為(検査や投薬等)実施の違いを比較する(マクロ分析)とともに、2)入院医療を受けた患者一人一人の個別の入院診療データを用いて、性・年齢階級・疾患群別に医療資源の消費状況を示し(ミクロ分析)、3)高齢者と非高齢者との間で医療資源消費に違いがあるのかどうか検討することを目的とするものである。 厚生労働省「社会医療診療行為別調査」を用いて、年齢階級・疾患群別に診療行為(検査や投薬等)実施の違いを比較した。その結果、高齢患者ほど検査・薬剤医療費が高額になるという知見は得られなかった。疾患別の比較では、総医療費では40歳以降から増加傾向にあるものや60歳以降から増加しはじめるもの等、疾患によってパターンは異なっていた。 次に患者の個別入院診療データを用いて、性・年齢階級・疾患群・退院時転帰別に、高齢者と非高齢者との間で医療資源消費を比較検討した。その結果、70歳以上の高齢患者よりも、40〜69歳の群で医療費が高くなっており、「高齢患者は非高齢患者よりも検査や投薬が多く医療費が高い」という結果は得られなかった。特に死亡退院患者群では、年齢階級が上がるにつれ医療費が少なくなる傾向にあった。疾患群別の検討では、損傷外因の場合のみ、年齢階級が上がるにつれて医療費総額が有意に高額になっていた。消化器系、尿路生殖器系、呼吸器系の生存退院患者群では、60歳代でピークに達し、その後は有意に減少していた。 以上の結果から、マクロ分析・ミクロ分析ともに、年齢と医療費との間に直線的な相関関係は認められなかった。医療費を年齢階級間で比較する場合には、階級間の疾病構造の違いを考慮する心要がある。
- 活動基準原価計算を活用した時間縦断的・多軸的な患者別原価測定方法の開発研究-妥当な施設間比較と政策応用に向けて-日本学術振興会:科学研究費助成事業 萌芽研究研究期間 : 2003年 -2004年代表者 : 今中 雄一; 石崎 達郎; 廣瀬 昌博本研究では、活動基準原価計算のフレームをも活用してより正確に原価計算を行うしくみとして多軸的に診療の原価を患者レベルで日常的に測定するシステム構築の設計を行う。その際に、日本のデータ下部構造や会計のしくみ、病院会計準則、医事データの標準フォーマット、医薬品・検査等に関わる標準コード体系、標準的なデータセットなどの諸要素と構造を整理して当原価計算に活用できるようにした。これらに基づき、多施設で共有して使えること、それにより、妥当な施設間比較ができるようになり、医療の経営品質と政策に資することを目指すものである。また、技術的には、原価の割り当ての方法について、正確さの程度により、直課から荒い配賦まで、整理してまとめ、原価計算に活用した。日常診療の診療情報管理、医事システム、給与システム、経理や物流のシステム、勤務の割振り実態などのデータを統合して、患者ごとのデータを日常的に継続的に出すしくみである。国内のデータコーディング、財務諸表の標準化、従来使われている部門別原価計算方法も踏まえて原価を妥当に算出する方法論基盤を既に作っている。医療機関内すべてを網羅する部門を設定して部門区分の粒度を高め、各種サービス種別に対応する細部門別の原価を第一段階とし、近年の医事コンピュータの電算化や抽出データの標準化を活用して直課相当しうる部分を患者に直課し、一方で細部門にプールされた原価を原価作用因でもって活動基準原価計算の一種として患者に按分する方法である。データは日毎に分割し、しかも、人、薬剤、診療材料などの勘定項目からなる原価諸要素と、手術、各種検査などサービス内容諸要素との、多軸構成を持たせてある。その上で、諸切り口で算出した原価について、診療科目や患者分類や重症度関連指標、ならびに部署や諸機能の質や効率・経済性を含む業績評価との関係性を分析し、活動基準管理への活用方法を検討した。
- 医療提供組織における経営品質の多軸的評価方法の研究開発日本学術振興会:科学研究費助成事業 基盤研究(B)研究期間 : 2001年 -2003年代表者 : 今中 雄一; 石崎 達郎医療の経営について以下のように多軸的な検討が可能であり有効であることを示した。 医療機関の経営システムの全体を評価できる仕組として、機能評価・認定、経営品質、ISOやBSのマネジメントシステムを比較研究し、1:方針の展開、目標管理、臨床的な統治におけるリーダーシップ、2:プロセス指向型の部門内・部門間連携の促進と維持、3:業務プロセスの標準化、4:個々のケアと組織レベルの計画とその系統的なレビュー、5:不満・苦情やリスクを全組織的に管理するシステム、要改善点の徹底的なフォローアップ、6:パフォーマンスの測定の標準化と維持、7:顧客満足の認識と継続的な改善が多くの医療機関で改善の余地がある点と考えられた。顧客満足としての患者満足度の測定では、施設間でばらつきを検知することができ、また、患者は在院日数などの条件で医療に期待する内容が異なり、同じ施設でも患者の満足度に影響する因子が異なることが実証された。 臨床評価指標の点では、10余の病院の入院データより虚血性心疾患、子宮筋腫手術、大腿骨頸部骨折治療、破裂性脳動脈瘤とそのクリッピング手術に焦点を当てて、治療方法の選択などのプロセスのばらつき、在院日数や死亡率などのアウトカムの指標化を行った。病院間の臨床評価指標値のばらつきを示され、その要因の一部が同定された。重症度で階層化すると施設間差が一層明確になることもしばしば見られた。財務面では、収入と従来より測定困難とされている原価について実証研究を進めた。我々が開発した患者毎勘定科目毎に原価を計算する手法を用い、協力モデル病院で実運用を試行して成果を出し、症例ごとの収支データを内部管理に活用し医療の効率化が促進されるかどうかの検証を進めた。
- 要介護高齢者の在宅ケアにおける医療費・介護費用の経時的評価日本学術振興会:科学研究費助成事業 若手研究(B)研究期間 : 2001年 -2002年代表者 : 石崎 達郎本研究は、在宅要介護高齢者を対象に、在宅ケアの実施に必要となる医療費と介護費用を把握することを目的とするものである。今年度は、某訪問看護ステーションの利用者(60名)を対象に、平成15年7月、8月、9月の3ヶ月間の医療費と介護費用を経時的に調査した。対象者の要介護度は、要介護度5が最も多く(16名、27%)、次いで要介護度1(15名、25%)、要介護度3(14名、23%)であった。 医療費(医療保険における診療報酬請求額)は3ヶ月間でやや減少傾向にあり、一人あたりの一ヶ月の医療費は7月約6万円、8月約5万6千円、そして9月は約5万3千円であった。一方の介護費用(介護保険における介護報酬請求額)は、3ヶ月間でほとんど変化がなく、一人あたりの一ヶ月の介護費用は約11万〜12万円であった。そして、医療費と介護費用とを合計した総費用も、3ヶ月間で大きな変化はなく、一人一月あたり、7月約20万円、8月約18万円、そして9月は約18万円であった。また、総費用に占める介護費用の平均割合は、7月68%、8月70%、9月69%と、ほとんど変化が認められなかった。さらに、介護保険支給限度基準額における使用割合は、7月45%、8月45%、9月41%と、これもほとんど変化が認められなかった。介護度と医療費、介護費用との関連をみると、介護度が高い者ほど介護費用が高くなる傾向が見られたが、介護度と介護保険支給限度基準額における使用割合との関係は認められなかった。 本研究の結果、今回調査した3ヶ月間では、医療費や介護費用の顕著な変化は認められなかったものの、在宅要介護高齢者の総費用(医療費+介護費用)における介護費用の占める割合が約70%を占めていることが明らかとなった。在宅要介護高齢者の医療・看護・介護ケアに費やされる費用を考慮する際に、介護費用が大きな割合を占めることを留意する必要があろう。
- 介護保険制度導入が在宅ケアを受ける高齢者とその介護者に及ぼす影響の経時的検討日本学術振興会:科学研究費助成事業 奨励研究(A)研究期間 : 1999年 -2000年代表者 : 石崎 達郎本研究の目的は、在宅要介護老人とその介護者を対象に、介護保険制度施行前後において、対象者の状況や在宅支援サービス利用状況などに変化が認められるかどうかを追跡調査によって検討することである。平成11年度の初回調査対象者(訪問看護ステーションからサービスを受けている患者とその家族40組)のうち、初回調査への参加者は21組であった。このうち、第1回追跡調査(平成12年9月)で回答が得られた者は17組であった。 被介護者のADLレベルは、厚生省自立度判定基準によると、A2:1名、B1:2名、B2:6名、C1:4名、C2:4名と、17名中16名が「寝たきり」状態にあった。8ヶ月間のADLレベルの変化は、B1からB2に低下した者1名以外には変化は認められなかった。一方、介護者の身体的状況についても、大きな変化は報告されなかった。 サービス利用に関する変化に関しては、デイサービス、ホームヘルパー、入浴サービスのいずれにおいても、第1回追跡調査の時点では、半数以上の者では利用に大きな変化は認められなかった。具体的には、介護保険制度施行前に各サービスを利用していなかった者(デイサービス:11名、ホームヘルパー:14名、入浴サービス:10名)のうち、制度施行後もサービスを利用していなかった者は、デイサービス9名、ホームヘルパー9名、入浴サービス8名であった。一方、介護保険制度施行後にサービス利用を開始した者は、ホームヘルパーで5名と最も多く、デイサービスや入浴サービスではそれぞれ2名であった。 研究代表者は平成12年10月に京都大学へ異動となるため、異動後に再度追跡調査を実施した後に、最終的な検討を実施する予定である。
- 在宅ケアを受ける要介護老人の身体的精神的健康状態の経時的変化に関連する要因の分析日本学術振興会:科学研究費助成事業 奨励研究(A)研究期間 : 1997年 -1998年代表者 : 石崎 達郎本研究は、訪問看護・在宅診療を受けている在宅要介護老人とその家族(介護者)を追跡調査し、患者とその介護者の身体的精神的状況の経時的変化を調べ、その変化に関連する要因を検討することを目的とする。平成10年度の研究では、平成9年度の初回調査対象者(患者とその家族19組)を追跡すると同時に、初回調査実施後に新たに訪問看護・訪問診療の対象となった患者・家族(16組)についても新規対象者として追跡した。初回調査対象者(19名)のうち、半年後の第2回調査で再調査が可能であった者は8組で、一年後の再調査でも追跡が可能であった者は6組であったが、身体的精神的状況の大きな変化を捉えることはできなかった。一方、介護者では、身体的精神的状況の変化は半年毎の観察でも把握することができ、約半数で体調悪化や介護負担感増強が報告された。この理由として自分の身体の変化が、体調悪化と負担感増強の両方においてほぼ全員で訴えられ、自分の気持ちの変化をその理由として挙げていた者も少数いた。また、介護者の体調悪化の理由として被介護者の病状変化を挙げた者は一人もいなかったが、介護負担感増強については理由として挙げていた者が少数いた。従って、今回の調査結果より、在宅ケアを支援する訪問看護・訪問診療では、患者の病状把握はもちろんのこと、介護者についても定期的に健康管理がなされる必要があることが示唆されよう。本研究では当初3-4ヶ月毎の再評価を予定していたが、初回追跡患者の追跡開始後3-4ヶ月では身体的精神的状況の変化は認められなかったため、観察間隔を半年毎に延長して、変化を捉えようとした。しかし、観察期間を延長したところで追跡可能であった患者の状況にはほとんど変化がなく、その一方で急性疾患発症によって入院して脱落群を多く生じる結果となってしまった。要介護高齢者の追跡研究は、健常集団とは異なった研究デザインが必要である。
- 在宅ケアを行う要介護老人の健康状態維持増進に関連する要因の分析日本学術振興会:科学研究費助成事業 奨励研究(A)研究期間 : 1994年 -1994年代表者 : 石崎 達郎今年度の研究では主に、同一の老人保健施設を複数回利用した者の、日常生活動作能力の変化と、利用者の家族の家庭介護力を調査した。対象:神奈川県川崎市にある帝京大学老人保健センター(定員156人)において、平成5年4月から8月の間に入所していた利用者(ショートステイを除く92名)とその家族(主たる介護者)を調査対象とした。まず、利用者の家族に自記式のアンケート用紙を渡し、後日施設内で回収した。次に、入所記録より利用者の利用状況を調べた。結果と考察:1)利用者の特徴:利用者は女性が73.1%、平均年齢は81.8(±6.2)歳であった。ADLレベル(Barthel index)の平均得点は入所時/退所時それぞれ、初回(92名)が62.1点(±30.1)/65.0点(±30.8)、2回目(72名)65.4(±31.9)/65.4(±33.1)、3回目(43名)58.3(±33.8)/55.7(±34.9)、4回目(13名)59.0(±29.6)/64.9(±30.1)と、複数回利用者は、退所後にADLが低下した状態で再入所し、入所によって一旦ADLは改善するが、家庭に戻るとまた下がってしまい、全体的には漸減傾向にあった。2)家庭介護力:主要介護者は68.9%が女性で、平均年齢54.8歳(±12.0)、平均世帯人員数3.8人(±1.7)であった。居住環境は65.6%が集合住宅に住み、平均部屋数は4.2部屋(±1.7)であった。SS平均得点は15.8点(±3.5)であった。家計状態は、49.4%が家計に「ゆとりがある」と答え、また48.3%が「家計に満足している」と答えていた。利用者-介護者間の人間関係は93.2%が仲がよいと答え、77.5%が「介護に負担を感じている」と答えていた。今回の調査では、4回以上の複数利用者が少なかったため、介護力との関連性を検討することができなかった。