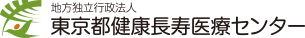研究者総覧
横山 友里 (ヨコヤマ ユリ)
|  | ||
Last Updated :2024/12/27
研究活動情報
論文
- Hidemi Takimoto; Emiko Okada; Jun Takebayashi; Yuki Tada; Takahiro Yoshizaki; Yuri Yokoyama; Yoshiko IshimiNutrients 13 8 2021年08月 [査読有り]
- Satoshi Seino; Yu Nofuji; Yuri Yokoyama; Yui Tomine; Mariko Nishi; Toshiki Hata; Shoji Shinkai; Yoshinori Fujiwara; Akihiko KitamuraJournal of epidemiology 31 6 401 - 402 2021年06月 [査読有り]
- Jun Yasuda; Tatsunosuke Gomi; Ayaka Kotemori; Yuri Yokoyama; Takahiro Yoshizaki; Azumi Hida; Yuki Tada; Yoichi Katsumata; Yukari KawanoNutrition 83 111088 - 111088 2021年03月 [査読有り]
- Yuri Yokoyama; Akihiko Kitamura; Satoshi Seino; Hunkyung Kim; Shuichi Obuchi; Hisashi Kawai; Hirohiko Hirano; Yutaka Watanabe; Keiko Motokawa; Miki Narita; Shoji ShinkaiNutrition journal 20 1 7 - 7 2021年01月 [査読有り]
- Akihiko Kitamura; Satoshi Seino; Takumi Abe; Yu Nofuji; Yuri Yokoyama; Hidenori Amano; Mariko Nishi; Yu Taniguchi; Miki Narita; Yoshinori Fujiwara; Shoji ShinkaiJournal of cachexia, sarcopenia and muscle 2020年11月 [査読有り]
- Yu Taniguchi; Akihiko Kitamura; Takumi Abe; Gotaro Kojima; Tomohiro Shinozaki; Satoshi Seino; Yuri Yokoyama; Yu Nofuji; Tomoko Ikeuchi; Yutaka Matsuyama; Yoshinori Fujiwara; Shoji ShinkaiGeriatrics & gerontology international 20 11 1072 - 1078 2020年11月 [査読有り]
- Takumi Abe; Akihiko Kitamura; Satoshi Seino; Yuri Yokoyama; Hidenori Amano; Yu Taniguchi; Mariko Nishi; Yu Nofuji; Tomoko Ikeuchi; Takemi Sugiyama; Shoji ShinkaiInternational journal of environmental research and public health 17 17 2020年09月 [査読有り]
- 清野 諭; 北村 明彦; 遠峰 結衣; 田中 泉澄; 西 真理子; 野藤 悠; 横山 友里; 野中 久美子; 倉岡 正高; 天野 秀紀; 藤原 佳典; 新開 省二日本公衆衛生雑誌 67 6 399 - 412 日本公衆衛生学会 2020年06月 [査読有り]
- Satoshi Seino; Akihiko Kitamura; Takumi Abe; Yu Taniguchi; Yuri Yokoyama; Hidenori Amano; Mariko Nishi; Yu Nofuji; Miki Narita; Tomoko Ikeuchi; Yoshinori Fujiwara; Shoji ShinkaiJournal of the American Medical Directors Association 21 6 726 - 733 2020年06月 [査読有り]
- Takumi Abe; Yu Nofuji; Satoshi Seino; Hiroshi Murayama; Yuka Yoshida; Tomomi Tanigaki; Yuri Yokoyama; Miki Narita; Mariko Nishi; Akihiko Kitamura; Shoji ShinkaiMaturitas 136 54 - 59 2020年06月 [査読有り]
- 都市部高齢者における食品摂取多様性および所得と精神的健康度との関連田中 泉澄; 北村 明彦; 横山 友里; 成田 美紀; 清野 諭; 遠峰 結衣; 西 真理子; 新開 省二厚生の指標 67 4 1 - 7 (一財)厚生労働統計協会 2020年04月
- Sho Kaito; Yu Taniguchi; Akihiko Kitamura; Satoshi Seino; Hidenori Amano; Yuri Yokoyama; Hiroshi Fukuda; Hirohide Yokokawa; Yoshinori Fujiwara; Shoji Shinkai; Toshio NaitoClinical and experimental nephrology 24 4 330 - 338 2020年04月 [査読有り]
- Yosuke Osuka; Hunkyung Kim; Hisashi Kawai; Yu Taniguchi; Yuri Yokoyama; Satoshi Seino; Shuichi Obuchi; Akihiko Kitamura; Shoji ShinkaiJournal of clinical medicine 9 3 2020年03月 [査読有り]
- 成田 美紀; 北村 明彦; 武見 ゆかり; 横山 友里; 森田 明美; 新開 省二日本公衆衛生雑誌 67 3 171 - 182 日本公衆衛生学会 2020年03月 [査読有り]
- 北村 明彦; 清野 諭; 谷口 優; 横山 友里; 天野 秀紀; 西 真理子; 野藤 悠; 成田 美紀; 池内 朋子; 阿部 巧; 藤原 佳典; 新開 省二日本公衆衛生雑誌 67 2 134 - 145 日本公衆衛生学会 2020年02月 [査読有り]
- Yu Taniguchi; Satoshi Seino; Mariko Nishi; Yui Tomine; Izumi Tanaka; Yuri Yokoyama; Tomoko Ikeuchi; Akihiko Kitamura; Shoji ShinkaiScientific reports 9 1 18604 - 18604 2019年12月 [査読有り]
- Yu Taniguchi; Akihiko Kitamura; Tatsuro Ishizaki; Yoshinori Fujiwara; Tomohiro Shinozaki; Satoshi Seino; Seigo Mitsutake; Hiroyuki Suzuki; Yuri Yokoyama; Takumi Abe; Tomoko Ikeuchi; Isao Yokota; Yutaka Matsuyama; Shoji ShinkaiGeriatrics & gerontology international 19 12 1236 - 1242 2019年12月 [査読有り]
- Yuri Yokoyama; A. Kitamura; T. Yoshizaki; M. Nishi; S. Seino; Y. Taniguchi; H. Amano; M. Narita; S. ShinkaiThe journal of nutrition, health & aging 23 9 896 - 903 2019年11月 [査読有り]
- Takumi Abe; Akihiko Kitamura; Satoshi Seino; Yuri Yokoyama; Hidenori Amano; Yu Taniguchi; Mariko Nishi; Miki Narita; Tomoko Ikeuchi; Yui Tomine; Yoshinori Fujiwara; Shoji ShinkaiInternational journal of environmental research and public health 16 20 2019年10月 [査読有り]
- Yuri Yokoyama; Akihiko Kitamura; Mariko Nishi; Satoshi Seino; Yu Taniguchi; Hidenori Amano; Tomoko Ikeuchi; Shoji ShinkaiJournal of epidemiology 29 10 370 - 376 2019年10月 [査読有り]
- 野藤 悠; 清野 諭; 村山 洋史; 吉田 由佳; 谷垣 知美; 横山 友里; 成田 美紀; 西 真理子; 中村 正和; 北村 明彦; 新開 省二日本公衆衛生雑誌 66 9 560 - 573 日本公衆衛生学会 2019年09月 [査読有り]
- Satoshi Seino; Akihiko Kitamura; Yui Tomine; Izumi Tanaka; Mariko Nishi; Y U Taniguchi; Yuri Yokoyama; Hidenori Amano; Yoshinori Fujiwara; Shoji ShinkaiMedicine and science in sports and exercise 51 6 1146 - 1153 2019年06月 [査読有り]
- Akihiko Kitamura; Yu Taniguchi; Satoshi Seino; Yuri Yokoyama; Hidenori Amano; Yoshinori Fujiwara; Shoji ShinkaiGeriatrics & gerontology international 19 5 423 - 428 2019年05月 [査読有り]
- Takumi Abe; Akihiko Kitamura; Yu Taniguchi; Hidenori Amano; Satoshi Seino; Yuri Yokoyama; Mariko Nishi; Miki Narita; Tomoko Ikeuchi; Yoshinori Fujiwara; Shoji ShinkaiMaturitas 123 32 - 36 2019年05月 [査読有り]
- Satoshi Seino; Akihiko Kitamura; Yui Tomine; Izumi Tanaka; Mariko Nishi; Kumiko Nonaka; Yu Nofuji; Miki Narita; Yu Taniguchi; Yuri Yokoyama; Hidenori Amano; Tomoko Ikeuchi; Yoshinori Fujiwara; Shoji ShinkaiJournal of epidemiology 29 2 73 - 81 2019年02月 [査読有り]
- 吉崎 貴大; 横山 友里; 大上 安奈; 川口 英夫栄養学雑誌 77 1 19 - 28 (NPO)日本栄養改善学会 2019年02月 [査読有り]
- Yu Taniguchi; Akihiko Kitamura; Yu Nofuji; Tatsuro Ishizaki; Satoshi Seino; Yuri Yokoyama; Tomohiro Shinozaki; Hiroshi Murayama; Seigo Mitsutake; Hidenori Amano; Mariko Nishi; Yutaka Matsuyama; Yoshinori Fujiwara; Shoji ShinkaiThe journals of gerontology. Series A, Biological sciences and medical sciences 74 2 211 - 218 2019年01月 [査読有り]
- Yu Taniguchi; Satoshi Seino; Mariko Nishi; Yui Tomine; Izumi Tanaka; Yuri Yokoyama; Hidenori Amano; Akihiko Kitamura; Shoji ShinkaiPloS one 14 3 e0214824 2019年 [査読有り]
- Yu Taniguchi; Akihiko Kitamura; Sho Kaito; Yuri Yokoyama; Isao Yokota; Tomohiro Shinozaki; Satoshi Seino; Hiroshi Murayama; Yutaka Matsuyama; Tomoko Ikeuchi; Yoshinori Fujiwara; Shoji ShinkaiDementia and geriatric cognitive disorders 47 4-6 233 - 242 2019年 [査読有り]
- Kaori Yamamoto; Masako Ota; Ayako Minematsu; Keiko Motokawa; Yuri Yokoyama; Tomohiro Yano; Yutaka Watanabe; Takahiro YoshizakiNutrients 10 12 2018年12月 [査読有り]
- 田中 泉澄; 北村 明彦; 清野 諭; 西 真理子; 遠峰 結衣; 谷口 優; 横山 友里; 成田 美紀; 新開 省二日本公衆衛生雑誌 65 12 744 - 754 日本公衆衛生学会 2018年12月 [査読有り]
- Yu Taniguchi; Akihiko Kitamura; Tomohiro Shinozaki; Satoshi Seino; Yuri Yokoyama; Miki Narita; Hidenori Amano; Yutaka Matsuyama; Yoshinori Fujiwara; Shoji ShinkaiGeriatrics & gerontology international 18 7 1108 - 1113 2018年07月 [査読有り]
- Satoshi Seino; Akihiko Kitamura; Mariko Nishi; Yui Tomine; Izumi Tanaka; Yu Taniguchi; Yuri Yokoyama; Hidenori Amano; Miki Narita; Tomoko Ikeuchi; Yoshinori Fujiwara; Shoji ShinkaiThe international journal of behavioral nutrition and physical activity 15 1 46 - 46 2018年05月 [査読有り]
- Satoshi Seino; K. Sumi; M. Narita; Y. Yokoyama; K. Ashida; A. Kitamura; S. ShinkaiJournal of Nutrition, Health and Aging 22 1 59 - 67 2018年01月 [査読有り]
- 横山 友里; 北村 明彦; 川野 因; 新開 省二日本食育学会誌 12 1 33 - 40 (一社)日本食育学会 2018年01月 [査読有り]
- Yu Taniguchi; Satoshi Seino; Mariko Nishi; Yui Tomine; Izumi Tanaka; Yuri Yokoyama; Hidenori Amano; Akihiko Kitamura; Shoji ShinkaiPloS one 13 11 e0206399 2018年 [査読有り]
- Yu Taniguchi; Akihiko Kitamura; Hiroshi Murayama; Hidenori Amano; Tomohiro Shinozaki; Isao Yokota; Satoshi Seino; Yu Nofuji; Mariko Nishi; Yuri Yokoyama; Yutaka Matsuyama; Yoshinori Fujiwara; Shoji ShinkaiGeriatrics & gerontology international 17 11 1928 - 1935 2017年11月 [査読有り]
- Satoshi Seino; Mariko Nishi; Hiroshi Murayama; Miki Narita; Yuri Yokoyama; Yu Nofuji; Yu Taniguchi; Hidenori Amano; Akihiko Kitamura; Shoji ShinkaiGeriatrics & gerontology international 17 11 2034 - 2045 2017年11月 [査読有り]
- 北村 明彦; 新開 省二; 谷口 優; 天野 秀紀; 清野 諭; 横山 友里; 西 真理子; 藤原 佳典日本公衆衛生雑誌 64 10 593 - 606 日本公衆衛生学会 2017年10月 [査読有り]
- Yu Taniguchi; Akihiko Kitamura; Satoshi Seino; Hiroshi Murayama; Hidenori Amano; Yu Nofuji; Mariko Nishi; Yuri Yokoyama; Tomohiro Shinozaki; Isao Yokota; Yutaka Matsuyama; Yoshinori Fujiwara; Shoji ShinkaiJournal of the American Medical Directors Association 18 2 192.e13-192.e20 2017年02月 [査読有り]
- Yuri Yokoyama; M. Nishi; H. Murayama; H. Amano; Y. Taniguchi; Y. Nofuji; M. Narita; E. Matsuo; S. Seino; Y. Kawano; S. ShinkaiThe journal of nutrition, health & aging 21 1 11 - 16 2017年01月 [査読有り]
- Takahiro Yoshizaki; Yukari Kawano; Osamu Noguchi; Junko Onishi; Reiko Teramoto; Ayaka Sunami; Yuri Yokoyama; Yuki Tada; Azumi Hida; Fumiharu TogoBMJ open 6 11 e011987 2016年11月 [査読有り]
- Yuri Yokoyama; M. Nishi; H. Murayama; H. Amano; Y. Taniguchi; Y. Nofuji; M. Narita; E. Matsuo; S. Seino; Y. Kawano; S. ShinkaiThe journal of nutrition, health & aging 20 7 691 - 696 2016年07月 [査読有り]
- Ayaka Sunami; Kazuto Sasaki; Yoshio Suzuki; Nobuhide Oguma; Junko Ishihara; Ayumi Nakai; Jun Yasuda; Yuri Yokoyama; Takahiro Yoshizaki; Yuki Tada; Azumi Hida; Yukari KawanoJournal of epidemiology 26 6 284 - 91 2016年06月 [査読有り]
- Yuki Kokubo; Yuri Yokoyama; Kumiko Kisara; Yoshiko Ohira; Ayaka Sunami; Takahiro Yoshizaki; Yuki Tada; Sakuko Ishizaki; Azumi Hida; Yukari KawanoInternational journal of sport nutrition and exercise metabolism 26 2 105 - 13 2016年04月 [査読有り]
- 砂見 綾香; 佐々木 和登; 江崎 治; 中井 あゆみ; 安田 純; 横山 友里; 吉崎 貴大; 多田 由紀; 日田 安寿美; 川野 因体力科学 65 1 189 - 196 (一社)日本体力医学会 2016年02月 [査読有り]
- Yuki Kokubo; Kumiko Kisara; Yuri Yokoyama; Yoshiko Ohira-Akiyama; Yuki Tada; Azumi Hida; Sakuko Ishizaki; Yukari KawanoSpringerPlus 5 1 862 - 862 2016年 [査読有り]
- Yuki Tada; Yasutake Tomata; Ayaka Sunami; Yuri Yokoyama; Azumi Hida; Tadasu Furusho; Yukari KawanoPublic health nutrition 18 17 3166 - 71 2015年12月 [査読有り]
- 安田 純; 横山 友里; 砂見 綾香; 多田 由紀; 外山 健二; 川野 因; 日田 安寿美東京農業大学農学集報 60 2 63 - 68 東京農業大学 2015年09月 [査読有り]
- Hiroshi Murayama; Mariko Nishi; Yu Nofuji; Eri Matsuo; Yu Taniguchi; Hidenori Amano; Yuri Yokoyama; Yoshinori Fujiwara; Shoji ShinkaiHealth & place 34 270 - 8 2015年07月 [査読有り]
- 中井 あゆみ; 古泉 佳代; 小川 睦美; 吉崎 貴大; 砂見 綾香; 横山 友里; 安田 純; 佐々木 和登; 多田 由紀; 日田 安寿美; 小久保 友貴; 外山 健二; 井上 久美子; 川野 因日本食育学会誌 9 1 41 - 51 (一社)日本食育学会 2015年01月 [査読有り]
- 谷口 優; 藤原 佳典; 篠崎 智大; 天野 秀紀; 西 真理子; 村山 洋史; 野藤 悠; 清野 諭; 成田 美紀; 松尾 恵理; 横山 友里; 新開 省二; 東京都健康長寿医療センター研究所社会参加と地域保健研究チーム日本老年医学会雑誌 52 1 86 - 93 (一社)日本老年医学会 2015年01月 [査読有り]
- Yuki Tada; Yukari Kawano; Izumi Maeda; Takahiro Yoshizaki; Ayaka Sunami; Yuri Yokoyama; Harumi Matsumoto; Azumi Hida; Taiki Komatsu; Fumiharu TogoObesity (Silver Spring, Md.) 22 12 2489 - 93 2014年12月 [査読有り]
- Takahiro Yoshizaki; Yuki Tada; Azumi Hida; Ayaka Sunami; Yuri Yokoyama; Jun Yasuda; Ayumi Nakai; Fumiharu Togo; Yukari KawanoEuropean journal of applied physiology 113 10 2603 - 11 2013年10月 [査読有り]
- Takahiro Yoshizaki; Yuki Tada; Azumi Hida; Ayaka Sunami; Yuri Yokoyama; Fumiharu Togo; Yukari KawanoPhysiology & behavior 118 122 - 8 2013年06月 [査読有り]
- 横山 友里; 山田 美恵子; 木皿 久美子; 橋爪 みすず; 小久保 友貴; 日田 安寿美; 多田 由紀; 吉崎 貴大; 砂見 綾香; 石崎 朔子; 川野 因栄養学雑誌 71 1 29 - 36 (NPO)日本栄養改善学会 2013年02月 [査読有り]
- 日田 安寿美; 山中 朋実; 永田 薫; 柏葉 名菜; 村上 ひかり; 横山 友里; 砂見 綾香; 吉崎 貴大; 多田 由紀; 手塚 貴子; 吉沢 博幸; 川野 因日本食育学会誌 7 1 33 - 40 (一社)日本食育学会 2013年01月 [査読有り]
MISC
- 横山 友里; 亀井 明子 臨床栄養 135 (4) 503 -505 2019年09月
- 横山 友里; 新開 省二 栄養 3 (4) 247 -253 2018年12月
- 食生活 いろいろ食べて、やせと栄養不足を防ごう!横山 友里 老年学・老年医学公開講座 151回 3 -16 2018年09月
- 横山 友里 Aging & Health 26 (4) 10 -12 2018年01月
- 横山 友里; 新開 省二 THE LUNG-perspectives 24 (3) 247 -251 2016年08月
- 【健康寿命延伸をめざす栄養戦略 フレイル・疾病重症化予防のために】低栄養予防と多様な食品摂取横山 友里; 新開 省二 臨床栄養 別冊 (JCNセレクト11 健康寿命延伸をめざす栄養戦略) 107 -114 2016年04月
- 横山 友里; 川野 因; 新開 省二 介護福祉・健康づくり 2 (2) 76 -80 2015年12月
共同研究・競争的資金等の研究課題
- 改良版食品摂取の多様性得点の開発と妥当性および有用性の検討日本学術振興会:科学研究費助成事業 若手研究研究期間 : 2018年04月 -2021年03月代表者 : 横山 友里本研究では、現在の日本人高齢者の食品摂取の多様性を適切かつ簡便に評価可能な『改良版食品摂取の多様性得点』を開発し、その妥当性およびフレイル予防に対する有用性を検証することを目的に、今年度は既存の食事調査データをもとに以下の検討と食事記録調査を行った。2012年鳩山コホート調査または2013年草津縦断調査に参加した65歳以上の地域在住高齢者1089名を解析対象とした。栄養素等摂取量および食品群別摂取量は、簡易型自記式食事歴法質問票(BDHQ)を用いて調べた。DVSは、熊谷らのDVS(日本公衛誌、2003)を用い、改良版DVSはDVSの構成食品である10食品群の各摂取量について、男女別の摂取量の中央値に対して多い場合(中央値以上)を1点・少ない場合(中央値未満)を0点とした合計点(0‐10点)として算出した(MDVS1)。食事の質の評価指標として、The Nutrient Rich Foods Index9.3に基づき、砂糖を除く11項目の栄養素摂取量について、「日本人の食事摂取基準(2015年版)」における推奨量に対する比率の平均値をとり、Overall nutrient adequacy score(ONA)得点を算出した。さらに、MDVSは、ONA得点に対する予測精度を高めるため、DVSの10の構成食品のほか、穀類、その他の野菜摂取量を追加し、重回帰分析の標準化係数で重みづけして算出した(MDVS2)。分析の結果、DVSとONA得点の間に有意な相関関係がみられたが、MDVS1とMDVS2ではDVSより強い関係がみられた。ONA得点を従属変数とした重回帰分析における調整済みR2乗は、DVSやMDVS1に比べ、MDVS2で高く、ONA得点に対する予測精度が高まった。摂取量を加味し、構成食品の追加や各構成要素の重みづけにより、食事全体の質をより反映できることが示された。
- 日本学術振興会:科学研究費助成事業 研究活動スタート支援研究期間 : 2016年08月 -2018年03月代表者 : 横山 友里地域在住高齢者を対象に、食事摂取パターンの実態を明らかにし、フレイルとの横断的関連を検討した。その結果、主食・主菜・副菜を揃えて食べるのが1日2回以上の頻度が、毎日と回答した群を基準としたとき、2~3日以下の群でプレフレイル・フレイルの該当リスクが有意に高かった。また、夕食たんぱく質摂取比率(P%)の代わりに朝食P%、昼食P%を1%増やすと、プレフレイル・フレイルの該当リスクが低値を示した。以上の結果から、主食・主菜・副菜を1日2回以上揃える頻度を増やすこと、朝食および昼食のたんぱく質摂取量を増加させ、毎食のたんぱく質摂取量を一定量確保することが、フレイル予防にかかわる可能性が示唆された。
- 高齢者における貧血と健康寿命の関連-食生活面からの検討-日本学術振興会:科学研究費助成事業 特別研究員奨励費研究期間 : 2014年04月 -2016年03月代表者 : 横山 友里本研究は高齢者の貧血と健康寿命の関連を検討するとともに、食生活面から高齢者の貧血予防策を明らかにすることを目的に、平成27年度は以下2つの研究課題を検討した。【課題1】平成15年~23年における国民健康・栄養調査のデータを用いて、高齢者の貧血の年次推移と食生活との関わりを検討した。その結果、貧血を有する高齢者の割合は、男性では、平成15年で24.1%、平成23年で20.9%であり、女性では、平成15年で26.2 %、平成23年で19.8%であった。年齢階級別に貧血を有する高齢者の割合をみてみると、65歳以降加齢とともに増加した。また、高齢者を貧血の有無により2群に分け、栄養素等摂取量および食品群別摂取量(粗摂取量およびエネルギー調整済み摂取量)を比較した結果、男女ともに貧血有群が貧血無群に比べて、エネルギー摂取量、たんぱく質をはじめとした多くの栄養素や食品群の摂取量が有意に少なかった。【課題2】平成26年度の研究結果より、食品摂取多様性得点が高いことと貧血との横断的関連が明らかになった。これらの関連をより詳細に検討するうえで、今年度は、貧血と密接に関連する血中のビタミンB群(葉酸、ビタミンB12)およびホモシステイン濃度と食品摂取多様性得点との関連を検討することとした。その結果、食品摂取多様性と血清葉酸、血清ビタミンB12とは正の関連がみられ、ホモシステインとは負の関連がみられた。これらの結果から、75歳以上の後期高齢者数が今後急増する我が国において、高齢者の貧血予防が今後益々重要になるとともに、食生活面からの貧血予防策として多様な食品摂取が関わる可能性が示唆された。