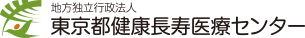Researchers Database
Okamura Tsuyoshi- Vice-director | |||
Last Updated :2025/06/27
Researcher Information
URL
J-Global ID
Research Interests
Research Areas
- Life sciences / Internal medicine - General
- Life sciences / Hygiene and public health (non-laboratory)
- Life sciences / Hygiene and public health (laboratory)
- Life sciences / Psychiatry
Academic & Professional Experience
Education
Published Papers
- Ito Kae; Ura Chiaki; Sugiyama Mika; Edahiro Ayako; Okamura TsuyoshiPsychogeriatrics : the official journal of the Japanese Psychogeriatric Society 25 (2) e70012 2025/03
- Chiaki Ura; Tsuyoshi Okamura; Akinori Takase; Yukan Ogawa; Ryosho ShojiBMC Research Notes Springer Science and Business Media LLC 18 (1) 2025/02
- 高齢期に働く動機の分析:高齢期に働く多様な場があることがのぞましい岡村毅、飯塚あい、三井美穂子、櫻井花、宇良千秋老年精神医学雑誌 36 (1) 65 - 71 2025/01 [Refereed]
- Tsuyoshi Okamura; Ai Iizuka; Mihoko Mitsui; Hana Sakurai; Mariko Nishi; Chiaki UraInternational journal of geriatric psychiatry 40 (1) e70043 2025/01
- Sho Hatanaka; Takashi Shida; Yosuke Osuka; Narumi Kojima; Keiko Motokawa; Tsuyoshi Okamura; Hirohiko Hirano; Shuichi Awata; Hiroyuki SasaiClinical Nutrition ESPEN Elsevier BV 64 114 - 121 2405-4577 2024/12
- 自宅死を見据えた地域包括ケアシステムの可視化 離島における高齢者の死を支える要素神谷 綾子; 小野 真由子; 問芝 志保; 松江 しのぶ; 青木 伸吾; 岡村 毅; 井藤 佳恵; 宮前 史子日本エンドオブライフケア学会誌 (一社)日本エンドオブライフケア学会 8 (2) 70 - 70 2433-2763 2024/09
- 自宅死を見据えた地域包括ケアシステムの可視化 離島における死別を経験した人に対する周囲のサポート小野 真由子; 神谷 綾子; 問芝 志保; 松江 しのぶ; 青木 伸吾; 岡村 毅; 井藤 佳恵; 宮前 史子日本エンドオブライフケア学会誌 (一社)日本エンドオブライフケア学会 8 (2) 78 - 78 2433-2763 2024/09
- 自宅死を見据えた地域包括ケアシステムの可視化 離島における組織を越えた連携や支援宮前 史子; 神谷 綾子; 小野 真由子; 問芝 志保; 松江 しのぶ; 青木 伸吾; 岡村 毅; 井藤 佳恵日本エンドオブライフケア学会誌 (一社)日本エンドオブライフケア学会 8 (2) 79 - 79 2433-2763 2024/09
- Keiko Motokawa; Maki Shirobe; Masanori Iwasaki; Yosuke Komatsu; Takuya Shibasaki; Yasuaki Wada; Yurie Mikami; Misato Hayakawa; Takashi Shida; Hiroyuki Sasai; Tsuyoshi Okamura; Hirohiko Hirano; Shuichi AwataGeriatrics & gerontology international 2024/08
- 稲垣 宏樹; 杉山 美香; 宇良 千秋; 枝広 あや子; 多賀 努; 宮前 史子; 本川 佳子; 村山 洋史; 岡村 毅; 粟田 主一老年精神医学雑誌 (株)ワールドプランニング 35 (増刊II) 230 - 230 0915-6305 2024/07
- Chiaki Ura; Tomoko Wakui; Yukiko Kugimiya; Mutsuko Okamura; Masako Yamamura; Hidemi Okado; Mayumi Kaneko; Mari Yamashita; Shuichi Awata; Tsuyoshi OkamuraPsychogeriatrics Wiley 1346-3500 2024/07
- Keiko Motokawa; Maki Shirobe; Masanori Iwasaki; Yasuaki Wada; Fuka Tabata; Kazuhiro Shigemoto; Yurie Mikami; Misato Hayakawa; Yosuke Osuka; Narumi Kojima; Hiroyuki Sasai; Hiroki Inagaki; Fumiko Miyamae; Tsuyoshi Okamura; Hirohiko Hirano; Shuichi AwataClinical nutrition ESPEN 63 157 - 161 2024/06
- Ai Iizuka; Chiaki Ura; Mari Yamashita; Koki Ito; Miyuko Yamashiro; Tsuyoshi OkamuraBrain and Behavior Wiley 14 (6) 2162-3279 2024/06
- 杉山 美香; 宮前 史子; 稲垣 宏樹; 宇良 千秋; 枝広 あや子; 岡村 毅; 粟田 主一老年社会科学 日本老年社会科学会 46 (2) 169 - 169 0388-2446 2024/06
- 稲垣 宏樹; 宇良 千秋; 枝広 あや子; 杉山 美香; 宮前 史子; 岩崎 正則; 笹井 浩行; 岡村 毅; 平野 浩彦; 粟田 主一老年社会科学 日本老年社会科学会 46 (2) 186 - 186 0388-2446 2024/06
- 地域在住高齢者におけるビタミンK充足度とうつ症状の関連 板橋健康長寿縦断研究東 浩太郎; 志田 隆史; 小島 成実; 大田 崇央; 笹井 浩行; 平野 浩彦; 宮前 史子; 稲垣 宏樹; 岡村 毅; 井上 聡日本抗加齢医学会総会プログラム・抄録集 (一社)日本抗加齢医学会 24回 243 - 243 2024/05
- 独居高齢者における地域生活継続のセルフ・エフィカシーの関連要因 将来認知症になっても近くに相談相手がいれば大丈夫?宇良 千秋; 稲垣 宏樹; 杉山 美香; 宮前 史子; 枝広 あや子; 井藤 佳恵; 岡村 毅; 粟田 主一日本認知症ケア学会誌 (一社)日本認知症ケア学会 23 (1) 164 - 164 1882-0255 2024/04
- 認知症の本人からの発信はどのようにして実現するか 市町村担当者から見た本人発信支援事業が抱える課題宮前 史子; 藤田 和子; 小森 由美子; 山梨 恵子; 粟田 主一; 岡村 毅; 永田 久美子日本認知症ケア学会誌 (一社)日本認知症ケア学会 23 (1) 165 - 165 1882-0255 2024/04
- Takashi Shida; Sho Hatanaka; Takahisa Ohta; Yosuke Osuka; Narumi Kojima; Keiko Motokawa; Masanori Iwasaki; Fumiko Miyamae; Tsuyoshi Okamura; Hirohiko Hirano; Shuichi Awata; Hiroyuki SasaiNutrition Elsevier BV 112453 - 112453 0899-9007 2024/04
- Hitomi Matsui; Takehiro Tamura; Tsuyoshi Okamura; Genichi Sugihara; Ko Furuta; Yuki Omori; Masashi Kameyama; Shuichi Awata; Takashi Takeuchi; Hidehiko TakahashiPCN reports : psychiatry and clinical neurosciences 3 (1) e171 2024/03
- Naoki Deguchi; Yosuke Osuka; Narumi Kojima; Keiko Motokawa; Masanori Iwasaki; Hiroki Inagaki; Fumiko Miyamae; Tsuyoshi Okamura; Hirohiko Hirano; Shuichi Awata; Hiroyuki SasaiFrontiers in Public Health Frontiers Media SA 12 2024/02
- Kaori Daimaru; Yosuke Osuka; Narumi Kojima; Katsuyoshi Mizukami; Keiko Motokawa; Masanori Iwasaki; Hiroki Inagaki; Fumiko Miyamae; Tsuyoshi Okamura; Hirohiko Hirano; Shuichi Awata; Hiroyuki SasaiGeriatrics & gerontology international 2024/01
- 地域レベルのソーシャルキャピタルと総死亡との関連 都市部でのマルチレベルコホート研究村山 洋史; 杉山 美香; 稲垣 宏樹; 宇良 千秋; 宮前 史子; 枝広 あや子; 本川 佳子; 岡村 毅; 粟田 主一Journal of Epidemiology (一社)日本疫学会 34 (Suppl.) 108 - 108 0917-5040 2024/01
- Hiroshi Murayama; Mika Sugiyama; Hiroki Inagaki; Ayako Edahiro; Fumiko Miyamae; Chiaki Ura; Keiko Motokawa; Tsuyoshi Okamura; Shuichi AwataJournal of Epidemiology Japan Epidemiological Association 0917-5040 2024
- Naoki Deguchi; Yosuke Osuka; Narumi Kojima; Keiko Motokawa; Masanori Iwasaki; Hiroki Inagaki; Fumiko Miyamae; Tsuyoshi Okamura; Hirohiko Hirano; Shuichi Awata; Hiroyuki SasaiGeriatrics & gerontology international 2023/12
- Tsuyoshi Okamura; Chiaki Ura; Yukiko Kugimiya; Mutsuko Okamura; Masako Yamamura; Hidemi Okado; Mayumi Kaneko; Mari Yamashita; Tomoko WakuiBMC Geriatrics Springer Science and Business Media LLC 23 (1) 2023/12
- Chiaki Ura; Hiroki Inagaki; Mika Sugiyama; Fumiko Miyamae; Ayako Edahiro; Kae Ito; Masanori Iwasaki; Hiroyuki Sasai; Tsuyoshi Okamura; Hirohiko Hirano; Shuichi AwataPsychogeriatrics Wiley 1346-3500 2023/12
- Ayako Edahiro; Tsuyoshi Okamura; Tetsuaki Arai; Takeshi Ikeuchi; Manabu Ikeda; Kumiko Utsumi; Hidetaka Ota; Tatsuyuki Kakuma; Shinobu Kawakatsu; Yoko Konagaya; Kyoko Suzuki; Satoshi Tanimukai; Kazuo Miyanaga; Shuichi AwataGeriatrics & Gerontology International Wiley 24 (1) 176 - 178 1444-1586 2023/11
- Sachiko Yamazaki; Chiaki Ura; Hiroki Inagaki; Mika Sugiyama; Fumiko Miyamae; Ayako Edahiro; Kae Ito; Masanori Iwasaki; Hiroyuki Sasai; Tsuyoshi Okamura; Hirohiko Hirano; Shuichi AwataPsychogeriatrics Wiley 1346-3500 2023/11
- Tsuyoshi Okamura; Chiaki Ura; Tomoko WakuiGeriatrics & Gerontology International Wiley 23 (12) 978 - 980 1444-1586 2023/11
- Sadaya Misaki; Hiroshi Murayama; Mika Sugiyama; Hiroki Inagaki; Tsuyoshi Okamura; Chiaki Ura; Fumiko Miyamae; Ayako Edahiro; Keiko Motokawa; Shuichi AwataNippon Ronen Igakkai Zasshi. Japanese Journal of Geriatrics The Japan Geriatrics Society 60 (4) 364 - 372 0300-9173 2023/10
- Peer support meeting of people with dementia: a qualitative descriptive analysis of the discussions.Fumiko Miyamae; Mika Sugiyama; Tsutomu Taga; Tsuyoshi OkamuraBMC geriatrics 23 (1) 637 - 637 2023/10
- 読経の高齢者への効果(第一報) 僧侶の機能特性に関する予備的調査枝広 あや子; 本橋 佳子; 金子 真由美; 宇良 千秋; 安藤 千晶; 白部 麻樹; 宮前 史子; 岡村 毅日本公衆衛生学会総会抄録集 日本公衆衛生学会 82回 376 - 376 1347-8060 2023/10
- 読経の高齢者への効果(第二報) 集合型プログラムの試行本橋 佳子; 金子 真由美; 枝広 あや子; 宇良 千秋; 安藤 千晶; 白部 麻樹; 宮前 史子; 岡村 毅日本公衆衛生学会総会抄録集 日本公衆衛生学会 82回 377 - 377 1347-8060 2023/10
- 読経の高齢者への効果(第三報) プログラム参加の促進要因の検討金子 真由美; 本橋 佳子; 枝広 あや子; 宇良 千秋; 安藤 千晶; 白部 麻樹; 宮前 史子; 岡村 毅日本公衆衛生学会総会抄録集 日本公衆衛生学会 82回 377 - 377 1347-8060 2023/10
- Sho Hatanaka; Yosuke Osuka; Narumi Kojima; Keiko Motokawa; Misato Hayakawa; Yurie Mikami; Masanori Iwasaki; Hiroki Inagaki; Fumiko Miyamae; Tsuyoshi Okamura; Hirohiko Hirano; Shuichi Awata; Hiroyuki SasaiNutrition Elsevier BV 112289 - 112289 0899-9007 2023/10
- Tsuyoshi Okamura; Tsutomu Taga; Hiroki Inagaki; Fumiko Miyamae; Chiaki Ura; Mika Sugiyama; Ayako Edahiro; Maki Shirobe; Keiko Motokawa; Narumi Kojima; Yosuke Osuka; Masanori Iwasaki; Hiroyuki Sasai; Hirohiko Hirano; Shuichi AwataGeriatrics & gerontology international 23 (10) 761 - 763 2023/10
- Hiroshi Murayama; Mika Sugiyama; Hiroki Inagaki; Chiaki Ura; Fumiko Miyamae; Ayako Edahiro; Keiko Motokawa; Tsuyoshi Okamura; Shuichi AwataThe journals of gerontology. Series B, Psychological sciences and social sciences 2023/09
- Kae Ito; Shuji Tsuda; Mayumi Hagiwara; Tsuyoshi OkamuraBMC Health Services Research Springer Science and Business Media LLC 23 (1) 2023/09
- 島薗 進; 宇良 千秋; 東海林 良昌; 高瀬 顕功; 小川 有閑; 岡村 毅Nippon Ronen Igakkai Zasshi. Japanese Journal of Geriatrics The Japan Geriatrics Society 60 (3) 245 - 250 0300-9173 2023/07
- 進 島薗; 千秋 宇良; 良昌 東海林; 顕功 高瀬; 有閑 小川; 毅 岡村Nippon Ronen Igakkai Zasshi. Japanese Journal of Geriatrics The Japan Geriatrics Society 60 (3) 245 - 250 0300-9173 2023/07
- Sachiko Yamazaki; Chiaki Ura; Tsuyoshi OkamuraPsychogeriatrics Wiley 23 (4) 730 - 731 1346-3500 2023/05
- Chiaki Ura; Ai Iizuka; Mari Yamashita; Koki Ito; Tsuyoshi OkamuraGeriatrics & Gerontology International Wiley 1444-1586 2023/05
- 地域在住高齢者における社会的孤立と栄養状態の関連の横断的検証 板橋健康長寿縦断研究カランタル 玲奈; 本川 佳子; 早川 美知; 三上 友里江; 白部 麻樹; 枝広 あや子; 岡村 毅; 笹井 浩行; 平野 浩彦; 粟田 主一日本老年医学会雑誌 (一社)日本老年医学会 60 (Suppl.) 186 - 186 0300-9173 2023/05
- 畠山 啓; 枝広 あや子; 椎名 貴恵; 近藤 康寛; 山田 悠佳; 新田 怜小; 佐古 真紀; 柏木 一惠; 岡村 毅; 井藤 佳恵; 粟田 主一老年精神医学雑誌 (株)ワールドプランニング 34 (5) 477 - 486 0915-6305 2023/05
- 認知症疾患医療センターにおける若年性認知症の診断後支援畠山 啓; 枝広 あや子; 椎名 貴恵; 近藤 康寛; 山田 悠佳; 新田 怜小; 岡村 毅; 井藤 佳恵; 粟田 主一日本認知症ケア学会誌 (一社)日本認知症ケア学会 22 (1) 184 - 184 1882-0255 2023/04
- Mari Yamashita; Mai Kato; Tomoya Kawanishi; Yoshiko Uehara; Yuko Kubota; Fumiko Ogisawa; Kiyo Kawakubo; Tsutomu Taga; Tsuyoshi Okamura; Kae Ito; Shin Kitamura; Akiko YamazakiInternational Journal of Geriatric Psychiatry Wiley 0885-6230 2023/03
- Ayako Edahiro; Tsuyoshi Okamura; Tetsuaki Arai; Takeshi Ikeuchi; Manabu Ikeda; Kumiko Utsumi; Hidetaka Ota; Tatsuyuki Kakuma; Shinobu Kawakatsu; Yoko Konagaya; Kyoko Suzuki; Satoshi Tanimukai; Kazuo Miyanaga; Shuichi AwataPsychogeriatrics Wiley 23 (3) 422 - 433 1346-3500 2023/02
- Shuji Tsuda; Hiroki Inagaki; Mika Sugiyama; Tsuyoshi Okamura; Fumiko Miyamae; Chiaki Ura; Ayako Edahiro; Shuichi AwataHealth & Social Care in the Community Hindawi Limited 2023 1 - 8 2023/02
- Ai Iizuka; Mari Yamashita; Chiaki Ura; Tsuyoshi OkamuraJournal of Community Health Nursing Informa UK Limited 40 (1) 52 - 63 0737-0016 2023/01
- Akinori Takase; Yuki Matoba; Tsutomu Taga; Kae Ito; Tsuyoshi OkamuraBMC health services research 22 (1) 1400 - 1400 2022/11
- 佐久間 尚子; 稲垣 宏樹; 宮前 史子; 枝広 あや子; 杉山 美香; 宇良 千秋; 山下 真里; 本川 佳子; 白部 麻樹; 岩崎 正則; 小島 成実; 大須賀 洋祐; 笹井 浩行; 平野 浩彦; 岡村 毅; 粟田 主一老年精神医学雑誌 (株)ワールドプランニング 33 (増刊II) 384 - 384 0915-6305 2022/11
- 井藤 佳恵; 岡村 毅; 津田 修治; 扇澤 史子; 粟田 主一老年精神医学雑誌 (株)ワールドプランニング 33 (増刊II) 387 - 388 0915-6305 2022/11
- Kae Ito; Tsuyoshi Okamura; Shuji Tsuda; Fumiko Ogisawa; Shuichi AwataGeriatrics & gerontology international 2022/10
- 栄養指標と位相角の関連性の横断的検証 板橋健康長寿縦断研究本川 佳子; 岩崎 正則; 早川 美知; 三上 友里江; 白部 麻樹; 大須賀 洋祐; 小島 成実; 畑中 翔; 笹井 浩行; 稲垣 宏樹; 宮前 史子; 枝広 あや子; 岡村 毅; 平野 浩彦; 粟田 主一日本サルコペニア・フレイル学会雑誌 (一社)日本サルコペニア・フレイル学会 6 (Suppl.) 207 - 207 2433-1805 2022/10
- 都市に暮らす高齢者の日常生活行動頻度の基礎的研究 板橋健康長寿縦断研究佐久間 尚子; 稲垣 宏樹; 宮前 史子; 枝広 あや子; 杉山 美香; 宇良 千秋; 山下 真里; 本川 佳子; 白部 麻樹; 岩崎 正則; 小島 成実; 大須賀 洋祐; 笹井 浩行; 平野 浩彦; 岡村 毅; 粟田 主一Dementia Japan (一社)日本認知症学会 36 (4) 814 - 814 1342-646X 2022/10
- 認知機能低下のある地域における高齢者困難事例の特徴 認知症の臨床ステージとの関連井藤 佳恵; 岡村 毅; 津田 修治; 扇澤 史子; 粟田 主一Dementia Japan (一社)日本認知症学会 36 (4) 816 - 816 1342-646X 2022/10
- Chiaki Ura; Tsuyoshi Okamura; Tsutomu Taga; Chieko Yanagisawa; Sachiko Yamazaki; Masaya ShimmeiInternational journal of geriatric psychiatry 37 (9) 2022/09
- Tsuyoshi Okamura; Chiaki Ura; Masaya Shimmei; Akinori Takase; Ryosho Shoji; Yukan OgawaDementia (London, England) 21 (5) 1856 - 1868 2022/07
- Fumiko Miyamae; Tsutomu Taga; Tsuyoshi Okamura; Shuichi AwataPsychogeriatrics : the official journal of the Japanese Psychogeriatric Society 22 (4) 586 - 587 2022/07
- Hiroki Inagaki; Mika Sugiyama; Kae Ito; Naoko Sakuma; Chiaki Ura; Fumiko Miyamae; Tsuyoshi Okamura; Shuichi Awata[Nihon koshu eisei zasshi] Japanese journal of public health 69 (6) 459 - 472 2022/06
- 稲垣 宏樹; 杉山 美香; 井藤 佳恵; 佐久間 尚子; 宇良 千秋; 宮前 史子; 岡村 毅; 粟田 主一日本公衆衛生雑誌 日本公衆衛生学会 69 (6) 459 - 472 0546-1766 2022/06
- 稲垣 宏樹; 杉山 美香; 井藤 佳恵; 佐久間 尚子; 宇良 千秋; 宮前 史子; 岡村 毅; 粟田 主一日本公衆衛生雑誌 日本公衆衛生学会 69 (6) 459 - 472 0546-1766 2022/06
- 90代高齢者の心理的well-beingの関連要因 人生100年時代のwell-being井藤 佳恵; 岡村 毅; 粟田 主一; 権藤 恭之; 増井 幸恵; 稲垣 宏樹; 神出 計; 池邉 一典; 新井 康通; 石崎 達郎日本老年医学会雑誌 (一社)日本老年医学会 59 (Suppl.) 155 - 155 0300-9173 2022/05
- 杉山 美香; 岡村 毅; 井藤 佳恵; 山下 真里; 粟田 主一老年精神医学雑誌 (株)ワールドプランニング 33 (5) 497 - 506 0915-6305 2022/05
- Tsuyoshi Okamura; Chiaki Ura; Mika Sugiyama; Hiroki Inagaki; Fumiko Miyamae; Ayako Edahiro; Tsutomu Taga; Shuji Tsuda; Riko Nakayama; Kae Ito; Shuichi AwataPsychogeriatrics : the official journal of the Japanese Psychogeriatric Society 22 (3) 332 - 342 2022/05 [Refereed]
- Shuji Tsuda; Hiroki Inagaki; Tsuyoshi Okamura; Mika Sugiyama; Madoka Ogawa; Fumiko Miyamae; Ayako Edahiro; Chiaki Ura; Naoko Sakuma; Shuichi AwataBMC geriatrics Springer Science and Business Media LLC 22 (1) 360 - 360 2022/04 [Refereed]
- 認知症の人と家族が経験した歯科通院での困りごととそれに対する工夫枝広 あや子; 白部 麻樹; 平野 浩彦; 岩崎 正則; 本川 佳子; 小原 由紀; 大堀 嘉子; 井藤 佳恵; 岡村 毅; 粟田 主一日本認知症ケア学会誌 (一社)日本認知症ケア学会 21 (1) 147 - 147 1882-0255 2022/04
- Kae Ito; Tsuyoshi Okamura; Shuichi Awata; Yasuyuki Gondo; Yukie Masui; Hiroki Inagaki; Kei Kamide; Kazunori Ikebe; Yasumichi Arai; Tatsuro IshizakiGeriatrics & gerontology international 22 (4) 364 - 366 2022/04
- Masanori Iwasaki; Yuki Ohara; Keiko Motokawa; Misato Hayakawa; Maki Shirobe; Ayako Edahiro; Yutaka Watanabe; Shuichi Awata; Tsuyoshi Okamura; Hiroki Inagaki; Naoko Sakuma; Shuichi Obuchi; Hisashi Kawai; Manami Ejiri; Kumiko Ito; Yoshinori Fujiwara; Akihiko Kitamura; Yu Nofuji; Takumi Abe; Katsuya Iijima; Tomoki Tanaka; Bo-Kyung Son; Shoji Shinkai; Hirohiko HiranoJournal of prosthodontic research 67 (1) 62 - 69 2022/01
- Tsuyoshi Okamura; Yukan Ogawa; Akinori Takase; Masaya Shimmei; Chiaki UraInternational journal of geriatric psychiatry Wiley 37 (2) 0885-6230 2022/01 [Refereed]
- Yukan Ogawa; Akinori Takase; Masaya Shimmei; Shiho Toishiba; Chiaki Ura; Mari Yamashita; Tsuyoshi OkamuraPloS one 17 (10) e0276275 2022
- 山下 真里; 岡村 毅; 宇良 千秋; 杉山 美香; 中山 莉子; 宮前 史子; 小川 まどか; 稲垣 宏樹; 枝広 あや子; 多賀 努; 津田 修治; 井藤 佳恵; 粟田 主一日本認知症ケア学会誌 (一社)日本認知症ケア学会 20 (4) 560 - 571 1882-0255 2022/01
- Naoko Sakuma; Hiroki Inagaki; Madoka Ogawa; Ayako Edahiro; Chiaki Ura; Mika Sugiyama; Fumiko Miyamae; Hiroyuki Suzuki; Yutaka Watanabe; Shoji Shinkai; Tsuyoshi Okamura; Shuichi AwataArchives of gerontology and geriatrics 100 104617 - 104617 2022 [Refereed]
- Yukan Ogawa; Akinori Takase; Masaya Shimmei; Chiaki Ura; Machiko Nakagawa; Tsuyoshi OkamuraInternational Journal of Geriatric Psychiatry Wiley 37 (1) 0885-6230 2022/01 [Refereed]
- Chiaki Ura; Tsuyoshi Okamura; Akinori Takase; Masaya Shimmei; Yukan OgawaGeriatrics & Gerontology International Wiley 22 (1) 87 - 89 1444-1586 2022/01 [Refereed]
- Chiaki Ura; Tsuyoshi Okamura; Sachiko Yamazaki; Masaya Shimmei; Keisuke Torishima; Akira Eboshida; Yu KawamuroBMC Geriatrics Springer Science and Business Media LLC 21 (1) 237 - 237 2021/12
- Chiaki Ura; Tsuyoshi Okamura; Mika Sugiyama; Fumiko Miyamae; Mari Yamashita; Riko Nakayama; Ayako Edahiro; Tsutomu Taga; Hiroki Inagaki; Madoka Ogawa; Shuichi AwataBMC Geriatrics Springer Science and Business Media LLC 21 (1) 131 - 131 2021/12
- Tsuyoshi Okamura; Yuki Matoba; Mikio Sato; Megumu Mizuta; Shuich AwataJournal of Social Distress and Homelessness Informa UK Limited 1 - 6 1053-0789 2021/11 [Refereed]
- Ayako Edahiro; Tsuyoshi Okamura; Yoshiko Motohashi; Chika Takahashi; Ayami Meguro; Mika Sugiyama; Fumiko Miyamae; Tsutomu Taga; Chiaki Ura; Riko Nakayama; Mari Yamashita; Shuichi AwataInternational Journal of Environmental Research and Public Health MDPI AG 18 (22) 11961 - 11961 2021/11 [Refereed]
- 地域に暮らす認知症機能低下高齢者への訪問調査 感染症流行下の口腔状態本橋 佳子; 枝広 あや子; 岡村 毅; 高橋 知佳; 宇良 千秋; 宮前 史子; 杉山 美香; 山下 真里; 粟田 主一日本公衆衛生学会総会抄録集 日本公衆衛生学会 80回 392 - 392 1347-8060 2021/11
- 地域に暮らす認知症機能低下高齢者への訪問調査 栄養状態低下の要因枝広 あや子; 岡村 毅; 本橋 佳子; 高橋 知佳; 宇良 千秋; 宮前 史子; 杉山 美香; 山下 真里; 粟田 主一日本公衆衛生学会総会抄録集 日本公衆衛生学会 80回 392 - 392 1347-8060 2021/11
- 大都市在住高齢者のTrail Making Testの成績 TMT-Bの完遂者と未完遂者の比較佐久間 尚子; 鈴木 宏幸; 稲垣 宏樹; 小川 将; 枝広 あや子; 杉山 美香; 宮前 史子; 宇良 千秋; 渡邊 裕; 新開 省二; 岡村 毅; 粟田 主一日本公衆衛生学会総会抄録集 日本公衆衛生学会 80回 398 - 398 1347-8060 2021/11
- Kae Ito; Tsuyoshi Okamura; Shuji Tsuda; Shuichi AwataInternational Journal of Geriatric Psychiatry Wiley 37 (1) 0885-6230 2021/10
- 認知症などの困難を抱えた高齢者に対する地域における歯科口腔保健相談の意義と方法論 権利ベースのアプローチという観点から枝広 あや子; 岡村 毅; 杉山 美香; 小川 まどか; 稲垣 宏樹; 宇良 千秋; 宮前 史子; 釘宮 由紀子; 森倉 三男; 岡村 睦子; 中山 莉子; 多賀 努; 山下 真里; 津田 修治; 井藤 佳恵; 粟田 主一日本認知症ケア学会誌 (一社)日本認知症ケア学会 20 (3) 435 - 445 1882-0255 2021/10
- 枝広 あや子; 岡村 毅; 杉山 美香; 小川 まどか; 稲垣 宏樹; 宇良 千秋; 宮前 史子; 釘宮 由紀子; 森倉 三男; 岡村 睦子; 中山 莉子; 多賀 努; 山下 真里; 津田 修治; 井藤 佳恵; 粟田 主一日本認知症ケア学会誌 (一社)日本認知症ケア学会 20 (3) 435 - 445 1882-0255 2021/10
- Tsuyoshi Okamura; Mika Sugiyama; Hiroki Inagaki; Fumiko Miyamae; Chiaki Ura; Naoko Sakuma; Ayako Edahiro; Tsutomu Taga; Shuji Tsuda; Shuichi AwataPsychogeriatrics Wiley 21 (6) 892 - 901 1346-3500 2021/09
- 多賀 努; 井藤 佳恵; 宇良 千秋; 枝広 あや子; 岡村 毅; 岡村 睦子; 釘宮 由紀子; 杉山 美香; 津田 修治; 中山 莉子; 宮前 史子; 山下 真理; 粟田 主一老年精神医学雑誌 (株)ワールドプランニング 32 (増刊I) 242 - 242 0915-6305 2021/09
- 森倉 三男; 多賀 努; 井藤 佳恵; 宇良 千秋; 岡村 毅; 見城 澄子; 釘宮 由紀子; 杉山 美香; 永瀬 雅子; 中山 莉子; 宮前 史子; 粟田 主一老年精神医学雑誌 (株)ワールドプランニング 32 (増刊I) 261 - 261 0915-6305 2021/09
- 大都市に暮らす高齢者のTrail Making Testの成績(その3) TMT-B完遂者のエラー1回は健常範囲か?佐久間 尚子; 鈴木 宏幸; 稲垣 宏樹; 小川 将; 枝広 あや子; 杉山 美香; 宮前 史子; 宇良 千秋; 岡村 毅; 粟田 主一老年精神医学雑誌 (株)ワールドプランニング 32 (増刊I) 251 - 251 0915-6305 2021/09
- 大都市に一人で暮らす認知機能低下高齢者の対人・社会関係に関する報告 高島平2019コホートにおける大規模郵送調査の結果から稲垣 宏樹; 粟田 主一; 宇良 千秋; 枝広 あや子; 岡村 毅; 杉山 美香; 宮前 史子; 多賀 努; 平野 浩彦; 本川 佳子; 小原 由紀; 横山 友里; 北村 明彦; 新開 省二老年精神医学雑誌 (株)ワールドプランニング 32 (増刊I) 271 - 271 0915-6305 2021/09
- 大都市に一人で暮らす認知機能低下高齢者の対人・社会関係に関する報告 高島平2019コホートにおける大規模郵送調査の結果から稲垣 宏樹; 粟田 主一; 宇良 千秋; 枝広 あや子; 岡村 毅; 杉山 美香; 宮前 史子; 多賀 努; 平野 浩彦; 本川 佳子; 小原 由紀; 横山 友里; 北村 明彦; 新開 省二老年精神医学雑誌 (株)ワールドプランニング 32 (増刊I) 271 - 271 0915-6305 2021/09
- Tsuyoshi Okamura; Chiaki Ura; Yukiko Kugimiya; Mutsuko Okamura; Masako Yamamura; Hidemi Okado; Mika Sugiyama; Hiroki Inagaki; Fumiko Miyamae; Ayako Edahiro; Tsutomu Taga; Kae Ito; Shuichi AwataInternational Journal of Geriatric Psychiatry Wiley 36 (12) 1970 - 1971 0885-6230 2021/08
- Chiaki Ura; Tsuyoshi Okamura; Akinori Takase; Masaya Shimmei; Yukan OgawaGeriatrics & Gerontology International Wiley 21 (10) 966 - 967 1444-1586 2021/08
- Tsuyoshi Okamura; Chiaki Ura; Tsutomu Taga; Chieko Yanagisawa; Sachiko Yamazaki; Masaya ShimmeiPsychogeriatrics Wiley 21 (5) 852 - 853 1346-3500 2021/08
- Tsuyoshi Okamura; Chiho Shimada; Mio Ito; Kae ItoPsychogeriatrics Wiley 21 (5) 854 - 855 1346-3500 2021/07
- Riko Nakayama; Mika Sugiyama; Chiaki Ura; Tsutomu Taga; Shuji Tsuda; Mari Yamashita; Fumiko Miyamae; Ayako Edahiro; Hiroki Inagaki; Madoka Ogawa; Tsuyoshi Okamura; Shuichi AwataPsychogeriatrics Wiley 21 (5) 841 - 843 1346-3500 2021/07
- Sachiko Yamazaki; Chiaki Ura; Masaya Shimmei; Tsuyoshi OkamuraInternational Journal of Geriatric Psychiatry Wiley 36 (10) 1590 - 1591 0885-6230 2021/05
- 高齢者/認知症の人に優しいまちづくり Dementia Friendly Communitiesに向けた口腔保健の実践 大規模団地の片隅の地域介入から枝広 あや子; 宮前 史子; 多賀 努; 杉山 美香; 佐久間 尚子; 宇良 千秋; 稲垣 宏樹; 岡村 毅; 粟田 主一; 東京都健康長寿医療センター研究所自立促進と精神保健研究チーム認知症と精神保健日本老年医学会雑誌 (一社)日本老年医学会 58 (Suppl.) 8 - 8 0300-9173 2021/05
- Tsuyoshi Okamura; Chiaki Ura; Mika Sugiyama; Yukiko Kugimiya; Mutsuko Okamura; Shuichi AwataInternational Journal of Geriatric Psychiatry Wiley 36 (9) 1465 - 1467 0885-6230 2021/04 [Refereed]
- 特養職員の看取り介護の経験・態度と精神的健康の関連(その1) 宗教者が施設ケアに関わる可能性について宇良 千秋; 岡村 毅; 高瀬 顕功; 新名 正弥; 中川 真知子; 小川 有閑日本認知症ケア学会誌 (一社)日本認知症ケア学会 20 (1) 147 - 147 1882-0255 2021/04
- 特養職員の看取り介護の経験・態度と精神的健康の関連(その2) 施設ケアラーの考える理想の死に関する予備的分析岡村 毅; 宇良 千秋; 高瀬 顕功; 新名 正弥; 中川 真知子; 小川 有閑日本認知症ケア学会誌 (一社)日本認知症ケア学会 20 (1) 147 - 147 1882-0255 2021/04
- 本邦におけるディオゲネス症候群 いわゆる「ごみ屋敷症候群」 臨床的特徴と長期予後井藤 佳恵; 岡村 毅; 津田 修治日本認知症ケア学会誌 (一社)日本認知症ケア学会 20 (1) 168 - 168 1882-0255 2021/04
- 訪問口腔調査で明らかになった都市部在住認知症高齢者の口腔機能低下枝広 あや子; 岡村 毅; 本橋 佳子; 宇良 千秋; 宮前 史子; 杉山 美香; 多賀 努; 中山 莉子; 山下 真里; 粟田 主一日本認知症ケア学会誌 (一社)日本認知症ケア学会 20 (1) 140 - 140 1882-0255 2021/04
- コロナ禍の認知症支援拠点の役割とその実践 第2回目の緊急事態宣言下での地域拠点の取り組み杉山 美香; 岡村 毅; 枝広 あや子; 宮前 史子; 中山 莉子; 宇良 千秋; 小川 まどか; 多賀 努; 井藤 佳恵; 粟田 主一日本認知症ケア学会誌 (一社)日本認知症ケア学会 20 (1) 165 - 165 1882-0255 2021/04
- 地域拠点において認知症とともに生きる独居高齢者の安心感を醸成するには? コーディネーションの観点から中山 莉子; 多賀 努; 岡村 毅; 杉山 美香; 宇良 千秋; 山下 真里; 宮前 史子; 枝広 あや子; 粟田 主一日本認知症ケア学会誌 (一社)日本認知症ケア学会 20 (1) 167 - 167 1882-0255 2021/04
- コロナ禍の認知症支援拠点の役割とその実践 第2回目の緊急事態宣言下での地域拠点の取り組み杉山 美香; 岡村 毅; 枝広 あや子; 宮前 史子; 中山 莉子; 宇良 千秋; 小川 まどか; 多賀 努; 井藤 佳恵; 粟田 主一日本認知症ケア学会誌 (一社)日本認知症ケア学会 20 (1) 165 - 165 1882-0255 2021/04
- 本邦におけるディオゲネス症候群 いわゆる「ごみ屋敷症候群」 臨床的特徴と長期予後井藤 佳恵; 岡村 毅; 津田 修治日本認知症ケア学会誌 (一社)日本認知症ケア学会 20 (1) 168 - 168 1882-0255 2021/04
- 訪問口腔調査で明らかになった都市部在住認知症高齢者の口腔機能低下枝広 あや子; 岡村 毅; 本橋 佳子; 宇良 千秋; 宮前 史子; 杉山 美香; 多賀 努; 中山 莉子; 山下 真里; 粟田 主一日本認知症ケア学会誌 (一社)日本認知症ケア学会 20 (1) 140 - 140 1882-0255 2021/04
- 地域拠点において認知症とともに生きる独居高齢者の安心感を醸成するには? コーディネーションの観点から中山 莉子; 多賀 努; 岡村 毅; 杉山 美香; 宇良 千秋; 山下 真里; 宮前 史子; 枝広 あや子; 粟田 主一日本認知症ケア学会誌 (一社)日本認知症ケア学会 20 (1) 167 - 167 1882-0255 2021/04
- Tsuyoshi Okamura; Yukan Ogawa; Akinori Takase; Masaya Shimmei; Shiho Toishiba; Chiaki UraNippon Ronen Igakkai Zasshi. Japanese Journal of Geriatrics The Japan Geriatrics Society 58 (1) 126 - 133 0300-9173 2021/01
- 岡村 毅; 小川 有閑; 高瀬 顕功; 新名 正弥; 問芝 志保; 宇良 千秋日本老年医学会雑誌 (一社)日本老年医学会 58 (1) 126 - 133 0300-9173 2021/01
- Syoji R; Ogawa Y; Takase A; Shimmei M; Ura C; Okamura TInternational journal of geriatric psychiatry 36 (9) 1462 - 1463 2021 [Refereed]
- Ayako Edahiro; Tsuyoshi Okamura; Yoshiko Motohashi; Chika Takahashi; Mika Sugiyama; Fumiko Miyamae; Tsutomu Taga; Chiaki Ura; Riko Nakayama; Mari Yamashita; Shuichi AwataPsychogeriatrics : the official journal of the Japanese Psychogeriatric Society 21 (1) 140 - 141 2021/01
- 佐久間 尚子; 稲垣 宏樹; 小川 まどか; 枝広 あや子; 杉山 美香; 宮前 史子; 宇良 千秋; 岡村 毅; 粟田 主一老年精神医学雑誌 (株)ワールドプランニング 31 (増刊II) 185 - 185 0915-6305 2020/12
- 杉山 美香; 宮前 史子; 岡村 毅; 佐久間 尚子; 稲垣 宏樹; 宇良 千秋; 小川 まどか; 枝広 あや子; 粟田 主一老年精神医学雑誌 (株)ワールドプランニング 31 (増刊II) 186 - 186 0915-6305 2020/12
- 稲垣 宏樹; 杉山 美香; 宇良 千秋; 枝広 あや子; 岡村 毅; 多賀 努; 宮前 史子; 本川 佳子; 村山 洋史; 粟田 主一老年精神医学雑誌 (株)ワールドプランニング 31 (増刊II) 186 - 186 0915-6305 2020/12
- Chiaki Ura; Tsuyoshi Okamura; Mika Sugiyama; Yukiko Kugimiya; Mutsuko Okamura; Madoka Ogawa; Fumiko Miyamae; Ayako Edahiro; Shuichi AwataGeriatrics & gerontology international 20 (12) 1245 - 1248 2020/12
- Tsuyoshi Okamura; Chiaki Ura; Mika Sugiyama; Madoka Ogawa; Hiroki Inagaki; Fumiko Miyamae; Ayako Edahiro; Yukiko Kugimiya; Mutsuko Okamura; Mari Yamashita; Shuichi AwataBMC Geriatrics Springer Science and Business Media LLC 20 (1) 68 - 68 2020/12 [Refereed]
- Ayako Edahiro; Fumiko Miyamae; Tsutomu Taga; Mika Sugiyama; Kazunori Kikuchi; Tsuyoshi Okamura; Shuichi AwataGeriatrics & gerontology international 20 (11) 1050 - 1055 2020/11
- COVID-19影響下で認知症支援のための地域拠点に何ができるのか杉山 美香; 岡村 毅; 枝広 あや子; 宮前 史子; 宇良 千秋; 小川 まどか; 小久保 奈緒美; 山下 真里; 稲垣 宏樹; 粟田 主一日本公衆衛生学会総会抄録集 日本公衆衛生学会 79回 397 - 397 1347-8060 2020/10
- Tsuyoshi Okamura; Chiaki Ura; Mika Sugiyama; Yukiko Kugimiya; Mutsuko Okamura; Madoka Ogawa; Fumiko Miyamae; Ayako Edahiro; Shuichi AwataPsychogeriatrics Wiley 20 (6) 944 - 945 1346-3500 2020/08 [Refereed]
- 介護保険データを用いた若年性認知症有病者数の推計における「みなし第2号被保険者」の影響菊地 和則; 中西 亜紀; 小長谷 陽子; 多賀 努; 枝広 あや子; 杉山 美香; 岡村 毅; 宮前 史子; 山村 正子; 粟田 主一日本老年医学会雑誌 (一社)日本老年医学会 57 (Suppl.) 112 - 112 0300-9173 2020/07
- 大都市に暮らす高齢者の健康度 会場調査と訪問調査の比較から佐久間 尚子; 稲垣 宏樹; 小川 まどか; 枝広 あや子; 杉山 美香; 宮前 史子; 宇良 千秋; 岡村 毅; 粟田 主一日本老年医学会雑誌 (一社)日本老年医学会 57 (Suppl.) 117 - 117 0300-9173 2020/07
- 継続的な囲碁の学習による精神的健康状態の経時的変化 囲碁を活用した認知機能低下抑制プログラム「iGOこち」より飯塚 あい; 鈴木 宏幸; 小川 将; 稲垣 宏樹; 宇良 千秋; 杉山 美香; 小川 まどか; 岡村 毅; 粟田 主一; 藤原 佳典日本老年医学会雑誌 (一社)日本老年医学会 57 (Suppl.) 137 - 137 0300-9173 2020/07
- 介護保険データを用いた若年性認知症有病者数の推計における「みなし第2号被保険者」の影響菊地 和則; 中西 亜紀; 小長谷 陽子; 多賀 努; 枝広 あや子; 杉山 美香; 岡村 毅; 宮前 史子; 山村 正子; 粟田 主一日本老年医学会雑誌 (一社)日本老年医学会 57 (Suppl.) 112 - 112 0300-9173 2020/07
- 大都市に暮らす高齢者の健康度 会場調査と訪問調査の比較から佐久間 尚子; 稲垣 宏樹; 小川 まどか; 枝広 あや子; 杉山 美香; 宮前 史子; 宇良 千秋; 岡村 毅; 粟田 主一日本老年医学会雑誌 (一社)日本老年医学会 57 (Suppl.) 117 - 117 0300-9173 2020/07
- Chiaki Ura; Tsuyoshi Okamura; Hiroki Inagaki; Madoka Ogawa; Hirotoshi Niikawa; Ayako Edahiro; Mika Sugiyama; Fumiko Miyamae; Naoko Sakuma; Ko Furuta; Akira Hatakeyama; Fumiko Ogisawa; Michiko Konno; Takahiro Suzuki; Shuichi AwataGeriatrics & Gerontology International Wiley 20 (6) 564 - 570 1444-1586 2020/06 [Refereed]
- 大都市団地で認知機能低下と共に暮らす高齢者の体験世界を知る 生活拠点の変化と属性の違いについて宇良 千秋; 岡村 毅; 杉山 美香; 中山 莉子; 山下 真里; 宮前 史子; 小川 まどか; 稲垣 宏樹; 枝広 あや子; 粟田 主一日本認知症ケア学会誌 (一社)日本認知症ケア学会 19 (1) 156 - 156 1882-0255 2020/04
- 大都市団地で認知機能低下と共に暮らす高齢者の体験世界を知る 地域生活の体験と主観的QOLの関連山下 真里; 岡村 毅; 宇良 千秋; 杉山 美香; 中山 莉子; 宮前 史子; 小川 まどか; 稲垣 宏樹; 枝広 あや子; 粟田 主一日本認知症ケア学会誌 (一社)日本認知症ケア学会 19 (1) 157 - 157 1882-0255 2020/04
- 大都市団地で認知機能低下と共に暮らす高齢者の体験世界を知る 本人の語りに基づいた、本人の生活世界の探求岡村 毅; 宇良 千秋; 杉山 美香; 中山 莉子; 山下 真里; 宮前 史子; 小川 まどか; 稲垣 宏樹; 枝広 あや子; 粟田 主一日本認知症ケア学会誌 (一社)日本認知症ケア学会 19 (1) 157 - 157 1882-0255 2020/04
- 地域包括ケアシステムにおける認知症支援のための居場所の役割 相談事業を通して地域拠点における多機関との連携を考える杉山 美香; 岡村 毅; 釘宮 由紀子; 枝広 あや子; 宮前 史子; 小川 まどか; 稲垣 宏樹; 宇良 千秋; 見城 澄子; 粟田 主一日本認知症ケア学会誌 (一社)日本認知症ケア学会 19 (1) 229 - 229 1882-0255 2020/04
- 地域包括ケアシステムにおける認知症支援のための居場所の役割 巨大団地に孤立して住む高齢者の最期の日々に寄り添って釘宮 由紀子; 岡村 睦子; 森倉 三男; 佐藤 恵; 田畑 文子; 宮前 史子; 杉山 美香; 枝広 あや子; 岡村 毅; 粟田 主一日本認知症ケア学会誌 (一社)日本認知症ケア学会 19 (1) 229 - 229 1882-0255 2020/04
- 岡村毅; 杉山美香; 枝広あや子; 宮前史子; 釘宮由紀子; 岡村睦子; 粟田主一日本老年医学雑誌 (一社)日本老年医学会 57 (4) 467 - 474 0300-9173 2020 [Refereed]
- Tsuyoshi Okamura; Mika Sugiyama; Ayako Edahiro; Fumiko Miyamae; Yukiko Kugimiya; Mutsuko Okamura; Shuich AwataNihon Ronen Igakkai zasshi. Japanese journal of geriatrics 57 (4) 467 - 474 2020
- Okamura et日本認知症ケア学会誌 19 (3) 1882-0255 2020 [Refereed]
- オランダにおけるケア・ファーミング:農作を認知症ケアに応用するための要件新名正弥; 宇良千秋; 岡村毅; 矢冨直美; 山崎幸子; 髙橋正彦認知症ケア学会誌 2020 [Refereed]
- 杉山 美香; 岡村 毅; 小川 まどか; 宮前 史子; 枝広 あや子; 宇良 千秋; 稲垣 宏樹; 釘宮 由紀子; 岡村 睦子; 森倉 三男; 見城 澄子; 佐久間 尚子; 粟田 主一日本認知症ケア学会誌 (一社)日本認知症ケア学会 18 (4) 847 - 854 1882-0255 2020/01 [Refereed]
- Dementia-friendly communitiesと死生観―ホームレス支援団体の実践から―OKAMURA Tsuyoshi現代宗教 2020 [Invited]
- Hiroshi Murayama; Fumiko Miyamae; Chiaki Ura; Naoko Sakuma; Mika Sugiyama; Hiroki Inagaki; Tsuyoshi Okamura; Shuichi AwataBMC public health 19 (1) 1442 - 1442 2019/11 [Refereed]
- Tsuyoshi Okamura; Mika Sugiyama; Hiroki Inagaki; Hiroshi Murayama; Chiaki Ura; Fumiko Miyamae; Ayako Edahiro; Keiko Motokawa; Shuich AwataPsychogeriatrics : the official journal of the Japanese Psychogeriatric Society 19 (6) 539 - 546 2019/11 [Refereed]
- Hiroshi Murayama; Chiaki Ura; Fumiko Miyamae; Naoko Sakuma; Mika Sugiyama; Hiroki Inagaki; Tsuyoshi Okamura; Shuichi AwataGeriatrics & gerontology international 19 (9) 950 - 955 2019/09 [Refereed]
- Sachiko Yamazaki; Chiaki Ura; Tsuyoshi Okamura; Masaya Shimmei; Taichi Ishiguro; Keisuke Torishima; Yu KawamuroPsychogeriatrics : the official journal of the Japanese Psychogeriatric Society 19 (5) 513 - 515 2019/09 [Refereed]
- Hiroshi Murayama; Mika Sugiyama; Hiroki Inagaki; Chiaki Ura; Fumiko Miyamae; Ayako Edahiro; Keiko Motokawa; Tsuyoshi Okamura; Shuichi AwataJournal of epidemiology 29 (7) 241 - 246 2019/07 [Refereed]
- 日本語版DEMQOL、DEMQOL-PROXYの作成と信頼性・妥当性の検討新川 祐利; 河野 禎之; 山中 克夫; 岡村 毅; 稲垣 宏樹; 井藤 佳恵; 粟田 主一日本在宅医療連合学会大会プログラム・講演抄録集 (一社)日本在宅医療連合学会 1回 365 - 365 2019/07
- 小川 有閑; 新名 正弥; 高瀬 顕功; 問芝 志保; 弓山 達也; 林田 康順; 東海林 良昌; 宇良 千秋; 岡村 毅老年精神医学雑誌 (株)ワールドプランニング 30 (増刊II) 227 - 227 0915-6305 2019/06
- 多賀 努; 枝広 あや子; 杉山 美香; 岡村 毅; 宮前 史子; 山村 正子; 菊地 和則; 粟田 主一老年精神医学雑誌 (株)ワールドプランニング 30 (増刊II) 187 - 187 0915-6305 2019/06
- 枝広 あや子; 杉山 美香; 多賀 努; 山村 正子; 宮前 史子; 岡村 毅; 菊地 和則; 粟田 主一老年精神医学雑誌 (株)ワールドプランニング 30 (増刊II) 202 - 202 0915-6305 2019/06
- 佐久間 尚子; 稲垣 宏樹; 本川 佳子; 渡邊 裕; 枝広 あや子; 宇良 千秋; 小川 まどか; 杉山 美香; 宮前 史子; 岡村 毅; 新開 省二; 粟田 主一老年精神医学雑誌 (株)ワールドプランニング 30 (増刊II) 208 - 208 0915-6305 2019/06
- 稲垣 宏樹; 佐久間 尚子; 本川 佳子; 渡邊 裕; 枝広 あや子; 宇良 千秋; 小川 まどか; 杉山 美香; 宮前 史子; 岡村 毅; 新開 省二; 粟田 主一老年精神医学雑誌 (株)ワールドプランニング 30 (増刊II) 209 - 209 0915-6305 2019/06
- 菊地 和則; 中西 亜紀; 小長谷 陽子; 多賀 努; 枝広 あや子; 杉山 美香; 岡村 毅; 宮前 史子; 山村 正子; 粟田 主一老年精神医学雑誌 (株)ワールドプランニング 30 (増刊II) 224 - 224 0915-6305 2019/06
- 小川 まどか; 稲垣 宏樹; 宇良 千秋; 杉山 美香; 宮前 史子; 岡村 毅; 枝広 あや子; 釘宮 由紀子; 森倉 三男; 岡村 睦子; 粟田 主一老年精神医学雑誌 (株)ワールドプランニング 30 (増刊II) 228 - 228 0915-6305 2019/06
- 杉山 美香; 宮前 史子; 佐久間 尚子; 稲垣 宏樹; 宇良 千秋; 小川 まどか; 枝広 あや子; 岡村 毅; 粟田 主一老年精神医学雑誌 (株)ワールドプランニング 30 (増刊II) 217 - 217 0915-6305 2019/06 [Refereed]
- Hirotoshi Niikawa; Yoshiyuki Kawano; Katsuo Yamanaka; Tsuyoshi Okamura; Hiroki Inagaki; Kae Ito; Shuichi AwataGeriatrics & Gerontology International Wiley 19 (6) 487 - 491 1444-1586 2019/06 [Refereed]
- Tsuyoshi Okamura; Chiaki Ura; Sachiko Yamazaki; Masaya Shimmei; Keisuke Torishima; Yu KawamuroInternational journal of geriatric psychiatry 34 (5) 777 - 778 2019/05 [Refereed]
- 認知症の人を包摂し、共生する基盤としての福祉と農業の融合 我が国の「農福連携」政策を対人援助サービスの視点から紐解く新名 正弥; 宇良 千秋; 岡村 毅; 山崎 幸子日本認知症ケア学会誌 (一社)日本認知症ケア学会 18 (1) 345 - 345 1882-0255 2019/04 [Refereed]
- Murayama H; Sugiyama M; Inagaki H; Edahiro A; Okamura T; Ura C; Miyamae F; Motokawa K; Awata SArchives of Gerontology & Geriatrics 87 103894 - 103894 2019 [Refereed]
- 我が国のホームレス研究の現状と展望 - 精神医学の視点から -岡村 毅最新精神医学 2019 [Invited]
- 都市の単身・独居・無縁・低所得高齢者を支える研究岡村 毅自殺予防と危機介入 2019 [Invited]
- Shiho Toishiba Masaya; Shimmei Yukan; Ogawa Akinori; Takase Kojun; Hayashida Tsuyoshi Okamura; Shuich AwataGeriatrics & Gerontology International 19 (4) 364 - 365 2019 [Refereed]
- Matoba Y; Okamura T; Funaki Y; Ishigami T; Awata S; Takeshima TPsychogeriatrics 19 (3) 286 - 288 2019 [Refereed]
- Wakeda T; Okamura T; Kawahara T; Heike YTumori Journal 106 (2) 95 - 100 2019 [Refereed]
- Hiroshi Murayama; Mika Sugiyama; Hiroki Inagaki; Tsuyoshi Okamura; Fumiko Miyamae; Chiaki Ura; Ayako Edahiro; Keiko Motokawa; Shuichi AwataGeriatrics & gerontology international 18 (11) 1537 - 1542 2018/11 [Refereed]
- Tsuyoshi Okamura; Chiaki Ura; Fumiko Miyamae; Mika Sugiyama; Hiroki Inagaki; Edahiro Ayako; Murayama Hiroshi; Keiko Motokawa; Shuichi AwataGeriatrics & gerontology international 18 (11) 1567 - 1572 2018/11 [Refereed]
- Tsuyoshi Okamura; Chiaki Ura; Fumiko Miyamae; Mika Sugiyama; Hiroki Inagaki; Ayako Edahiro; Hiroshi Murayama; Keiko Motokawa; Shuichi AwataInternational journal of geriatric psychiatry 33 (5) 798 - 799 2018/05 [Refereed]
- 高齢者ケアにおける仏教者に対するニーズ調査 超高齢多死社会の終末期ケアに関する新たな研究枠組み高瀬 顕功; 小川 有閑; 新名 正弥; 問芝 志保; 岡村 毅; 今井 幸充日本認知症ケア学会誌 (一社)日本認知症ケア学会 17 (1) 208 - 208 1882-0255 2018/04
- Chiaki Ura; Tsuyoshi Okamura; Sachiko Yamazaki; Taichi Ishiguro; Masumi Ibe; Mayako Miyazaki; Yu KawamuroInternational journal of geriatric psychiatry 33 (2) 435 - 437 2018/02 [Refereed]
- 宗教者と医療者の協働の可能性―医療者の立場から―岡村 毅宗教研究 91 93 - 94 2018
- Chiaki Ura; Tsuyoshi Okamura; Sachiko Yamazaki; Taichi Ishiguro; Masumi Ibe; Mayako Miyazaki; Keisuke Torishima; Yu KawamuroNihon Ronen Igakkai zasshi. Japanese journal of geriatrics 55 (1) 106 - 116 2018 [Refereed]
- 貧困、孤独、絶望にある人の終末期を支える岡村 毅; 川室 優精神科 32 (2) 106 - 110 2018 [Invited]
- Okamura T; Shimmei M; Takase A; Toishiba S; Hayashida K; Yumiyama T; Ogawa YPLoS ONE 13 (8) e0202277 2018 [Refereed]
- Kanako Ikeya; Jun-Ichi Aoki; Noriko Ikeda; Tsuneki Ninomiya; Takao Tashiro; Tsuyoshi Okamura; Jun-Ichi SuzukiGeriatrics and Gerontology International Blackwell Publishing 18 (1) 188 - 190 1447-0594 2018/01 [Refereed]
- 過量服薬による救命救急センター入院患者への精神科介入と再入院の関連金原 明子; 山名 隼人; 康永 秀生; 松居 宏樹; 安藤 俊太郎; 岡村 毅; 熊倉 陽介; 伏見 清秀; 笠井 清登総合病院精神医学 (一社)日本総合病院精神医学会 29 (Suppl.) S - 101 0915-5872 2017/11
- 岡村 毅; 粟田 主一刑政 矯正協会 128 (9) 12 - 25 0287-4628 2017/09 [Invited]
- Hirotoshi Niikawa; Tsuyoshi Okamura; Kae Ito; Chiaki Ura; Fumiko Miyamae; Naoko Sakuma; Mutsuo Ijuin; Hiroki Inagaki; Mika Sugiyama; Shuichi AwataGERIATRICS & GERONTOLOGY INTERNATIONAL 17 (9) 1286 - 1293 1444-1586 2017/09 [Refereed]
- 岡村 毅; 熊倉 陽介; 宮脇 護; 津田 多佳子; 鈴木 剛; 明田 久美子; 高瀬 顕功; 小川 有閑; 島薗 進; 笠井 清登日本社会精神医学会雑誌 (一社)日本社会精神医学会 26 (3) 256 - 256 0919-1372 2017/08
- Naoko Sakuma; Chiaki Ura; Fumiko Miyamae; Hiroki Inagaki; Kae Ito; Hirotoshi Niikawa; Mutsuo Ijuin; Tsuyoshi Okamura; Mika Sugiyama; Shuichi AwataINTERNATIONAL JOURNAL OF GERIATRIC PSYCHIATRY 32 (7) 718 - 725 0885-6230 2017/07 [Refereed]
- Tsuyoshi Okamura; Shuichi Awata; Kae Ito; Ken Takiwaki; Yuki Matoba; Hirotoshi Niikawa; Hisateru Tachimori; Tadashi TakeshimaPSYCHOGERIATRICS 17 (3) 206 - 207 1346-3500 2017/05 [Refereed]
- Tatsushi Yokoyama; Tsuyoshi Okamura; Miwako Takahashi; Toshimitsu Momose; Shinsuke KondoBMC PSYCHIATRY 17 (1) 150 - 150 1471-244X 2017/04 [Refereed]
- 宮前 史子; 宇良 千秋; 佐久間 尚子; 新川 祐利; 稲垣 宏樹; 伊集院 睦雄; 岡村 毅; 杉山 美香; 粟田 主一日本老年医学会雑誌 (一社)日本老年医学会 53 (4) 354 - 362 0300-9173 2016/10 [Refereed]
- Tsuyoshi Okamura; Chiaki Ura; Fumiko Miyamae; Mika Sugiyama; Hirotoshi Niikawa; Kae Ito; Shuichi AwataPSYCHOGERIATRICS 16 (3) 196 - 201 1346-3500 2016/05 [Refereed]
- Shuichi Awata; Mika Sugiyama; Kae Ito; Chiaki Ura; Fumiko Miyamae; Naoko Sakuma; Hirotoshi Niikawa; Tsuyoshi Okamura; Hiroki Inagaki; Mutsuo IjuinGERIATRICS & GERONTOLOGY INTERNATIONAL 16 (Supp) 123 - 131 1444-1586 2016/03 [Refereed]
- Tsuyoshi Okamura; Kae Ito; Chiaki Ura; Fumiko Miyamae; Hirotoshi Niikawa; Shuichi AwataGERIATRICS & GERONTOLOGY INTERNATIONAL 16 (3) 398 - 399 1444-1586 2016/03 [Refereed]
- Fumiko Miyamae; Chiaki Ura; Naoko Sakuma; Hirotoshi Niikawa; Hiroki Inagaki; Mutsuo Ijuin; Tsuyoshi Okamura; Mika Sugiyama; Shuichi AwataNihon Ronen Igakkai zasshi. Japanese journal of geriatrics 53 (4) 354 - 362 0300-9173 2016
- フレイルと貧困岡村毅; 的場由木老年精神医学雑誌 27 521 - 527 2016 [Invited]
- ホームレス支援における当事者中心の支援論岡村毅; 的場由木精神療法 42 (6) 818 - 825 2016 [Invited]
- Tsuyoshi Okamura; Tadashi Takeshima; Hisateru Tachimori; Ken Takiwaki; Yuki Matoba; Shuichi AwataPSYCHIATRIC SERVICES 66 (12) 1290 - 1295 1075-2730 2015/12 [Refereed]
- Akiko Kanehara; Hayato Yamana; Hideo Yasunaga; Hiroki Matsui; Shuntaro Ando; Tsuyoshi Okamura; Yousuke Kumakura; Kiyohide Fushimi; Kiyoto KasaiBJPsych open 1 (2) 158 - 163 2056-4724 2015/10 [Refereed]
- Chiaki Ura; Fumiko Miyamae; Naoko Sakuma; Hirotoshi Niikawa; Hiroki Inagaki; Mutsuo Ijuin; Kae Ito; Tsuyoshi Okamura; Mika Sugiyama; Shuichi AwataNihon Ronen Igakkai zasshi. Japanese journal of geriatrics (一社)日本老年医学会 52 (3) 243 - 253 0300-9173 2015/07 [Refereed]
- 粟田 主一; 杉山 美香; 井藤 佳恵; 宇良 千秋; 宮前 史子; 佐久間 尚子; 新川 祐利; 岡村 毅; 稲垣 宏樹; 伊集院 睦雄老年精神医学雑誌 (株)ワールドプランニング 26 (6) 675 - 686 0915-6305 2015/06 [Refereed]
- 杉山 美香; 伊集院 睦雄; 佐久間 尚子; 宮前 史子; 井藤 佳恵; 宇良 千秋; 稲垣 宏樹; 岡村 毅; 矢冨 直美; 山口 晴保; 藤原 佳典; 高橋 龍太郎; 粟田 主一老年精神医学雑誌 (株)ワールドプランニング 26 (2) 183 - 195 0915-6305 2015/02
- 井藤 佳恵; 佐久間 尚子; 伊集院 睦雄; 稲垣 宏樹; 宇良 千秋; 宮前 史子; 杉山 美香; 岡村 毅; 新川 祐利; 粟田 主一; 松下 正明生存科学 (公財)生存科学研究所 25 (1) 173 - 185 0917-0138 2014/09
- Tsuyoshi Okamura; Kae Ito; Suimei Morikawa; Shuichi AwataSOCIAL PSYCHIATRY AND PSYCHIATRIC EPIDEMIOLOGY 49 (4) 573 - 582 0933-7954 2014/04 [Refereed]
- Kae Ito; Suimei Morikawa; Tsuyoshi Okamura; Kentaro Shimokado; Shuichi AwataPSYCHIATRY AND CLINICAL NEUROSCIENCES 68 (2) 145 - 153 1323-1316 2014/02 [Refereed]
- Tsuyoshi Okamura; Hitomi Arai; Masaomi Furukaw; Osamu Tanaka; Masuhiro Hosoda; Sayaka Nakajima; Kou Furuta; Kae Ito; Shuichi Awata; Masaaki MatsushitaActivitas Nervosa Superior Neuroscientia o.s. 56 (4) 135 - 139 1802-9698 2014 [Refereed]
- Inagaki H; Ito K; Sakuma N; Sugiyama M; Okamura T; Awata S[Nihon koshu eisei zasshi] Japanese journal of public health 60 (5) 294 - 301 0546-1766 2013/05 [Refereed]
- 稲垣宏樹; 井藤佳恵; 佐久間尚子; 杉山美香; 岡村毅; 粟田主一日本公衆衛生雑誌 60 (5) 294 - 301 2013 [Refereed]
- 生活困窮者の自殺とその予防粟田主一; 井藤佳恵; 岡村毅; 森川すいめい; 的場由木; 竹島正精神神経学雑誌 2013
- 単身生活者の実態と支援ニーズを把握するための調査瀧脇憲; 竹島正; 立森久照; 岡村毅; 的場由木貧困研究 11 2013 [Refereed]
- Kae Ito; Hiroki Inagaki; Mika Sugiyama; Tsuyoshi Okamura; Kentaro Shimokado; Shuichi AwataGERIATRICS & GERONTOLOGY INTERNATIONAL 13 (1) 234 - 235 1444-1586 2013/01 [Refereed]
- Okamura T; Ito K; Konno M; Inagaki H; Sugiyama M; Sakuma N; Awata S[Nihon koshu eisei zasshi] Japanese journal of public health 59 (9) 675 - 683 0546-1766 2012/09 [Refereed]
- 日野原 重明; 中村 洋子; 大串 佐江子; 奥 知子; 三瀬 麻紀子; 池畑 克江; 荻原 美智恵; 岩永 妙子; 高橋 淳; 高瀬 義昌; 武藤 初恵; 中嶋 恵子; 木下 朋雄; 井藤 佳恵; 岡村 毅; 佐野 けさ美; 小林 正宏コミュニティケア (株)日本看護協会出版会 14 (6) 68 - 71 2012/06
- 都市在住生活困窮者の自殺関連行動の分布と関連要因の検討岡村 毅; 森川 すいめい; 井藤 佳恵; 栗田 主一精神神経学雑誌 (公社)日本精神神経学会 (2012特別) S - 556 0033-2658 2012/05
- Kae Ito; Hiroki Inagaki; Tsuyoshi Okamura; Shuichi Awata; Kae Ito; Kentaro Shimokado; Tsuyoshi Okamura; Tsuyoshi OkamuraJapanese Journal of Geriatrics 49 (1) 82 - 89 0300-9173 2012 [Refereed]
- Kae Ito; Hiroki Inagaki; Tsuyoshi Okamura; Shuichi Awata; Kae Ito; Kentaro Shimokado; Tsuyoshi Okamura; Tsuyoshi OkamuraJapanese Journal of Geriatrics 49 (1) 82 - 89 0300-9173 2012 [Refereed]
- 岡村毅; 杉下和行; 荒井仁美; 田中修; 細田益宏; 古田光; 井藤佳恵; 粟田主一; 松田博史; 松下正明精神医学 (株)医学書院 54 (8) 811 - 817 0488-1281 2012 [Refereed]
- 岡村毅; 松原全宏; 笠井清登; 粟田主一老年精神医学雑誌 ワールドプランニング 23 (11) 1323 - 1328 0915-6305 2012
- Okamura T; Awata SNihon rinsho. Japanese journal of clinical medicine 69 Suppl 10 Pt 2 59 - 63 0047-1852 2011/12 [Refereed]
- 岡村毅; 荒井仁美; 古川賢臣; 田中修; 細田益弘; 中島さやか; 古田光; 井藤佳恵; 粟田主一; 松下正明老年精神医学雑誌 (株)ワールドプランニング 22 (6) 734 - 739 0915-6305 2011 [Refereed]
- せん妄と認知症岡村毅; 粟田主一診断と治療 99 (6) 969 - 973 2011
- Hiroyuki Tamiya; Tsuyoshi Okamura; Norichika Iwashiro; Kazuma Ishiki; Hidenori Yamasue; Kiyoto KasaiPSYCHIATRY AND CLINICAL NEUROSCIENCES 65 (5) 536 - 537 1323-1316 2011 [Refereed]
- Tsuyoshi Okamura; Kazue Isoya; Masuhiro HosodaPrimary Care Companion to the Journal of Clinical Psychiatry 13 (5) 1523-5998 2011 [Refereed]
- 双極性障害様の症状・経過を呈した高カルシウム血症の1例田宮 寛之; 岡村 毅; 岩白 訓周; 伊敷 一馬; 山末 英典; 笠井 清登精神神経学雑誌 (公社)日本精神神経学会 112 (9) 945 - 946 0033-2658 2010/09 [Refereed]
- 急激に発症し、入院中は診断がつかず退院後に診断がついた認知機能障害の1例岡村 毅; 西山 潤; 音羽 健司; 斎藤 正彦; 笠井 清登精神神経学雑誌 (公社)日本精神神経学会 111 (5) 601 - 601 0033-2658 2009/05
- T Kamura; K Kudo; N Sata; T Sameshima; N Doi; N KatoJOURNAL OF ECT 22 (2) 148 - 149 1095-0680 2006/06 [Refereed]
MISC
- 岡村毅; 宇良千秋; 枝広あや子; 高瀬顕功; 郷堀ヨゼフ; ティムグラフ; 島薗進; 小川有閑 老年精神医学雑誌 35- 2024
- 中山莉子; 中山莉子; 櫻井花; 櫻井花; 杉山美香; 見城澄子; 釘宮由紀子; 岡村睦子; 多賀努; 宮前史子; 岡村毅; 粟田主一 日本認知症ケア学会誌 23- (1) 2024
- 杉山美香; 宮前史子; 中山莉子; 枝広あや子; 井藤佳恵; 櫻井花; 多賀努; 宇良千秋; 岡村毅; 粟田主一 日本認知症ケア学会誌 23- (1) 2024
- 見城澄子; 中山莉子; 中山莉子; 枝広あや子; 岡村毅; 宇良千秋 認知症ケア事例ジャーナル 16- (4) 2024
- 中山莉子; 中山莉子; 枝広あや子; 岡村毅 認知症ケア事例ジャーナル 16- (3) 2023
- 岡村毅; 小川有閑; 高瀬顕功; 新名正弥; 問芝志保; 林田康順 老年精神医学雑誌 31- 2020
- 若年性認知症の診断後支援のあり方に関する検討 東京都若年性認知症の有病率及び生活実態に関する調査の経過報告多賀 努; 枝広 あや子; 杉山 美香; 岡村 毅; 宮前 史子; 山村 正子; 菊地 和則; 粟田 主一 老年精神医学雑誌 30- (増刊II) 187 -187 2019/06
- 認知症疾患医療センターにおける若年性認知症の年間鑑別診断数と発生率の検討枝広 あや子; 杉山 美香; 多賀 努; 山村 正子; 宮前 史子; 岡村 毅; 菊地 和則; 粟田 主一 老年精神医学雑誌 30- (増刊II) 202 -202 2019/06
- 高島平studyにおける会場健診参加者の2年後の追跡 MMSE-J得点の変化佐久間 尚子; 稲垣 宏樹; 本川 佳子; 渡邊 裕; 枝広 あや子; 宇良 千秋; 小川 まどか; 杉山 美香; 宮前 史子; 岡村 毅; 新開 省二; 粟田 主一 老年精神医学雑誌 30- (増刊II) 208 -208 2019/06
- 高島平studyにおける会場健診参加者の2年後の追跡 認知機能低下と社会的孤立との関連稲垣 宏樹; 佐久間 尚子; 本川 佳子; 渡邊 裕; 枝広 あや子; 宇良 千秋; 小川 まどか; 杉山 美香; 宮前 史子; 岡村 毅; 新開 省二; 粟田 主一 老年精神医学雑誌 30- (増刊II) 209 -209 2019/06
- 地域在住高齢者の認知機能低下と日常生活支援ニーズ杉山 美香; 宮前 史子; 佐久間 尚子; 稲垣 宏樹; 宇良 千秋; 小川 まどか; 枝広 あや子; 岡村 毅; 粟田 主一 老年精神医学雑誌 30- (増刊II) 217 -217 2019/06
- 介護保険第2号被保険者データを用いた若年性認知症の状態像に関する研究菊地 和則; 中西 亜紀; 小長谷 陽子; 多賀 努; 枝広 あや子; 杉山 美香; 岡村 毅; 宮前 史子; 山村 正子; 粟田 主一 老年精神医学雑誌 30- (増刊II) 224 -224 2019/06
- 権利ベースのアプローチによる認知症支援の担い手育成の効果の検証小川 まどか; 稲垣 宏樹; 宇良 千秋; 杉山 美香; 宮前 史子; 岡村 毅; 枝広 あや子; 釘宮 由紀子; 森倉 三男; 岡村 睦子; 粟田 主一 老年精神医学雑誌 30- (増刊II) 228 -228 2019/06
- 高島平スタディ 認知症支援のための地域拠点における医療・保健・心理相談 高島平ココからステーションの実践杉山 美香; 岡村 毅; 枝広 あや子; 宮前 史子; 小川 まどか; 稲垣 宏樹; 宇良 千秋; 釘宮 由紀子; 森倉 三男; 岡村 睦子; 粟田 主一 日本認知症ケア学会誌 18- (1) 181 -181 2019/04
- 高島平スタディ 医療を受けるための支援 医師が地域相談をして分かったこと岡村 毅; 杉山 美香; 小川 まどか; 稲垣 宏樹; 宇良 千秋; 宮前 史子; 枝広 あや子; 釘宮 由紀子; 岡村 睦子; 森倉 三男; 粟田 主一 日本認知症ケア学会誌 18- (1) 181 -181 2019/04
- 高島平スタディ 地域拠点における歯科相談 歯の相談から生まれる生活の希望枝広 あや子; 釘宮 由紀子; 森倉 三男; 岡村 睦子; 杉山 美香; 岡村 毅; 小川 まどか; 宮前 史子; 稲垣 宏樹; 宇良 千秋; 粟田 主一 日本認知症ケア学会誌 18- (1) 182 -182 2019/04
- ソーシャルキャピタルと認知機能低下者割合の地域相関分析 Dementia Friendly Communitiesに向けた定量的検証村山 洋史; 宇良 千秋; 宮前 史子; 佐久間 尚子; 杉山 美香; 稲垣 宏樹; 岡村 毅; 新川 祐利; 粟田 主一 日本認知症ケア学会誌 18- (1) 215 -215 2019/04
- 小川有閑; 新名正弥; 高瀬顕功; 問芝志保; 弓山達也; 林田康順; 東海林良昌; 宇良千秋; 岡村毅 老年精神医学雑誌 30- 2019
- 認知症治療はどこまで進んでいるか―エビデンスからの検証岡村 毅 医事新報 2019
- 稲垣宏樹; 杉山美香; 宇良千秋; 宮前史子; 枝広あや子; 岡村毅; 本川佳子; 村山洋史; 粟田主一 日本公衆衛生学会総会抄録集 77th- 420 -420 2018/10
- 大都市に暮らす高齢者の認知機能低下と身体・口腔機能低下との関連 高島平スタディ枝広 あや子; 稲垣 宏樹; 宇良 千秋; 岡村 毅; 小川 まどか; 佐久間 尚子; 杉山 美香; 新川 祐利; 宮前 史子; 鈴木 宏幸; 白部 麻樹; 本川 佳子; 渡邊 裕; 金 憲経; 粟田 主一 老年精神医学雑誌 29- (増刊II) 195 -195 2018/06
- 大都市に暮らす認知症高齢者の実態調査(その1) 高島平スタディ 診断へのアクセスと社会支援ニーズ宇良 千秋; 岡村 毅; 稲垣 宏樹; 小川 まどか; 新川 祐利; 枝広 あや子; 杉山 美香; 宮前 史子; 佐久間 尚子; 古田 光; 畠山 啓; 扇澤 史子; 金野 倫子; 鈴木 貴浩; 粟田 主一 老年精神医学雑誌 29- (増刊II) 210 -210 2018/06
- 杉山美香; 岡村毅; 釘宮由紀子; 宮前史子; 小川まどか; 枝広あや子; 稲垣宏樹; 宇良千秋; 森倉三男; 新川祐利; 岡村睦子; 佐久間尚子; 粟田主一 老年精神医学雑誌 29- (増刊II) 211 -211 2018/06
- 稲垣宏樹; 宇良千秋; 枝広あや子; 岡村毅; 小川まどか; 佐久間尚子; 杉山美香; 鈴木宏幸; 新川祐利; 宮前史子; 渡邊裕; 金憲経; 粟田主一 老年精神医学雑誌 29- (増刊II) 213 -213 2018/06
- 宇良千秋; 岡村毅; 稲垣宏樹; 小川まどか; 新川祐利; 枝広あや子; 杉山美香; 宮前史子; 佐久間尚子; 古田光; 畠山啓; 扇澤史子; 金野倫子; 鈴木貴浩; 粟田主一 老年精神医学雑誌 29- (増刊II) 210 -210 2018/06
- 枝広あや子; 稲垣宏樹; 宇良千秋; 岡村毅; 小川まどか; 佐久間尚子; 杉山美香; 新川祐利; 宮前史子; 鈴木宏幸; 白部麻樹; 本川佳子; 渡邉裕; 金憲経; 粟田主一 老年精神医学雑誌 29- (増刊II) 195 -195 2018/06
- 新川祐利; 岡村毅; 宇良千秋; 宮前史子; 佐久間尚子; 稲垣宏樹; 杉山美香; 小川まどか; 枝広あや子; 粟田主一 老年精神医学雑誌 29- (増刊II) 195 -195 2018/06
- 宮前史子; 杉山美香; 稲垣宏樹; 小川まどか; 宇良千秋; 岡村毅; 枝広あや子; 佐久間尚子; 新川祐利; 粟田主一 老年精神医学雑誌 29- (増刊II) 212 -212 2018/06
- 小川まどか; 稲垣宏樹; 宇良千秋; 杉山美香; 宮前史子; 釘宮由紀子; 枝広あや子; 岡村毅; 佐久間尚子; 粟田主一 老年精神医学雑誌 29- (増刊II) 212 -212 2018/06
- 岡村毅; 宇良千秋; 杉山美香; 稲垣宏樹; 小川まどか; 枝広あや子; 宮前史子; 新川祐利; 釘宮由紀子; 岡村睦子; 加藤徳子; 粟田主一 老年精神医学雑誌 29- (増刊II) 211 -211 2018/06
- 飯塚あい; 鈴木宏幸; 小川将; 稲垣宏樹; 宇良千秋; 杉山美香; 小川まどか; 岡村毅; 粟田主一; 藤原佳典 日本老年医学会雑誌 55- (Suppl.) 92 -92 2018/05
- 囲碁を活用した認知機能低下抑制プログラムの評価 知的活動頻度による介入効果の検討飯塚 あい; 鈴木 宏幸; 小川 将; 稲垣 宏樹; 宇良 千秋; 杉山 美香; 小川 まどか; 岡村 毅; 粟田 主一; 藤原 佳典 日本老年医学会雑誌 55- (Suppl.) 92 -92 2018/05
- 岡村 毅; 杉山 美香; 宇良 千秋; 稲垣 宏樹; 宮前 史子; 村山 洋史; 枝広 あや子; 本川 佳子; 粟田 主一 日本老年医学会雑誌 55- (Suppl.) 163 -164 2018/05
- 宇良 千秋; 杉山 美香; 稲垣 宏樹; 枝広 あや子; 本川 佳子; 宮前 史子; 岡村 毅; 村山 洋史; 粟田 主一 日本老年医学会雑誌 55- (Suppl.) 168 -169 2018/05
- 岡村 毅; 杉山 美香; 宇良 千秋; 稲垣 宏樹; 宮前 史子; 村山 洋史; 枝広 あや子; 本川 佳子; 粟田 主一 日本老年医学会雑誌 55- (Suppl.) 163 -164 2018/05
- 宇良 千秋; 杉山 美香; 稲垣 宏樹; 枝広 あや子; 本川 佳子; 宮前 史子; 岡村 毅; 村山 洋史; 粟田 主一 日本老年医学会雑誌 55- (Suppl.) 168 -169 2018/05
- 住まいを失った生活困窮高齢者の特徴 社会的背景および身体・精神的健康岡村 毅; 的場 由木; 井藤 佳恵; 粟田 主一 日本認知症ケア学会誌 17- (1) 228 -228 2018/04
- 社会的文脈からみた認知症高齢者の支援の課題岡村 毅 認知症の最新医療 8- 127 -132 2018
- 複雑化する援助希求と行政職員が直面する課題-質問紙調査による困難事例の探索-岡村 毅 精神保健政策研究 26- 2018
- 枝広あや子; 杉山美香; 稲垣宏樹; 小川まどか; 宇良千秋; 佐久間尚子; 宮前史子; 本川佳子; 本橋佳子; 渡邊裕; 岡村毅; 金憲経; 新開省二; 粟田主一 日本公衆衛生学会総会抄録集 76th- 398 -398 2017/10
- 杉山美香; 宮前史子; 佐久間尚子; 稲垣宏樹; 宇良千秋; 小川まどか; 枝広あや子; 本川佳子; 岡村毅; 渡邊裕; 金憲経; 新開省二; 粟田主一 日本公衆衛生学会総会抄録集 76th- 398 -398 2017/10
- 枝広 あや子; 本川 佳子; 白部 麻樹; 小原 由紀; 杉山 美香; 稲垣 宏樹; 宇良 千秋; 宮前 史子; 岡村 毅; 村山 洋史; 大渕 修一; 藤原 佳典; 金 憲経; 井原 一成; 河合 恒; 渡邊 裕; 平野 浩彦; 粟田 主一 日本サルコペニア・フレイル学会雑誌 1- (2) 96 -96 2017/10
- 岡村 毅; 宇良 千秋; 宮前 史子; 杉山 美香; 稲垣 宏樹; 枝広 あや子; 本川 佳子; 村山 洋史; 粟田 主一 老年精神医学雑誌 28- (増刊II) 221 -221 2017/06
- 認知症の人の社会参加を促す稲作ケアの試み 認知症ケアのパラダイムシフトを目指して宇良 千秋; 岡村 毅; 山崎 幸子; 石黒 太一; 宮崎 眞也子; 井部 真澄; 久保田 あゆみ; 鳥島 佳祐; 粟田 主一; 川室 優 日本認知症ケア学会誌 16- (1) 348 -348 2017/04
- 与えるサポートと受けるサポートはどちらがこころの健康に有用か 都市部地域在住高齢者の調査から岡村 毅; 宇良 千秋; 宮前 史子; 杉山 美香; 稲垣 宏樹; 枝広 あや子; 本川 佳子; 村山 洋史; 粟田 主一 日本認知症ケア学会誌 16- (1) 203 -203 2017/04
- 岡村毅; 岡村毅; 岡村毅; 岡村毅; 熊倉陽介; 宮脇護; 津田多佳子; 鈴木剛; 明田久美子; 高瀬顕功; 小川有閑; 島薗進; 笠井清登 日本社会精神医学会雑誌 26- (3) 2017
- 双極性障害の過剰診断と過剰治療岡村 毅 精神科治療学 32- 1299 -1303 2017 [Invited]
- 高齢者の日中の眠気岡村 毅 Pharma Medica 2017 [Invited]
- 精神科医から見たホームレスの現状岡村 毅 こころと社会 48- (2) 117 -123 2017 [Invited]
- 過量服薬による救命救急センター入院患者への精神科介入と再入院の関連金原 明子; 山名 隼人; 康永 秀生; 松居 宏樹; 安藤 俊太郎; 岡村 毅; 熊倉 陽介; 伏見 清秀; 笠井 清登 総合病院精神医学 28- (4) 345 -352 2016/10
- 主観的口腔機能評価には認知機能低下とうつ傾向が関係するか?枝広 あや子; 杉山 美香; 稲垣 宏樹; 村山 洋史; 岡村 毅; 本川 佳子; 平野 浩彦; 粟田 主一 日本公衆衛生学会総会抄録集 75回- 494 -494 2016/10
- 岡村 毅; 粟田 主一; 井藤 佳恵; 瀧脇 憲; 的場 由木; 立森 久照; 竹島 正 日本社会精神医学会雑誌 25- (3) 251 -252 2016/08
- 佐久間尚子; 宇良千秋; 宮前史子; 宮前史子; 新川祐利; 新川祐利; 稲垣宏樹; 井藤佳恵; 伊集院睦雄; 伊集院睦雄; 岡村毅; 岡村毅; 杉山美香; 粟田主一 老年精神医学雑誌 27- (増刊II) 244 -244 2016/06
- 杉山 美香; 宇良 千秋; 稲垣 宏樹; 宮前 史子; 村山 洋史; 枝広 あや子; 岡村 毅; 本川 佳子; 粟田 主一 老年精神医学雑誌 27- (増刊II) 273 -273 2016/06
- 本川 佳子; 枝広 あや子; 杉山 美香; 稲垣 宏樹; 宇良 千秋; 宮前 史子; 岡村 毅; 村山 洋史; 平野 浩彦; 粟田 主一 日本老年医学会雑誌 53- (Suppl.) 167 -167 2016/05
- 認知症アセスメントシート(DASC-21)における認知症疑いの関連要因について宇良 千秋; 宮前 史子; 佐久間 尚子; 新川 祐利; 稲垣 宏樹; 杉山 美香; 井藤 佳恵; 伊集院 睦雄; 岡村 毅; 粟田 主一 日本認知症ケア学会誌 15- (1) 180 -180 2016/04
- 地域レベルのソーシャルキャピタルは認知症への不安感と関連するか? 都市部在住高齢者での検討村山 洋史; 杉山 美香; 稲垣 宏樹; 宇良 千秋; 宮前 史子; 枝広 あや子; 岡村 毅; 本川 佳子; 粟田 主一 日本認知症ケア学会誌 15- (1) 294 -294 2016/04
- 警告うつ病岡村 毅 精神医学症候群 560 -563 2016 [Invited]
- M. Sugiyama; M. Ijuin; K. Ito; N. Sakuma; H. Inagaki; F. Miyamae; T. Okamura; S. Awata GERONTOLOGIST 55- 189 -189 2015/11
- 扇澤 史子; 粟田 主一; 古田 光; 岡本 一枝; 白取 絹恵; 畠山 啓; 今村 陽子; 市川 幸子; 齋藤 久美子; 井藤 佳恵; 須田 潔子; 菊地 幸子; 岡村 毅; 萩原 寛子; 福島 康浩; 竹部 裕香; 松下 正明 生存科学 26- (1) 233 -242 2015/09
- 困窮者支援NPO法人における精神疾患を持つものの支援実態の把握の試み的場 由木; 石神 朋敏; 船木 友里恵; 岡村 毅; 粟田 主一; 竹島 正 日本社会精神医学会雑誌 24- (3) 317 -318 2015/08
- 刑事施設等出所後に困窮者支援NPO法人の支援を受けたものの精神医学的検討岡村 毅; 船木 友里恵; 的場 由木; 石神 朋敏; 粟田 主一; 竹島 正 日本社会精神医学会雑誌 24- (3) 318 -318 2015/08
- 精神科病院退院後に困窮者支援NPO法人の支援を受けたものの精神医学的検討船木 友里恵; 的場 由木; 岡村 毅; 石神 朋敏; 粟田 主一; 竹島 正 日本社会精神医学会雑誌 24- (3) 318 -318 2015/08
- S. Awata; K. Ito; T. Okamura; H. Niikawa ASIA-PACIFIC PSYCHIATRY 7- 16 -16 2015/06
- 新井祐利; 新井祐利; 岡村毅; 井藤佳恵; 宇良千秋; 宮前史子; 佐久間尚子; 稲垣宏樹; 伊集院睦雄; 杉山美香; 粟田主一 日本精神神経学会総会プログラム・抄録集 111th- (2015特別) S594 -S594 2015/06
- 新川祐利; 宇良千秋; 宮前史子; 佐久間尚子; 稲垣宏樹; 井藤佳恵; 岡村毅; 杉山美香; 粟田主一 日本老年医学会雑誌 52- (Suppl.) 78 -78 2015/05
- 佐久間尚子; 宇良千秋; 宮前史子; 宮前史子; 新川祐利; 新川祐利; 稲垣宏樹; 伊集院睦雄; 井藤佳恵; 岡村毅; 岡村毅; 杉山美香; 粟田主一 老年精神医学雑誌 26- (増刊II) 193 -193 2015/05
- 扇澤 史子; 古田 光; 岡本 一枝; 今村 陽子; 白取 絹恵; 畠山 啓; 齋藤 久美子; 千田 亜希子; 佐々木 優子; 井藤 佳恵; 須田 潔子; 菊地 幸子; 岡村 毅; 萩原 寛子; 福島 康浩; 粟田 主一 老年精神医学雑誌 26- (増刊II) 182 -182 2015/05
- 岡本 一枝; 古田 光; 扇澤 史子; 今村 陽子; 市川 幸子; 須田 潔子; 菊地 幸子; 萩原 寛子; 福島 康浩; 三瀬 耕平; 筒井 啓太; 井藤 佳恵; 岡村 毅; 粟田 主一 老年精神医学雑誌 26- (増刊II) 200 -200 2015/05
- 認知症アセスメントシート(DASC)における自己評価と他者評価の関連性について宇良 千秋; 宮前 史子; 佐久間 尚子; 新川 祐利; 稲垣 宏樹; 伊集院 睦雄; 井藤 佳恵; 岡村 毅; 杉山 美香; 粟田 主一 日本認知症ケア学会誌 14- (1) 312 -312 2015/04
- 岡村毅; 宇良千秋; 宮前史子; 井藤佳恵; 新川祐利; 粟田主一 日本社会精神医学会プログラム・抄録集 34th- (3) 100 -322 2015
- C. Ura; F. Miyamae; N. Sakuma; H. Niikawa; K. Ito; T. Okamura; S. Awata GERONTOLOGIST 54- 198 -198 2014/11
- 扇澤 史子; 古田 光; 岡本 一枝; 白取 絹恵; 畠山 啓; 今村 陽子; 市川 幸子; 齋藤 久美子; 須田 潔子; 菊地 幸子; 萩原 寛子; 三瀬 耕平; 福島 康浩; 竹部 裕香; 粟田 主一; 井藤 佳恵; 岡村 毅; 松下 正明 生存科学 25- (1) 187 -194 2014/09
- 高齢生活困窮者における認知機能岡村 毅; 新川 祐利; 井藤 佳恵; 粟田 主一 精神神経学雑誌 (2014特別) S393 -S393 2014/06
- 岡村毅; 宇良千秋; 宮前史子; 佐久間尚子; 稲垣宏樹; 伊集院睦雄; 井藤佳恵; 新川祐利; 杉山美香; 粟田主一 老年精神医学雑誌 25- (増刊II) 210 -210 2014/05
- 稲垣宏樹; 宇良千秋; 宮前史子; 佐久間尚子; 新川祐利; 井藤佳恵; 伊集院睦雄; 岡村毅; 杉山美香; 粟田主一 老年精神医学雑誌 25- (増刊II) 180 -180 2014/05
- 新川祐利; 宇良千秋; 宮前史子; 佐久間尚子; 稲垣宏樹; 伊集院睦雄; 井藤佳恵; 岡村毅; 杉山美香; 粟田主一 老年精神医学雑誌 25- (増刊II) 181 -181 2014/05
- 扇澤 史子; 古田 光; 磯谷 一枝; 白取 絹恵; 畠山 啓; 齋藤 久美子; 今村 陽子; 井藤 佳恵; 須田 潔子; 菊地 幸子; 岡村 毅; 田中 修; 萩原 寛子; 三瀬 耕平; 福島 康浩; 粟田 主一 老年精神医学雑誌 25- (増刊II) 190 -190 2014/05
- 自記式認知症チェックシートの開発 因子分析および項目反応理論を用いた尺度項目案の検討宇良 千秋; 宮前 史子; 佐久間 尚子; 新川 祐利; 稲垣 宏樹; 伊集院 睦雄; 井藤 佳恵; 岡村 毅; 杉山 美香; 粟田 主一 日本認知症ケア学会誌 13- (1) 242 -242 2014/04
- 自記式認知症チェックシートの開発 信頼性・妥当性の検討宮前 史子; 宇良 千秋; 佐久間 尚子; 新川 祐利; 稲垣 宏樹; 伊集院 睦雄; 井藤 佳恵; 岡村 毅; 杉山 美香; 粟田 主一 日本認知症ケア学会誌 13- (1) 242 -242 2014/04
- 都市部高齢者専門病院の物忘れ外来初診患者の家族介護者における介護負担感とその要因 認知症アセスメントシートとソーシャルサポートに着目した検討扇澤 史子; 古田 光; 磯谷 一枝; 白取 絹恵; 畠山 啓; 齋藤 久美子; 菊地 ひろみ; 井藤 佳恵; 岡村 毅; 菊地 幸子; 粟田 主一 日本認知症ケア学会誌 13- (1) 329 -329 2014/04
- 竹島正; 西大輔; 立森久照; 臼田謙太郎; 後藤基行; 下田陽樹; 岡村毅; 金田一正史; 家原敏彰; 大澤日登美; 中村征人; 佐々木英司; 的場由木; 山田全啓 新たな地域精神保健医療体制の構築のための実態把握および活動の評価等に関する研究 平成25年度 総括・分担研究報告書 7 -16 2014
- 栗田主一; 宇良千秋; 宮前史子; 新川祐利; 佐久間尚子; 杉山美香; 井藤佳恵; 岡村毅; 伊集院睦雄; 稲垣宏樹; 岩佐一 認知症のケア及び看護技術に関する研究 平成25年度 総括・分担研究報告書 108 -114 2014
- 認知症の根本治療薬は、現時点では存在しない岡村 毅 治療 96- 468 -469 2014 [Invited]
- 今村 陽子; 扇澤 史子; 磯谷 一枝; 古田 光; 磯野 沙月; 大浪 里枝; 井藤 佳恵; 岡村 毅; 細田 益宏; 菊地 幸子; 田中 修; 中島 さやか; 粟田 主一 老年精神医学雑誌 24- (増刊II) 229 -229 2013/06
- 磯谷 一枝; 古田 光; 扇澤 史子; 白取 絹恵; 畠山 啓; 川口 東子; 井藤 佳恵; 岡村 毅; 菊地 幸子; 田中 修; 粟田 主一 老年精神医学雑誌 24- (増刊II) 259 -259 2013/06
- 扇澤 史子; 古田 光; 磯谷 一枝; 白取 絹恵; 畠山 啓; 川口 東子; 今村 陽子; 井藤 佳恵; 須田 潔子; 菊地 幸子; 岡村 毅; 田中 修; 大浪 里枝; 磯野 沙月; 粟田 主一 老年精神医学雑誌 24- (増刊II) 260 -260 2013/06
- 井藤佳恵; 稲垣宏樹; 杉山美香; 宮前史子; 宇良千秋; 佐久間尚子; 伊集院睦雄; 岡村毅; 下門顯太郎; 粟田主一 老年精神医学雑誌 24- (増刊II) 244 -244 2013/06
- 郵送による生活機能調査回答未返送後期高齢者を対象とした訪問調査井藤 佳恵; 稲垣 宏樹; 杉山 美香; 宮前 史子; 宇良 千秋; 佐久間 尚子; 伊集院 睦雄; 岡村 毅; 下門 顯太郎; 粟田 主一 日本老年医学会雑誌 50- (Suppl.) 129 -129 2013/05
- 訪問相談により認知症専門病棟に入院となった認知症高齢者の特徴須田 潔子; 三瀬 耕平; 福島 康浩; 菊池 幸子; 古田 光; 扇沢 史子; 磯谷 一枝; 筒井 啓太; 井上 悟; 岡村 毅; 井藤 佳恵; 粟田 主一; 松下 正明 精神神経学雑誌 (2013特別) S -401 2013/05
- アウトリーチ型認知症高齢者相談事業の対象となる困難事例の特徴井藤 佳恵; 佐々木 由香理; 櫻井 千絵; 原 美由紀; 水澤 佑太; 山田 志保; 小林 紀和; 松崎 尊信; 古田 光; 岡村 毅; 粟田 主一 精神神経学雑誌 (2013特別) S -558 2013/05
- 自殺関連行動の見られる生活困窮者の生活課題と支援 ケースシリーズ研究岡村 毅; 井藤 佳恵; 粟田 主一 精神神経学雑誌 (2013特別) S -678 2013/05
- 岡村毅; 宇良千秋; 宮前史子; 井藤佳恵; 粟田主一 日本精神保健・予防学会学術集会プログラム・抄録集 17th- 116 2013
- amnesticMCIで長期間経過し、精査の結果嗜銀顆粒認知症が疑われた1例古田 光; 田中 修; 菊地 幸子; 岡村 毅; 金丸 和富; 石井 賢二; 村山 繁雄; 粟田 主一; 松下 正明 日本老年医学会雑誌 49- (6) 836 -837 2012/11
- 特定高齢者基本チェックリストとうつ項目と精神的健康尺度との関連稲垣 宏樹; 井藤 佳恵; 佐久間 尚子; 杉山 美香; 岡村 毅; 粟田 主一 日本公衆衛生学会総会抄録集 71回- 387 -387 2012/10
- 田中 修; 古田 光; 杉下 瑞希; 菊地 幸子; 岡村 毅; 井藤 佳恵; 粟田 主一; 松下 正明 老年精神医学雑誌 23- (増刊II) 171 -171 2012/06
- 磯谷 一枝; 古田 光; 扇澤 史子; 今村 陽子; 磯野 沙月; 大浪 里枝; 井藤 佳恵; 岡村 毅; 細田 益宏; 菊地 幸子; 田中 修; 中島 さやか; 粟田 主一 老年精神医学雑誌 23- (増刊II) 234 -234 2012/06
- 扇澤 史子; 古田 光; 磯谷 一枝; 白取 絹恵; 今村 陽子; 井藤 佳恵; 中島 さやか; 菊地 幸子; 岡村 毅; 田中 修; 細田 益弘; 藤原 佳典; 大浪 里枝; 磯野 沙月; 粟田 主一 老年精神医学雑誌 23- (増刊II) 248 -248 2012/06
- 古田 光; 扇澤 史子; 磯谷 一枝; 今村 陽子; 大浪 里枝; 磯野 沙月; 田中 修; 菊地 幸子; 岡村 毅; 井藤 佳恵; 粟田 主一; 松下 正明 老年精神医学雑誌 23- (増刊II) 264 -264 2012/06
- 井藤佳恵; 稲垣宏樹; 杉山美香; 宮前史子; 宇良千秋; 佐久間尚子; 伊集院睦雄; 岡村毅; 森倉三男; 三崎真理; 下門顯太郎; 粟田主一 老年精神医学雑誌 23- (増刊II) 258 -258 2012/06
- 嗜銀顆粒認知症が疑われたamnestic MCIの2例古田 光; 田中 修; 菊地 幸子; 岡村 毅; 井藤 佳恵; 粟田 主一; 松下 正明 精神神経学雑誌 (2012特別) S -297 2012/05
- 都市在住生活困窮者の精神的健康度の分布と関連要因の検討井藤 佳恵; 森川 すいめい; 岡村 毅; 粟田 主一; 東京都立健康長寿医療センター研究所自立促進と介護予防研究チーム 精神神経学雑誌 (2012特別) S -556 2012/05
- 多職種協働における専門性の違い及び、協働の利点と留意点 もの忘れ外来の受診援助を通しての検討磯谷 一枝; 古田 光; 扇澤 史子; 白取 絹恵; 畠山 啓; 上田 まゆら; 菊地 ひろみ; 井藤 佳恵; 岡村 毅; 菊地 幸子; 粟田 主一 日本認知症ケア学会誌 11- (1) 290 -290 2012/04
- 物忘れ外来初診患者の家族介護者における介護負担感とその要因 大都市高齢者専門病院・物忘れ外来の介護者支援のための実態調査扇澤 史子; 古田 光; 磯谷 一枝; 白取 絹恵; 畠山 啓; 上田 まゆら; 菊地 ひろみ; 井藤 佳恵; 岡村 毅; 菊地 幸子; 粟田 主一 日本認知症ケア学会誌 11- (1) 335 -335 2012/04
- 認知機能低下抑制のためのウォーキング・プログラムの影響評価に関する検討宇良 千秋; 宮前 史子; 杉山 美香; 小島 成実; 井藤 佳恵; 岡村 毅; 佐久間 尚子; 伊集院 睦雄; 稲垣 宏樹; 粟田 主一; 高橋 龍太郎 日本認知症ケア学会誌 11- (1) 389 -389 2012/04
- 高橋龍太郎; 粟田主一; 藤原佳典; 大渕修一; 金憲経; 井藤佳恵; 伊集院睦雄; 佐久間尚子; 稲垣宏樹; 小島成実; 宇良千秋; 児玉寛子; 新名正弥; 平山亮; 宮前史子; 杉山美香; 岡村毅; 野本恵美 認知症早期発見のためのツール開発と認知機能低下抑制介入に関する研究 平成23年度 総括・分担研究報告書 9 -18 2012
- 認知症医療・介護連携施設~東京大学医学部附属病院メモリークリニック岡村毅; 岩田淳 Cognition and Dementia 11- (1) 72 -74 2012
- 岡村 毅 精神科 21- (1) 92 -95 2012
- 岡村 毅; 粟田 主一 日本臨床 69- (増刊10 認知症学(下)) 59 -63 2011/12
- 日本語版WHO-5を用いた都市在住高齢者の精神的健康度の分布とその関連要因の検討 要介護要支援認定群と非認定群との比較井藤 佳恵; 岡村 毅; 粟田 主一 精神神経学雑誌 (2011特別) S -444 2011/10
- 都市在住高齢者における日中の眠気の分布と関連要因に関する研究岡村 毅; 井藤 佳恵; 金野 倫子; 粟田 主一 精神神経学雑誌 (2011特別) S -444 2011/10
- Kae Ito; H. Inagaki; M. Sugiyama; F. Miyamae; M. Ijuin; N. Sakuma; S. Awata; T. Okamura INTERNATIONAL PSYCHOGERIATRICS 23- S261 -S262 2011/09
- 抑うつ、幻視、パーキンソニズムに対して修正型電気けいれん療法(mECT)が著効したレビー小体型認知症の1例八木 智子; 林 宜亨; 荒木 剛; 岡村 毅; 粟田 主一; 岩田 淳; 笠井 清登 精神神経学雑誌 113- (9) 928 -929 2011/09
- 認知症高齢者の家族介護者の介護負担感・肯定感に影響を与える要因の検討 介護者の認知症の心理的な受け止めの段階と家族機能に着目して扇澤 史子; 古田 光; 磯谷 一枝; 井藤 佳恵; 中島 さやか; 岡村 毅; 須田 潔子; 細田 益宏; 田中 修; 藤原 佳典; 粟田 主一 日本認知症ケア学会誌 10- (2) 450 -450 2011/08
- 岡村 毅; 粟田 主一 診断と治療 99- (6) 969 -973 2011/06
- 口腔内セネストパチーの統計と分析 当院における過去4年の入院症例より荒井 仁美; 岡村 毅; 杉下 和行; 細田 益宏; 中島 さやか; 古田 光; 井藤 佳恵; 粟田 主一; 松下 正明 精神神経学雑誌 113- (6) 632 -632 2011/06
- 粟田 主一; 井藤 佳恵; 岡村 毅; 古田 光; 佐藤 大介; 佐野 ゆり; 野呂 雅人; 佐藤 泰啓; 井上 由紀子; 高橋 ふみ; 山下 元康; 福島 攝; 水野 重樹; 久保 信彦; 河村 雅明 老年精神医学雑誌 22- (増刊III) 164 -164 2011/06
- 扇澤 史子; 古田 光; 磯谷 一枝; 稲垣 千草; 白取 絹恵; 今村 陽子; 新田 朗子; 井藤 佳恵; 中島 さやか; 細田 益宏; 岡村 毅; 須田 潔子; 秋元 和美; 小山 恵子; 粟田 主一 老年精神医学雑誌 22- (増刊III) 214 -214 2011/06
- 井藤佳恵; 稲垣宏樹; 杉山美香; 宮前史子; 伊集院睦雄; 佐久間尚子; 岡村毅; 粟田主一 老年精神医学雑誌 22- (増刊III) 161 -161 2011/06
- 粟田主一; 杉山美香; 宮前史子; 宇良千秋; 井藤佳恵; 伊集院睦雄; 佐久間尚子; 稲垣宏樹; 小島成美; 矢冨直美; 河野直子; 岡村毅 認知症早期発見のためのツール開発と認知機能低下抑制介入に関する研究 平成22年度 総括・分担研究報告書 12 -23 2011
- 認知症診断・加療における客観的指標づくり杉下和行; 岡村毅 Cognition and Dementia 10- (4) 358 -361 2011
- 認知症とうつ岡村 毅 臨床放射線 55- (11) 1545 -1554 2010 [Invited]
- うつは認知症の危険因子であるーフラミンガムスタディよりー岡村 毅 Cognition and dementia 9- 324 -325 2010
- 岡村毅; 西山潤; 音羽健司; 斎藤正彦; 笠井清登 精神神経学雑誌 111- (5) 2009
- 解離性障害の疫学と虐待の記憶岡村毅; 杉下和行; 柴山雅俊 心の臨床a la carte 28- (2) 341 -347 2009
- 杉下和行; 岡村毅; 柴山雅俊 Japanese journal of clinical psychiatry 38- (10) 1433 -1441 2009
Research Grants & Projects
- 日本学術振興会:科学研究費助成事業Date (from‐to) : 2025/04 -2030/03Author : 高瀬 顕功; 小川 有閑; 岡村 毅; 宇良 千秋
- 認知症診断後支援の総合的・学際的研究厚生労働科学研究費:Date (from‐to) : 2024/04 -2025/03Author : 岡村毅; 山下真理; 井原涼子; 枝広あや子; 杉山美香; 飯塚愛; 井藤佳恵; 古田光; 宮前史子; 矢吹知之
- 超高齢・多死社会への新しいケア・アプローチ:地域包括ケアにおけるFBOの役割Japan Society for the Promotion of Science:Grants-in-Aid for Scientific Research Challenging Research (Pioneering)Date (from‐to) : 2018/06 -2023/03Author : 小川 有閑; 岡村 毅; 林田 康順; 宇良 千秋; 新名 正弥; 高瀬 顕功本年度は主に以下の研究を進めた。 ①国内外の寺院・仏教者を中心に組織化されている福祉資源の事例を視察・調査し、協働に資する組織・制度要件を検討した。国内では、北陸地方での僧侶による高齢者福祉活動の視察調査を行なった。また、国外では、台湾での臨床宗教仏教師の制度について視察調査を行った。台湾では、「善終」という理想的な死の概念があり、善終のためのケアが宗教者に求められている。そのために、医療界と仏教界が協力をして、臨床宗教仏教師育成プログラムを作成し、専門の教育・訓練を受けた宗教者が育成されている。医療者、宗教者双方に聞き取り調査を行ない、台湾の精神風土に根差したスピリチュアルケアの構築(スピリチュアルケアの本土化)の背景・動機、その過程や将来像について知見を得た。国内の事例とともに、地域に根差した精神風土に適した医療・高齢者ケアの重要性を明らかにできたと言える。 ②寺院での介護者カフェを推進する浄土宗総合研究所の「超高齢社会における浄土宗寺院の可能性」プロジェクトについて、カフェの立ち上げや実施状況の記録や聞き取り調査を行なった。東京都葛飾区、宮城県塩竈市、静岡県富士宮市等で開かれた寺院での介護者カフェに参加、さらに地域の社会福祉協議会への聞き取りなども実施した。 ③西日本を中心に広く行われている月参りの風習に着目し、僧侶への聞き取り調査を行なった。僧侶が訪問する檀信徒宅の多くは、独居高齢者もしくは夫婦のみの高齢者であり、多世帯同居でも交流する家族は高齢者という結果であった。また、定期的な訪問の中で、高齢者の異変に気付くことや高齢者の話し相手としての役割を僧侶が感じることが多々あり、月参りが高齢者の見守り機能を有していることが明らかとなった。 ④浄土宗の全国の組長に月参り、中陰参りの実施状況についてのアンケート調査を行ない、全国の実施状況を地図化し、可視化を行なった。
- 精神医学